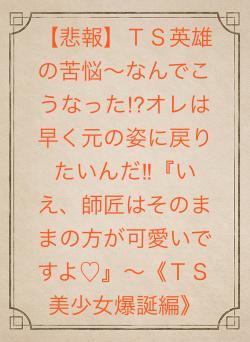ここは市場街の空き家。私とメーメルは、グレイ達が居る部屋の隣にいた。
「ルイ、何をやっておる。脱がなければ、調べられぬのじゃ」
「うん、分かってるんだけどね。なんかメーメルに、ジーっとみられているとさぁ」
「ハァー、分かったのじゃ。妾は、後ろを向いておる」
そう言いながらメーメルは後ろを向く。
それを確認すると私は急いで脱いだ。
「メーメル、脱いだよ。恥ずかしいから早くしてね」
それを聞きメーメルは振り返る。そして私を、ジッとみた。
「うむ、思ったより育っておるのう」
「えーっと……メーメル、どこみてるの?」
そう聞くとメーメルは、私のそばまできて胸を指差す。
「ルイの胸じゃ。それにくびれも……羨ましいのう」
そう言われ私は顔が熱くなり……。
「な、って……きゃあぁぁぁあああああ――――!?」
つい叫んでしまった。
すると扉が開く。
「何かあったのか?」
「ルイさん、どうされました?」
その声がする方を私とメーメルは向いた。出入口でグレイとムドルさんが私の方をみて固まっている。
「ちょ、出てけぇぇえええええええ――――。うわあぁぁん――――」
そう言いながら服を持ち蹲る。メーメルは自分が着ている服を私に被せてくれた。
「二人共、何をやっておるのじゃ!」
そう言いメーメルは、猛スピードでグレイとムドルさんの方に駆け出した。と同時に、二人を隣の部屋へ押し出す。
その後メーメルは、私のそばに駆け寄る。
「二人は追い出したから心配ないのじゃ。それよりも大丈夫かのう?」
「ヒクッ……間違いなく……ヒクッ……みられた、よね? あーどうしよう……最悪、お嫁にいけないよ〜!!」
そう言い私は泣きながらメーメルをみた。
「気持ちは分かるのじゃが。そこまで考えなくても、良いと思うがのう」
「うう……グスン……だって、真面にみられたんだよ」
「うむ、そうじゃな。それなら、こういうのはどうじゃ。二人にみた責任をとってもらうというのは?」
そう問われ私は考える。
責任、っていう事は……結婚? でも、やっぱりそういうのは……二人が愛し合ってするもんだよね。それにムドルさんまで巻き込むのは違うし。
そう思い扉の方へ視線を向けた。
「ねぇ、メーメル。あの扉からみえたと思う?」
「みえたと思うのじゃ。特にムドルはのう」
「……そうなんだね。ハァ……」
私は落ち込んだ。メーメルに慰めてもらっても、流石に立ち直れない。これからどうすればいいのかと自問自答した。だけど、思いつかず。
「ルイ、二人のこと嫌いなのかのう?」
「ううん、好きだよ。グレイのことが好き。ムドルさんも好きだけど多分、グレイに抱いている感情と違う。それにムドルさんはメーメルの……」
「前にもムドルにフラれたと言ったのじゃ」
メーメルはそう言い私を覗き込む。
「うん、聞いた。だけどメーメルは、まだムドルさんのこと好きなんでしょ?」
「そうじゃな。今でも好きじゃ。でもムドルには、既に想い人がおる」
「そうかぁ。だけど、ムドルさんの想い人って誰だろう。でも、私の知らない人だよね」
そう言いメーメルをみた。メーメルは溜息をつく。
「ルイの知ってる者じゃ」
「私が知ってる人? 誰だろう……んー、分からないよ」
「分からぬなら良い。そのうち、分かると思うのじゃ」
そう言われ私は頷いた。
「そっかぁ、どんな人だろう」
「……ムドルも報われんのう」
ボソッとメーメルが呟く。私はその言葉が、ハッキリ聞こえなかった。
「報われないって、何が?」
「なんでもない。ただの一人言じゃ。それよりも、落ち着いたようじゃな」
「んーそういえば、いつの間にか気持ちが楽になってる」
それを聞きメーメルは、ニコリと笑みを浮かべる。
「良かったのじゃ」
「うん、ありがとう。だけど、真面に顔を合わせられるかだけどね」
「そうじゃな。それはそうと、早く調べるのじゃ」
そう言われ私は、コクリと頷いた。そして立ち上がる。
メーメルは私の体を調べ始めた。
「あったのじゃ!」
「えっ!? どこどこ……」
それを聞き探すが見当たらない。
「右側の腰じゃ。後ろだからみえぬ」
「そうなんだね。どんな証だろう?」
「これは、下向きに交差した二本の剣と盾と竜じゃ。色は紫じゃな」
そう言うとメーメルは考え始める。
「なんの証だろう? 雰囲気だけなら、勇者の紋章みたいだね」
「そうじゃな。その部分なら捲ればみせられるのじゃ」
「じゃあ、判断してもらうってこと?」
そう問うとメーメルは頷いた。
「その方が良いのじゃ」
「そうだね。まだちょっと恥ずかしいけど……」
「服を着たら隣の部屋に行くのじゃ」
そう言われ私は、急いで服を着る。
そして服を着ると私は、まだちょっと恥ずかしい気持ちが残りながらも、メーメルと隣の部屋へと向かったのだった。
「ルイ、何をやっておる。脱がなければ、調べられぬのじゃ」
「うん、分かってるんだけどね。なんかメーメルに、ジーっとみられているとさぁ」
「ハァー、分かったのじゃ。妾は、後ろを向いておる」
そう言いながらメーメルは後ろを向く。
それを確認すると私は急いで脱いだ。
「メーメル、脱いだよ。恥ずかしいから早くしてね」
それを聞きメーメルは振り返る。そして私を、ジッとみた。
「うむ、思ったより育っておるのう」
「えーっと……メーメル、どこみてるの?」
そう聞くとメーメルは、私のそばまできて胸を指差す。
「ルイの胸じゃ。それにくびれも……羨ましいのう」
そう言われ私は顔が熱くなり……。
「な、って……きゃあぁぁぁあああああ――――!?」
つい叫んでしまった。
すると扉が開く。
「何かあったのか?」
「ルイさん、どうされました?」
その声がする方を私とメーメルは向いた。出入口でグレイとムドルさんが私の方をみて固まっている。
「ちょ、出てけぇぇえええええええ――――。うわあぁぁん――――」
そう言いながら服を持ち蹲る。メーメルは自分が着ている服を私に被せてくれた。
「二人共、何をやっておるのじゃ!」
そう言いメーメルは、猛スピードでグレイとムドルさんの方に駆け出した。と同時に、二人を隣の部屋へ押し出す。
その後メーメルは、私のそばに駆け寄る。
「二人は追い出したから心配ないのじゃ。それよりも大丈夫かのう?」
「ヒクッ……間違いなく……ヒクッ……みられた、よね? あーどうしよう……最悪、お嫁にいけないよ〜!!」
そう言い私は泣きながらメーメルをみた。
「気持ちは分かるのじゃが。そこまで考えなくても、良いと思うがのう」
「うう……グスン……だって、真面にみられたんだよ」
「うむ、そうじゃな。それなら、こういうのはどうじゃ。二人にみた責任をとってもらうというのは?」
そう問われ私は考える。
責任、っていう事は……結婚? でも、やっぱりそういうのは……二人が愛し合ってするもんだよね。それにムドルさんまで巻き込むのは違うし。
そう思い扉の方へ視線を向けた。
「ねぇ、メーメル。あの扉からみえたと思う?」
「みえたと思うのじゃ。特にムドルはのう」
「……そうなんだね。ハァ……」
私は落ち込んだ。メーメルに慰めてもらっても、流石に立ち直れない。これからどうすればいいのかと自問自答した。だけど、思いつかず。
「ルイ、二人のこと嫌いなのかのう?」
「ううん、好きだよ。グレイのことが好き。ムドルさんも好きだけど多分、グレイに抱いている感情と違う。それにムドルさんはメーメルの……」
「前にもムドルにフラれたと言ったのじゃ」
メーメルはそう言い私を覗き込む。
「うん、聞いた。だけどメーメルは、まだムドルさんのこと好きなんでしょ?」
「そうじゃな。今でも好きじゃ。でもムドルには、既に想い人がおる」
「そうかぁ。だけど、ムドルさんの想い人って誰だろう。でも、私の知らない人だよね」
そう言いメーメルをみた。メーメルは溜息をつく。
「ルイの知ってる者じゃ」
「私が知ってる人? 誰だろう……んー、分からないよ」
「分からぬなら良い。そのうち、分かると思うのじゃ」
そう言われ私は頷いた。
「そっかぁ、どんな人だろう」
「……ムドルも報われんのう」
ボソッとメーメルが呟く。私はその言葉が、ハッキリ聞こえなかった。
「報われないって、何が?」
「なんでもない。ただの一人言じゃ。それよりも、落ち着いたようじゃな」
「んーそういえば、いつの間にか気持ちが楽になってる」
それを聞きメーメルは、ニコリと笑みを浮かべる。
「良かったのじゃ」
「うん、ありがとう。だけど、真面に顔を合わせられるかだけどね」
「そうじゃな。それはそうと、早く調べるのじゃ」
そう言われ私は、コクリと頷いた。そして立ち上がる。
メーメルは私の体を調べ始めた。
「あったのじゃ!」
「えっ!? どこどこ……」
それを聞き探すが見当たらない。
「右側の腰じゃ。後ろだからみえぬ」
「そうなんだね。どんな証だろう?」
「これは、下向きに交差した二本の剣と盾と竜じゃ。色は紫じゃな」
そう言うとメーメルは考え始める。
「なんの証だろう? 雰囲気だけなら、勇者の紋章みたいだね」
「そうじゃな。その部分なら捲ればみせられるのじゃ」
「じゃあ、判断してもらうってこと?」
そう問うとメーメルは頷いた。
「その方が良いのじゃ」
「そうだね。まだちょっと恥ずかしいけど……」
「服を着たら隣の部屋に行くのじゃ」
そう言われ私は、急いで服を着る。
そして服を着ると私は、まだちょっと恥ずかしい気持ちが残りながらも、メーメルと隣の部屋へと向かったのだった。