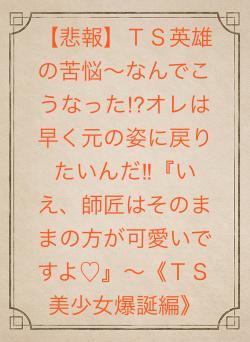ここはタルキニアの町の市場街。その路地の古びた倉庫がみえる空き家に、グレイフェズとメーメルはいた。
「グレイ、どうするつもりなのじゃ?」
そう言いメーメルは、窓から古びた倉庫をのぞきみる。
「下手に乗りこむのは危険だ。それに、この件の主犯がコルザ様なら……その尻尾をつかまないと」
「うむ、そっちはムドルがいると思うのじゃが」
「そうだが……どうやって連絡をとる? 何か方法があれば……」
それを聞きメーメルは、グレイフェズのバッグを指差した。
「そこに、便箋があるじゃろう」
そう言われグレイフェズは、自分のバッグに視線を向ける。
「そうか、ムドルに手紙を送れば。だが……文面をどうする? 下手に送ってバレたら……」
「恋文を書けばよい」
「こ、恋文!? ちょっと待て、それはどういう事だ? なんでそうなる……」
グレイフェズは驚いた。なんでそんなことを突然、言い出したのか……その意図が分からなかったからだ。
「そのまま送っては、内容をみられた時にバレてしまうじゃろう。それなら、恋文のように書いて送れば良いと思ったのじゃ」
「なるほど……それなら、問題ないか。だけど、それを誰が書く? 勿論、メーメルだよな」
そう問われメーメルは首を横に振る。
「妾よりグレイの方が良い。それに余り時間もないしのう。伝えたいことは自分で書いた方がいいじゃろう」
メーメルは、ニタアと笑みを浮かべた。
「その顔は、楽しんでないか? だが……そうだな、その方が確かに早い。嫌だが……書くか」
そう言い渋々グレイフェズは、バッグの中からペンと便箋をだす。
そして、床に便箋を置くと書き始めた。
それをメーメルはどんな文を書くのかと、ワクワクしながらグレイフェズの手元をみる。
グレイフェズはメーメルにみられ書きづらい。額に汗をかきながら書いている。書きながらイライラし始めた。
「ああぁぁぁぁー、なんで俺がムドル宛にこんな文を書かなきゃいけねえー」
そう叫び頭をかきむしる。
「シー、なのじゃ」
そう言われグレイフェズは、メーメルをジト目でみた。
「……そうだな」
グレイフェズは不貞腐れた態度でそう言う。その後、また書き始める。
それをメーメルは、ニヤニヤしながらみていた。
それから数十分後グレイフェズは、なんとか暗号まじりに恋文を書き上げる。
書き上げたグレイフェズはゲッソリしていた。そして、もうこんな恋文は絶対に書かないと思い心に刻んだ。
「あとは、これをムドルに送るだけだ」
「うむ、そうじゃな。ムドルが、どういう反応をするか楽しみじゃ」
「メーメル、やっぱり楽しんでるよな」
そう聞かれメーメルは頷いた。
「勿論じゃ。滅多に、こんなことは起きないからのう」
そう言い切られグレイフェズは、ガクッと肩を落とす。
「まぁいい。それよりも、早くこれを送らないとな」
そう言いグレイフェズは、便箋の魔法陣に触れ魔力を注いだ。すると便箋が発光して、パッと消える。
「これで、いい。あとは……」
グレイフェズは古びた倉庫の方に視線を向けた。
「グレイ、どうするつもりなのじゃ?」
そう言いメーメルは、窓から古びた倉庫をのぞきみる。
「下手に乗りこむのは危険だ。それに、この件の主犯がコルザ様なら……その尻尾をつかまないと」
「うむ、そっちはムドルがいると思うのじゃが」
「そうだが……どうやって連絡をとる? 何か方法があれば……」
それを聞きメーメルは、グレイフェズのバッグを指差した。
「そこに、便箋があるじゃろう」
そう言われグレイフェズは、自分のバッグに視線を向ける。
「そうか、ムドルに手紙を送れば。だが……文面をどうする? 下手に送ってバレたら……」
「恋文を書けばよい」
「こ、恋文!? ちょっと待て、それはどういう事だ? なんでそうなる……」
グレイフェズは驚いた。なんでそんなことを突然、言い出したのか……その意図が分からなかったからだ。
「そのまま送っては、内容をみられた時にバレてしまうじゃろう。それなら、恋文のように書いて送れば良いと思ったのじゃ」
「なるほど……それなら、問題ないか。だけど、それを誰が書く? 勿論、メーメルだよな」
そう問われメーメルは首を横に振る。
「妾よりグレイの方が良い。それに余り時間もないしのう。伝えたいことは自分で書いた方がいいじゃろう」
メーメルは、ニタアと笑みを浮かべた。
「その顔は、楽しんでないか? だが……そうだな、その方が確かに早い。嫌だが……書くか」
そう言い渋々グレイフェズは、バッグの中からペンと便箋をだす。
そして、床に便箋を置くと書き始めた。
それをメーメルはどんな文を書くのかと、ワクワクしながらグレイフェズの手元をみる。
グレイフェズはメーメルにみられ書きづらい。額に汗をかきながら書いている。書きながらイライラし始めた。
「ああぁぁぁぁー、なんで俺がムドル宛にこんな文を書かなきゃいけねえー」
そう叫び頭をかきむしる。
「シー、なのじゃ」
そう言われグレイフェズは、メーメルをジト目でみた。
「……そうだな」
グレイフェズは不貞腐れた態度でそう言う。その後、また書き始める。
それをメーメルは、ニヤニヤしながらみていた。
それから数十分後グレイフェズは、なんとか暗号まじりに恋文を書き上げる。
書き上げたグレイフェズはゲッソリしていた。そして、もうこんな恋文は絶対に書かないと思い心に刻んだ。
「あとは、これをムドルに送るだけだ」
「うむ、そうじゃな。ムドルが、どういう反応をするか楽しみじゃ」
「メーメル、やっぱり楽しんでるよな」
そう聞かれメーメルは頷いた。
「勿論じゃ。滅多に、こんなことは起きないからのう」
そう言い切られグレイフェズは、ガクッと肩を落とす。
「まぁいい。それよりも、早くこれを送らないとな」
そう言いグレイフェズは、便箋の魔法陣に触れ魔力を注いだ。すると便箋が発光して、パッと消える。
「これで、いい。あとは……」
グレイフェズは古びた倉庫の方に視線を向けた。