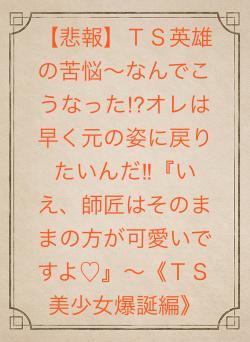ここはバールドア城の清美の部屋。
清美はあれからサクリスを使い、色々と城の内情を調べていた。
現在、清美は豪華なソファーに座り本を読んでいる。
(……そうなると……そうよね。だけど……んー……)
そうこう思考を巡らせていた。
扉の近くに置かれた椅子には、サクリスが座り清美をジーっとみている。
(クッ、油断した。聖女が、ここまでとはな。まぁ、服従か……それも悪くない。手は出せないが、こうやってキヨミを眺めていられる)
そう思考をグルグル巡らせながら、ニヤニヤしている。奇妙な光景だ。
清美は本をテーブルに置くと立ち上がる。
「そろそろ着替えた方が良いわよね」
そう言うと白いクローゼットの方に向かう。
それをみたサクリスは、椅子から立ち上がると清美の方へ行こうとする。
「サクリス、お座り!!」
清美がそう命令するとサクリスは、強制的に床にベタッと座った。
「キヨミ様、これはあんまりです。ただ、お着替えの手伝いをと……」
そう言うもののサクリスの表情は明らかにニタニタしており、顔を赤らめよだれを垂らしている。
「着替えは自分でします! そこでみてるだけにしなさい」
ムッとした面持ちで清美はそう言い放つ。
「そんなぁ……生殺しだぁ」
「私は、それだけでも嫌なんだけど。だから我慢して、ね」
清美が困った顔でそう言うと、サクリスは「んー」と考えたあとコクリと頷いた。
「そうだなぁ。キヨミ様には逆らえないし。こうやって着替えを眺めるだけでも……良しとしないと、か」
そう言うとサクリスは、ニヤッと口角を上げる。
「……」
それをみた清美は、ゾッとし絶句した。
その後、清美はサクリスをチラ見しながら着替える。
(悪い人じゃないんだろうけど。違う意味で、女性でも流石にね。んー、そういえば着替えだけでいいのかな?)
そう思いながら髪を軽く触った。
「キヨミ様! 髪のセットだけでもやらせて、もらえないかなぁ……と」
「そうだなぁ。どうしよう……そのぐらいならいいか、な」
そう言われサクリスは嬉しくなり、清美の傍に駆け寄る。
「あ、ありがとうございます!」
「但し、もし変なことしたら髪も触らせないからね!!」
それを聞きサクリスは、ウンウンと思いっきり頷いた。
清美は不安ながらも鏡の前に座る。それを視認するとサクリスは、ニコニコしながら台の上のブラシを手に持った。そして、清美の後ろに立つ。……清美は、ゾクッとする。
その後サクリスは、ブラシで清美の長い髪を梳かし始めた。
「キヨミ様の髪って綺麗だなぁ。こんな癖の少ない髪はみたことない」
「そうかな? でも私の髪よりもね、泪の方が艶があって綺麗なんだよ」
そう清美が言うとサクリスは小首を傾げる。
「泪……とは、誰だ?」
「サクリスは、知らないのね。じゃあ、私の他に召喚された人がいるってことは?」
「いいえ、聞いてない。……ってことは、もう一人……」
サクリスは妄想全開で、ニタニタと笑みを浮かべた。
「その人も、女なんだよな。どんな娘、だろう……」
「サクリス、泪は確かに女性だけど。もし手を出したら、その場でお座りだよ!」
そう言われサクリスは、不満な表情になる。
「はーい、残念だなぁ。だけど、そのルイって今どこに居るんだ?」
「この城には居ない。それにこの城から追い出されたみたいだから……今、どこに居るか分からないのよね」
清美は泪のことを思い出し不安な表情になった。
「そのルイのこと心配なのか?」
「うん、誰かと……男の人と一緒だったけど。何もされてないか、ね」
それを聞いたサクリスは、んーっと考えながら口を開く。
「その男ってどんなヤツだ?」
「そう……ね。遠くからだったから良く分からないけど。白っぽいような銀色な感じで短い髪の人だった気がする」
「なるほど、白銀の髪で短い……。そんで最近この城から外に、ねえ」
そう言いながらサクリスは、ニタァっと笑った。
「もしかして、その人のこと知ってるの?」
「ああ……多分、うちの隊の副隊長だよ」
「そうなの? でも、なんでそんな人が泪と」
清美は不思議に思い首を傾げる。
「確か隊長の話だと。監視って、言ってたような気がする」
「そっかぁ。泪、大丈夫かな……」
「まぁそのルイが副隊長を怒らせなければ、な」
そう言われ清美は更に不安になった。
その後も話しながらサクリスは、清美の髪をアップにしセットしていく。そして、髪のセットを終える。
すると清美は、サクリスに「ありがとう」と言い立ち上がりソファーに向かった。
それを確認するとサクリスは扉の方に向かい椅子に座る。
そしてその後ソファーに座り清美は、カイルディが呼びにくるのを待ちながら色々と考えていたのだった。
清美はあれからサクリスを使い、色々と城の内情を調べていた。
現在、清美は豪華なソファーに座り本を読んでいる。
(……そうなると……そうよね。だけど……んー……)
そうこう思考を巡らせていた。
扉の近くに置かれた椅子には、サクリスが座り清美をジーっとみている。
(クッ、油断した。聖女が、ここまでとはな。まぁ、服従か……それも悪くない。手は出せないが、こうやってキヨミを眺めていられる)
そう思考をグルグル巡らせながら、ニヤニヤしている。奇妙な光景だ。
清美は本をテーブルに置くと立ち上がる。
「そろそろ着替えた方が良いわよね」
そう言うと白いクローゼットの方に向かう。
それをみたサクリスは、椅子から立ち上がると清美の方へ行こうとする。
「サクリス、お座り!!」
清美がそう命令するとサクリスは、強制的に床にベタッと座った。
「キヨミ様、これはあんまりです。ただ、お着替えの手伝いをと……」
そう言うもののサクリスの表情は明らかにニタニタしており、顔を赤らめよだれを垂らしている。
「着替えは自分でします! そこでみてるだけにしなさい」
ムッとした面持ちで清美はそう言い放つ。
「そんなぁ……生殺しだぁ」
「私は、それだけでも嫌なんだけど。だから我慢して、ね」
清美が困った顔でそう言うと、サクリスは「んー」と考えたあとコクリと頷いた。
「そうだなぁ。キヨミ様には逆らえないし。こうやって着替えを眺めるだけでも……良しとしないと、か」
そう言うとサクリスは、ニヤッと口角を上げる。
「……」
それをみた清美は、ゾッとし絶句した。
その後、清美はサクリスをチラ見しながら着替える。
(悪い人じゃないんだろうけど。違う意味で、女性でも流石にね。んー、そういえば着替えだけでいいのかな?)
そう思いながら髪を軽く触った。
「キヨミ様! 髪のセットだけでもやらせて、もらえないかなぁ……と」
「そうだなぁ。どうしよう……そのぐらいならいいか、な」
そう言われサクリスは嬉しくなり、清美の傍に駆け寄る。
「あ、ありがとうございます!」
「但し、もし変なことしたら髪も触らせないからね!!」
それを聞きサクリスは、ウンウンと思いっきり頷いた。
清美は不安ながらも鏡の前に座る。それを視認するとサクリスは、ニコニコしながら台の上のブラシを手に持った。そして、清美の後ろに立つ。……清美は、ゾクッとする。
その後サクリスは、ブラシで清美の長い髪を梳かし始めた。
「キヨミ様の髪って綺麗だなぁ。こんな癖の少ない髪はみたことない」
「そうかな? でも私の髪よりもね、泪の方が艶があって綺麗なんだよ」
そう清美が言うとサクリスは小首を傾げる。
「泪……とは、誰だ?」
「サクリスは、知らないのね。じゃあ、私の他に召喚された人がいるってことは?」
「いいえ、聞いてない。……ってことは、もう一人……」
サクリスは妄想全開で、ニタニタと笑みを浮かべた。
「その人も、女なんだよな。どんな娘、だろう……」
「サクリス、泪は確かに女性だけど。もし手を出したら、その場でお座りだよ!」
そう言われサクリスは、不満な表情になる。
「はーい、残念だなぁ。だけど、そのルイって今どこに居るんだ?」
「この城には居ない。それにこの城から追い出されたみたいだから……今、どこに居るか分からないのよね」
清美は泪のことを思い出し不安な表情になった。
「そのルイのこと心配なのか?」
「うん、誰かと……男の人と一緒だったけど。何もされてないか、ね」
それを聞いたサクリスは、んーっと考えながら口を開く。
「その男ってどんなヤツだ?」
「そう……ね。遠くからだったから良く分からないけど。白っぽいような銀色な感じで短い髪の人だった気がする」
「なるほど、白銀の髪で短い……。そんで最近この城から外に、ねえ」
そう言いながらサクリスは、ニタァっと笑った。
「もしかして、その人のこと知ってるの?」
「ああ……多分、うちの隊の副隊長だよ」
「そうなの? でも、なんでそんな人が泪と」
清美は不思議に思い首を傾げる。
「確か隊長の話だと。監視って、言ってたような気がする」
「そっかぁ。泪、大丈夫かな……」
「まぁそのルイが副隊長を怒らせなければ、な」
そう言われ清美は更に不安になった。
その後も話しながらサクリスは、清美の髪をアップにしセットしていく。そして、髪のセットを終える。
すると清美は、サクリスに「ありがとう」と言い立ち上がりソファーに向かった。
それを確認するとサクリスは扉の方に向かい椅子に座る。
そしてその後ソファーに座り清美は、カイルディが呼びにくるのを待ちながら色々と考えていたのだった。