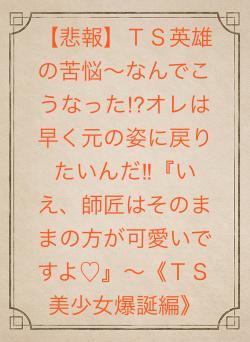ここはスイラジュンムの、遥か北東部に位置する孤島。辺りは、人っ子一人いる気配もないような辺境の地。
その孤島の北西部に位置する険しい山々の山頂付近には、西洋の城を思わせるこの地に似つかわしくないような建物が立っている。
建物内は、広く迷いそうになるほどだ。
この建物の三階にある階段付近の廊下では、銀色で長い髪のみた目がヴァンパイアのような男が絵をみながら立っていた。
「そろそろ勇者が召喚されていてもいいはず。されど数体の使い魔を放つも、いまだにその気配すらない。どういう事だ?」
そうこのヴァンパイアのような男がヴァンディロードだ。
ちなみにヴァンパイアのようにみえるだけで違う種族であり、ヴァンデエルフという知能に優れた魔族である。
(うむ。考えたくはないが。既に勇者がこの世界に現れていたとしたら厄介だ。
魔王様が復活するまでに、なんとか勇者を始末せねば--。このままではあの女神の思惑通りになってしまうではないか!)
そうこう考えていると、ヴァンディロードの左手の腕輪の黒い石が光りだす。
「……!? これは使い魔の知らせ。勇者をみつけたのか?」
ヴァンディロードは、腕輪の黒い石に右手の人差し指と中指を添え小さく魔法陣を描いた。
すると腕輪からヴァウロイの声が聞こえてくる。
「その声はヴァウロイ。勇者がみつかったのか?」
「それが。みつかったといえばそうなのですが。ただ普通の勇者ではなくて」
「普通じゃない? それはどういう事だっ!」
ヴァウロイはそのことについて説明した。
その話を聞きながらヴァンディロードは、不敵な笑みをみせる。その後、話を終えると通信を切った。
「フッ、ハッハッハッ! これは面白くなりそうだ」
そう言いヴァンディロードは、高笑いをしながら部屋へと向かい歩きだす。
その孤島の北西部に位置する険しい山々の山頂付近には、西洋の城を思わせるこの地に似つかわしくないような建物が立っている。
建物内は、広く迷いそうになるほどだ。
この建物の三階にある階段付近の廊下では、銀色で長い髪のみた目がヴァンパイアのような男が絵をみながら立っていた。
「そろそろ勇者が召喚されていてもいいはず。されど数体の使い魔を放つも、いまだにその気配すらない。どういう事だ?」
そうこのヴァンパイアのような男がヴァンディロードだ。
ちなみにヴァンパイアのようにみえるだけで違う種族であり、ヴァンデエルフという知能に優れた魔族である。
(うむ。考えたくはないが。既に勇者がこの世界に現れていたとしたら厄介だ。
魔王様が復活するまでに、なんとか勇者を始末せねば--。このままではあの女神の思惑通りになってしまうではないか!)
そうこう考えていると、ヴァンディロードの左手の腕輪の黒い石が光りだす。
「……!? これは使い魔の知らせ。勇者をみつけたのか?」
ヴァンディロードは、腕輪の黒い石に右手の人差し指と中指を添え小さく魔法陣を描いた。
すると腕輪からヴァウロイの声が聞こえてくる。
「その声はヴァウロイ。勇者がみつかったのか?」
「それが。みつかったといえばそうなのですが。ただ普通の勇者ではなくて」
「普通じゃない? それはどういう事だっ!」
ヴァウロイはそのことについて説明した。
その話を聞きながらヴァンディロードは、不敵な笑みをみせる。その後、話を終えると通信を切った。
「フッ、ハッハッハッ! これは面白くなりそうだ」
そう言いヴァンディロードは、高笑いをしながら部屋へと向かい歩きだす。