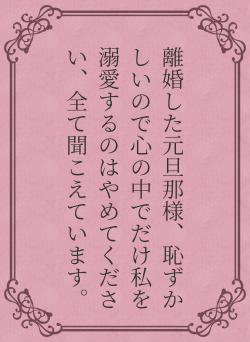3月23日(土) 夕暮れの海岸にて
水平線の向こうに、夕陽が沈んでいく。
燃えるような赤と、群青のコントラスト。
ざあっと、寄せては返す波の音。
海風が運ぶ潮の匂い。
そばを走り去る車のエンジン音。
高柳冬真は、ひとけのない海岸に、ひとり立っていた。
ぼんやりと波をみつめていると、ザクッと海岸の砂を踏みしめる足音がして、「未来?」と振り向く。
振り向いた先、真っ赤な日差しを浴びながら、冬真のほうへと歩いてきたのは、未来ではなかった。
冬真は驚きに目を見開く。
「チカ……近松さん……どうしてここに?」
『久しぶりね、高柳さん。未来のふりをしてあなたを呼び出したの。騙しちゃってごめんなさいね』
「いえ……でも、どうして近松さんが……」
『わからない?あなたが契約を破ったからよ』
チカがそう告げると、高柳は体を90度折り曲げて、頭を下げ、「すみませんでした!」と叫んだ。
チカは冷たく高柳を見下ろすといった。
『あなた、遊び相手を探してたんでしょう?
あたしは、あくまで遊び相手として未来を斡旋したのよ。
それがなに?本気になった?結婚する?
話が違うわ。
悪いけど、結婚を許すわけにはいかないわね』
すると、なりふり構わずに、高柳は砂浜に土下座した。
「すみませんでした!……確かに、最初は遊ぶだけのつもりで、未来に近づきました。
でも、今は……未来を本気で好きになってしまって、未来が、なにより一番大切で……」
夕陽が映える砂浜に、高柳がぼとぼとと、大粒の涙を落としながら懇願する。
「どうか、未来との結婚を許してください。
彼女は、運命のひとなんです!」
砂浜の砂に、頭を埋めるように額を擦りつけながら、高柳は切実に訴える。
そんな高柳を冷酷な瞳で見下ろしながら、チカは腕を組んだ。
『認められないわ。あたし、未来に幸せになられちゃ困るのよ』
「そんな……どうして……?」
『あの子の不幸話を肴に酒を呑むのがあたしの最大の幸せな瞬間なの。
男に無惨に棄てられて、男運のなさを、盛大に嘆くあの子の愚痴をききながら、酒を呑むのが一番のストレス解消なのよ。酒の美味さも桁違いだわ。
それを、失うわけにはいかないの。
あたしのために、あの子には、とことん不幸でいてもらわなきゃ。
そのために、あなたみたいな、付き合うと不幸な目に遭うこと間違いなしのクズと、未来を出会わせてきたのよ。
全ては、あたしのため。
だから、結婚なんて認めるわけないでしょう?
わかった?』
「そんな……ひどい……」
『あんたにいわれる筋合いないわ』
ぴしゃり、とチカが高柳の言葉を撥ねつける。
「どうして、そこまで未来を不幸にすることにこだわるんですか?どうして未来を、そこまで恨んでいるんですか?」
『恨む?別に未来を恨んでなんかいないわ』
「だったら、どうして……」
『あたしはね、女が嫌いなの。未来だけじゃない、女という生き物が、ひとりの例外もなく、大嫌い。
男と結ばれて幸せになる?
男をたぶらかすことしか脳のない、低俗な女をみていると、虫酸が走るわ』
「どうしてそこまで……」
チカは、少し考えるように口を閉ざす。
腕組みを解くと、遥か彼方の水平線に沈みゆく夕陽に目を細め、視線を遠くに投げながら再び口を開いた。
『……そうね。こんなこと急にいわれても、理解できないわよね。
いいわ。順を追って話しましょう。
あたしがなぜ女を嫌うようになったのか、その理由を、話してあげる』
一度、唇を舐めると、チカは宣言通り話しだした。
『あたしね、高校時代まで、100キロ超えの、デブで、ブサイクで、冴えない眼鏡をかけたうえにオカマだったの。
クラスメイトの女たちが、嘲りの対象にするのにぴったりの条件を揃えてたわけ。
女たちは、あたしの見た目を、隠しもせずに馬鹿にして、嗤ったわ。
ひとり残らずね。
悔しかった。
許せなかった。
男に依存して、色目を使うことしかできない、ふしだらな女に、自分は嗤われていたんだって思ったら、見返してやりたいと思った』
「ちょ、ちょっと待ってください!オカマ?
近松さん、男なんですか?」
堪えきれずに、高柳はチカの話を遮った。
『そうよ。見えないでしょ?努力したのよ。信じられないなら……そうね』
チカは、すうっと深く息を吸うと、『動くな!警察だ!』と、野太い男性の声で叫ぶと、『こんな感じ。どう?』と薄く笑って、首を傾げてみせた。
間違いなく、それは男の声帯から放たれた声だった。
ぽかんとした顔で見上げてくる高柳をみて、風になびく、緩くウェーブがかったブラウンの長い髪を手で押さえながら、チカは満足そうに微笑んだ。
『面白くなってきたから、ついでにあたしの本名教えてあげる。あたしね、近松史朗っていうの。ダサいでしょ?笑えるでしょ?』
絶句したまま、高柳はチカを見上げることしかできない。
海岸が濃い碧に染まる。
チカの昔語りは続く。
『いいのよ、笑って。続けるわね。
高校を卒業したあと、あたしはダイエットをはじめた。
両親や親戚は、田舎特有の気質のせいもあって、息子であるあたしがオカマであることを近所に知られることを嫌ったし、あたしが女になりたいって打ち明けた瞬間に、勘当された。
もうどうでもいいことだけど、本当に理解のない両親だったわ。
高校卒業を機に家を出て、一度も実家には帰っていない。もう一生帰らないでしょうね。
たとえ両親が死んでも。
お葬式に行ったとしても、幽霊になってまで、恥ずかしいから来るなってあたしを追い出すでしょうし。
ま、そんなことは、本当にどうでもいいことだったわね。
話が逸れたわ。
未来と、もうひとりサキって子と知り合ったのは、こっちにきて大学に入学してすぐのことだった。
だから、未来は、あたしがデブで男の格好をしていたころの姿を知ってる。
未来とサキは、ダイエットのサポートをしてくれたり、痩せたあとのあたしに、メイクを教えてくれたり、洋服を買うのに付き合ってくれた』
「そこまで親しくしていた未来にどうしてこんな仕打ちを……?未来は、近松さんに、優しくしてくれたんでしょう?」
チカは淡白に突き放す。
『関係ないわ。親友だろうが友達だろうが、例外なんてない。女の不幸はあたしの幸せ。だって、みんな等しく女なのよ?同じ女という生物を、どうやって区別しろっていうの?どうやって違いを探せっていうの?親友だからなに?それが、他の女と未来を分ける違いになるの?
あたしにはわからない。
ねえ、あなたなら、どうやってひとを見分ける?違いを探す?例外を作れる?
わからない。本当にわからないわ』
チカは、途方に暮れたように、まるで幼い子どもが、大人に問うように、真っ直ぐに高柳をみつめる。
高柳は言葉を失った。
チカの、言葉の意味がわからない。
高柳の理解を超えた範疇の考え方で、常識で、チカという人間は生きている。
わかろうとしても、無駄なことだった。
陽が沈む。
海岸に冷たい風が吹く。
無言の時間が過ぎていく。
「どうすれば……認めてくれますか?」
『しつこい男ね。認めないっていってるでしょ』
押し問答が続く。
食い下がる高柳に根負けしたのか、街灯が照らすささやかな光りを背後にしたチカが、思案するように高柳を見下ろす。
「仕方ないわね。
じゃあ、交渉しましょう。
あなたが一生未来に近づかないと誓うのなら、未来にクズを斡旋するのをやめる。
未来を本当に愛しているなら、未来のために身を引けるでしょう?
他の男と結婚しても、未来の幸せを祝福してあげられるでしょう?」
唇を噛みしめた高柳の表情が絶望に染まる。
くす、と小さくチカが笑う。
『条件はもうひとつあるわ。
あなたに別れを告げられても、未来があなたこそ運命のひとだと、高柳さんのもとに戻ってきたら、そのときは、あなたたちが本物の運命の恋人だと認めてあげる。
結婚だってなんだって、好きにすればいいわ。あたしも祝福する。
どう?
あなたは、未来が自分のもとに帰ってくると、信じられるかしら?
未来は、あなたに棄てられたと思ってもなお、まだあなたを愛するかしら?
なりふり構わずに、あなたしかいないと、自分を棄てたあなたにすがりつくかしら?
いつ帰るともしれない、帰ってこない可能性が高い恋人を、あなたは待ち続けられる?
悪いけど、あなたと未来を引き離す手段なんて、あたしには、山ほどあるのよ。
変な気は起こさないことね。
……これ以上未来に、不幸になってほしくなければ』
チカの、理不尽極まりない条件に、高柳は声も出せずに膝立ちになったまま、しばらく放心していたが、数秒が過ぎるうち、虚ろだったその瞳に、強い意志を宿した。
「待ちます。未来を信じます。俺たちは、運命の糸で結ばれた相手なんだから」
3月29日(金) 仕事帰りの居酒屋にて
「またやられたよー」
早くも酔いが回った未来が、呂律が怪しい口調で、チカ相手にくだを巻いていた。
『もう棄てられたの?あれだけ自信満々に運命のひと!なんて自慢げにいってたのは、どこの誰かしら』
「うう……安アパートに部屋借りて、やっとのことで、新しい職場もみつかって、ようやくこれからってときに、《他に好きなひとができた。まだまだ遊びたいから、結婚は白紙に戻してほしい》とかいいだしてさ。部屋も出ていって、今はどこにいるかもわからない」
『劇団にはまだいるんでしょ?舞台観にいけば会えるじゃない』
「振られたんだよ?どんな顔して会えばいいの。もう、あんなに応援してたのに、裏切られるなんて」
『別にはじめてのことじゃないでしょうに。もう高柳さんのこと好きじゃなくなったの?』
「好きだけどさ。でももう駄目。結局いつものクズつかまえたパターン。ほら、お酒美味しいでしょ」
『格別よ。アンタが運命の相手に出会うまで、この楽しみが続くと思ったら、本当幸せ』
「結局私も冬真の遊び相手のひとりにすぎなかったんだよね。あれだけドラマチックに再会して、運命だなんだって盛り上がったのは、なんだったんだろう。
みんなにあんなことしてるのかな。
私、全然特別じゃなかったってこと?
あんな男のために、辛い時期も耐えて、世間にいいたい放題いわれて、仕事もなくしてさ。お母さんにも迷惑かけて……それで棄てられたんじゃ割に合わないよ。
お母さんにも、婚約者つれていくからっていっちゃったのに……。
調子のいいクズにまた棄てられた。
……もう、立ち直れない」
『あら、そんなに高柳さんに未練があるならもう一度付き合いたいっていってみれば?』
「どうせ冬真は本気になんかならないよ。また遊ばれて傷つくのは、もううんざり。
冬真ならって思ったのに、運命のひとだって思ったのに、あんなんただの女好きじゃん。
結婚したってすぐ浮気されるよ。麗香さんみたいにさ。
冬真のいうことを、信じるほうが馬鹿。
もう、冬真のことはきっぱり忘れる。
少し時間はかかるだろうけど、もう冬真にとらわれることはやめるよ。
チカのいう通り、冬真とは出会わなかったんだって、そう思うことにする。
もう、こんなん、いらない」
テーブルに突っ伏していた未来は、やおら顔をあげると、左手薬指の指輪を外し、テーブルに叩きつけた。
『あらあら、荒れてるわねえ。本当に高柳さんのことはもういいの?』
「いいんだって。冬真と付き合ったって辛いだけ。運命の恋人は冬真じゃなかった。錯覚だったんだよ。運命のひとは、他にいるんだ」
『もったいないわねえ。あれだけ燃え上がってたのに。あたしには、お似合いにみえたけど』
「じゃあ、チカにあげる。チカ、付き合ってみたら?」
口元を、ジョッキで隠し、チカはビールをあおる未来にきこえないくらいの小声で呟いた。
『ふうん。もったいない。運命のひとに、ようやく会えたのにねえ』
未来の耳には届かないチカの嘲笑。
未来はすでに、運命の相手と出会っている。
今も、高柳冬真は、未来が自分のもとに帰ってくると小さな希望を抱いて、未来を待っている。
未来が気づきさえすれば、念願の運命の恋人との結婚が叶えられる。
しかし、未来が高柳と復縁する可能性はほぼないだろう。
チカは、そう踏んでいる。
高柳を逃せば、未来の婚期は遠のくだろう。
そうすれば、美味い酒を呑むことができる。
酔った未来をみながら、チカは笑いを堪えることができない。
馬鹿な女。
本当に、男を見分けるセンスがないんだから。
また、あたしが男を斡旋してあげるしかないかしらね。
きっと、もうアンタに運命のひとは現れないわ。
でもね、それでいいの。
『サキの不幸も、そのうち、はじまるころかしらね』
酔いつぶれてテーブルに突っ伏したまま眠ってしまった未来の顔をみながら、チカは思い出したように独りごちた。
いい気分になって、チカが追加のビールを飲んでいると、目を覚ました未来が、頬を紅潮させながら、とろんとした目つきでチカを見上げた。
「おふかい……」
『え?』
「今度のオフ会、チカ行く?」
『オフ会?なによ、やぶからぼうに』
チカの飲酒以外の趣味は、オンラインゲームだ。
未来も、チカの影響でゲームをはじめた。
陸に奪われなかった愛用のノートパソコンで、ゲームは続けていた。
辛い状況のなかにあっても、ゲームに没頭することで、ストレスを紛らわせていた。
そのオンラインゲームの、オフ会に誘われているのだ。
チカも未来も、オフ会に行ったことはない。
顔も名前も知らない画面の向こうの仲間と、現実で会うことに躊躇いがあったからだ。
『行く気なの?アンタ、オフ会』
「うん。行ってみようかなあ。なに着ていけばいいんだろ。素敵なひとと出会えたらいいな。ゲームを通してコミュニケーションは取ってるんだから、話が合わないっていう心配はないよね」
チカは心底、呆れた声でため息混じりに頬杖をついて、赤ら顔の未来を眺めた。
『アンタねえ……。オフ会は合コンじゃないのよ。出会いを求めて行く場所じゃないの。
純粋にゲームが好きなひとが集まる場なんだから、あからさまに男漁りにきたら、みんな引くわよ』
「でもさあ、失恋の傷は新しい恋で癒やせ、みたいなこというじゃない?
冬真のことを忘れるには、新しい恋が必要なんじゃないかなって思って」
『さっきまで立ち直れないとかいってたのは誰よ。本当アンタって根っからの恋愛体質よね。呆れてものもいえないわ。愚かな女』
「なんとでもいってよ。とにかく、私は運命のひとと出会いたいの!早く結婚したいのよ!
それだけのことなのに、それ以上は望まないのに、どうして縁結びの神様は、叶えてくれないんだろう。
どうすれば私は幸せになれるの?」
滑稽なまでに自分の思惑にはまっていく未来に、チカは内心で必死に笑いを堪えていた。
『まだまだお祈りが足りないんじゃない?
慎ましく暮らして、高望みしなければ、いつかはきっと相手が現れるわよ』
高柳さんのような、ね、という言葉をチカはぐっと喉で押し潰す。
これだけ発破をかけたのに、未来の心は高柳からどんどん離れていく。
理想の展開だ。
高柳には悪いが、彼がどれだけ改心しようと、もう遅い。
彼が犯した過ちが、足を引っ張り、未来のなかで揺るがなかったはずの、高柳に対する信用の一切を奪っていったのだ。
自業自得ね。
未だ、まだ見ぬ運命の相手がいるはずだと、心を弾ませる未来を、チカは嘲るように笑っていった。
『あたしも結婚相手、一緒に探してあげるから、これに懲りずに恋愛続けてね』
「チカ!ありがとう。うん、私、頑張るね。
いつか運命のひとと結婚して、チカの手を煩わせないようにするから。
私の取り柄は、恋愛体質しかないもん。
いつか絶対みつけるんだ、運命の相手を!」
『はいはい、ほどほどに頑張んなさい。
いちいちアンタを助けに行けないんだからね、殺されるようなことだけにはやめてちょうだい』
「怖いなあ……そんなこといわれると。
なるべく、そうならないようにするね」
『なるべくじゃない。絶対!そんなことにならないようにするの』
「はーい」
『じゃ、未来の新しい門出を祝って……』
未来とチカが目を合わせる。
「『乾杯ー!』」
幸せそうにアルコールを摂取する未来を満足げに見ながら、チカは心のなかだけで毒づいた。
そう、あなたは、不幸なままでいいの。
これからも、あたしを愉しませてよね。
クソ女。
いつかの夜。
月明かりすら差さない、じめじめした部屋で、スマホの画面が放つわずかな光りが、無表情の未来の顔をほの暗く照らしていた。
画面には、高柳冬真のスマホの番号が表示されている。
番号を消去しようとして、スマホに触れる寸前で、ふと見えざる幽霊かなにかに掴まれたように、未来の手が止まる。
ため息をつきながら、ラインの画面に切り替える。
《とうま、あいたい》
そこまで文章を打ちこむが、送信ボタンを押す勇気が出ない。
うろうろと、未来の指が画面の付近をさまようあいだに、夜は、普段通りの顔をして、過ぎ去っていった。
水平線の向こうに、夕陽が沈んでいく。
燃えるような赤と、群青のコントラスト。
ざあっと、寄せては返す波の音。
海風が運ぶ潮の匂い。
そばを走り去る車のエンジン音。
高柳冬真は、ひとけのない海岸に、ひとり立っていた。
ぼんやりと波をみつめていると、ザクッと海岸の砂を踏みしめる足音がして、「未来?」と振り向く。
振り向いた先、真っ赤な日差しを浴びながら、冬真のほうへと歩いてきたのは、未来ではなかった。
冬真は驚きに目を見開く。
「チカ……近松さん……どうしてここに?」
『久しぶりね、高柳さん。未来のふりをしてあなたを呼び出したの。騙しちゃってごめんなさいね』
「いえ……でも、どうして近松さんが……」
『わからない?あなたが契約を破ったからよ』
チカがそう告げると、高柳は体を90度折り曲げて、頭を下げ、「すみませんでした!」と叫んだ。
チカは冷たく高柳を見下ろすといった。
『あなた、遊び相手を探してたんでしょう?
あたしは、あくまで遊び相手として未来を斡旋したのよ。
それがなに?本気になった?結婚する?
話が違うわ。
悪いけど、結婚を許すわけにはいかないわね』
すると、なりふり構わずに、高柳は砂浜に土下座した。
「すみませんでした!……確かに、最初は遊ぶだけのつもりで、未来に近づきました。
でも、今は……未来を本気で好きになってしまって、未来が、なにより一番大切で……」
夕陽が映える砂浜に、高柳がぼとぼとと、大粒の涙を落としながら懇願する。
「どうか、未来との結婚を許してください。
彼女は、運命のひとなんです!」
砂浜の砂に、頭を埋めるように額を擦りつけながら、高柳は切実に訴える。
そんな高柳を冷酷な瞳で見下ろしながら、チカは腕を組んだ。
『認められないわ。あたし、未来に幸せになられちゃ困るのよ』
「そんな……どうして……?」
『あの子の不幸話を肴に酒を呑むのがあたしの最大の幸せな瞬間なの。
男に無惨に棄てられて、男運のなさを、盛大に嘆くあの子の愚痴をききながら、酒を呑むのが一番のストレス解消なのよ。酒の美味さも桁違いだわ。
それを、失うわけにはいかないの。
あたしのために、あの子には、とことん不幸でいてもらわなきゃ。
そのために、あなたみたいな、付き合うと不幸な目に遭うこと間違いなしのクズと、未来を出会わせてきたのよ。
全ては、あたしのため。
だから、結婚なんて認めるわけないでしょう?
わかった?』
「そんな……ひどい……」
『あんたにいわれる筋合いないわ』
ぴしゃり、とチカが高柳の言葉を撥ねつける。
「どうして、そこまで未来を不幸にすることにこだわるんですか?どうして未来を、そこまで恨んでいるんですか?」
『恨む?別に未来を恨んでなんかいないわ』
「だったら、どうして……」
『あたしはね、女が嫌いなの。未来だけじゃない、女という生き物が、ひとりの例外もなく、大嫌い。
男と結ばれて幸せになる?
男をたぶらかすことしか脳のない、低俗な女をみていると、虫酸が走るわ』
「どうしてそこまで……」
チカは、少し考えるように口を閉ざす。
腕組みを解くと、遥か彼方の水平線に沈みゆく夕陽に目を細め、視線を遠くに投げながら再び口を開いた。
『……そうね。こんなこと急にいわれても、理解できないわよね。
いいわ。順を追って話しましょう。
あたしがなぜ女を嫌うようになったのか、その理由を、話してあげる』
一度、唇を舐めると、チカは宣言通り話しだした。
『あたしね、高校時代まで、100キロ超えの、デブで、ブサイクで、冴えない眼鏡をかけたうえにオカマだったの。
クラスメイトの女たちが、嘲りの対象にするのにぴったりの条件を揃えてたわけ。
女たちは、あたしの見た目を、隠しもせずに馬鹿にして、嗤ったわ。
ひとり残らずね。
悔しかった。
許せなかった。
男に依存して、色目を使うことしかできない、ふしだらな女に、自分は嗤われていたんだって思ったら、見返してやりたいと思った』
「ちょ、ちょっと待ってください!オカマ?
近松さん、男なんですか?」
堪えきれずに、高柳はチカの話を遮った。
『そうよ。見えないでしょ?努力したのよ。信じられないなら……そうね』
チカは、すうっと深く息を吸うと、『動くな!警察だ!』と、野太い男性の声で叫ぶと、『こんな感じ。どう?』と薄く笑って、首を傾げてみせた。
間違いなく、それは男の声帯から放たれた声だった。
ぽかんとした顔で見上げてくる高柳をみて、風になびく、緩くウェーブがかったブラウンの長い髪を手で押さえながら、チカは満足そうに微笑んだ。
『面白くなってきたから、ついでにあたしの本名教えてあげる。あたしね、近松史朗っていうの。ダサいでしょ?笑えるでしょ?』
絶句したまま、高柳はチカを見上げることしかできない。
海岸が濃い碧に染まる。
チカの昔語りは続く。
『いいのよ、笑って。続けるわね。
高校を卒業したあと、あたしはダイエットをはじめた。
両親や親戚は、田舎特有の気質のせいもあって、息子であるあたしがオカマであることを近所に知られることを嫌ったし、あたしが女になりたいって打ち明けた瞬間に、勘当された。
もうどうでもいいことだけど、本当に理解のない両親だったわ。
高校卒業を機に家を出て、一度も実家には帰っていない。もう一生帰らないでしょうね。
たとえ両親が死んでも。
お葬式に行ったとしても、幽霊になってまで、恥ずかしいから来るなってあたしを追い出すでしょうし。
ま、そんなことは、本当にどうでもいいことだったわね。
話が逸れたわ。
未来と、もうひとりサキって子と知り合ったのは、こっちにきて大学に入学してすぐのことだった。
だから、未来は、あたしがデブで男の格好をしていたころの姿を知ってる。
未来とサキは、ダイエットのサポートをしてくれたり、痩せたあとのあたしに、メイクを教えてくれたり、洋服を買うのに付き合ってくれた』
「そこまで親しくしていた未来にどうしてこんな仕打ちを……?未来は、近松さんに、優しくしてくれたんでしょう?」
チカは淡白に突き放す。
『関係ないわ。親友だろうが友達だろうが、例外なんてない。女の不幸はあたしの幸せ。だって、みんな等しく女なのよ?同じ女という生物を、どうやって区別しろっていうの?どうやって違いを探せっていうの?親友だからなに?それが、他の女と未来を分ける違いになるの?
あたしにはわからない。
ねえ、あなたなら、どうやってひとを見分ける?違いを探す?例外を作れる?
わからない。本当にわからないわ』
チカは、途方に暮れたように、まるで幼い子どもが、大人に問うように、真っ直ぐに高柳をみつめる。
高柳は言葉を失った。
チカの、言葉の意味がわからない。
高柳の理解を超えた範疇の考え方で、常識で、チカという人間は生きている。
わかろうとしても、無駄なことだった。
陽が沈む。
海岸に冷たい風が吹く。
無言の時間が過ぎていく。
「どうすれば……認めてくれますか?」
『しつこい男ね。認めないっていってるでしょ』
押し問答が続く。
食い下がる高柳に根負けしたのか、街灯が照らすささやかな光りを背後にしたチカが、思案するように高柳を見下ろす。
「仕方ないわね。
じゃあ、交渉しましょう。
あなたが一生未来に近づかないと誓うのなら、未来にクズを斡旋するのをやめる。
未来を本当に愛しているなら、未来のために身を引けるでしょう?
他の男と結婚しても、未来の幸せを祝福してあげられるでしょう?」
唇を噛みしめた高柳の表情が絶望に染まる。
くす、と小さくチカが笑う。
『条件はもうひとつあるわ。
あなたに別れを告げられても、未来があなたこそ運命のひとだと、高柳さんのもとに戻ってきたら、そのときは、あなたたちが本物の運命の恋人だと認めてあげる。
結婚だってなんだって、好きにすればいいわ。あたしも祝福する。
どう?
あなたは、未来が自分のもとに帰ってくると、信じられるかしら?
未来は、あなたに棄てられたと思ってもなお、まだあなたを愛するかしら?
なりふり構わずに、あなたしかいないと、自分を棄てたあなたにすがりつくかしら?
いつ帰るともしれない、帰ってこない可能性が高い恋人を、あなたは待ち続けられる?
悪いけど、あなたと未来を引き離す手段なんて、あたしには、山ほどあるのよ。
変な気は起こさないことね。
……これ以上未来に、不幸になってほしくなければ』
チカの、理不尽極まりない条件に、高柳は声も出せずに膝立ちになったまま、しばらく放心していたが、数秒が過ぎるうち、虚ろだったその瞳に、強い意志を宿した。
「待ちます。未来を信じます。俺たちは、運命の糸で結ばれた相手なんだから」
3月29日(金) 仕事帰りの居酒屋にて
「またやられたよー」
早くも酔いが回った未来が、呂律が怪しい口調で、チカ相手にくだを巻いていた。
『もう棄てられたの?あれだけ自信満々に運命のひと!なんて自慢げにいってたのは、どこの誰かしら』
「うう……安アパートに部屋借りて、やっとのことで、新しい職場もみつかって、ようやくこれからってときに、《他に好きなひとができた。まだまだ遊びたいから、結婚は白紙に戻してほしい》とかいいだしてさ。部屋も出ていって、今はどこにいるかもわからない」
『劇団にはまだいるんでしょ?舞台観にいけば会えるじゃない』
「振られたんだよ?どんな顔して会えばいいの。もう、あんなに応援してたのに、裏切られるなんて」
『別にはじめてのことじゃないでしょうに。もう高柳さんのこと好きじゃなくなったの?』
「好きだけどさ。でももう駄目。結局いつものクズつかまえたパターン。ほら、お酒美味しいでしょ」
『格別よ。アンタが運命の相手に出会うまで、この楽しみが続くと思ったら、本当幸せ』
「結局私も冬真の遊び相手のひとりにすぎなかったんだよね。あれだけドラマチックに再会して、運命だなんだって盛り上がったのは、なんだったんだろう。
みんなにあんなことしてるのかな。
私、全然特別じゃなかったってこと?
あんな男のために、辛い時期も耐えて、世間にいいたい放題いわれて、仕事もなくしてさ。お母さんにも迷惑かけて……それで棄てられたんじゃ割に合わないよ。
お母さんにも、婚約者つれていくからっていっちゃったのに……。
調子のいいクズにまた棄てられた。
……もう、立ち直れない」
『あら、そんなに高柳さんに未練があるならもう一度付き合いたいっていってみれば?』
「どうせ冬真は本気になんかならないよ。また遊ばれて傷つくのは、もううんざり。
冬真ならって思ったのに、運命のひとだって思ったのに、あんなんただの女好きじゃん。
結婚したってすぐ浮気されるよ。麗香さんみたいにさ。
冬真のいうことを、信じるほうが馬鹿。
もう、冬真のことはきっぱり忘れる。
少し時間はかかるだろうけど、もう冬真にとらわれることはやめるよ。
チカのいう通り、冬真とは出会わなかったんだって、そう思うことにする。
もう、こんなん、いらない」
テーブルに突っ伏していた未来は、やおら顔をあげると、左手薬指の指輪を外し、テーブルに叩きつけた。
『あらあら、荒れてるわねえ。本当に高柳さんのことはもういいの?』
「いいんだって。冬真と付き合ったって辛いだけ。運命の恋人は冬真じゃなかった。錯覚だったんだよ。運命のひとは、他にいるんだ」
『もったいないわねえ。あれだけ燃え上がってたのに。あたしには、お似合いにみえたけど』
「じゃあ、チカにあげる。チカ、付き合ってみたら?」
口元を、ジョッキで隠し、チカはビールをあおる未来にきこえないくらいの小声で呟いた。
『ふうん。もったいない。運命のひとに、ようやく会えたのにねえ』
未来の耳には届かないチカの嘲笑。
未来はすでに、運命の相手と出会っている。
今も、高柳冬真は、未来が自分のもとに帰ってくると小さな希望を抱いて、未来を待っている。
未来が気づきさえすれば、念願の運命の恋人との結婚が叶えられる。
しかし、未来が高柳と復縁する可能性はほぼないだろう。
チカは、そう踏んでいる。
高柳を逃せば、未来の婚期は遠のくだろう。
そうすれば、美味い酒を呑むことができる。
酔った未来をみながら、チカは笑いを堪えることができない。
馬鹿な女。
本当に、男を見分けるセンスがないんだから。
また、あたしが男を斡旋してあげるしかないかしらね。
きっと、もうアンタに運命のひとは現れないわ。
でもね、それでいいの。
『サキの不幸も、そのうち、はじまるころかしらね』
酔いつぶれてテーブルに突っ伏したまま眠ってしまった未来の顔をみながら、チカは思い出したように独りごちた。
いい気分になって、チカが追加のビールを飲んでいると、目を覚ました未来が、頬を紅潮させながら、とろんとした目つきでチカを見上げた。
「おふかい……」
『え?』
「今度のオフ会、チカ行く?」
『オフ会?なによ、やぶからぼうに』
チカの飲酒以外の趣味は、オンラインゲームだ。
未来も、チカの影響でゲームをはじめた。
陸に奪われなかった愛用のノートパソコンで、ゲームは続けていた。
辛い状況のなかにあっても、ゲームに没頭することで、ストレスを紛らわせていた。
そのオンラインゲームの、オフ会に誘われているのだ。
チカも未来も、オフ会に行ったことはない。
顔も名前も知らない画面の向こうの仲間と、現実で会うことに躊躇いがあったからだ。
『行く気なの?アンタ、オフ会』
「うん。行ってみようかなあ。なに着ていけばいいんだろ。素敵なひとと出会えたらいいな。ゲームを通してコミュニケーションは取ってるんだから、話が合わないっていう心配はないよね」
チカは心底、呆れた声でため息混じりに頬杖をついて、赤ら顔の未来を眺めた。
『アンタねえ……。オフ会は合コンじゃないのよ。出会いを求めて行く場所じゃないの。
純粋にゲームが好きなひとが集まる場なんだから、あからさまに男漁りにきたら、みんな引くわよ』
「でもさあ、失恋の傷は新しい恋で癒やせ、みたいなこというじゃない?
冬真のことを忘れるには、新しい恋が必要なんじゃないかなって思って」
『さっきまで立ち直れないとかいってたのは誰よ。本当アンタって根っからの恋愛体質よね。呆れてものもいえないわ。愚かな女』
「なんとでもいってよ。とにかく、私は運命のひとと出会いたいの!早く結婚したいのよ!
それだけのことなのに、それ以上は望まないのに、どうして縁結びの神様は、叶えてくれないんだろう。
どうすれば私は幸せになれるの?」
滑稽なまでに自分の思惑にはまっていく未来に、チカは内心で必死に笑いを堪えていた。
『まだまだお祈りが足りないんじゃない?
慎ましく暮らして、高望みしなければ、いつかはきっと相手が現れるわよ』
高柳さんのような、ね、という言葉をチカはぐっと喉で押し潰す。
これだけ発破をかけたのに、未来の心は高柳からどんどん離れていく。
理想の展開だ。
高柳には悪いが、彼がどれだけ改心しようと、もう遅い。
彼が犯した過ちが、足を引っ張り、未来のなかで揺るがなかったはずの、高柳に対する信用の一切を奪っていったのだ。
自業自得ね。
未だ、まだ見ぬ運命の相手がいるはずだと、心を弾ませる未来を、チカは嘲るように笑っていった。
『あたしも結婚相手、一緒に探してあげるから、これに懲りずに恋愛続けてね』
「チカ!ありがとう。うん、私、頑張るね。
いつか運命のひとと結婚して、チカの手を煩わせないようにするから。
私の取り柄は、恋愛体質しかないもん。
いつか絶対みつけるんだ、運命の相手を!」
『はいはい、ほどほどに頑張んなさい。
いちいちアンタを助けに行けないんだからね、殺されるようなことだけにはやめてちょうだい』
「怖いなあ……そんなこといわれると。
なるべく、そうならないようにするね」
『なるべくじゃない。絶対!そんなことにならないようにするの』
「はーい」
『じゃ、未来の新しい門出を祝って……』
未来とチカが目を合わせる。
「『乾杯ー!』」
幸せそうにアルコールを摂取する未来を満足げに見ながら、チカは心のなかだけで毒づいた。
そう、あなたは、不幸なままでいいの。
これからも、あたしを愉しませてよね。
クソ女。
いつかの夜。
月明かりすら差さない、じめじめした部屋で、スマホの画面が放つわずかな光りが、無表情の未来の顔をほの暗く照らしていた。
画面には、高柳冬真のスマホの番号が表示されている。
番号を消去しようとして、スマホに触れる寸前で、ふと見えざる幽霊かなにかに掴まれたように、未来の手が止まる。
ため息をつきながら、ラインの画面に切り替える。
《とうま、あいたい》
そこまで文章を打ちこむが、送信ボタンを押す勇気が出ない。
うろうろと、未来の指が画面の付近をさまようあいだに、夜は、普段通りの顔をして、過ぎ去っていった。