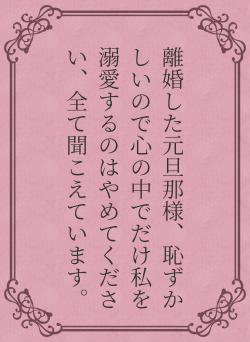12月8日(金) 仕事終わりの病院の敷地にて
仕事を終え、帰宅するために、未来が勤務先の病院を出ると、「あ、あの……」とか細い声に呼び止められ、振り返った。
振り向いた先には、未来とそう年齢の変わらなそうな長身の男性が立っていた。
若干戸惑いながらも、「はい?」と返事する。
邪険にするわけにもいかない。
声をかけてきたのは、顔見知りの男性だった。
男性は自身の靴の辺りに視線を落とすと、もじもじと、女々しい動作をしながら、言葉を続ける。
「小野寺さん、ですよね」
「……そうですけど」
「あの……実は、僕……」
12月10日(日) 焼き鳥屋にて
『ナンパされた?』
「そう。一昨日の仕事帰りに。仕事終わるまで待ってたみたいで、病院を出たところで声をかけられた」
『仕事が終わるまで待ってた?ちょっと、それって、またストーカーのたぐいじゃないの?』
「うーん、まだわからない。でも、一応顔見知りではある」
『顔見知り?』
「うん。うちの病院に通院してる患者さんなの。左腕を骨折して、しばらくうちに通ってる。だから、私の名前を知ってても不思議じゃない」
『ふーん、どんなひと?』
「すごいイケメン。すらっとしてて、顔もすごい整ってる、ちょっと陰のある感じのひと」
『それが、なんていってきたの?』
「病院に通ってるうちに、私をみかけて、好きになったって。付き合ってほしいっていわれた」
『……で、なんて返事したの?』
「ちょっと待ってほしいって。まだ高柳さんのことよくわかんないし、まずはお友達からって」
『アンタにしては理性的な対応。告白されただけですぐに頭に血がのぼって、付き合う、っていったのかと思った』
「色々経験してるからね、私も。しなくてもいいことまで。さすがに前みたいに後先考えずに付き合うことはしないよ」
『相手、高柳さんていうんだ』
「そ。高柳冬真さん。すっごいイケメンではあるけど、用心するに越したことはないから、もうちょっと様子見かも」
『そのいいかたからすると、その彼に運命は感じなかったわけね。……ん?高柳冬真……?』
「そうだけど……?」
『高柳冬真って……。ちょっと待ってよ』
チカはスマホを取り出すと、検索をはじめた。
未来もその様子を興味津々にみつめる。
「どうしたの?」
チカは、珍しく感極まったように興奮すると、スマホの画面を未来に見せてくる。
『高柳冬真って、もしかして、このひと?』
そこには、カメラ目線で、こちらを鋭く睨みつける高柳冬真が写っていた。
普段未来がみている高柳とは、雰囲気がだいぶ違うので、一瞬同一人物だと思えなかった。
「あ、そう、このひと。高柳さん」
『嘘!すごい!本物の高柳冬真に会ってるのね!羨ましいわ』
「なにものなの?高柳さんて」
『『絶命』に出てた俳優よ。あたしあの映画、3回も観にいったんだから』
「ああ、毎回号泣したって、あの映画か。なるほど俳優さんね。どうりで顔が整ってると思った」
『ちょっと待ってよ……。少し前のネットニュースでその名前をみた気がする……。あ!これだ。俳優の高柳冬真、撮影中の現場で事故、左腕を骨折、だって。やっぱりアンタに告白してきたの、高柳冬真だわ!』
チカがここまで熱く男について語るのは、珍しい。
『絶命』に心酔していたようだし、チカの熱にあてられて、未来も高柳に興味を抱きはじめる。
芸能人なんて初めてみた。
いわゆる芸能人オーラは感じなかったが、そんなひとに告白されたなんて、自慢話にできるかもしれない。
一体自分のなにを気に入ってくれたのだろう。
芸能界にいれば、綺麗な女優さんなんて飽きるほどいるだろう。
そんなひとたちを見慣れているであろう高柳が、何故自分を選んだのか。
未来の体が熱を持つ。
ああ、結局またいつもの恋愛モードに入ろうとしている。
自制を胸に決めたばかりなのに。
未来は、自分のなかにわだかまる熱気を冷まそうと、冷えたビールをあおる。
火照った体はなかなか冷めない。
高柳の顔が、頭に浮かんでは消える。
チカは、串刺しの焼き鳥をくわえながら、なおも高柳を検索している。
『『STARS』所属の25歳か。業界大手の事務所ね。高校在学中にスカウトされモデルデビュー。卒業後は俳優に転身。出演作も並べてあるけど、脇役のさらに脇役ってところね。代表作はなし。いわゆる売れない俳優ってやつね』
しかしチカは、満足そうに口角を吊り上げている。
『舞台もやってるのね。『絶命』でも演技力は光るものがあったもの。将来有望に違いないわ。舞台、やるならチケットでも取ってみようかしら』
チカは、いたく高柳を気に入っているようだ。
未来は、高柳が舞台に立っている姿を想像する。
胸が高鳴った。
トクン、と心臓が脈打つ。
観てみたい、と思った。
未来の知らない高柳の姿を。
恥ずかしそうに告白してきた高柳とは違う、凛々しい彼の姿を。
ああ、自分はどうしてこうも単純なのだろう。
高柳が、売れない俳優だと知った時点で、未来のなかに焦りが生まれる。
早く手に入れないと、誰かに掠め取れてしまうのではないか。
みすみす逃すわけにはいかない。
付き合ってから、彼のことを知っていったって遅くないのではないか。
少なくとも、向こうは未来を好きだといってくれている。
あとは、未来の気持ちひとつだ。
友達からはじめましょう、でも、付き合うこと前提で。
冷静な対応をしてしまった以上、すぐに付き合うことは軽い女にみられるからできない。
芸能人だと知って、それで付き合ってみたくなったなんて、口が裂けてもいえない。
ミーハー極まりないからだ。
そんなこと知られれば、せっかく彼から寄せてくれた好意が、翻されるかもしれない。
それだけは避けたい。
きちんと素性のはっきりした相手。
立場上、はじめから未来を騙すために近づいてきたとも思えない。
自分は世間を知らない素人だが、高柳にとって今は大切な時期で、イメージも大切な職業であることから、未来はそう判断した。
彼が誠実なひとであると、決して下心だけで自分に近づいてきたわけではないと確信できたら、新しい恋をするのも悪くないかもしれない。
まだ25歳と若く、売り出し中の俳優であることを考えると、付き合ってすぐに結婚というのは、難しいかもしれない。
結婚を焦る未来にとっては、痛いタイムロス。
それを上回るなにかを彼が与えてくれたなら、それは運命の相手だ。
彼がブレイクしたりすれば、結婚は更に遠のく可能性だってある。
けれど、それこそが運命というのなら。
未来は、待つ決意を持つことができる。
『顔、にやけてるわよ』
冷たいチカの声で、はっと未来は我に返った。
いけない、またチカにお説教される。
「す、すぐに付き合うとはいわないよ。うん、いわない。彼のことをよく知ってから……」
『まだなにもいってないけど。付き合う気は大いにあるってことね』
「だ、だって、チカが煽るから!なんか惜しい気がしてきて……。今逃したら後悔するかもって焦ったというか……」
『まあ、あたしも興奮しすぎたわ。でも、煽ってはいない。あたしのせいにするのはやめてよね』
「わかってるって。慎重に、でしょ?彼が遊びでなく真剣に私のことを想ってくれてたのなら、私も誠実に向き合うよ。それならいいでしょ?」
『いちいちあたしに確認とる必要はなし。あたしはアンタの保護者じゃないんだから』
「え、似たようなものでしょ?」
『ちょっと、やめてよね。あたしに依存しすぎ。なんであたしがアンタの世話しなきゃならないのよ。いくつまであたしに頼るつもり?アンタ、あたしが死んだら破滅するんじゃないの?』
「するよ。だから、チカはいつまでも私の面倒をみなきゃいけない。私が男選びに失敗したら、正義のヒーローみたいに助けてにきてくれて、愚かな私に説法をする。私が幸せな結婚をするまで、チカは私の親みたいなもん」
『やだやだ、そんな人生いやよ!なにが悲しくて自分のこと愚かとかいってるアホ女のためにあたしの時間を削らなきゃいけないの!アンタにとって貴重な時間はあたしにとっても貴重な時間なのよ』
「だから、私が結婚すればチカはお役御免なわけよ。早く私から解放されたかったら、協力して運命の相手探しを手伝うしかないの」
『厚かましいわね、アンタ!全然あたしを巻きこんで悪いと思ってないのね。大学時代のあたし、こんな女と親しくなっちゃ駄目よ、あたしの人生が破滅するわ!』
やけ酒をあおったチカの悲痛な声が、焼き鳥を焼く煙とともに舞い上がり、換気扇から冬の街を流れ、消えていった。
12月15日(金) ランチタイムのそば屋にて
『相当夢中になってるみたいね』
熱々の天ぷらそばに息を吹きかけながら、チカがからかうようにいった。
相変わらずチカは猫舌だ。
それを指摘すると、不機嫌になって『第一子は総じて猫舌なのよ。親に大事にされた証』と、決まっていう。
しかし今の未来には、チカをからかう余裕すらない。
そう、実際、未来は夢中になっていた。
高柳冬真に。
あれから、チカにお情けでプレゼントされたプレイヤーで、高柳が出演した映画やドラマを漁るように毎晩見続けていた。
ちらとでも映った高柳の姿を、何度も巻き戻しては、うっとりと彼に見惚れる。
学校が舞台のドラマでは、制服姿の生徒役のなかから、その他大勢の高柳を見つけ出すことに熱中したし、殺人犯の青年役を演じたドラマを観たときには、役名がついたことに感激した。
配信でのみ視聴できる作品では、3番手、4番手の役柄も着実に増えてきている。
近年は、漫画やアニメなど2次元の作品を舞台化したミュージカルなどにも出演していて、かなりの美声を響かせている動画も、見漁っていた。
高校生から大学生、新社会人役が多いが、この先更に、演じる役柄の幅も増えれば、たくさんのひとに高柳冬真という役者を知ってもらえるかもしれない。
輝かしい高柳の将来に思いを馳せ、未来の頬は緩みっぱなしだ。
高柳の怪我は完治していた。
しかし、彼は未来の勤務先までやってきて、夕食に誘ってくれる。
会うたびに、彼に驚かされる。
毎回、雰囲気が違うのだ。
前までは、どこか陰気な、陰のあるひとにみえたのに、今は爽やかな好青年の笑みを浮かべている。
未来に、自分の職業が俳優だと知られたと知った彼は、どこか恥ずかしそうに役柄が憑依するのだと語った。
実生活にまで役柄が影響するとは、大変な仕事なのだなあ、と感心せざるを得ない。
それだけ、高柳が演技派だということなのだろう。
天職を実際に仕事にできる高柳は、恵まれているほうなのかもしれない。
普段の彼は、飾らない年相応の青年で、連絡先を交換したあと、こまめに連絡をくれる。
地に足のついた、身の丈に合った生活を送っているようで、未来を連れていく店も、リーズナブルな場所ばかりだ。
変に背伸びしない、高柳の人柄が伺えて、好感度はうなぎのぼりだ。
画面越しに観る彼と、目の前で屈託なく笑う高柳をみるたびに、高柳の全てを知るのは、自分だけに与えられた特権のような気がして、妙にこそばゆい心持ちになる。
もっと高柳冬真という俳優を認知してほしい、けれど、皆が高柳の魅力に気づいたときには、すでに高柳は未来だけのものとなっている。
そんな明るい展望まで抱きはじめている。
恋に恋する暴走がはじまる一歩手前。
興味はあるが、特に仕事の話はきかない。
高柳に、自分が芸能人だから興味を持たれたと誤解してほしくないからだ。
しかし、何回目かのデートを重ねたとき、高柳のほうから、「今度出演する舞台を観にきませんか」と誘われた。
画面越しにしか観たことがなかった高柳の演技を間近でみられる。
未来はふたつ返事で了承したが、そこでふと考えて、「友達も連れて行っていいですか?」ときいてみた。
高柳は、少し驚きながらも、いいですよ、といってくれた。
ボロアパートを見られるのは恥ずかしいので、デートはいつも、アパート手前の公園で終わる。
吐く息が白く凍りつきそうな夜、高柳は、名残惜しそうに、初めて未来の冷え切った手を繋いできた。
ふたりは、まだ恋人ではない、あやふやな関係だった。
いつまでもは待てない、高柳のそんな意思表示のようにも思えた。
求められている。
高柳の真摯な瞳が、ひたと未来を見据える。
静寂が落ちる住宅街で、ふたりは無言でみつめあう。
やがて、未来の手が温まったころ、高柳がぽつりといった。
「稽古、本当に頑張っているんです。小野寺さんに観てほしくて」
未来は、彼に抱きつきたい衝動に駆られた。
それは、いじらしい愛情表現をしてきた高柳も、同じなのかもしれない。
ふたりは互いの意思を確認し合うように見つめ合ったあと、どちらからともなく手を離して、それぞれの帰路についたのだった。
舞台の幕が開いた。
ライブやコンサートに行ったことすらない未来にとって、舞台鑑賞というハードルはなかなかに高かった。
『だからってあたしを誘わなくてもいいんじゃない?』
一緒に劇場の席についたチカは、『せっかくの休みなのに』と不満な様子を隠そうともしない。
「高柳さんのファンなんでしょ?彼が出る舞台に興味ないの?チケット取るとかいってたのに」
『あれは、勢いよ。あたしは『絶命』のファンなの。『絶命』の片瀬智久には興味あるけど、高柳冬真のファンなわけじゃないわ。それに、アンタの恋人候補の晴れ舞台を一緒に鑑賞なんて趣味悪い』
片瀬智久とは、映画『絶命』で、高柳が演じた役名だ。
確か、あの映画でも彼は非業の死を遂げる役だった。
これから初日の幕が開く舞台でも、彼は悪役で、最後は死を迎える。
勧善懲悪で人気を博した漫画の舞台化。
原作の漫画を借りて読んできたが、またしても与えられた役柄が悪役ということに、歯がゆい思いもしている。
勧善懲悪の舞台なのだから、主人公が倒す悪がいなければ始まらないわけで、わかってはいるのだが、物足りなさを感じてしまのも事実だった。
早く主役を演じられる役者になってほしい。
早く賞を取れる役者になってほしい。
早く人気も知名度も高い役者になってほしい。
そんな複雑な思いを振り切るように、舞台が幕を開けた。
漫画の再現度の高さと、圧倒的なエンターテインメントの迫力に、2時間半、未来は息をするのも忘れて魅入っていた。
役者の熱量とそれを裏切らない演出。
観るもの全てを物語のなかに惹き込む引力。
高柳の役は、なくてはならないものだった。
彼の役がいるからこそ、正義とはなにかを考えさせられる。
一筋縄ではいかない現実の矛盾を孕んだ高柳の役は、勧善懲悪のなかにありながらも、果たして彼を悪役というだけの言葉に押しこめてしまっていいのかを考えさせられる。
正義と悪が、混濁するなか、彼は死を迎える。
そこに、すっきりした結末は訪れない。
彼は本当に悪なのか。
主人公がかざす正義とはなんなのか。
どちらが悪でどちらが正義なのか、その明確な答えを提示しないまま、舞台は終わりを迎える。
終演後、現実に戻れず呆然とする未来を引きずってチカは劇場をあとにした。
ついてきてよかったと、チカはため息をつきながら未来を引っ張って電車に乗る。
『全く手間かけさせないでよね』
電車に乗ったあとも、愚痴を垂れ流すチカを尻目に、未来は舞台で輝く高柳の姿をひたすら反芻していた。
高柳の演技力は圧巻だった。
主役を食ってしまいそうなほど、という感想を抱くのは、未来が高柳に特別な感情を感じているからだろうか。
約2時間半のあいだ観た舞台で、未来の脳裏に蘇るのは、脇役のはずの高柳の姿ばかりだ。
結婚相手に求める条件として、「尊敬できる」というのは、かなり上位にくる項目ではないかと、未来は思う。
それをいうと、今日の高柳は未来の想像の遥か上を行く才能を感じさせた。
尊敬する、どころかその才能に簡単にひれ伏せてしまえるレベルの。
頭が痺れたように思考が停止している。
目の前の風景すらぼやける。
完全に、のぼせ上がっている。
胸が絞めつけられて痛い。
高柳を想うたびに、吐息が熱を持つ。
彼の才能に、憧れさえ覚える。
そしてそれを自覚するたびに、なんの取り柄もない自分に失望する。
高柳は、こんな自分で本当にいいのだろうか。
もっと、彼の才能に相応しい相手がいるのではないか。
未来が空っぽの女だと知ったら、棄てられてしまうのではないか。
夜景が残像を残しながら流れていく。
未来の火照った体に、ガタンゴトンという電車の心地よい揺れが興奮を鎮めてゆく。
隣に座ったチカが、ことん、と事切れた人形のように、未来の肩に頭を預けてくる。
未来の面倒をみすぎて疲れたのか、眠ってしまったようだ。
未来は親友の寝顔を微笑ましげに眺めながら、スマホをバッグから取り出した。
何度も打ち損じながら、筋の通った文章を作成しようとする。
……上手くいかない。
未来は諦めて、ごくシンプルな言葉を終演後で疲れているであろう高柳に送信した。
『私と、お付き合いしてください』
12月25日(月) イタリアンレストランにて
夕食時の小洒落たイタリアンレストランは、カップルで溢れていた。
ワインをひとくち飲んだチカが、窺うように未来を見つめると、小首をかしげた。
『なんか、落ち着いたわね、アンタ』
「そう?満たされてるからかな」
未来は大人びた微笑を浮かべてみせた。
『上手くいってるんだ、高柳さんと』
「うん。あれからひとりでも舞台観に行ったし、彼も仕事のあいだに時間を作ってくれてデートしてる。順調だよ。
ねえ、きいて。冬真くんね、来年ドラマの準主役に決まったの。月曜日のドラマ枠の。
すごくない?やっぱり今やってる舞台が評価されたみたい。
……でも、撮影に入っちゃったらなかなか会えなくなるみたいで、嬉しいやら寂しいやら、複雑なんだよねえ。
今は寝る前にかかってくる電話で喋ることが楽しみ。
仕事も冬真くん見習って頑張るようになったし、そうしたら生活が上手く回るようになって、なんていうか、幸せ」
『いいことじゃない、忙しくなるなんて。売れっ子俳優まっしぐらね。変装もせずにデートしたらまずいんじゃないの?スキャンダルは、一番事務所が気を使ってるんじゃないの?』
「そうだね。なかなか外では会いづらくなるかもしれない。でもいいの。今は仕事に専念してほしいし、私と彼の絆はそんなことで壊れたりしないって信じてる。だって、この出会いは……」
『運命なんだから』
「当たり。不思議なの、今は不安が全くない状態で、彼を見守れてる。単純に彼が評価されることが嬉しいし、才能が認められてもっとたくさんのひとに彼の演技をみてほしい。冬真くんは、もっと早く発掘されてもよかった役者だよ。これからどんどん有名になって成功してほしい。それが叶うなら、私はいつまでだって彼のそばで支えるよ。……でも、恋人の座は、誰にも譲らない」
『献身的なんだか強欲なんだかわからないわね』
チカは、賑わう店内を見回して、ため息をつくようにいった。
『で、今日、愛しの彼は?恋人の一大イベントのクリスマスに、あたしなんかと過ごしてていいの?』
店内にも、窓からみえる大通りにも、イルミネーションに照らされたカップルが街を闊歩している姿が目立つ。
店にも、大きなクリスマスツリーが置かれ、きらびやかな電飾がチカチカと瞬いていた。
恋人にとっては特別な意味を持つ日。
この日のために恋人を作るひとも多い。
未来も、そうしようとしていた。
けれど今は、焦りを感じない。
街ゆくカップルたちを見ても、心は凪いだままだ。
未来はゆっくりワインを飲むと唇を笑みの形にした。
「仕事なんだって。ファンクラブのイベント」
『ファンクラブ?』
「そう。冬真くんにもあるんだよ、ファンクラブ。芸能人はカレンダー通りに休みがあるわけじゃないし、休みの日こそ仕事がある職業だから。そこは割り切らないとね」
『ファンクラブかあ……。売り出し中の若手俳優の恋人なんて、見動きが自由に取れない立場になんてよくなる気になるわね。高柳冬真に恋人がいるなんてファンが知ったらアンタ、後ろから刺されるんじゃない?』
「確かに、私にも推しがいたら、そう考えるかもね。応援してたのに、裏切り者って」
『アンタはファンクラブ入らないの?』
「私も入ろうかなっていったことあるんだけど、恋人とファンは違うからって冬真くんに断られちゃって。クリスマスは一緒に過ごせないけど、年末に少しだけ時間ができたから会おうって約束してる」
『じゃあ、年末年始は恋人がいるのに、基本的にスケジュールは空いてるわけね』
「まあね。ねえ、チカ、お正月に初詣、一緒に行かない?縁結び神社」
『気が早いわねえ。付き合ってる相手がいながら、まだ縁結びのご加護がほしいの?』
「彼と縁が離れませんようにってお祈りしたいの。彼の成功も祈願したいし」
『やっぱ強欲だわ、アンタ。神様もそこまで寛容じゃないわよ、きっと。願いはひとつだけにしなさいよね。
……それにしても、お正月、なんであたしのスケジュールが空いてるって決めつけてるわけ?』
「え?だってチカ、お盆も年末年始も帰省しないじゃない。友達だって私とサキしかいないし……予定、なんかあった?」
『……ないけど。友達が少ないっていうの、結構コンプレックスなんだから、思い出させないでよ。
家族とは、もう絶縁状態だし、あたし、もしかして孤独なんじゃない……?』
「あれ、今更気づいた?仕事をしすぎるのも考えものだねえ。
趣味の合う仲間とか作ってプライベート充実させたら?」
『あたしのこの性格に付き合ってくれる友達なんてこの歳から新しくみつけるのはなかなか難しいんじゃないかしら』
「まだ家族と喧嘩してるの?大人になってチカから歩み寄ってみたら?親だって歳とるし、絶縁したまま死んじゃったら後悔するんじゃない?」
『あたしだって歩み寄ろうとしてるわよ。頑なにあたしを拒絶してるのは向こうなんだから、どうしようもないじゃない』
チカは、ぶすっと不機嫌そうにワインを煽る。
「まだ家族のひと理解してくれないの?」
『もう永遠に理解なんてできないわよ、頭が堅いんだから。親だから、どんな子どもでも受け入れてくれる、なんて幻想だわ』
「ふうん。寂しい話だね」
『もう慣れたわ。だから、あたしには仕事が必要なの。家族にも頼れずに、ひとりで生きていくしかないんだから。甘いこといっていられないのよ』
「うちも親、離婚してるから、家族には苦労させられてきたけど、お母さんは私のことちゃんと育ててくれたし、感謝しないとかな」
『当たり前。感謝しなさい』
「だから、やっぱり早く結婚して孫の顔みせてあげるのが親孝行なのかな。……やばい、また焦ってきたかも……」
『自分で自分を追いこんで、馬鹿じゃないの?今は高柳さんと上手く関係を続けることが親孝行への近道よ。慌てず焦らずがっちり高柳さんを離さずにしがみついてなさい』
「わかった!やっぱり縁結び神社行こう!」
『仕方ないわねえ……。ま、いいわ。初詣、行きましょう。あたしもお願いしてあげる。未来と高柳さんが、なんのトラブルもなく結婚できますようにって』
「……トラブルがあるの前提でお願いしてない?」
『してる。アンタがなんのトラブルもなく男と付き合えるわけないもの。でも、運命の恋人なら、どんな試練だって乗り越えられるでしょ?』
「もちろん!冬真くんとなら、なんだって乗り越えられる!運命の恋人だもん!」
拳を握りながら、叫んだ未来を、周りのテーブルの客たちがくすくすと笑い合っている。
恋人たちが未来たちを優越感たっぷりにみつめている。
でも、気にならない。
見てろよ、カップルたち!
私は、あんたたち以上の幸せを手に入れてみせる。
『ちょっと、恥ずかしい!』
チカが未来の服の裾を掴んで座らせる。
すっかり酔った未来は、高柳との未来を想像して、過ぎゆく聖夜をいい気分で終えたのだった。
12月30日(土) ホテルにて
来年ブレイクしそうな俳優ランキングに、高柳冬真がランクインした。
高柳は、仕事についてあまり多くを語らないが、世間の風潮が、高柳への期待値が高まっているのは、未来も感じはじめていた。
来年早々はじまるドラマで注目が更に集まるのは間違いない。
こつこつとキャリアを積み上げてきた、高柳の努力の結晶ともいえる結果だった。
風向きは確実に変わっている。
世間は高柳に気づきはじめている。
ブレイク前に彼と出会えたのは幸運だった。
スターへの階段を、駆け足で昇っていく彼の後ろ姿を、未来は必死で追いかけていた。
今、高柳のスケジュールは着実に埋まっている。
そんなブレイク前夜、わずかな時間を利用して、未来と高柳は逢瀬を重ねていた。
「こんなホテルでごめん」
けばけばしい色で彩られた部屋で、バスルームからでてきた高柳が、長く伸びたブラウンの髪をタオルで拭いながらいった。
甘い時間の余韻に浸っていた未来は、首を左右に振ると、自分もシャワーを浴びようとベッドから立ち上がる。
未来の色白で柔らかな体を見た高柳は、シャワーを浴びたにも関わらず、またも未来の体を抱き寄せた。
首筋にキスを落とし、ベッドに押し倒す。
「もう……これから仕事なんでしょ?」
甘い誘惑に負けそうになりながら、未来は高柳の体をやんわりと押し返す。
しっかりと鍛えられた胸板に顔を埋めると、
彼の匂いを少しもこぼさないように、深く息を吸う。
我ながら変態的な行為だと思う。
でも、高柳のなにもかもを逃したくないという独占欲に抗えない。
永遠に続いてほしいと願いながらも、刹那の快楽に溺れる退廃的なこの瞬間も、未来はたまらず好きだった。
重い女になりたくない。
でもきかずにおれない。
「冬真……私のこと好き……?」
絶え間なくキスの雨を降らせる高柳の合間を縫って未来はそう問いかける。
荒い呼吸をしながら、「好きだよ。世界で一番未来が大切だ」あえぐように高柳は答えた。
お互いの体温で汗が滲む。
高柳の鼓動を感じる。
ああ、幸せだ。
今度こそ、遠い憧れを手に入れられるかもしれない。
結婚という、究極の愛の行き着く先を。
「仕事行かなきゃ」
高柳のそのひとことで、夢のような時間が終わる。
抱き合ったあとの気だるさを全身に感じながら、未来はベッドから、服を着る高柳を眺めていた。
愛し合ったあとの高柳はどこか冷淡だ。
現実が、未来にそう思わせた。
ずっと高柳と一緒にいたい。
甘えて抱き合ってキスをしていたい。
高柳をひとり占めして離したくない。
すっかり服を着終わった高柳は、今の今まで未来にみせていた、快感で蕩けそうな表情を一切消し、余所行きの顔に戻っていた。
未来を一抹の寂しさが襲う。
それでも未来は、笑顔を作っていった。
「うん、お仕事頑張って」
「未来がいるから頑張れるよ」
「……次、いつ会える?」
「……そうだな、次に休みが取れるのは……ちょっといつになるかわからないな」
「……そっか……。わかった、忙しいもんね、冬真。私のことは二の次でいいから。冬真が楽しくお仕事できるのが一番。電話で話せるだけで私は満足だから」
「我慢強いな、未来は。もう少しわがままでも可愛いと思うけど。ま、そこが未来のいいところか」
コートを羽織ってバッグを持つと、「また連絡する」といい残して、高柳はホテルの部屋を出ていった。
ひとり残された未来は、ベッドに寝転んで、高柳の残り香を堪能するように大きく息を吸う。
満たされた空間。
未来と高柳だけが知る秘められた濃密な時間。
未来は、知らず知らず緩む頬を自覚しながら、余韻に浸るように目を閉じた。
1月1日(月) 初詣帰りのカフェにて
『すごいひと。初詣なんて久々にきたけど、元旦にくるもんじゃないわね。神社で並んでるときなんて、真冬なのに汗かいたもの』
「チカは汗かきだもんね。でも、神様に願いを叶えてもらうには、このくらいで音をあげちゃいけないんだよ」
『あたしは無宗教なの。必要なときだけ思い出したように神頼みする日本人て罰当たりね』
「私は毎年きて、縁結びを祈願してるけど……。どうしようもないときに最後に頼るのが神様でしょ。いつもは意識していないだけで、心のどこかには神様はいるんじゃないかな。心の支えっていうかさ」
『神様も普段から崇めてほしいでしょうね。一方的に頼られて、案外神様も迷惑してるかもね。見返りはなにもないんだから。普段から信心深いひとの願いだけ叶えていたいって思ってるかもよ』
「うーん、確かに。でも、冬真に関する願いだけは叶えてほしいなあ。それ以外は、高望みしないからさ」
『高柳さんのなにを?ドラマがヒットしますように?それとも結婚できますように?』
「もちろん、冬真の仕事が上手くいきますように、だよ。結婚はあとでいいの。今は、彼が成功するのが一番」
『へえ。25歳になるまでに死にものぐるいで結婚をゴリ押しするのかと思ってた。どういう心境の変化?』
「自分より大切に思えるひとと出会ったから、かな。仕事に没頭する彼をみてたら、自分の結婚願望とかが、ちっぽけに思えたというか。
もっと人間として成長しないと彼に置いていかれる気がしてさ。
努力家な彼に相応しいのは、今の私じゃない。もっとひととして一人前のひとなんじゃないかなって」
『ほお。それはそれは。向上心の欠片もなかったアンタにそんなことをいわせるとは、高柳さんてすごいわね。本当に、運命の相手なのかも』
「……なんか、チカが褒めると調子狂うな」
『ま、いい加減、神様も根負けしたのかもね、アンタの結婚願望に。そろそろ、運命の相手と出会わせてやるか、って』
「そうだと嬉しいなあ」
高柳は、慣れないドラマの撮影に奮闘しているようだった。
これまでの、一瞬しか映らない名もない端役ではない。
物語の中心的役割だ。
忙しさも、比べものにならないのだろう。
また、半年先まで仕事が決まったと、端的に高柳は語っていた。
今が一番の勝負所であると、未来も薄々わかっていた。
だから、会いたい、などと未来からはいわない。
いいたい気持ちをぐっと堪え、物分りのいい彼女を演じた。
わずかに取れる休みをやりくりして、高柳は会いたいと連絡してくる。
未来は、そのたびに自分が忘れてられたわけではなかったことに胸を撫で下ろす。
高柳が、新しい環境に身を置いたことによって、彼が目移りする可能性はいくらでもある。
華やかな世界を知って、どこにでもいるような一般人の未来に魅力を感じなくなることだって有り得ると、どこか危機感を持ち、仕方のないことだと予防線を張っている自分もいた。
だから、高柳から会いたいといわれると天にも昇る心地だったし、高柳との間に、決して切れない赤い糸があると信じることができた。
最近、高柳と会うのは、もっぱらホテルと決まっていた。
街中を歩くデートはできないし、お互いの部屋へ出入りするのも危険だった。
結果的にふたりはホテルで落ち合い、必然のように体を重ねた。
貪るように、むき出しの欲望をぶつけてくる高柳に、未来は内心で幸福を叫ぶ。
高柳がどこまで有名になっても、彼が自分を切り捨てることはない。
会うたびにそう確信ができた。
自信を持つことができた。
彼の原動力になれるのなら、この体をいくらでも差し出そう。
隣で寝息を立てる高柳の寝顔を見て、未来は感じたことのない充実感にどっぷりと浸かっていた。
投げ出された高柳の手を取り、そっと小指を絡める。
ふたりだけの秘密。
ふたりだけしか知らない時間。
永遠に解けないふたりの絆。
「ずっと一緒。約束だよ」眠る高柳の耳に、そっとささやく。
未来は幸せに押し潰れそうになりながら、必死で息をして、高柳を悦ばせる存在でいたいと強く願った。
縁結びの神様に。
1月14日(日) 喫茶店にて
「今からきてほしい」と高柳から連絡を受け、未来は指定された喫茶店を訪れていた。
初めてくる店だ。
キョロキョロと狭い店内を見回し、高柳の姿を探すが、彼の姿はみえない。
店に入ってきて、戸惑ったような表情を浮かべる未来に、席に座っていた若い女性が気づき、つかつかと、パンプスを鳴らしながら近づいてきた。
背の高い、非の打ち所がない美形の女性だった。
銀縁の眼鏡が、どこか冷たさを感じさせる。
ブラウンの髪を伸ばし、スタイルの良さを隠すようなロングスカートをはいている。
清潔感を漂わせる、大人びた女性だった。
彼女が真っ直ぐに自分のほうに向かっていると気づき、未来は困惑しながら女性を目で追う。
「小野寺未来さん?」
涼やかな声が冷たく響く。
「そう……ですけど」
同性で、更に同年代でありながら、未来は女性の気迫に気圧されていた。
ただものではない。
そんなオーラが、女性からは溢れていた。
「どうぞ、席へ」
女性に案内されるがまま、未来はボックス席に腰を下ろす。
誰なんだろう、このひと。
自分の名前を知っているということは、高柳の知り合いなのかもしれない。
今日、この店へくるよう連絡してきたのは、高柳なのだから。
もしかして、高柳の所属事務所のひとだろうか。
交際がバレたとか……?
勝手に想像が膨らんで未来は蒼白になる。
まさか、別れろ、といわれるのではないか。
妄想取り混ぜて頭を混乱させていた未来は、対面に座る男性の存在にようやく気づいた。
かっちりとスーツを着こなし、黒髪を撫でつけた壮年の男性だった。
未来を案内した女性が、男性の隣に座り、未来と対峙する。
店内は閑散としていて、内緒話をするにはこれ以上ないほどの環境だった。
不安そうな顔つきの未来を安心させるように、女性が薄く微笑んだ。
「初めまして、小野寺さん。わたしは、高柳冬真の妻の、高柳麗香といいます」
「……は?」
未来が投げつけられた言葉を咀嚼できずに、呆けた声を出すと、くすりと麗香が小さく笑った。
「急に呼び出してごめんなさいね。なんのことだかわからないわよね。
主人がお世話になっています。
妻として、お礼を言わせてもらうわ」
……妻?
……高柳麗香?
未来の脳が理解を拒絶する。
高柳に、妻がいた……?
高柳に、結婚しているかどうか、尋ねたことはない。
そんな可能性、思いつきもしなかったからだ。
高柳は、付き合いたいと声をかけてきた。
未来を好きになったと。
歳もまだ若く、そんなふうに告白してきた男性が、結婚しているなんて可能性すら思い浮かんだことがなかった。
高柳が妻帯者……。
ふと、働かない未来の頭がある事実を突きつける。
……自分は、気づかないうちに不倫していたのではないか。
高柳冬真に、騙されていた?
……いや、冬真は騙してなどいない。
未来が無意識にその可能性を排除して、きかなかっただけだ。
高柳は既婚者だとも、独身だとも、明言していない。
高柳から告白してきた以上、彼が自分から結婚していることを話すわけがなかった。
知らない間に、自分は高柳の不倫相手になってしまっていた。
麗香は、微苦笑しながら、柔らかい口調で言葉を続ける。
「主人……冬真は、わたしの存在を隠してあなたと付き合ってたんでしょう?
本当、女好きで困っちゃう。可哀想に、あなた、彼に騙されていたのよ」
……冬真に、裏切られた。
そう頭のなかで瞬時に思ったのに、未来の口からは、自分でも信じられない言葉が流れ出す。
「私……知りません、そんなひと」
未来の返答に、麗香は切れ長の目を細めて、軽くため息をつくようにバッグに手を差し入れる。
「そう。あなた、彼に遊ばれたのよ。彼に、庇う価値はないと思うけど」
麗香は、1枚の紙をテーブルに置き、未来にもみえる位置まで滑らせていく。
それをみた未来の顔色が青ざめた。
動揺していることは明らかだった。
唇が細かく震える。
手足が冬の街を歩いたあとのように熱を奪われて冷たくなっていく。
頭のなかが真っ白になって、呼吸が浅くなる。
麗香が差し出したのは、1枚の写真だった。
親密な様子で、顔を寄せ合ってホテルから出てくる高柳と未来が映った浮気の決定的な証拠だった。
全身から汗が噴き出す。
いい逃れできないその証拠に、未来はうなだれる。
「浮気調査専門の探偵を雇って、あなたと主人のことは調べてもらいました。まだいい逃れをするつもり?」
探偵など、映画やドラマなどでみるだけの、想像上の職業で、決して未来が生きる世界には縁のない存在だと思っていた。
空想の存在にも等しい探偵に、後をつけられていたなんて、全く気づかなかったし、気づかれては探偵を名乗れないのだろうと、放心した未来は回らない頭で無意味なことを考え続ける。
「……ごめん、なさい……」
うなだれた未来は蚊の鳴くような声でもごもごと、謝罪の言葉を述べる。
「認めるのね?」
勝ち誇ったように麗香が未来の顔を覗きこむ。
「でもっ!」
がばっと勢いよく未来は顔を上げ、声を張り上げた。
「悪いのは私なんですっ。ただのファンのくせに、強引に彼をホテルに誘って、それで、彼は仕方なく私に付き合ってくれて……。無理やりだったんです、本当は彼も奥様を裏切るつもりなんてなくて……」
未来の言葉をきいた瞬間、麗香の表情が険しくなる。
「どうしてそこまで彼を庇うの?彼は、あなたに嘘をついて騙していたのよ?体目当てで近づいて」
「結婚しているかどうかをきかなかった私が悪いんです」
はあ、と麗香が苛立たしげにため息をつく。
「あなたに現実を教えてあげる。冬真の遊び相手は、あなただけじゃないのよ」
「……え?」
「彼ね、SNSで浮気相手を募集していたの。あなただけが特別だったわけじゃないってこと。彼が浮気していることに気づいて、彼と別れてもらうために、こうして浮気相手たちに会ってるの。あなたで3人目よ。でもまだまだ遊び相手は10人近くいるの。骨が折れるわ。彼を運命の相手だなんだと信じてるひとに、現実を突きつけて別れるよう説得するのは……。まあ、わたしにも悪いところがあるんでしょうけど」
麗香は未来から視線を外し、焦点の定まらないどこか遠くを眺める。
「わたしと冬真はモデル仲間で、同い年だった。付き合うようになってすぐ、わたしは妊娠した。冬真は、責任を取るといって、わたしたちは結婚することになった。21歳のときだったわ。でも、結婚してほどなくして、流産してしまった。わたしは、そのことを、すぐに冬真にいえなかった。わたしたちを繋いでいたのは、望まずにできてしまった子どもだけだった。
その子どもがいなくなったら、彼を繋ぎ止めることができなくなるんじゃないか。責任を果たさなくてよくなった冬真は、わたしのもとから去ってしまうのではないか……。と、わたしは怖かったの。結局自分に自信が持てなかったのね。彼を信頼することができなかった」
ひと息つくように、麗香は冷めきったコーヒーに口をつける。
未来は、身じろぎひとつできずに麗香の昔語りをきいていた。
「ずっと流産したことを隠し通すことはできなかった。ついに彼はその事実を知って、懸念した通りのことが起こった。わたしを顧みずに、遊び歩くようになったの。子どもができた責任を取ってわたしと結婚はしたけど、彼はまだまだ遊び足りない年齢だった。わたしだけじゃ満足できなくて、常に複数の女のひとが彼のそばにいた。結婚は、ただ紙切れ1枚で交わした契約にすぎなかった。彼を繋ぎ止めることはできなかったの。
でも、わたしは彼が好きだった。今でも、彼以上の存在が現れるとは思えない。
運命の相手だったの。
だから、いつ離婚を言い渡されるのか、ずっと怯えている。
でもね、まだわたしは冬真の妻なの。
彼がわたし以外のひとと付き合うことは許せないし、許さない。
彼に愛される資格があるのは、妻であるわたしだけ。
彼は離婚したいようだけど、わたしは絶対に応じない。やり直してみせる。
彼と、一生を生きていくのはわたしだけ。
だから、小野寺さん、悪いけど冬真と別れてちょうだい」
毅然とした口調とは裏腹に、麗香の目は保護者を失った子どものように、不安げに揺れていた。
未来を一抹の罪悪感が襲う。
麗香が語り終わると、示し合わせたように、今まで黙していた壮年男性が書類を取り出した。麗香が男性を手で示していう。
「この方は、弁護士の先生。彼の遊び相手のひとと交渉するために同席してもらっているの」
「……交渉?」
「そう。冬真と2度と会わないと、誓約書にサインをしてほしいの。もちろん、見返りは約束するわ」
「見返り?」
「ええ。小野寺さんは、いくらがいいかしら?そんなに稼ぎがあるわけじゃないから、上限はあるけど、あなたが望む金額をなるべく用意したいとは思ってる。そのすり合わせの交渉に、先生に立ち合ってもらっているの」
「……つまり、手切れ金ってことですか?」
「そう思ってもらってかまわないわ。お金で解決するなら安いものよ。彼に寄ってくる虫を札束で追い払うようなものね」
未来は悔しさに奥歯を噛みしめる。
高柳への思いは、金で清算できるものではない。
彼の才能に惚れこみ、誰よりも彼の成功を近くで見届けたいと強く願ってきた。
彼が妻帯者であることも、彼に遊び相手としてしかみられていなかったことも、未来の願いを微塵も揺らすことはなかった。
彼の一番そばにいたい。
「……お断りします」
「……え?」
「お金なんかいりません。だから、彼とも別れません」
「あなた、本気?今までわたしの申し出を断ったひとはいないわよ。冬真が欲しいのは、あなたじゃない。あなたの体なのよ?体目当ての男と関係を続けるより、お金をもらって新しいひとを探すほうが賢明な判断だと思うけど」
未来の脳裏に、高柳と過ごした甘くて密やかな、狂おしいまでに求め合ったあの時間が鮮明に蘇る。
あのときの、濡れたような高柳の瞳には、未来しか映っていなかった。
同じように、未来は高柳しか自分の瞳に映したくなかった。
あの時間が幻であろうと、仮初めであろうと 、確かにあの瞬間、世界にはふたりしかいなかった。
その事実は消えない。
高柳の肌の温もりも、すべすべの肌の感触も、未来のためだけに存在していた。
手放したくない。
たとえ、このひとから奪うことになっても。
「高柳さんは、私の運命のひとなんです」
ぴくり、と麗香が眉を吊り上げる。
「……あなた、馬鹿ね。冬真は、今が一番大切な時期なのよ。冬真のスキャンダルが発覚するまえに、わたしがその芽を摘んでいるの。あなただって、彼のことを好きなら、身を引くのが、彼のためだと思わない?」
「私が、彼を支えます」
麗香の顔つきが更に険しくなる。
「……後悔するわよ。なにがあっても、わたしのせいじゃないわ。全ては、愚かな決断をしたあなたのせい。冬真は渡さない。たかがファンの分際で、冬真の隣に並ぼうとするなんて、身の程知らず。絶対冬真と別れさせてみせる。冬真が選ぶのはわたしなんだから」
「高柳さんは、あなたの独占欲に辟易して他のひとに癒やしを求めるんじゃないんですか」
「うるさい!あんたみたいな女、絶対に破滅させてやる!大人しく金をもらって冬真のもとからいなくなれば、許してやったのに。交渉決裂ね、先生、行きましょう」
麗香は、怒りに顔を染め、美しい顔を鬼のような形相に変えて、隣の弁護士を伴って席を立ち、足早に店から去っていった。
ひとり残された未来は、自分の口から溢れるように出てきた言葉たちに、自分で一番驚いていた。
自分は世間でいう、浮気相手だ。
本妻に別れろと迫られてしかるべき存在。
未来のほうが悪だと、誰もが答えるだろう。
未来だってそう思う。
浮気という倫理に反する行為をしておきながら、本妻に別れない、と啖呵を切るなど、非常識極まりない。
しかしなぜか、未来はそうしてしまった。
おかしい。
自分は本来、こんな性格ではない。
自分が悪いと知りながら、浮気相手を本妻から略奪するなんて、正気の沙汰とは思えない。
世の中の、誰からも非難される行為だ。
でも、未来は思ってしまった。
高柳冬真の、世界で一番の味方でいたいと、周囲の誰もに非難されようとも、彼を護れる盾になりたいと、そう願ってしまった。
誰に嫌われようとも、責められようとも、彼を手に入れたい。
悪女になってもいい。
奪いたい。
麗香も、高柳のファンも、誰を傷つけることになっても。
未来は、悪役になることを決めた。
1月21日(日) ファミレスにて
『アンタ、馬鹿じゃないの!?高柳さんの本妻に喧嘩売ったの?既婚ってだけで充分スキャンダルなのに、浮気相手がたんまりいて、更に浮気相手のひとりが本気になって略奪を宣言するなんて、どんな泥沼よ?そもそも、高柳さんとは連絡が取れたの?』
「……取れてない。奥さんに呼び出されてから、連絡がとれなくなった」
『ああ……。まさかアンタが不倫略奪する悪女だったなんて想像もしなかったわ……。高柳さんの本心も知らずに運命のひとだとか宣言するなんて……。ちょっと目を離した隙に、なにが起こってるのよ。未来、本当にアンタどうしちゃったの?高柳さんが奥さんとやり直すって決めたらどうするの?』
「そのときはそのときだよ。冬真が奥さんを選ぶなら、私だって身を引く。でもね、まだ冬真の気持ちきいてないんだよ。冬真の気持ちがわかるまで、私は諦めない」
『浮気相手と別れさせたい奥さんに会うよう高柳さんが指示してきたことを考えると、自ずと高柳さんの気持ちもわかるような気がするけどね。アンタとの関係を清算したがってるって。奥さんに、高柳さんから頼んだ可能性だってあるわ』
「とにかく、私は冬真の本心を知るまで、彼を諦めない。きっと私を選んでくれるって信じてる」
『自分に自信があるのは悪いことじゃないけど、今のアンタの自信は根拠がなさすぎ。
考えてもみてよ。高柳さん、遊び人なのよ?結婚してるのに、浮気相手募集しちゃうような、だらしのないクズなのよ?
今までアンタが出会ってきた数々のクズと同じじゃない。
痛い目みたはずなのに、どうしてそこまで執着できるのよ。
傷つくのは、自分なんだからね。
何度もいうけど、高柳さんはやめておきなさい。節操のないクズよ。
私生活が足を引っ張って、芸能界で身を滅ぼすかもしれない。
そうなったとき、責められるのはアンタよ。
高柳さんのために、アンタは自分の人生を捨てられるの?
世間を敵に回して、誰も助けてなんてくれない状態になって初めて失敗したって後悔しても遅いのよ?
たかがひとりの男のために、人生を滅ぼすことはない。アンタは、まだ若いんだから。
高柳さんとの関係を終わらせて、新しい運命のひとを探しなさい。それが賢明な判断よ』
反対されればされるほど、燃え上がるのはなぜだろう。
高柳を失いそうになって初めて、未来は自分が是が非でも彼を手放したくないと頑なに思っていることに気づいた。
結婚を焦って選ぶ男はクズばかり。
それは、今回のケースにも残念ながら当てはまる。
けれど、なにかがいつもと違う。
「クズだから」で済まされないなにかを、高柳に感じている。
彼の、一生そばにいたい。
健やかなるときも、病めるときも。
スキャンダルにさらされるときも。
ふたりでなら乗り越えていける気がしたのだ。
それを、世間では略奪愛だといっても。
自分を一番大切だといってくれた高柳の甘い声。
たとえ高柳にとって未来が、遊び相手のひとりにすぎないとしても、彼を振り向かせたい、本気にさせたい、そんな闘志が、未来のなかでは燃え上がっていた。
絶対的な自信があるわけではない。
それは、願いなのだ。
叶えたい祈り。
冬真と、この先の人生をともに歩けますように、と神様に祈った純粋な願い。
透き通った水のような、晴れ渡った青空のような、純度の高い願い。
それは、なんの確証もないのに、この恋は永遠に続くと、無邪気に信じられた初恋に、どこか似ている。
ただ相手がそばにいるだけでいい。
それ以上のことは望まない。
それは、強欲という大罪に当てはまるのだろうか。
未来がそう尋ねると、間髪入れずにチカが切って捨てた。
『当たり前じゃない。大罪よ大罪。だって不倫よ?アンタをみる周囲の目だって厳しくなるに決まっているじゃない。娘が不倫のうえに略奪したなんて知ったら、アンタのお母さんどう思うか想像できる?悲しむに決まってるわ。それだけじゃない、もし世間にアンタがしたことがバレたら、お母さんの立場だって悪くなるかもしれない。アンタ責任取れるの?親に迷惑かけてまで手に入れたい男ってなんなのよ?』
「……わかんない。でも、私は冬真と一緒にいたい。ただ、それだけ」
『だから!それが許されないことだっていってんの!アンタ奥さんに訴えられたら負けるわよ。それが筋、世間の常識。
子どものころに習わなかった?
ひとに迷惑をかけてはいけません。
悪いことをしてはいけませんって。
アンタのしていることは悪いこと。
今すぐ悔い改めないと、アンタがすがった縁結びの神様に見放されるわよ。
天罰だって下るんだからね』
「天罰……重い言葉だね」
『そうでしょう。神の怒りに触れないように生きる人間にだけ、神様は祝福を与えるのよ。今のアンタは神様を裏切って、顔に泥まで塗ってる。いい加減目を覚まして。高柳さんのことは、出会わなかったものとして、違う男にしなさい。なんなら、あたしが適当に見繕って紹介してあげるから、ね、それならいいでしょ』
「……いい、のかな、それで」
『悪いことはいわない。あたしのいう通りにしなさい。自分から不幸に飛びこんでいく必要なんてないんだから。ね、だから、この話はもう終わり。高柳さんなんて男に、アンタは出会わなかった。恋もしなかった。それで終わり。忘れるの、いや、なかったことにするのよ、未来。
アンタなら、すぐに切り替えて違う男に夢中になれるわ。
これ以上、高柳夫妻に関わるのはやめなさい。
いい、誓えるわね?』
チカにいいくるめられ、未来は小さくうなずいた。
チカの言葉は、いつも正しく未来の心に染み渡る。
チカがそういうなら、そうなのだろうと、考えさせられてしまう。
未来がクズに夢中になるのを、破滅寸前で引き止めてくれるのはいつもチカだった。
チカがいうのだから、間違いはないのだろう。
未来は、自分に男を見分けるセンスがないとわかっている。それは自覚している。
恋に落ちると周りが見えなくなり暴走する未来を、チカは先回りして辛らつながらも的確な指摘で夢見る未来の目を覚ましてくれる。
だから、今回の件も、きっと……。
「忘れられないよ……」
チカにきこえないよう、未来は反抗するように呟いた。
2月9日(金) 未来の職場にて
昼休憩のために席を立とうとした未来のスマホが振動した。チカからだ。
「もしもし?」
『未来、大変なことになってるわよ!』
「……え?」
いつになく切迫した様子のチカに、未来は無意識に身構える。
「なにがあったの?」
『今日発売の週刊誌に……』
チカとの通話を終えると、未来は病院を飛び出して、近くの本屋に駆けこんだ。
呼吸も荒く雑誌のコーナに辿り着くと、今日発売の週刊誌を手に取り、周囲の目も気にせず、ページをめくる。
【今大注目の俳優 高柳冬真は結婚していた! さらに、10人以上の浮気相手がいることが発覚!中には、若手女優やモデルも! 泥沼不倫発覚で仕事に影響も?】
未来は頭のなかが、真っ白になり、衝撃的な内容を報じる雑誌を持つ手が震え出す。
ついに、恐れていたことが、現実になってしまった。
記事には、モデル仲間の女性を妊娠させ、結婚したこと、妻がいるにも関わらず、浮気相手を募集し、不倫を繰り返していたことが、詳細に、なんの誇張もなく書き綴られていた。
それだけに、高柳がしてきたことが下衆だったと痛感させられる。
高柳と不倫していたとして、若手女優や、未成年のアイドル、有名なモデルの名前などが並べられている。
彼女たちの写真とともに、見覚えのある写真が掲載されていることに、未来は震撼した。
顔をぼかされているが、それは確かに未来と高柳がホテルから出てくるところを収めた写真。
喫茶店で、高柳麗香に突きつけられた、探偵が撮ったという、あの、高柳と未来の不倫の証拠写真が、芸能人たちに混じって載せられていたのだ。
この写真を流失させたのは、高柳麗香だ。
麗香は、夫である高柳を、社会的に抹殺するために、週刊誌に情報を提供したのだ。
高柳は、高柳の仕事はどうなってしまうのか。
今撮影しているドラマは?
決定したと報じられたCMは?
果たして、高柳はこの先も芸能活動を続けることができるのか?
麗香は、別れないと執着していた冬真を、どうしたいのか。
自分と高柳の関係は、どうなってしまうのか。
高柳のしたことは、確かに最低だ。
妻がいながら浮気を繰り返していた。
それは責められてしかるべきだ。
知らなかったとはいえ、未来も不倫の片棒をかついでいた。
未来も、高柳に騙され、遊ばれている女のうちの、ひとりにすぎなかった。
しかし、本妻である麗香に、略奪宣言までするほど、高柳に心酔してしまった。
麗香も、他の不倫相手も関係なかった。
ただ純粋に、高柳が好きだった。
そばにいたかった。
それ以上は、望まなかった。
わなわなと、雑誌を持つ未来の手が震える。
雑誌を読み進めるうちに、未来の心に純粋に生まれてきたのは、怒りだった。
高柳がやったことは悪い。
それは認める。
だが、週刊誌のたった2ページに名前を載せられただけで、何人もの人間の人生が、大きく変わる。狂ってしまう。
これを執筆したひとは、この記事が、ひとを簡単に破滅させることを承知で書いているのか。
高柳から、信頼と仕事を奪って、彼の芸能活動を殺すも同然のことを、どうして平気な顔をしてできるのだろう。
高柳から俳優活動を奪うということは、彼の人生を奪うことに、場合によっては死に追いやることでもある。
ひとひとりを殺すことに他ならない。
高柳の演技は、見たひとを魅了する力がある。
惹きつける引力がある。
役者、高柳冬真を失うことは、芸能界にとって大きな損失になるだろう。
抜きん出るなにかがある。
目を離せないなにかがある。
役者、高柳冬真が一番輝く場所。
活き活きと泳ぎ回れる場所。
高柳には、スポットライトがよく似合う。
舞台のカーテンコールでみせた、達成感に満ち溢れる高柳の笑顔を、きらめく汗を、未来は忘れることができない。
高柳の、その笑顔を、護りたい、彼を害するものの盾になりたい。
己の立場もわきまえず、そんなことを思った自分に腹が立つ。
なんの力も持たない、非力な存在のくせに。
彼の役に立ちたいなんて、おこがましい考えだったのだ。
苛立ち紛れに、平積みにされた週刊誌を叩きつけるように棚に戻す。
誰の目にも触れないように、この憎き週刊誌を買い占めてしまいたかったが、未来にそんな資金はない。
くるりと週刊誌売り場に背を向けると、ポケットからスマホを取り出す。
麗香と対面してから、高柳にどれだけラインを送っても、既読はつかなかった。
虚しく未来が送ったメッセージが並ぶ画面に、習慣のように新しく文章を作成し、送信する。
「冬真、大丈夫?」
今、高柳はどうしているだろう。
なにを思い、どこにいるのだろう。
このメッセージにも既読がつかないだろうことは、わかりきっている。
だから、特に反応がなくてもショックは受けない。
しかし、予想外の展開に、未来は目を見開く。
未来の送ったラインにすぐに既読がつき、次の瞬間軽やかな音をスマホが奏でて、ラインがきたことを告げた。
「大丈夫。俺を信じて。約束」
未来は、その文面を、何度も何度も読み返す。
最終的には、文字の意味がわからなくなる現象まで起きるほど、高柳から送られてきたメッセージに目を凝らし続ける。
心が、喝采を叫ぶ。
ここが、店内であることも忘れて、叫んで回りたい気分にとらわれる。
とうとう、高柳から返事があった。
大丈夫だと。信じてほしいと。自分だけに向けられた言葉で、彼の想いが綴られている。
未来はスマホを胸に抱きしめ、深呼吸するように目を閉じ、天井をあおぐ。
油断すると、涙が溢れてしまいそうだった。
感じたことのない安心感に包まれていた。
自分と高柳の繋がりが、消えたわけではないと。
運命の赤い糸が、途切れたわけではなかったと。
はたと、未来の動きが止まる。
約束とは、なんのことだろう。
過去に、高柳となにか約束したことがあっただろうか?
記憶を辿って、高柳の伝えたい言葉の意味を考える。
……約束……なんの?
しばらく立ち尽くしたまま、天井を睨んでいた未来は、はっと、その場でとある場面を思い出し、瞠目する。
ホテルで逢瀬を重ねていたころ。
ベッドに並んで寝ていたときのこと。
隣で寝息を立てる高柳の小指に、自分の小指を絡ませ、「ずっと一緒。約束だよ」と、彼の耳元で未来はささやいた。
あのときは、高柳はきいていないと思っていたので、あの言葉は、あくまで自己満足でいったにすぎなかった。
高柳は、きいていたのだ。
そして、それを覚えてくれていた。
今度こそ、未来の頬を涙が伝った。
我慢できなかった。
ひとの目などどうでもいい。
今はひたすら泣きたかった。
嬉しくて、全身が震えるほど幸せで、満たされて、味わったことがない感情が飽和するほど押し寄せてくる。
好きだ。高柳が、たまらなく好きだ。
この想いに、もう嘘はつけない。
涙を拭き、病院に戻るためにきた道を歩いていると、スマホが振動した。
高柳だろうか。
期待に胸を膨らませてスマホを取り出すと、画面に表示されていたのは、チカの名前だった。
今の幸せな出来事を、早速報告しなければと、嬉々としてスマホを耳にあてる。
「もしもし、チカ、きいてよ……」
未来が弾んだ声で話しはじめると、未来の声に被さるようにチカが叫んだ。
『未来!ネットみて!大変なことになってるわよ、アンタ!』
再びの緊迫感溢れるチカの声。
未来の幸せな気分は、すぐさま熱を冷まされ、背中に緊張が走る。
チカとの通話を早々に切り上げ、スマホで高柳の名前を検索する。
すぐに画面に、高柳のスキャンダルを報じるネットニュースが表示される。
先ほど読んだ週刊誌と変わらない内容が載っているが、違う点があった。
高柳の浮気相手として、女優やアイドルと並んで、週刊誌では「一般人のOさん」とされていた未来の実名が、ネットでは隠されることなく書かれていた。
週刊誌では、未来の顔がぼかされていた高柳と未来がホテルから出てくる写真も、未来が麗香からみせられたままの、ぼかしのない鮮明な状態で、さらされていた。
ネットのコメント欄を、恐る恐る覗いてみる。
《冬真くん、ファンだったのにショック》
《浮気相手10人とかサイテー。奥さん可哀想》
《他はわかるんだけどさ、小野寺未来って誰?》
《小野寺未来はただの一般人》
《高柳冬真が通院していた中野病院で働いてる医療事務、24歳》
《実家は新潟。東京の大学を卒業。両親は小野寺未来が幼いころに離婚。実家の住所は……》
《横島社長がこのまえストーカーで捕まったけど、当時付き合ってたのが小野寺未来らしい》
《えー、テレビでみただけだけど、横島社長かっこよくて好きだったんだけどなー。この女のせいでおかしくなっちゃったのかな?》
《小野寺未来は、付き合った男の数がエグい》
《高柳に遊ばれて可哀想だと思ったけど、この女も男遊びすごかったんだね。自業自得》
《っていうか、尻軽じゃない?》
《名前さらされても身から出た錆》
《高柳冬真を潰した小野寺未来の情報をさらそう》
未来は目を疑った。
ネットに、実名、職場、住所、スマホの番号、学歴、出身地、実家の住所に実家の電話番号、小中高の文集や卒業アルバムの写真、更には過去、付き合った男の名前まで、未来の情報の、なにもかもが、ネットにさらされていた。
ネットに溢れる顔のみえない、名前すら知らないひとから向けられる、むき出しの悪意。
未来を貶めようと画策する大勢の敵意。
恐怖を感じて辺りを見回すが、当然ながらすれ違うひとは未来に目を向けない。
でも、何食わぬ顔をして、未来に気づかないふりをしながら、手元のスマホでは、未来を糾弾するコメントを書きこんでいるひとがいるのではないか。
嗤いながら、未来にスマホを向けているひとがいるのではないか。
疑心暗鬼に陥って、うつむくと、病院までの道のりを、未来は走った。
未来の情報がネットに上がってから、まだ短時間にも関わらず、未来の個人情報は倍速で拡散されていく。
一体誰が、こんなに詳細な情報を投稿したのだろう。
まるで犯罪者の気分だ。
自分を守ってくれる盾は、なにひとつない。
未来だけが悪者。
未来だけが高柳冬真を殺した凶悪犯。
みえない、ひとの悪意にさらされたとき、どう身を守ればよいのかを、未来は知らない。
ただ無防備に、光の速さで駆け抜ける自分の情報が、雪だるまを転がすように、人々の悪意を吸収して、小野寺未来が罪人であるというイメージを、転がりながら膨らませていく様子を、眺めていることしかできない。
一体、なにが起きているのだろう。
週刊誌をみて絶望に堕とされたかと思えば、高柳からの返信に天にも昇る心地になり、そしてまた、今度は、個人情報が悪意によって拡散されていることを知り、再び奈落の底へと突き落とされる。
まるでジェットコースターだ。
未来は、ジェットコースターが得意ではない。
だから、今、なにが自分の身に起きているのか、理解できず、頭がこの事態についていけなかった。
病院に戻った未来を迎えたのは、出ていく前とは、別世界だった。
電話が鳴り止まない。
電話対応をしていた、福沢諭吉似の上司《ユキチ》が、乱暴に受話器を叩きつけ、未来を認めたとたん、大股で近づいてきた。
「ちょっと、小野寺さん、どういうこと?君を出せって迷惑電話が鳴り止まないんだけど。説明してくれない?」
「す、すみません……」
もう職場にまで、嫌がらせの電話がかかってきているのか。
未来は軽いめまいを覚える。
しおらしく、小声で謝ることしかできない。
「これじゃ仕事になんないよ」
頭を掻きむしりながら、ユキチが席へと戻っていく。
「君、本当になにをしたの?これ以上仕事に支障が出るようなら、休んでもらうことも考えないといけないからね」
「……はい。本当にすみません」
未来は、かかってきた電話を取る。
「小野寺未来を殺す。高柳冬真に2度と近づくな」
若い女のひとの声が、無機質にそれだけ告げると、ぷつりと切れてしまった。
受話器を戻す。
戻したとたん、電話が鳴り始める。
「小野寺未来を解雇しろ。さもないと、病院を爆破する」
またしても、電話はそれだけで切れる。
受話器を戻したとたん、また着信音がけたたましく鳴り響く。
業務に関わる電話かもしれないので、無視することはできない。
「はい……」
「小野寺未来か?そんなに男と遊びたいなら、俺が相手してやるよ」
卑わいな言葉を垂れ流す若い男の声に耐えきれず、未来は電話を切った。
その様子をみていたユキチが、はあと聞こえよがしにため息をつく。
「なにがあったのか知らないけど、小野寺さん、今日はもう帰って。仕事にならないから。君も、相当疲れてるみたいだし。落ち着くまで、来なくていいからね」
ユキチは事情をきこうともせずにそういうと、業務に戻ってしまった。
鳴り響く電話に、「ああ、もう」と悪態をついている。
未来は肩身が狭い思いになりながら、帰り仕度をはじめた。
午後の診察の時間になり、患者の対応をしていた受付の横を通りすぎたとき、同僚の困惑した声が耳に入った。
受付の女性のか細い声に被さって、男が怒声を張り上げている。
「だから、小野寺未来を出せっていってんの。一番乗りで小野寺未来を直撃して、配信するんだから。フォロワー増えるだろうなあ。だ、か、ら!小野寺未来を早く連れてこいって!」
若い男が、受付の女性に噛みついている。
戸惑っていた彼女と、目が合うと、彼女は男の背後を歩く未来に目配せして、小さくうなずいた。
今のうちに行け、という合図だった。
彼女に最大限の感謝を込めて、頭を下げると、気配を消して男の後ろを通り抜け、未来は病院をあとにした。
2月16日(金) 未来の自宅にて
週刊誌が発売され、高柳冬真の衝撃的なスキャンダルが世間に報じられてから一週間が経った。
高柳と未来を取り巻く環境は、悪化の一途を辿っていた。
高柳は、未だ沈黙を保っている。
謝罪会見が開かれるのではないか。
事務所による何らかの発表があるのではないか。
マスコミは、今か今かと高柳の動きを待っている。
すでに、決まっていた仕事は白紙になったとの報道もある。
テレビやネットでは、高柳に関する報道が激化し、不倫の事実、不倫相手への糾弾が繰り返し報じられていた。
今や、高柳冬真は時のひととなっていた。
本業の俳優としてではなく、不貞を犯した大罪人として。
好奇の目にさらされ、人格まで否定するコメントが無秩序に垂れ流され、高柳冬真という人格が、なにもしらない人々によって、上塗りされ、彼の本質が曖昧にされていく。
高柳冬真が、作り変えられていく。
顔だけはいいクズの浮気男。
彼を知らなかったひとは、その上書きを、そっくりそのまま信じ、無責任な正義感で彼を責め立てる。
報道から丸一週間経ったこの日、所属事務所は、高柳冬真の解雇処分を発表した。
その報道を、自室のテレビで観ていた未来は、ただ呆然と、その事実をみつめることしかできなかった。
「未来?未来、どうしたの、大丈夫?」
スマホから漏れ聞こえる声に、未来のぼやけかけた意識が引き戻される。
「あ、うん、ごめんね、大丈夫。お母さん、本当にごめんね。わたしのせいで辛い思いさせて」
「お母さんなら、大丈夫よ。それより未来、あなたこそ平気なの?仕事も行っていないんでしょう?お母さん、そっちまで行こうか」
電話の向こうの母は、気丈に振る舞い、未来を励ました。
騒動の余波は、未来の新潟の実家まで及んでいた。
嫌がらせ電話はもちろん、未来を更には母までもを罵った張り紙が家の外壁に貼られ、押しかけてきた高柳のファンや野次馬が、その様子を得意げに動画投稿していた。
近所のひとからも、母は白い目でみられているのだろう。
届く声には、疲労が滲んでいた。
母だって、娘がどんなことをしたのか、承知しているだろう。
にも関わらず、変わらず優しい言葉をかけてくれる。
母に、とんでもない迷惑をかけてしまった。
なんて親不孝な娘なのだろう。
未来は両目に滲んだ涙を拭いながら、意識して声を張った。
「ありがとう、私は大丈夫だよ、心配しないで。お母さんも仕事あるでしょ?」
「でも、ちょっとくらいなら平気よ。ちゃんと食べてる?寝られてる?お母さん、それだけが心配で……」
「うん、大丈夫だよ。またすぐに、そっちに帰るね」
「いつでも帰ってきてね。じゃ、また連絡する」
未来が言外に、来なくていいと伝えると、母は、気づかないふりをして明るい声で通話を切った。
今、母にこの部屋にきてほしくなかった。
カーテンを閉め切り、薄暗くなった部屋に、テレビの青白い光りだけが、疲れ切った未来の横顔を映し出している。
薄いドアの向こうでは、数人の男女が未来の名前を叫びながら、ドアを叩き続けていた。
壊れたようにチャイムが鳴り続ける。
耐えきれず、未来は耳を塞いで体を丸めた。
アパートのドアにはいたずらの張り紙が貼られ、外壁にはスプレーで落書きがされていた。
外に出れば、スマホを向けて見知らぬ男たちがつきまとってくる。
ひとときも、気が休まる暇がなかった。
職場にも、相変わらず迷惑電話がかかり続け、ひとが押し寄せている。
未来を追いこむことは、ひとつのエンターテインメントと化していた。
未来なら、どんなに傷つけても構わない。
そんな恐ろしい風潮が、世間には充満していた。
日常で溜まったストレスを、未来を攻撃することで、発散しているのだ。
母との通話を切ったばかりのスマホが振動する。
非通知。
スマホの電源を落として対抗する。
ずっとそうしているわけにはいかないので、電源を入れるが、間髪を入れずに着信がある。
その繰り返しだ。
未来の神経が、がりがりと粗く削れていく。
こんな日が、あと何日続くのだろう。
自分の精神はいつまで持つのか。
《約束》
高柳が送ってきたラインの文面が蘇る。
今、未来がなんとか耐えられているのも、あの言葉があるからだった。
今朝、辞表を出してきた。
診療がはじまる前のことだ。
ネットを参考にしながら、辞表を書き、ユキチのデスクに置いた。
出勤してきたユキチは、辞表を一瞥すると、未来を見ることもなく、パソコンに視線を移した。
小さい声で「ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした」と謝り、頭を下げると、荷物をまとめて病院を出た。
ユキチは、引き留めもしなかった。
またひとつ、自分はなにかを失った。
これが、浅はかにも自分が取った行動が引き起こした結果だった。
ひとつひとつ確実に、未来はなにかを失ってゆく。
それが、未来が選んだ結果に対する答え。
全て自分が引き起こしたこと。
誰を責めることも、恨むことも許されない。
未来は今起きていることの全てを、受け入れなければならない。
テレビを消し、真っ暗になった部屋にチャイムが鳴り響いた。
無視を決めこんでいると、ドアを叩きながら、くぐもった高齢の女性の声が、「小野寺さん、松野だけど」と呼びかけてきた。
このアパートの大家の女性だ。
未来は警戒するように、狭くドアを開ける。
小柄で痩せた年配の大家が、隙間から皺だらけの顔を、ぬっと覗かせる。
少しほっとする。
「小野寺さん、困るのよねえ。張り紙、早く剥がしてくれない?壁のいたずら書きも、消してもらえるんでしょうねえ?原状回復、してくれないと困るのよ」
「原状回復……退居しろって、ことですか?」
松野は、苦虫を噛み潰したような顔で未来から目を逸らす。
「まあ、ねえ……。他の部屋のひとに迷惑だし、変なうわさが広がって次の入居者が来なくなると、困るし……。うちも商売やってるのよ、わかってちょうだい。荷物も少ないようだし、明日には出ていってもらえるかしら」
松野は無慈悲にそういい捨てると、未来の顔をみることなく立ち去っていった。
あ然とした表情で、玄関先に立ち尽くす未来に向かって、複数のフラッシュが瞬き、その姿を切り取った画像が拡散された。
2月28日(水) ネットカフェにて
狭い個室で、机に突っ伏していた未来のスマホが振動した。
緩慢な動きで顔をあげ、スマホを目の高さに掲げると表示された名前に目を見開く。
ラインに高柳からのメッセージが届いていた。
《会いたい。これから会える?》
逢瀬の場として、ホテルの住所が書かれていた。
弾かれたように、未来は立ち上がった。
アパートの部屋を追い出された未来は、翌日から、キャリーケースに荷物を詰め、ファミレスやネットカフェを転々としていた。
仕事を失っているので、日雇いのバイトをしながら、わずかな稼ぎでその日暮らしをしていた。
いつかは冬真に会える。
その思いだけを支えに、未来は惨めに傾きそうになる心を、なんとか保って生きてきた。
あれだけ騒がれた高柳冬真の泥沼不倫騒動は、いつしか下火になっていた。
世間の関心はすでに高柳冬真にはなく、今は別の話題がメディアを賑わしている。
高柳冬真は、すでに忘れ去られた存在となっていた。
しつこく未来を追い回していた野次馬も、今はもういない。
それでも、未来は仕事を失い、住む家を失い、信用を失い、穏やかな生活を失った。
それでも彼女を支えていたものは……。
「冬真!」
格安ホテルの一室。
冬真の姿をみるなり、居ても立っても居られず、未来は彼に抱きついた。
冬真も、「未来……」といったきり、感極まったように声を詰らせながら未来を抱きしめ返した。
そこに、言葉はいらなかった。
ふたりの心は、誰に侵されても揺らぐことはなかった。
冬真は、《約束》を果たしたのだ。
温かく柔らかい高柳の感触。
知っていた。体が覚えていた。
全身が熱を持つ。温かい涙が自然と頬を伝う。
未来の涙を親指で拭うと、高柳は抱擁を解かずに言葉を絞り出した。
「迎えに来るの、遅くなってごめん。でも、未来なら待っててくれるって信じてたから」
「うん。私も信じてた。冬真が必ず会いに来てくれるって。約束、守ってくれるって、信じてた……だから、辛くなんて、なかったよ」
「辛い思いさせてごめん。……俺、事務所も解雇されて、なんにもなくなったよ。それでも、いい?」
「いい。そんなこと、構わない。冬真がそばにいてくれるなら、なんにもいらないよ」
互いの体温を確かめ合いながら、ふたりはしばらく抱き合っていた。
やがて、そっと体を離すと、手を絡ませたまま、ソファに並んで座り、ふたりはぽつぽつと言葉を交わした。
「麗香とは、離婚が成立した。夫婦関係は、とっくに破綻してたんだけど、負い目もあって、ずるずると関係を続けてしまった。
それが、麗香をより苦しめる結果になって、未来まで辛い思いをさせた……。
俺の浮気相手を、麗香が金をちらつかせて別れさせていることを、便利に思ってもいた……。サイテーだよな、俺」
「……うん。それは……最低だね」
「反省してる。心のどこかで、金を払えば別れる程度の女なんだって、そんな判断基準を作ってた。でも未来は、金を受け取らなかった。俺のことを、本気で思ってくれてた。未来との約束だけは、なんとしても守らなきゃいけないと思った。未来と会っていたのは、そりゃ、最初に声をかけたのは、遊び相手を探すためだった。でも未来に会うたびに、どんどん好きになっていった。止められなかった。特別だった。正直今でも、他の女と未来のどこが違うのか、わからない。でも、今回の騒動で、強く実感したんだ。未来を失いたくないって……。
運命の、相手だって」
未来が息を呑む。
運命の相手、それは、未来が度々口にした言葉。
もう出会えないのではないかと、諦めにも似た存在だった。
ようやく、出会えたのだ。
探し求めていた運命の相手に。
万感の思いだった。
ふと見上げると、隣の高柳が、泣いていることに気づいた。
つられて、未来まで泣き出してしまう。
「なんで泣いてるのよ。冬真」
「泣いてない。未来こそ、泣いてるじゃん」
乱暴に涙を拭うと、高柳は恥ずかしそうに、赤くなった顔を背ける。
「未来、本当に俺でいいの?イチからのスタートじゃない、ゼロからやり直すことになるけど」
「それくらい、覚悟してる。ゼロなのは私も一緒だし」
「未来となら、やり直せる。未来……」
「ん?」
足もとのバッグに手を伸ばした高柳は、小さな箱を未来に差し出す。
未来に緊張が走る。
「俺と、結婚してもらえますか?」
改まった口調で、箱を開け、高柳は照明に光る指輪を取り出した。
夢のような光景だった。
運命の相手にプロポーズされる。
長年憧れ続けたその奇跡が、現実として自分の前に広がっている。
未来は、震えながら左手を差し出した。
高柳がゆっくり指輪を未来の左手薬指に嵌めていく。
高柳の手も、緊張で汗ばみ、震えていた。
指輪を、照明にかざす。
子どものころから思い描いていた夢を、ようやく叶えることができた。
あまりに幸福に満たされて、肺がいっぱいになり、呼吸がうまくできない。
未来は泣き笑いの顔になっていった。
「よろしくお願いします」
3月17日(日) 馴染みのカフェにて
『はーん。で、結局うまくいっちゃったんだ』
未来は、結婚指輪をチカにみせつけるようにかざしながら、満面の笑みでうなずいた。
「これ以上の幸せはないよ。とうとう念願の結婚。縁結びの神様は、本当に願いを叶えてくれるんだね。初詣行ってよかったなあ。お礼に行かないとね」
『でもさ、アンタたち、ふたりとも職を失ったわけでしょ?生活はどうするの?』
「冬真ね、劇団に入ることになったの」
『劇団?』
「冬真が子どものころ所属してた劇団のひとが、声かけてくれて、今は舞台出演に向けて稽古中。
冬真の演技は格別だから、役者辞めないですんで、本当によかった。
冬真にはどうしても演技を続けてほしかったし、そう考えてたひとが、私だけじゃないってわかって心強かった。
生活は苦しいけど、私も、次の職場がみつかるまでは日雇いのバイト続けて、資金を貯めて、冬真と一緒に住む家をみつけるつもり」
『まだなにも決まってないわけね。スタートラインにも立ってないじゃない。本当にそんなことで大丈夫なの?高柳さんに甲斐性があるのかしら?』
「大丈夫だよ。貢ぐことには慣れてる。チカも知ってるでしょ。冬真が、役者として大成するのを、私は命がけで支える。誰よりも近くで彼が仕事に没頭できる環境を整えてあげるの。今は、彼の夢が私の夢」
『命がけ……。大げさねえ』
チカは、コーヒーをひとくち飲んでから、遠い目をカフェの窓の向こうへ送る。
『ま、頑張んなさいよ、気が済むまで。マイナスからのスタートで、生活は苦しいかもしれないけど、いつか、アンタの願い通り、高柳冬真って役者の実力が認められるといいわね』
「うん。本当、そう思う。私も冬真も、まだ発展途上。力を合わせて、どんな困難もふたりで乗り越えていけるよ」
『何度きいたんだかねえ、そのセリフ。また浮気相手募集されて棄てられるんじゃないの?治ってんのかしらねえ、高柳さんの浮気グセ。今はお互い盲目になってるけど、やっぱり違うって棄てられないようにね。
ま、そうなったら、また不幸話きかせてよ。
酒の肴にするからさ。アンタの不幸話に勝る肴はないからね』
「相変わらず趣味悪いなあ。運命の恋人に二言はありません。もう一生チカには美味しい酒の肴はありません。残念でした」
『だからさあ、何度きかせるのよ、そのセリフ。もうきき飽きたって。
やっぱり不安になってきたわ。
また同じ繰り返しになる予感が、ぷんぷんするわよ』
「縁起でもないこといわないでよ。結婚は決まったことなんだから、次はないの!遊んで棄てられるの繰り返しだった過去の恋愛は、冬真と出会うためにあったの。だから、繰り返しはもうありません!」
じっと未来を眺めていたチカの口元が、ふっと緩んだ。
『いじめるのもこれくらいにしておくか。
未来、結婚、おめでとう』
はにかむように未来が柔らかく笑った。
「ありがとう。チカにこんな報告する日がくるとは思わなかったよ。本当に、私、結婚するんだなあ。ふふっ」
『気色悪い笑い方しないでよ。ご祝儀は弾むかあ』
「あ、それ助かる。今は少しでもお金がほしいところだから」
『生活費を渡すわけじゃないわよ!ひとを金づるみたいに……』
「えー、ちょっとくらいいいじゃない。チカ、稼いでるのに使い道ないでしょ?人助けだと思ってさ」
『冗談じゃない!ようやくアンタが結婚して、お役御免になったっていうのに、なんでまだアンタの生活の面倒みなきゃいけないのよ。あたしを見習って自立しなさい』
「ケチだなあ、チカは」
『ケチで結構。で、籍はいつ入れるの?』
「まずは新潟の実家にふたりで挨拶に行こうって話してる。お母さんには、迷惑とか心配とか、いっぱいかけたし、安心させてあげなきゃねって。仕事が軌道に乗って、落ち着いたら籍入れようって。だから、まだ少し先の話になりそうかな」
『その間になにもないといいわね』
「今度こそうまくいってほしいけどね。上がって下がってのジェットコースターはもううんざり」
『ま、ここまでくれば大丈夫でしょ。あたしのためにもちゃんと結婚してよ』
「はいはい。ちゃんとお嫁さんになります」
『お嫁さん!似合わないわね、アンタ!』
けたけたと愉快そうにチカが笑う。
未来もつられて笑いながら、「本当だね」と返した。
穏やかな時間が、未来の横を通り過ぎていった。
仕事を終え、帰宅するために、未来が勤務先の病院を出ると、「あ、あの……」とか細い声に呼び止められ、振り返った。
振り向いた先には、未来とそう年齢の変わらなそうな長身の男性が立っていた。
若干戸惑いながらも、「はい?」と返事する。
邪険にするわけにもいかない。
声をかけてきたのは、顔見知りの男性だった。
男性は自身の靴の辺りに視線を落とすと、もじもじと、女々しい動作をしながら、言葉を続ける。
「小野寺さん、ですよね」
「……そうですけど」
「あの……実は、僕……」
12月10日(日) 焼き鳥屋にて
『ナンパされた?』
「そう。一昨日の仕事帰りに。仕事終わるまで待ってたみたいで、病院を出たところで声をかけられた」
『仕事が終わるまで待ってた?ちょっと、それって、またストーカーのたぐいじゃないの?』
「うーん、まだわからない。でも、一応顔見知りではある」
『顔見知り?』
「うん。うちの病院に通院してる患者さんなの。左腕を骨折して、しばらくうちに通ってる。だから、私の名前を知ってても不思議じゃない」
『ふーん、どんなひと?』
「すごいイケメン。すらっとしてて、顔もすごい整ってる、ちょっと陰のある感じのひと」
『それが、なんていってきたの?』
「病院に通ってるうちに、私をみかけて、好きになったって。付き合ってほしいっていわれた」
『……で、なんて返事したの?』
「ちょっと待ってほしいって。まだ高柳さんのことよくわかんないし、まずはお友達からって」
『アンタにしては理性的な対応。告白されただけですぐに頭に血がのぼって、付き合う、っていったのかと思った』
「色々経験してるからね、私も。しなくてもいいことまで。さすがに前みたいに後先考えずに付き合うことはしないよ」
『相手、高柳さんていうんだ』
「そ。高柳冬真さん。すっごいイケメンではあるけど、用心するに越したことはないから、もうちょっと様子見かも」
『そのいいかたからすると、その彼に運命は感じなかったわけね。……ん?高柳冬真……?』
「そうだけど……?」
『高柳冬真って……。ちょっと待ってよ』
チカはスマホを取り出すと、検索をはじめた。
未来もその様子を興味津々にみつめる。
「どうしたの?」
チカは、珍しく感極まったように興奮すると、スマホの画面を未来に見せてくる。
『高柳冬真って、もしかして、このひと?』
そこには、カメラ目線で、こちらを鋭く睨みつける高柳冬真が写っていた。
普段未来がみている高柳とは、雰囲気がだいぶ違うので、一瞬同一人物だと思えなかった。
「あ、そう、このひと。高柳さん」
『嘘!すごい!本物の高柳冬真に会ってるのね!羨ましいわ』
「なにものなの?高柳さんて」
『『絶命』に出てた俳優よ。あたしあの映画、3回も観にいったんだから』
「ああ、毎回号泣したって、あの映画か。なるほど俳優さんね。どうりで顔が整ってると思った」
『ちょっと待ってよ……。少し前のネットニュースでその名前をみた気がする……。あ!これだ。俳優の高柳冬真、撮影中の現場で事故、左腕を骨折、だって。やっぱりアンタに告白してきたの、高柳冬真だわ!』
チカがここまで熱く男について語るのは、珍しい。
『絶命』に心酔していたようだし、チカの熱にあてられて、未来も高柳に興味を抱きはじめる。
芸能人なんて初めてみた。
いわゆる芸能人オーラは感じなかったが、そんなひとに告白されたなんて、自慢話にできるかもしれない。
一体自分のなにを気に入ってくれたのだろう。
芸能界にいれば、綺麗な女優さんなんて飽きるほどいるだろう。
そんなひとたちを見慣れているであろう高柳が、何故自分を選んだのか。
未来の体が熱を持つ。
ああ、結局またいつもの恋愛モードに入ろうとしている。
自制を胸に決めたばかりなのに。
未来は、自分のなかにわだかまる熱気を冷まそうと、冷えたビールをあおる。
火照った体はなかなか冷めない。
高柳の顔が、頭に浮かんでは消える。
チカは、串刺しの焼き鳥をくわえながら、なおも高柳を検索している。
『『STARS』所属の25歳か。業界大手の事務所ね。高校在学中にスカウトされモデルデビュー。卒業後は俳優に転身。出演作も並べてあるけど、脇役のさらに脇役ってところね。代表作はなし。いわゆる売れない俳優ってやつね』
しかしチカは、満足そうに口角を吊り上げている。
『舞台もやってるのね。『絶命』でも演技力は光るものがあったもの。将来有望に違いないわ。舞台、やるならチケットでも取ってみようかしら』
チカは、いたく高柳を気に入っているようだ。
未来は、高柳が舞台に立っている姿を想像する。
胸が高鳴った。
トクン、と心臓が脈打つ。
観てみたい、と思った。
未来の知らない高柳の姿を。
恥ずかしそうに告白してきた高柳とは違う、凛々しい彼の姿を。
ああ、自分はどうしてこうも単純なのだろう。
高柳が、売れない俳優だと知った時点で、未来のなかに焦りが生まれる。
早く手に入れないと、誰かに掠め取れてしまうのではないか。
みすみす逃すわけにはいかない。
付き合ってから、彼のことを知っていったって遅くないのではないか。
少なくとも、向こうは未来を好きだといってくれている。
あとは、未来の気持ちひとつだ。
友達からはじめましょう、でも、付き合うこと前提で。
冷静な対応をしてしまった以上、すぐに付き合うことは軽い女にみられるからできない。
芸能人だと知って、それで付き合ってみたくなったなんて、口が裂けてもいえない。
ミーハー極まりないからだ。
そんなこと知られれば、せっかく彼から寄せてくれた好意が、翻されるかもしれない。
それだけは避けたい。
きちんと素性のはっきりした相手。
立場上、はじめから未来を騙すために近づいてきたとも思えない。
自分は世間を知らない素人だが、高柳にとって今は大切な時期で、イメージも大切な職業であることから、未来はそう判断した。
彼が誠実なひとであると、決して下心だけで自分に近づいてきたわけではないと確信できたら、新しい恋をするのも悪くないかもしれない。
まだ25歳と若く、売り出し中の俳優であることを考えると、付き合ってすぐに結婚というのは、難しいかもしれない。
結婚を焦る未来にとっては、痛いタイムロス。
それを上回るなにかを彼が与えてくれたなら、それは運命の相手だ。
彼がブレイクしたりすれば、結婚は更に遠のく可能性だってある。
けれど、それこそが運命というのなら。
未来は、待つ決意を持つことができる。
『顔、にやけてるわよ』
冷たいチカの声で、はっと未来は我に返った。
いけない、またチカにお説教される。
「す、すぐに付き合うとはいわないよ。うん、いわない。彼のことをよく知ってから……」
『まだなにもいってないけど。付き合う気は大いにあるってことね』
「だ、だって、チカが煽るから!なんか惜しい気がしてきて……。今逃したら後悔するかもって焦ったというか……」
『まあ、あたしも興奮しすぎたわ。でも、煽ってはいない。あたしのせいにするのはやめてよね』
「わかってるって。慎重に、でしょ?彼が遊びでなく真剣に私のことを想ってくれてたのなら、私も誠実に向き合うよ。それならいいでしょ?」
『いちいちあたしに確認とる必要はなし。あたしはアンタの保護者じゃないんだから』
「え、似たようなものでしょ?」
『ちょっと、やめてよね。あたしに依存しすぎ。なんであたしがアンタの世話しなきゃならないのよ。いくつまであたしに頼るつもり?アンタ、あたしが死んだら破滅するんじゃないの?』
「するよ。だから、チカはいつまでも私の面倒をみなきゃいけない。私が男選びに失敗したら、正義のヒーローみたいに助けてにきてくれて、愚かな私に説法をする。私が幸せな結婚をするまで、チカは私の親みたいなもん」
『やだやだ、そんな人生いやよ!なにが悲しくて自分のこと愚かとかいってるアホ女のためにあたしの時間を削らなきゃいけないの!アンタにとって貴重な時間はあたしにとっても貴重な時間なのよ』
「だから、私が結婚すればチカはお役御免なわけよ。早く私から解放されたかったら、協力して運命の相手探しを手伝うしかないの」
『厚かましいわね、アンタ!全然あたしを巻きこんで悪いと思ってないのね。大学時代のあたし、こんな女と親しくなっちゃ駄目よ、あたしの人生が破滅するわ!』
やけ酒をあおったチカの悲痛な声が、焼き鳥を焼く煙とともに舞い上がり、換気扇から冬の街を流れ、消えていった。
12月15日(金) ランチタイムのそば屋にて
『相当夢中になってるみたいね』
熱々の天ぷらそばに息を吹きかけながら、チカがからかうようにいった。
相変わらずチカは猫舌だ。
それを指摘すると、不機嫌になって『第一子は総じて猫舌なのよ。親に大事にされた証』と、決まっていう。
しかし今の未来には、チカをからかう余裕すらない。
そう、実際、未来は夢中になっていた。
高柳冬真に。
あれから、チカにお情けでプレゼントされたプレイヤーで、高柳が出演した映画やドラマを漁るように毎晩見続けていた。
ちらとでも映った高柳の姿を、何度も巻き戻しては、うっとりと彼に見惚れる。
学校が舞台のドラマでは、制服姿の生徒役のなかから、その他大勢の高柳を見つけ出すことに熱中したし、殺人犯の青年役を演じたドラマを観たときには、役名がついたことに感激した。
配信でのみ視聴できる作品では、3番手、4番手の役柄も着実に増えてきている。
近年は、漫画やアニメなど2次元の作品を舞台化したミュージカルなどにも出演していて、かなりの美声を響かせている動画も、見漁っていた。
高校生から大学生、新社会人役が多いが、この先更に、演じる役柄の幅も増えれば、たくさんのひとに高柳冬真という役者を知ってもらえるかもしれない。
輝かしい高柳の将来に思いを馳せ、未来の頬は緩みっぱなしだ。
高柳の怪我は完治していた。
しかし、彼は未来の勤務先までやってきて、夕食に誘ってくれる。
会うたびに、彼に驚かされる。
毎回、雰囲気が違うのだ。
前までは、どこか陰気な、陰のあるひとにみえたのに、今は爽やかな好青年の笑みを浮かべている。
未来に、自分の職業が俳優だと知られたと知った彼は、どこか恥ずかしそうに役柄が憑依するのだと語った。
実生活にまで役柄が影響するとは、大変な仕事なのだなあ、と感心せざるを得ない。
それだけ、高柳が演技派だということなのだろう。
天職を実際に仕事にできる高柳は、恵まれているほうなのかもしれない。
普段の彼は、飾らない年相応の青年で、連絡先を交換したあと、こまめに連絡をくれる。
地に足のついた、身の丈に合った生活を送っているようで、未来を連れていく店も、リーズナブルな場所ばかりだ。
変に背伸びしない、高柳の人柄が伺えて、好感度はうなぎのぼりだ。
画面越しに観る彼と、目の前で屈託なく笑う高柳をみるたびに、高柳の全てを知るのは、自分だけに与えられた特権のような気がして、妙にこそばゆい心持ちになる。
もっと高柳冬真という俳優を認知してほしい、けれど、皆が高柳の魅力に気づいたときには、すでに高柳は未来だけのものとなっている。
そんな明るい展望まで抱きはじめている。
恋に恋する暴走がはじまる一歩手前。
興味はあるが、特に仕事の話はきかない。
高柳に、自分が芸能人だから興味を持たれたと誤解してほしくないからだ。
しかし、何回目かのデートを重ねたとき、高柳のほうから、「今度出演する舞台を観にきませんか」と誘われた。
画面越しにしか観たことがなかった高柳の演技を間近でみられる。
未来はふたつ返事で了承したが、そこでふと考えて、「友達も連れて行っていいですか?」ときいてみた。
高柳は、少し驚きながらも、いいですよ、といってくれた。
ボロアパートを見られるのは恥ずかしいので、デートはいつも、アパート手前の公園で終わる。
吐く息が白く凍りつきそうな夜、高柳は、名残惜しそうに、初めて未来の冷え切った手を繋いできた。
ふたりは、まだ恋人ではない、あやふやな関係だった。
いつまでもは待てない、高柳のそんな意思表示のようにも思えた。
求められている。
高柳の真摯な瞳が、ひたと未来を見据える。
静寂が落ちる住宅街で、ふたりは無言でみつめあう。
やがて、未来の手が温まったころ、高柳がぽつりといった。
「稽古、本当に頑張っているんです。小野寺さんに観てほしくて」
未来は、彼に抱きつきたい衝動に駆られた。
それは、いじらしい愛情表現をしてきた高柳も、同じなのかもしれない。
ふたりは互いの意思を確認し合うように見つめ合ったあと、どちらからともなく手を離して、それぞれの帰路についたのだった。
舞台の幕が開いた。
ライブやコンサートに行ったことすらない未来にとって、舞台鑑賞というハードルはなかなかに高かった。
『だからってあたしを誘わなくてもいいんじゃない?』
一緒に劇場の席についたチカは、『せっかくの休みなのに』と不満な様子を隠そうともしない。
「高柳さんのファンなんでしょ?彼が出る舞台に興味ないの?チケット取るとかいってたのに」
『あれは、勢いよ。あたしは『絶命』のファンなの。『絶命』の片瀬智久には興味あるけど、高柳冬真のファンなわけじゃないわ。それに、アンタの恋人候補の晴れ舞台を一緒に鑑賞なんて趣味悪い』
片瀬智久とは、映画『絶命』で、高柳が演じた役名だ。
確か、あの映画でも彼は非業の死を遂げる役だった。
これから初日の幕が開く舞台でも、彼は悪役で、最後は死を迎える。
勧善懲悪で人気を博した漫画の舞台化。
原作の漫画を借りて読んできたが、またしても与えられた役柄が悪役ということに、歯がゆい思いもしている。
勧善懲悪の舞台なのだから、主人公が倒す悪がいなければ始まらないわけで、わかってはいるのだが、物足りなさを感じてしまのも事実だった。
早く主役を演じられる役者になってほしい。
早く賞を取れる役者になってほしい。
早く人気も知名度も高い役者になってほしい。
そんな複雑な思いを振り切るように、舞台が幕を開けた。
漫画の再現度の高さと、圧倒的なエンターテインメントの迫力に、2時間半、未来は息をするのも忘れて魅入っていた。
役者の熱量とそれを裏切らない演出。
観るもの全てを物語のなかに惹き込む引力。
高柳の役は、なくてはならないものだった。
彼の役がいるからこそ、正義とはなにかを考えさせられる。
一筋縄ではいかない現実の矛盾を孕んだ高柳の役は、勧善懲悪のなかにありながらも、果たして彼を悪役というだけの言葉に押しこめてしまっていいのかを考えさせられる。
正義と悪が、混濁するなか、彼は死を迎える。
そこに、すっきりした結末は訪れない。
彼は本当に悪なのか。
主人公がかざす正義とはなんなのか。
どちらが悪でどちらが正義なのか、その明確な答えを提示しないまま、舞台は終わりを迎える。
終演後、現実に戻れず呆然とする未来を引きずってチカは劇場をあとにした。
ついてきてよかったと、チカはため息をつきながら未来を引っ張って電車に乗る。
『全く手間かけさせないでよね』
電車に乗ったあとも、愚痴を垂れ流すチカを尻目に、未来は舞台で輝く高柳の姿をひたすら反芻していた。
高柳の演技力は圧巻だった。
主役を食ってしまいそうなほど、という感想を抱くのは、未来が高柳に特別な感情を感じているからだろうか。
約2時間半のあいだ観た舞台で、未来の脳裏に蘇るのは、脇役のはずの高柳の姿ばかりだ。
結婚相手に求める条件として、「尊敬できる」というのは、かなり上位にくる項目ではないかと、未来は思う。
それをいうと、今日の高柳は未来の想像の遥か上を行く才能を感じさせた。
尊敬する、どころかその才能に簡単にひれ伏せてしまえるレベルの。
頭が痺れたように思考が停止している。
目の前の風景すらぼやける。
完全に、のぼせ上がっている。
胸が絞めつけられて痛い。
高柳を想うたびに、吐息が熱を持つ。
彼の才能に、憧れさえ覚える。
そしてそれを自覚するたびに、なんの取り柄もない自分に失望する。
高柳は、こんな自分で本当にいいのだろうか。
もっと、彼の才能に相応しい相手がいるのではないか。
未来が空っぽの女だと知ったら、棄てられてしまうのではないか。
夜景が残像を残しながら流れていく。
未来の火照った体に、ガタンゴトンという電車の心地よい揺れが興奮を鎮めてゆく。
隣に座ったチカが、ことん、と事切れた人形のように、未来の肩に頭を預けてくる。
未来の面倒をみすぎて疲れたのか、眠ってしまったようだ。
未来は親友の寝顔を微笑ましげに眺めながら、スマホをバッグから取り出した。
何度も打ち損じながら、筋の通った文章を作成しようとする。
……上手くいかない。
未来は諦めて、ごくシンプルな言葉を終演後で疲れているであろう高柳に送信した。
『私と、お付き合いしてください』
12月25日(月) イタリアンレストランにて
夕食時の小洒落たイタリアンレストランは、カップルで溢れていた。
ワインをひとくち飲んだチカが、窺うように未来を見つめると、小首をかしげた。
『なんか、落ち着いたわね、アンタ』
「そう?満たされてるからかな」
未来は大人びた微笑を浮かべてみせた。
『上手くいってるんだ、高柳さんと』
「うん。あれからひとりでも舞台観に行ったし、彼も仕事のあいだに時間を作ってくれてデートしてる。順調だよ。
ねえ、きいて。冬真くんね、来年ドラマの準主役に決まったの。月曜日のドラマ枠の。
すごくない?やっぱり今やってる舞台が評価されたみたい。
……でも、撮影に入っちゃったらなかなか会えなくなるみたいで、嬉しいやら寂しいやら、複雑なんだよねえ。
今は寝る前にかかってくる電話で喋ることが楽しみ。
仕事も冬真くん見習って頑張るようになったし、そうしたら生活が上手く回るようになって、なんていうか、幸せ」
『いいことじゃない、忙しくなるなんて。売れっ子俳優まっしぐらね。変装もせずにデートしたらまずいんじゃないの?スキャンダルは、一番事務所が気を使ってるんじゃないの?』
「そうだね。なかなか外では会いづらくなるかもしれない。でもいいの。今は仕事に専念してほしいし、私と彼の絆はそんなことで壊れたりしないって信じてる。だって、この出会いは……」
『運命なんだから』
「当たり。不思議なの、今は不安が全くない状態で、彼を見守れてる。単純に彼が評価されることが嬉しいし、才能が認められてもっとたくさんのひとに彼の演技をみてほしい。冬真くんは、もっと早く発掘されてもよかった役者だよ。これからどんどん有名になって成功してほしい。それが叶うなら、私はいつまでだって彼のそばで支えるよ。……でも、恋人の座は、誰にも譲らない」
『献身的なんだか強欲なんだかわからないわね』
チカは、賑わう店内を見回して、ため息をつくようにいった。
『で、今日、愛しの彼は?恋人の一大イベントのクリスマスに、あたしなんかと過ごしてていいの?』
店内にも、窓からみえる大通りにも、イルミネーションに照らされたカップルが街を闊歩している姿が目立つ。
店にも、大きなクリスマスツリーが置かれ、きらびやかな電飾がチカチカと瞬いていた。
恋人にとっては特別な意味を持つ日。
この日のために恋人を作るひとも多い。
未来も、そうしようとしていた。
けれど今は、焦りを感じない。
街ゆくカップルたちを見ても、心は凪いだままだ。
未来はゆっくりワインを飲むと唇を笑みの形にした。
「仕事なんだって。ファンクラブのイベント」
『ファンクラブ?』
「そう。冬真くんにもあるんだよ、ファンクラブ。芸能人はカレンダー通りに休みがあるわけじゃないし、休みの日こそ仕事がある職業だから。そこは割り切らないとね」
『ファンクラブかあ……。売り出し中の若手俳優の恋人なんて、見動きが自由に取れない立場になんてよくなる気になるわね。高柳冬真に恋人がいるなんてファンが知ったらアンタ、後ろから刺されるんじゃない?』
「確かに、私にも推しがいたら、そう考えるかもね。応援してたのに、裏切り者って」
『アンタはファンクラブ入らないの?』
「私も入ろうかなっていったことあるんだけど、恋人とファンは違うからって冬真くんに断られちゃって。クリスマスは一緒に過ごせないけど、年末に少しだけ時間ができたから会おうって約束してる」
『じゃあ、年末年始は恋人がいるのに、基本的にスケジュールは空いてるわけね』
「まあね。ねえ、チカ、お正月に初詣、一緒に行かない?縁結び神社」
『気が早いわねえ。付き合ってる相手がいながら、まだ縁結びのご加護がほしいの?』
「彼と縁が離れませんようにってお祈りしたいの。彼の成功も祈願したいし」
『やっぱ強欲だわ、アンタ。神様もそこまで寛容じゃないわよ、きっと。願いはひとつだけにしなさいよね。
……それにしても、お正月、なんであたしのスケジュールが空いてるって決めつけてるわけ?』
「え?だってチカ、お盆も年末年始も帰省しないじゃない。友達だって私とサキしかいないし……予定、なんかあった?」
『……ないけど。友達が少ないっていうの、結構コンプレックスなんだから、思い出させないでよ。
家族とは、もう絶縁状態だし、あたし、もしかして孤独なんじゃない……?』
「あれ、今更気づいた?仕事をしすぎるのも考えものだねえ。
趣味の合う仲間とか作ってプライベート充実させたら?」
『あたしのこの性格に付き合ってくれる友達なんてこの歳から新しくみつけるのはなかなか難しいんじゃないかしら』
「まだ家族と喧嘩してるの?大人になってチカから歩み寄ってみたら?親だって歳とるし、絶縁したまま死んじゃったら後悔するんじゃない?」
『あたしだって歩み寄ろうとしてるわよ。頑なにあたしを拒絶してるのは向こうなんだから、どうしようもないじゃない』
チカは、ぶすっと不機嫌そうにワインを煽る。
「まだ家族のひと理解してくれないの?」
『もう永遠に理解なんてできないわよ、頭が堅いんだから。親だから、どんな子どもでも受け入れてくれる、なんて幻想だわ』
「ふうん。寂しい話だね」
『もう慣れたわ。だから、あたしには仕事が必要なの。家族にも頼れずに、ひとりで生きていくしかないんだから。甘いこといっていられないのよ』
「うちも親、離婚してるから、家族には苦労させられてきたけど、お母さんは私のことちゃんと育ててくれたし、感謝しないとかな」
『当たり前。感謝しなさい』
「だから、やっぱり早く結婚して孫の顔みせてあげるのが親孝行なのかな。……やばい、また焦ってきたかも……」
『自分で自分を追いこんで、馬鹿じゃないの?今は高柳さんと上手く関係を続けることが親孝行への近道よ。慌てず焦らずがっちり高柳さんを離さずにしがみついてなさい』
「わかった!やっぱり縁結び神社行こう!」
『仕方ないわねえ……。ま、いいわ。初詣、行きましょう。あたしもお願いしてあげる。未来と高柳さんが、なんのトラブルもなく結婚できますようにって』
「……トラブルがあるの前提でお願いしてない?」
『してる。アンタがなんのトラブルもなく男と付き合えるわけないもの。でも、運命の恋人なら、どんな試練だって乗り越えられるでしょ?』
「もちろん!冬真くんとなら、なんだって乗り越えられる!運命の恋人だもん!」
拳を握りながら、叫んだ未来を、周りのテーブルの客たちがくすくすと笑い合っている。
恋人たちが未来たちを優越感たっぷりにみつめている。
でも、気にならない。
見てろよ、カップルたち!
私は、あんたたち以上の幸せを手に入れてみせる。
『ちょっと、恥ずかしい!』
チカが未来の服の裾を掴んで座らせる。
すっかり酔った未来は、高柳との未来を想像して、過ぎゆく聖夜をいい気分で終えたのだった。
12月30日(土) ホテルにて
来年ブレイクしそうな俳優ランキングに、高柳冬真がランクインした。
高柳は、仕事についてあまり多くを語らないが、世間の風潮が、高柳への期待値が高まっているのは、未来も感じはじめていた。
来年早々はじまるドラマで注目が更に集まるのは間違いない。
こつこつとキャリアを積み上げてきた、高柳の努力の結晶ともいえる結果だった。
風向きは確実に変わっている。
世間は高柳に気づきはじめている。
ブレイク前に彼と出会えたのは幸運だった。
スターへの階段を、駆け足で昇っていく彼の後ろ姿を、未来は必死で追いかけていた。
今、高柳のスケジュールは着実に埋まっている。
そんなブレイク前夜、わずかな時間を利用して、未来と高柳は逢瀬を重ねていた。
「こんなホテルでごめん」
けばけばしい色で彩られた部屋で、バスルームからでてきた高柳が、長く伸びたブラウンの髪をタオルで拭いながらいった。
甘い時間の余韻に浸っていた未来は、首を左右に振ると、自分もシャワーを浴びようとベッドから立ち上がる。
未来の色白で柔らかな体を見た高柳は、シャワーを浴びたにも関わらず、またも未来の体を抱き寄せた。
首筋にキスを落とし、ベッドに押し倒す。
「もう……これから仕事なんでしょ?」
甘い誘惑に負けそうになりながら、未来は高柳の体をやんわりと押し返す。
しっかりと鍛えられた胸板に顔を埋めると、
彼の匂いを少しもこぼさないように、深く息を吸う。
我ながら変態的な行為だと思う。
でも、高柳のなにもかもを逃したくないという独占欲に抗えない。
永遠に続いてほしいと願いながらも、刹那の快楽に溺れる退廃的なこの瞬間も、未来はたまらず好きだった。
重い女になりたくない。
でもきかずにおれない。
「冬真……私のこと好き……?」
絶え間なくキスの雨を降らせる高柳の合間を縫って未来はそう問いかける。
荒い呼吸をしながら、「好きだよ。世界で一番未来が大切だ」あえぐように高柳は答えた。
お互いの体温で汗が滲む。
高柳の鼓動を感じる。
ああ、幸せだ。
今度こそ、遠い憧れを手に入れられるかもしれない。
結婚という、究極の愛の行き着く先を。
「仕事行かなきゃ」
高柳のそのひとことで、夢のような時間が終わる。
抱き合ったあとの気だるさを全身に感じながら、未来はベッドから、服を着る高柳を眺めていた。
愛し合ったあとの高柳はどこか冷淡だ。
現実が、未来にそう思わせた。
ずっと高柳と一緒にいたい。
甘えて抱き合ってキスをしていたい。
高柳をひとり占めして離したくない。
すっかり服を着終わった高柳は、今の今まで未来にみせていた、快感で蕩けそうな表情を一切消し、余所行きの顔に戻っていた。
未来を一抹の寂しさが襲う。
それでも未来は、笑顔を作っていった。
「うん、お仕事頑張って」
「未来がいるから頑張れるよ」
「……次、いつ会える?」
「……そうだな、次に休みが取れるのは……ちょっといつになるかわからないな」
「……そっか……。わかった、忙しいもんね、冬真。私のことは二の次でいいから。冬真が楽しくお仕事できるのが一番。電話で話せるだけで私は満足だから」
「我慢強いな、未来は。もう少しわがままでも可愛いと思うけど。ま、そこが未来のいいところか」
コートを羽織ってバッグを持つと、「また連絡する」といい残して、高柳はホテルの部屋を出ていった。
ひとり残された未来は、ベッドに寝転んで、高柳の残り香を堪能するように大きく息を吸う。
満たされた空間。
未来と高柳だけが知る秘められた濃密な時間。
未来は、知らず知らず緩む頬を自覚しながら、余韻に浸るように目を閉じた。
1月1日(月) 初詣帰りのカフェにて
『すごいひと。初詣なんて久々にきたけど、元旦にくるもんじゃないわね。神社で並んでるときなんて、真冬なのに汗かいたもの』
「チカは汗かきだもんね。でも、神様に願いを叶えてもらうには、このくらいで音をあげちゃいけないんだよ」
『あたしは無宗教なの。必要なときだけ思い出したように神頼みする日本人て罰当たりね』
「私は毎年きて、縁結びを祈願してるけど……。どうしようもないときに最後に頼るのが神様でしょ。いつもは意識していないだけで、心のどこかには神様はいるんじゃないかな。心の支えっていうかさ」
『神様も普段から崇めてほしいでしょうね。一方的に頼られて、案外神様も迷惑してるかもね。見返りはなにもないんだから。普段から信心深いひとの願いだけ叶えていたいって思ってるかもよ』
「うーん、確かに。でも、冬真に関する願いだけは叶えてほしいなあ。それ以外は、高望みしないからさ」
『高柳さんのなにを?ドラマがヒットしますように?それとも結婚できますように?』
「もちろん、冬真の仕事が上手くいきますように、だよ。結婚はあとでいいの。今は、彼が成功するのが一番」
『へえ。25歳になるまでに死にものぐるいで結婚をゴリ押しするのかと思ってた。どういう心境の変化?』
「自分より大切に思えるひとと出会ったから、かな。仕事に没頭する彼をみてたら、自分の結婚願望とかが、ちっぽけに思えたというか。
もっと人間として成長しないと彼に置いていかれる気がしてさ。
努力家な彼に相応しいのは、今の私じゃない。もっとひととして一人前のひとなんじゃないかなって」
『ほお。それはそれは。向上心の欠片もなかったアンタにそんなことをいわせるとは、高柳さんてすごいわね。本当に、運命の相手なのかも』
「……なんか、チカが褒めると調子狂うな」
『ま、いい加減、神様も根負けしたのかもね、アンタの結婚願望に。そろそろ、運命の相手と出会わせてやるか、って』
「そうだと嬉しいなあ」
高柳は、慣れないドラマの撮影に奮闘しているようだった。
これまでの、一瞬しか映らない名もない端役ではない。
物語の中心的役割だ。
忙しさも、比べものにならないのだろう。
また、半年先まで仕事が決まったと、端的に高柳は語っていた。
今が一番の勝負所であると、未来も薄々わかっていた。
だから、会いたい、などと未来からはいわない。
いいたい気持ちをぐっと堪え、物分りのいい彼女を演じた。
わずかに取れる休みをやりくりして、高柳は会いたいと連絡してくる。
未来は、そのたびに自分が忘れてられたわけではなかったことに胸を撫で下ろす。
高柳が、新しい環境に身を置いたことによって、彼が目移りする可能性はいくらでもある。
華やかな世界を知って、どこにでもいるような一般人の未来に魅力を感じなくなることだって有り得ると、どこか危機感を持ち、仕方のないことだと予防線を張っている自分もいた。
だから、高柳から会いたいといわれると天にも昇る心地だったし、高柳との間に、決して切れない赤い糸があると信じることができた。
最近、高柳と会うのは、もっぱらホテルと決まっていた。
街中を歩くデートはできないし、お互いの部屋へ出入りするのも危険だった。
結果的にふたりはホテルで落ち合い、必然のように体を重ねた。
貪るように、むき出しの欲望をぶつけてくる高柳に、未来は内心で幸福を叫ぶ。
高柳がどこまで有名になっても、彼が自分を切り捨てることはない。
会うたびにそう確信ができた。
自信を持つことができた。
彼の原動力になれるのなら、この体をいくらでも差し出そう。
隣で寝息を立てる高柳の寝顔を見て、未来は感じたことのない充実感にどっぷりと浸かっていた。
投げ出された高柳の手を取り、そっと小指を絡める。
ふたりだけの秘密。
ふたりだけしか知らない時間。
永遠に解けないふたりの絆。
「ずっと一緒。約束だよ」眠る高柳の耳に、そっとささやく。
未来は幸せに押し潰れそうになりながら、必死で息をして、高柳を悦ばせる存在でいたいと強く願った。
縁結びの神様に。
1月14日(日) 喫茶店にて
「今からきてほしい」と高柳から連絡を受け、未来は指定された喫茶店を訪れていた。
初めてくる店だ。
キョロキョロと狭い店内を見回し、高柳の姿を探すが、彼の姿はみえない。
店に入ってきて、戸惑ったような表情を浮かべる未来に、席に座っていた若い女性が気づき、つかつかと、パンプスを鳴らしながら近づいてきた。
背の高い、非の打ち所がない美形の女性だった。
銀縁の眼鏡が、どこか冷たさを感じさせる。
ブラウンの髪を伸ばし、スタイルの良さを隠すようなロングスカートをはいている。
清潔感を漂わせる、大人びた女性だった。
彼女が真っ直ぐに自分のほうに向かっていると気づき、未来は困惑しながら女性を目で追う。
「小野寺未来さん?」
涼やかな声が冷たく響く。
「そう……ですけど」
同性で、更に同年代でありながら、未来は女性の気迫に気圧されていた。
ただものではない。
そんなオーラが、女性からは溢れていた。
「どうぞ、席へ」
女性に案内されるがまま、未来はボックス席に腰を下ろす。
誰なんだろう、このひと。
自分の名前を知っているということは、高柳の知り合いなのかもしれない。
今日、この店へくるよう連絡してきたのは、高柳なのだから。
もしかして、高柳の所属事務所のひとだろうか。
交際がバレたとか……?
勝手に想像が膨らんで未来は蒼白になる。
まさか、別れろ、といわれるのではないか。
妄想取り混ぜて頭を混乱させていた未来は、対面に座る男性の存在にようやく気づいた。
かっちりとスーツを着こなし、黒髪を撫でつけた壮年の男性だった。
未来を案内した女性が、男性の隣に座り、未来と対峙する。
店内は閑散としていて、内緒話をするにはこれ以上ないほどの環境だった。
不安そうな顔つきの未来を安心させるように、女性が薄く微笑んだ。
「初めまして、小野寺さん。わたしは、高柳冬真の妻の、高柳麗香といいます」
「……は?」
未来が投げつけられた言葉を咀嚼できずに、呆けた声を出すと、くすりと麗香が小さく笑った。
「急に呼び出してごめんなさいね。なんのことだかわからないわよね。
主人がお世話になっています。
妻として、お礼を言わせてもらうわ」
……妻?
……高柳麗香?
未来の脳が理解を拒絶する。
高柳に、妻がいた……?
高柳に、結婚しているかどうか、尋ねたことはない。
そんな可能性、思いつきもしなかったからだ。
高柳は、付き合いたいと声をかけてきた。
未来を好きになったと。
歳もまだ若く、そんなふうに告白してきた男性が、結婚しているなんて可能性すら思い浮かんだことがなかった。
高柳が妻帯者……。
ふと、働かない未来の頭がある事実を突きつける。
……自分は、気づかないうちに不倫していたのではないか。
高柳冬真に、騙されていた?
……いや、冬真は騙してなどいない。
未来が無意識にその可能性を排除して、きかなかっただけだ。
高柳は既婚者だとも、独身だとも、明言していない。
高柳から告白してきた以上、彼が自分から結婚していることを話すわけがなかった。
知らない間に、自分は高柳の不倫相手になってしまっていた。
麗香は、微苦笑しながら、柔らかい口調で言葉を続ける。
「主人……冬真は、わたしの存在を隠してあなたと付き合ってたんでしょう?
本当、女好きで困っちゃう。可哀想に、あなた、彼に騙されていたのよ」
……冬真に、裏切られた。
そう頭のなかで瞬時に思ったのに、未来の口からは、自分でも信じられない言葉が流れ出す。
「私……知りません、そんなひと」
未来の返答に、麗香は切れ長の目を細めて、軽くため息をつくようにバッグに手を差し入れる。
「そう。あなた、彼に遊ばれたのよ。彼に、庇う価値はないと思うけど」
麗香は、1枚の紙をテーブルに置き、未来にもみえる位置まで滑らせていく。
それをみた未来の顔色が青ざめた。
動揺していることは明らかだった。
唇が細かく震える。
手足が冬の街を歩いたあとのように熱を奪われて冷たくなっていく。
頭のなかが真っ白になって、呼吸が浅くなる。
麗香が差し出したのは、1枚の写真だった。
親密な様子で、顔を寄せ合ってホテルから出てくる高柳と未来が映った浮気の決定的な証拠だった。
全身から汗が噴き出す。
いい逃れできないその証拠に、未来はうなだれる。
「浮気調査専門の探偵を雇って、あなたと主人のことは調べてもらいました。まだいい逃れをするつもり?」
探偵など、映画やドラマなどでみるだけの、想像上の職業で、決して未来が生きる世界には縁のない存在だと思っていた。
空想の存在にも等しい探偵に、後をつけられていたなんて、全く気づかなかったし、気づかれては探偵を名乗れないのだろうと、放心した未来は回らない頭で無意味なことを考え続ける。
「……ごめん、なさい……」
うなだれた未来は蚊の鳴くような声でもごもごと、謝罪の言葉を述べる。
「認めるのね?」
勝ち誇ったように麗香が未来の顔を覗きこむ。
「でもっ!」
がばっと勢いよく未来は顔を上げ、声を張り上げた。
「悪いのは私なんですっ。ただのファンのくせに、強引に彼をホテルに誘って、それで、彼は仕方なく私に付き合ってくれて……。無理やりだったんです、本当は彼も奥様を裏切るつもりなんてなくて……」
未来の言葉をきいた瞬間、麗香の表情が険しくなる。
「どうしてそこまで彼を庇うの?彼は、あなたに嘘をついて騙していたのよ?体目当てで近づいて」
「結婚しているかどうかをきかなかった私が悪いんです」
はあ、と麗香が苛立たしげにため息をつく。
「あなたに現実を教えてあげる。冬真の遊び相手は、あなただけじゃないのよ」
「……え?」
「彼ね、SNSで浮気相手を募集していたの。あなただけが特別だったわけじゃないってこと。彼が浮気していることに気づいて、彼と別れてもらうために、こうして浮気相手たちに会ってるの。あなたで3人目よ。でもまだまだ遊び相手は10人近くいるの。骨が折れるわ。彼を運命の相手だなんだと信じてるひとに、現実を突きつけて別れるよう説得するのは……。まあ、わたしにも悪いところがあるんでしょうけど」
麗香は未来から視線を外し、焦点の定まらないどこか遠くを眺める。
「わたしと冬真はモデル仲間で、同い年だった。付き合うようになってすぐ、わたしは妊娠した。冬真は、責任を取るといって、わたしたちは結婚することになった。21歳のときだったわ。でも、結婚してほどなくして、流産してしまった。わたしは、そのことを、すぐに冬真にいえなかった。わたしたちを繋いでいたのは、望まずにできてしまった子どもだけだった。
その子どもがいなくなったら、彼を繋ぎ止めることができなくなるんじゃないか。責任を果たさなくてよくなった冬真は、わたしのもとから去ってしまうのではないか……。と、わたしは怖かったの。結局自分に自信が持てなかったのね。彼を信頼することができなかった」
ひと息つくように、麗香は冷めきったコーヒーに口をつける。
未来は、身じろぎひとつできずに麗香の昔語りをきいていた。
「ずっと流産したことを隠し通すことはできなかった。ついに彼はその事実を知って、懸念した通りのことが起こった。わたしを顧みずに、遊び歩くようになったの。子どもができた責任を取ってわたしと結婚はしたけど、彼はまだまだ遊び足りない年齢だった。わたしだけじゃ満足できなくて、常に複数の女のひとが彼のそばにいた。結婚は、ただ紙切れ1枚で交わした契約にすぎなかった。彼を繋ぎ止めることはできなかったの。
でも、わたしは彼が好きだった。今でも、彼以上の存在が現れるとは思えない。
運命の相手だったの。
だから、いつ離婚を言い渡されるのか、ずっと怯えている。
でもね、まだわたしは冬真の妻なの。
彼がわたし以外のひとと付き合うことは許せないし、許さない。
彼に愛される資格があるのは、妻であるわたしだけ。
彼は離婚したいようだけど、わたしは絶対に応じない。やり直してみせる。
彼と、一生を生きていくのはわたしだけ。
だから、小野寺さん、悪いけど冬真と別れてちょうだい」
毅然とした口調とは裏腹に、麗香の目は保護者を失った子どものように、不安げに揺れていた。
未来を一抹の罪悪感が襲う。
麗香が語り終わると、示し合わせたように、今まで黙していた壮年男性が書類を取り出した。麗香が男性を手で示していう。
「この方は、弁護士の先生。彼の遊び相手のひとと交渉するために同席してもらっているの」
「……交渉?」
「そう。冬真と2度と会わないと、誓約書にサインをしてほしいの。もちろん、見返りは約束するわ」
「見返り?」
「ええ。小野寺さんは、いくらがいいかしら?そんなに稼ぎがあるわけじゃないから、上限はあるけど、あなたが望む金額をなるべく用意したいとは思ってる。そのすり合わせの交渉に、先生に立ち合ってもらっているの」
「……つまり、手切れ金ってことですか?」
「そう思ってもらってかまわないわ。お金で解決するなら安いものよ。彼に寄ってくる虫を札束で追い払うようなものね」
未来は悔しさに奥歯を噛みしめる。
高柳への思いは、金で清算できるものではない。
彼の才能に惚れこみ、誰よりも彼の成功を近くで見届けたいと強く願ってきた。
彼が妻帯者であることも、彼に遊び相手としてしかみられていなかったことも、未来の願いを微塵も揺らすことはなかった。
彼の一番そばにいたい。
「……お断りします」
「……え?」
「お金なんかいりません。だから、彼とも別れません」
「あなた、本気?今までわたしの申し出を断ったひとはいないわよ。冬真が欲しいのは、あなたじゃない。あなたの体なのよ?体目当ての男と関係を続けるより、お金をもらって新しいひとを探すほうが賢明な判断だと思うけど」
未来の脳裏に、高柳と過ごした甘くて密やかな、狂おしいまでに求め合ったあの時間が鮮明に蘇る。
あのときの、濡れたような高柳の瞳には、未来しか映っていなかった。
同じように、未来は高柳しか自分の瞳に映したくなかった。
あの時間が幻であろうと、仮初めであろうと 、確かにあの瞬間、世界にはふたりしかいなかった。
その事実は消えない。
高柳の肌の温もりも、すべすべの肌の感触も、未来のためだけに存在していた。
手放したくない。
たとえ、このひとから奪うことになっても。
「高柳さんは、私の運命のひとなんです」
ぴくり、と麗香が眉を吊り上げる。
「……あなた、馬鹿ね。冬真は、今が一番大切な時期なのよ。冬真のスキャンダルが発覚するまえに、わたしがその芽を摘んでいるの。あなただって、彼のことを好きなら、身を引くのが、彼のためだと思わない?」
「私が、彼を支えます」
麗香の顔つきが更に険しくなる。
「……後悔するわよ。なにがあっても、わたしのせいじゃないわ。全ては、愚かな決断をしたあなたのせい。冬真は渡さない。たかがファンの分際で、冬真の隣に並ぼうとするなんて、身の程知らず。絶対冬真と別れさせてみせる。冬真が選ぶのはわたしなんだから」
「高柳さんは、あなたの独占欲に辟易して他のひとに癒やしを求めるんじゃないんですか」
「うるさい!あんたみたいな女、絶対に破滅させてやる!大人しく金をもらって冬真のもとからいなくなれば、許してやったのに。交渉決裂ね、先生、行きましょう」
麗香は、怒りに顔を染め、美しい顔を鬼のような形相に変えて、隣の弁護士を伴って席を立ち、足早に店から去っていった。
ひとり残された未来は、自分の口から溢れるように出てきた言葉たちに、自分で一番驚いていた。
自分は世間でいう、浮気相手だ。
本妻に別れろと迫られてしかるべき存在。
未来のほうが悪だと、誰もが答えるだろう。
未来だってそう思う。
浮気という倫理に反する行為をしておきながら、本妻に別れない、と啖呵を切るなど、非常識極まりない。
しかしなぜか、未来はそうしてしまった。
おかしい。
自分は本来、こんな性格ではない。
自分が悪いと知りながら、浮気相手を本妻から略奪するなんて、正気の沙汰とは思えない。
世の中の、誰からも非難される行為だ。
でも、未来は思ってしまった。
高柳冬真の、世界で一番の味方でいたいと、周囲の誰もに非難されようとも、彼を護れる盾になりたいと、そう願ってしまった。
誰に嫌われようとも、責められようとも、彼を手に入れたい。
悪女になってもいい。
奪いたい。
麗香も、高柳のファンも、誰を傷つけることになっても。
未来は、悪役になることを決めた。
1月21日(日) ファミレスにて
『アンタ、馬鹿じゃないの!?高柳さんの本妻に喧嘩売ったの?既婚ってだけで充分スキャンダルなのに、浮気相手がたんまりいて、更に浮気相手のひとりが本気になって略奪を宣言するなんて、どんな泥沼よ?そもそも、高柳さんとは連絡が取れたの?』
「……取れてない。奥さんに呼び出されてから、連絡がとれなくなった」
『ああ……。まさかアンタが不倫略奪する悪女だったなんて想像もしなかったわ……。高柳さんの本心も知らずに運命のひとだとか宣言するなんて……。ちょっと目を離した隙に、なにが起こってるのよ。未来、本当にアンタどうしちゃったの?高柳さんが奥さんとやり直すって決めたらどうするの?』
「そのときはそのときだよ。冬真が奥さんを選ぶなら、私だって身を引く。でもね、まだ冬真の気持ちきいてないんだよ。冬真の気持ちがわかるまで、私は諦めない」
『浮気相手と別れさせたい奥さんに会うよう高柳さんが指示してきたことを考えると、自ずと高柳さんの気持ちもわかるような気がするけどね。アンタとの関係を清算したがってるって。奥さんに、高柳さんから頼んだ可能性だってあるわ』
「とにかく、私は冬真の本心を知るまで、彼を諦めない。きっと私を選んでくれるって信じてる」
『自分に自信があるのは悪いことじゃないけど、今のアンタの自信は根拠がなさすぎ。
考えてもみてよ。高柳さん、遊び人なのよ?結婚してるのに、浮気相手募集しちゃうような、だらしのないクズなのよ?
今までアンタが出会ってきた数々のクズと同じじゃない。
痛い目みたはずなのに、どうしてそこまで執着できるのよ。
傷つくのは、自分なんだからね。
何度もいうけど、高柳さんはやめておきなさい。節操のないクズよ。
私生活が足を引っ張って、芸能界で身を滅ぼすかもしれない。
そうなったとき、責められるのはアンタよ。
高柳さんのために、アンタは自分の人生を捨てられるの?
世間を敵に回して、誰も助けてなんてくれない状態になって初めて失敗したって後悔しても遅いのよ?
たかがひとりの男のために、人生を滅ぼすことはない。アンタは、まだ若いんだから。
高柳さんとの関係を終わらせて、新しい運命のひとを探しなさい。それが賢明な判断よ』
反対されればされるほど、燃え上がるのはなぜだろう。
高柳を失いそうになって初めて、未来は自分が是が非でも彼を手放したくないと頑なに思っていることに気づいた。
結婚を焦って選ぶ男はクズばかり。
それは、今回のケースにも残念ながら当てはまる。
けれど、なにかがいつもと違う。
「クズだから」で済まされないなにかを、高柳に感じている。
彼の、一生そばにいたい。
健やかなるときも、病めるときも。
スキャンダルにさらされるときも。
ふたりでなら乗り越えていける気がしたのだ。
それを、世間では略奪愛だといっても。
自分を一番大切だといってくれた高柳の甘い声。
たとえ高柳にとって未来が、遊び相手のひとりにすぎないとしても、彼を振り向かせたい、本気にさせたい、そんな闘志が、未来のなかでは燃え上がっていた。
絶対的な自信があるわけではない。
それは、願いなのだ。
叶えたい祈り。
冬真と、この先の人生をともに歩けますように、と神様に祈った純粋な願い。
透き通った水のような、晴れ渡った青空のような、純度の高い願い。
それは、なんの確証もないのに、この恋は永遠に続くと、無邪気に信じられた初恋に、どこか似ている。
ただ相手がそばにいるだけでいい。
それ以上のことは望まない。
それは、強欲という大罪に当てはまるのだろうか。
未来がそう尋ねると、間髪入れずにチカが切って捨てた。
『当たり前じゃない。大罪よ大罪。だって不倫よ?アンタをみる周囲の目だって厳しくなるに決まっているじゃない。娘が不倫のうえに略奪したなんて知ったら、アンタのお母さんどう思うか想像できる?悲しむに決まってるわ。それだけじゃない、もし世間にアンタがしたことがバレたら、お母さんの立場だって悪くなるかもしれない。アンタ責任取れるの?親に迷惑かけてまで手に入れたい男ってなんなのよ?』
「……わかんない。でも、私は冬真と一緒にいたい。ただ、それだけ」
『だから!それが許されないことだっていってんの!アンタ奥さんに訴えられたら負けるわよ。それが筋、世間の常識。
子どものころに習わなかった?
ひとに迷惑をかけてはいけません。
悪いことをしてはいけませんって。
アンタのしていることは悪いこと。
今すぐ悔い改めないと、アンタがすがった縁結びの神様に見放されるわよ。
天罰だって下るんだからね』
「天罰……重い言葉だね」
『そうでしょう。神の怒りに触れないように生きる人間にだけ、神様は祝福を与えるのよ。今のアンタは神様を裏切って、顔に泥まで塗ってる。いい加減目を覚まして。高柳さんのことは、出会わなかったものとして、違う男にしなさい。なんなら、あたしが適当に見繕って紹介してあげるから、ね、それならいいでしょ』
「……いい、のかな、それで」
『悪いことはいわない。あたしのいう通りにしなさい。自分から不幸に飛びこんでいく必要なんてないんだから。ね、だから、この話はもう終わり。高柳さんなんて男に、アンタは出会わなかった。恋もしなかった。それで終わり。忘れるの、いや、なかったことにするのよ、未来。
アンタなら、すぐに切り替えて違う男に夢中になれるわ。
これ以上、高柳夫妻に関わるのはやめなさい。
いい、誓えるわね?』
チカにいいくるめられ、未来は小さくうなずいた。
チカの言葉は、いつも正しく未来の心に染み渡る。
チカがそういうなら、そうなのだろうと、考えさせられてしまう。
未来がクズに夢中になるのを、破滅寸前で引き止めてくれるのはいつもチカだった。
チカがいうのだから、間違いはないのだろう。
未来は、自分に男を見分けるセンスがないとわかっている。それは自覚している。
恋に落ちると周りが見えなくなり暴走する未来を、チカは先回りして辛らつながらも的確な指摘で夢見る未来の目を覚ましてくれる。
だから、今回の件も、きっと……。
「忘れられないよ……」
チカにきこえないよう、未来は反抗するように呟いた。
2月9日(金) 未来の職場にて
昼休憩のために席を立とうとした未来のスマホが振動した。チカからだ。
「もしもし?」
『未来、大変なことになってるわよ!』
「……え?」
いつになく切迫した様子のチカに、未来は無意識に身構える。
「なにがあったの?」
『今日発売の週刊誌に……』
チカとの通話を終えると、未来は病院を飛び出して、近くの本屋に駆けこんだ。
呼吸も荒く雑誌のコーナに辿り着くと、今日発売の週刊誌を手に取り、周囲の目も気にせず、ページをめくる。
【今大注目の俳優 高柳冬真は結婚していた! さらに、10人以上の浮気相手がいることが発覚!中には、若手女優やモデルも! 泥沼不倫発覚で仕事に影響も?】
未来は頭のなかが、真っ白になり、衝撃的な内容を報じる雑誌を持つ手が震え出す。
ついに、恐れていたことが、現実になってしまった。
記事には、モデル仲間の女性を妊娠させ、結婚したこと、妻がいるにも関わらず、浮気相手を募集し、不倫を繰り返していたことが、詳細に、なんの誇張もなく書き綴られていた。
それだけに、高柳がしてきたことが下衆だったと痛感させられる。
高柳と不倫していたとして、若手女優や、未成年のアイドル、有名なモデルの名前などが並べられている。
彼女たちの写真とともに、見覚えのある写真が掲載されていることに、未来は震撼した。
顔をぼかされているが、それは確かに未来と高柳がホテルから出てくるところを収めた写真。
喫茶店で、高柳麗香に突きつけられた、探偵が撮ったという、あの、高柳と未来の不倫の証拠写真が、芸能人たちに混じって載せられていたのだ。
この写真を流失させたのは、高柳麗香だ。
麗香は、夫である高柳を、社会的に抹殺するために、週刊誌に情報を提供したのだ。
高柳は、高柳の仕事はどうなってしまうのか。
今撮影しているドラマは?
決定したと報じられたCMは?
果たして、高柳はこの先も芸能活動を続けることができるのか?
麗香は、別れないと執着していた冬真を、どうしたいのか。
自分と高柳の関係は、どうなってしまうのか。
高柳のしたことは、確かに最低だ。
妻がいながら浮気を繰り返していた。
それは責められてしかるべきだ。
知らなかったとはいえ、未来も不倫の片棒をかついでいた。
未来も、高柳に騙され、遊ばれている女のうちの、ひとりにすぎなかった。
しかし、本妻である麗香に、略奪宣言までするほど、高柳に心酔してしまった。
麗香も、他の不倫相手も関係なかった。
ただ純粋に、高柳が好きだった。
そばにいたかった。
それ以上は、望まなかった。
わなわなと、雑誌を持つ未来の手が震える。
雑誌を読み進めるうちに、未来の心に純粋に生まれてきたのは、怒りだった。
高柳がやったことは悪い。
それは認める。
だが、週刊誌のたった2ページに名前を載せられただけで、何人もの人間の人生が、大きく変わる。狂ってしまう。
これを執筆したひとは、この記事が、ひとを簡単に破滅させることを承知で書いているのか。
高柳から、信頼と仕事を奪って、彼の芸能活動を殺すも同然のことを、どうして平気な顔をしてできるのだろう。
高柳から俳優活動を奪うということは、彼の人生を奪うことに、場合によっては死に追いやることでもある。
ひとひとりを殺すことに他ならない。
高柳の演技は、見たひとを魅了する力がある。
惹きつける引力がある。
役者、高柳冬真を失うことは、芸能界にとって大きな損失になるだろう。
抜きん出るなにかがある。
目を離せないなにかがある。
役者、高柳冬真が一番輝く場所。
活き活きと泳ぎ回れる場所。
高柳には、スポットライトがよく似合う。
舞台のカーテンコールでみせた、達成感に満ち溢れる高柳の笑顔を、きらめく汗を、未来は忘れることができない。
高柳の、その笑顔を、護りたい、彼を害するものの盾になりたい。
己の立場もわきまえず、そんなことを思った自分に腹が立つ。
なんの力も持たない、非力な存在のくせに。
彼の役に立ちたいなんて、おこがましい考えだったのだ。
苛立ち紛れに、平積みにされた週刊誌を叩きつけるように棚に戻す。
誰の目にも触れないように、この憎き週刊誌を買い占めてしまいたかったが、未来にそんな資金はない。
くるりと週刊誌売り場に背を向けると、ポケットからスマホを取り出す。
麗香と対面してから、高柳にどれだけラインを送っても、既読はつかなかった。
虚しく未来が送ったメッセージが並ぶ画面に、習慣のように新しく文章を作成し、送信する。
「冬真、大丈夫?」
今、高柳はどうしているだろう。
なにを思い、どこにいるのだろう。
このメッセージにも既読がつかないだろうことは、わかりきっている。
だから、特に反応がなくてもショックは受けない。
しかし、予想外の展開に、未来は目を見開く。
未来の送ったラインにすぐに既読がつき、次の瞬間軽やかな音をスマホが奏でて、ラインがきたことを告げた。
「大丈夫。俺を信じて。約束」
未来は、その文面を、何度も何度も読み返す。
最終的には、文字の意味がわからなくなる現象まで起きるほど、高柳から送られてきたメッセージに目を凝らし続ける。
心が、喝采を叫ぶ。
ここが、店内であることも忘れて、叫んで回りたい気分にとらわれる。
とうとう、高柳から返事があった。
大丈夫だと。信じてほしいと。自分だけに向けられた言葉で、彼の想いが綴られている。
未来はスマホを胸に抱きしめ、深呼吸するように目を閉じ、天井をあおぐ。
油断すると、涙が溢れてしまいそうだった。
感じたことのない安心感に包まれていた。
自分と高柳の繋がりが、消えたわけではないと。
運命の赤い糸が、途切れたわけではなかったと。
はたと、未来の動きが止まる。
約束とは、なんのことだろう。
過去に、高柳となにか約束したことがあっただろうか?
記憶を辿って、高柳の伝えたい言葉の意味を考える。
……約束……なんの?
しばらく立ち尽くしたまま、天井を睨んでいた未来は、はっと、その場でとある場面を思い出し、瞠目する。
ホテルで逢瀬を重ねていたころ。
ベッドに並んで寝ていたときのこと。
隣で寝息を立てる高柳の小指に、自分の小指を絡ませ、「ずっと一緒。約束だよ」と、彼の耳元で未来はささやいた。
あのときは、高柳はきいていないと思っていたので、あの言葉は、あくまで自己満足でいったにすぎなかった。
高柳は、きいていたのだ。
そして、それを覚えてくれていた。
今度こそ、未来の頬を涙が伝った。
我慢できなかった。
ひとの目などどうでもいい。
今はひたすら泣きたかった。
嬉しくて、全身が震えるほど幸せで、満たされて、味わったことがない感情が飽和するほど押し寄せてくる。
好きだ。高柳が、たまらなく好きだ。
この想いに、もう嘘はつけない。
涙を拭き、病院に戻るためにきた道を歩いていると、スマホが振動した。
高柳だろうか。
期待に胸を膨らませてスマホを取り出すと、画面に表示されていたのは、チカの名前だった。
今の幸せな出来事を、早速報告しなければと、嬉々としてスマホを耳にあてる。
「もしもし、チカ、きいてよ……」
未来が弾んだ声で話しはじめると、未来の声に被さるようにチカが叫んだ。
『未来!ネットみて!大変なことになってるわよ、アンタ!』
再びの緊迫感溢れるチカの声。
未来の幸せな気分は、すぐさま熱を冷まされ、背中に緊張が走る。
チカとの通話を早々に切り上げ、スマホで高柳の名前を検索する。
すぐに画面に、高柳のスキャンダルを報じるネットニュースが表示される。
先ほど読んだ週刊誌と変わらない内容が載っているが、違う点があった。
高柳の浮気相手として、女優やアイドルと並んで、週刊誌では「一般人のOさん」とされていた未来の実名が、ネットでは隠されることなく書かれていた。
週刊誌では、未来の顔がぼかされていた高柳と未来がホテルから出てくる写真も、未来が麗香からみせられたままの、ぼかしのない鮮明な状態で、さらされていた。
ネットのコメント欄を、恐る恐る覗いてみる。
《冬真くん、ファンだったのにショック》
《浮気相手10人とかサイテー。奥さん可哀想》
《他はわかるんだけどさ、小野寺未来って誰?》
《小野寺未来はただの一般人》
《高柳冬真が通院していた中野病院で働いてる医療事務、24歳》
《実家は新潟。東京の大学を卒業。両親は小野寺未来が幼いころに離婚。実家の住所は……》
《横島社長がこのまえストーカーで捕まったけど、当時付き合ってたのが小野寺未来らしい》
《えー、テレビでみただけだけど、横島社長かっこよくて好きだったんだけどなー。この女のせいでおかしくなっちゃったのかな?》
《小野寺未来は、付き合った男の数がエグい》
《高柳に遊ばれて可哀想だと思ったけど、この女も男遊びすごかったんだね。自業自得》
《っていうか、尻軽じゃない?》
《名前さらされても身から出た錆》
《高柳冬真を潰した小野寺未来の情報をさらそう》
未来は目を疑った。
ネットに、実名、職場、住所、スマホの番号、学歴、出身地、実家の住所に実家の電話番号、小中高の文集や卒業アルバムの写真、更には過去、付き合った男の名前まで、未来の情報の、なにもかもが、ネットにさらされていた。
ネットに溢れる顔のみえない、名前すら知らないひとから向けられる、むき出しの悪意。
未来を貶めようと画策する大勢の敵意。
恐怖を感じて辺りを見回すが、当然ながらすれ違うひとは未来に目を向けない。
でも、何食わぬ顔をして、未来に気づかないふりをしながら、手元のスマホでは、未来を糾弾するコメントを書きこんでいるひとがいるのではないか。
嗤いながら、未来にスマホを向けているひとがいるのではないか。
疑心暗鬼に陥って、うつむくと、病院までの道のりを、未来は走った。
未来の情報がネットに上がってから、まだ短時間にも関わらず、未来の個人情報は倍速で拡散されていく。
一体誰が、こんなに詳細な情報を投稿したのだろう。
まるで犯罪者の気分だ。
自分を守ってくれる盾は、なにひとつない。
未来だけが悪者。
未来だけが高柳冬真を殺した凶悪犯。
みえない、ひとの悪意にさらされたとき、どう身を守ればよいのかを、未来は知らない。
ただ無防備に、光の速さで駆け抜ける自分の情報が、雪だるまを転がすように、人々の悪意を吸収して、小野寺未来が罪人であるというイメージを、転がりながら膨らませていく様子を、眺めていることしかできない。
一体、なにが起きているのだろう。
週刊誌をみて絶望に堕とされたかと思えば、高柳からの返信に天にも昇る心地になり、そしてまた、今度は、個人情報が悪意によって拡散されていることを知り、再び奈落の底へと突き落とされる。
まるでジェットコースターだ。
未来は、ジェットコースターが得意ではない。
だから、今、なにが自分の身に起きているのか、理解できず、頭がこの事態についていけなかった。
病院に戻った未来を迎えたのは、出ていく前とは、別世界だった。
電話が鳴り止まない。
電話対応をしていた、福沢諭吉似の上司《ユキチ》が、乱暴に受話器を叩きつけ、未来を認めたとたん、大股で近づいてきた。
「ちょっと、小野寺さん、どういうこと?君を出せって迷惑電話が鳴り止まないんだけど。説明してくれない?」
「す、すみません……」
もう職場にまで、嫌がらせの電話がかかってきているのか。
未来は軽いめまいを覚える。
しおらしく、小声で謝ることしかできない。
「これじゃ仕事になんないよ」
頭を掻きむしりながら、ユキチが席へと戻っていく。
「君、本当になにをしたの?これ以上仕事に支障が出るようなら、休んでもらうことも考えないといけないからね」
「……はい。本当にすみません」
未来は、かかってきた電話を取る。
「小野寺未来を殺す。高柳冬真に2度と近づくな」
若い女のひとの声が、無機質にそれだけ告げると、ぷつりと切れてしまった。
受話器を戻す。
戻したとたん、電話が鳴り始める。
「小野寺未来を解雇しろ。さもないと、病院を爆破する」
またしても、電話はそれだけで切れる。
受話器を戻したとたん、また着信音がけたたましく鳴り響く。
業務に関わる電話かもしれないので、無視することはできない。
「はい……」
「小野寺未来か?そんなに男と遊びたいなら、俺が相手してやるよ」
卑わいな言葉を垂れ流す若い男の声に耐えきれず、未来は電話を切った。
その様子をみていたユキチが、はあと聞こえよがしにため息をつく。
「なにがあったのか知らないけど、小野寺さん、今日はもう帰って。仕事にならないから。君も、相当疲れてるみたいだし。落ち着くまで、来なくていいからね」
ユキチは事情をきこうともせずにそういうと、業務に戻ってしまった。
鳴り響く電話に、「ああ、もう」と悪態をついている。
未来は肩身が狭い思いになりながら、帰り仕度をはじめた。
午後の診察の時間になり、患者の対応をしていた受付の横を通りすぎたとき、同僚の困惑した声が耳に入った。
受付の女性のか細い声に被さって、男が怒声を張り上げている。
「だから、小野寺未来を出せっていってんの。一番乗りで小野寺未来を直撃して、配信するんだから。フォロワー増えるだろうなあ。だ、か、ら!小野寺未来を早く連れてこいって!」
若い男が、受付の女性に噛みついている。
戸惑っていた彼女と、目が合うと、彼女は男の背後を歩く未来に目配せして、小さくうなずいた。
今のうちに行け、という合図だった。
彼女に最大限の感謝を込めて、頭を下げると、気配を消して男の後ろを通り抜け、未来は病院をあとにした。
2月16日(金) 未来の自宅にて
週刊誌が発売され、高柳冬真の衝撃的なスキャンダルが世間に報じられてから一週間が経った。
高柳と未来を取り巻く環境は、悪化の一途を辿っていた。
高柳は、未だ沈黙を保っている。
謝罪会見が開かれるのではないか。
事務所による何らかの発表があるのではないか。
マスコミは、今か今かと高柳の動きを待っている。
すでに、決まっていた仕事は白紙になったとの報道もある。
テレビやネットでは、高柳に関する報道が激化し、不倫の事実、不倫相手への糾弾が繰り返し報じられていた。
今や、高柳冬真は時のひととなっていた。
本業の俳優としてではなく、不貞を犯した大罪人として。
好奇の目にさらされ、人格まで否定するコメントが無秩序に垂れ流され、高柳冬真という人格が、なにもしらない人々によって、上塗りされ、彼の本質が曖昧にされていく。
高柳冬真が、作り変えられていく。
顔だけはいいクズの浮気男。
彼を知らなかったひとは、その上書きを、そっくりそのまま信じ、無責任な正義感で彼を責め立てる。
報道から丸一週間経ったこの日、所属事務所は、高柳冬真の解雇処分を発表した。
その報道を、自室のテレビで観ていた未来は、ただ呆然と、その事実をみつめることしかできなかった。
「未来?未来、どうしたの、大丈夫?」
スマホから漏れ聞こえる声に、未来のぼやけかけた意識が引き戻される。
「あ、うん、ごめんね、大丈夫。お母さん、本当にごめんね。わたしのせいで辛い思いさせて」
「お母さんなら、大丈夫よ。それより未来、あなたこそ平気なの?仕事も行っていないんでしょう?お母さん、そっちまで行こうか」
電話の向こうの母は、気丈に振る舞い、未来を励ました。
騒動の余波は、未来の新潟の実家まで及んでいた。
嫌がらせ電話はもちろん、未来を更には母までもを罵った張り紙が家の外壁に貼られ、押しかけてきた高柳のファンや野次馬が、その様子を得意げに動画投稿していた。
近所のひとからも、母は白い目でみられているのだろう。
届く声には、疲労が滲んでいた。
母だって、娘がどんなことをしたのか、承知しているだろう。
にも関わらず、変わらず優しい言葉をかけてくれる。
母に、とんでもない迷惑をかけてしまった。
なんて親不孝な娘なのだろう。
未来は両目に滲んだ涙を拭いながら、意識して声を張った。
「ありがとう、私は大丈夫だよ、心配しないで。お母さんも仕事あるでしょ?」
「でも、ちょっとくらいなら平気よ。ちゃんと食べてる?寝られてる?お母さん、それだけが心配で……」
「うん、大丈夫だよ。またすぐに、そっちに帰るね」
「いつでも帰ってきてね。じゃ、また連絡する」
未来が言外に、来なくていいと伝えると、母は、気づかないふりをして明るい声で通話を切った。
今、母にこの部屋にきてほしくなかった。
カーテンを閉め切り、薄暗くなった部屋に、テレビの青白い光りだけが、疲れ切った未来の横顔を映し出している。
薄いドアの向こうでは、数人の男女が未来の名前を叫びながら、ドアを叩き続けていた。
壊れたようにチャイムが鳴り続ける。
耐えきれず、未来は耳を塞いで体を丸めた。
アパートのドアにはいたずらの張り紙が貼られ、外壁にはスプレーで落書きがされていた。
外に出れば、スマホを向けて見知らぬ男たちがつきまとってくる。
ひとときも、気が休まる暇がなかった。
職場にも、相変わらず迷惑電話がかかり続け、ひとが押し寄せている。
未来を追いこむことは、ひとつのエンターテインメントと化していた。
未来なら、どんなに傷つけても構わない。
そんな恐ろしい風潮が、世間には充満していた。
日常で溜まったストレスを、未来を攻撃することで、発散しているのだ。
母との通話を切ったばかりのスマホが振動する。
非通知。
スマホの電源を落として対抗する。
ずっとそうしているわけにはいかないので、電源を入れるが、間髪を入れずに着信がある。
その繰り返しだ。
未来の神経が、がりがりと粗く削れていく。
こんな日が、あと何日続くのだろう。
自分の精神はいつまで持つのか。
《約束》
高柳が送ってきたラインの文面が蘇る。
今、未来がなんとか耐えられているのも、あの言葉があるからだった。
今朝、辞表を出してきた。
診療がはじまる前のことだ。
ネットを参考にしながら、辞表を書き、ユキチのデスクに置いた。
出勤してきたユキチは、辞表を一瞥すると、未来を見ることもなく、パソコンに視線を移した。
小さい声で「ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした」と謝り、頭を下げると、荷物をまとめて病院を出た。
ユキチは、引き留めもしなかった。
またひとつ、自分はなにかを失った。
これが、浅はかにも自分が取った行動が引き起こした結果だった。
ひとつひとつ確実に、未来はなにかを失ってゆく。
それが、未来が選んだ結果に対する答え。
全て自分が引き起こしたこと。
誰を責めることも、恨むことも許されない。
未来は今起きていることの全てを、受け入れなければならない。
テレビを消し、真っ暗になった部屋にチャイムが鳴り響いた。
無視を決めこんでいると、ドアを叩きながら、くぐもった高齢の女性の声が、「小野寺さん、松野だけど」と呼びかけてきた。
このアパートの大家の女性だ。
未来は警戒するように、狭くドアを開ける。
小柄で痩せた年配の大家が、隙間から皺だらけの顔を、ぬっと覗かせる。
少しほっとする。
「小野寺さん、困るのよねえ。張り紙、早く剥がしてくれない?壁のいたずら書きも、消してもらえるんでしょうねえ?原状回復、してくれないと困るのよ」
「原状回復……退居しろって、ことですか?」
松野は、苦虫を噛み潰したような顔で未来から目を逸らす。
「まあ、ねえ……。他の部屋のひとに迷惑だし、変なうわさが広がって次の入居者が来なくなると、困るし……。うちも商売やってるのよ、わかってちょうだい。荷物も少ないようだし、明日には出ていってもらえるかしら」
松野は無慈悲にそういい捨てると、未来の顔をみることなく立ち去っていった。
あ然とした表情で、玄関先に立ち尽くす未来に向かって、複数のフラッシュが瞬き、その姿を切り取った画像が拡散された。
2月28日(水) ネットカフェにて
狭い個室で、机に突っ伏していた未来のスマホが振動した。
緩慢な動きで顔をあげ、スマホを目の高さに掲げると表示された名前に目を見開く。
ラインに高柳からのメッセージが届いていた。
《会いたい。これから会える?》
逢瀬の場として、ホテルの住所が書かれていた。
弾かれたように、未来は立ち上がった。
アパートの部屋を追い出された未来は、翌日から、キャリーケースに荷物を詰め、ファミレスやネットカフェを転々としていた。
仕事を失っているので、日雇いのバイトをしながら、わずかな稼ぎでその日暮らしをしていた。
いつかは冬真に会える。
その思いだけを支えに、未来は惨めに傾きそうになる心を、なんとか保って生きてきた。
あれだけ騒がれた高柳冬真の泥沼不倫騒動は、いつしか下火になっていた。
世間の関心はすでに高柳冬真にはなく、今は別の話題がメディアを賑わしている。
高柳冬真は、すでに忘れ去られた存在となっていた。
しつこく未来を追い回していた野次馬も、今はもういない。
それでも、未来は仕事を失い、住む家を失い、信用を失い、穏やかな生活を失った。
それでも彼女を支えていたものは……。
「冬真!」
格安ホテルの一室。
冬真の姿をみるなり、居ても立っても居られず、未来は彼に抱きついた。
冬真も、「未来……」といったきり、感極まったように声を詰らせながら未来を抱きしめ返した。
そこに、言葉はいらなかった。
ふたりの心は、誰に侵されても揺らぐことはなかった。
冬真は、《約束》を果たしたのだ。
温かく柔らかい高柳の感触。
知っていた。体が覚えていた。
全身が熱を持つ。温かい涙が自然と頬を伝う。
未来の涙を親指で拭うと、高柳は抱擁を解かずに言葉を絞り出した。
「迎えに来るの、遅くなってごめん。でも、未来なら待っててくれるって信じてたから」
「うん。私も信じてた。冬真が必ず会いに来てくれるって。約束、守ってくれるって、信じてた……だから、辛くなんて、なかったよ」
「辛い思いさせてごめん。……俺、事務所も解雇されて、なんにもなくなったよ。それでも、いい?」
「いい。そんなこと、構わない。冬真がそばにいてくれるなら、なんにもいらないよ」
互いの体温を確かめ合いながら、ふたりはしばらく抱き合っていた。
やがて、そっと体を離すと、手を絡ませたまま、ソファに並んで座り、ふたりはぽつぽつと言葉を交わした。
「麗香とは、離婚が成立した。夫婦関係は、とっくに破綻してたんだけど、負い目もあって、ずるずると関係を続けてしまった。
それが、麗香をより苦しめる結果になって、未来まで辛い思いをさせた……。
俺の浮気相手を、麗香が金をちらつかせて別れさせていることを、便利に思ってもいた……。サイテーだよな、俺」
「……うん。それは……最低だね」
「反省してる。心のどこかで、金を払えば別れる程度の女なんだって、そんな判断基準を作ってた。でも未来は、金を受け取らなかった。俺のことを、本気で思ってくれてた。未来との約束だけは、なんとしても守らなきゃいけないと思った。未来と会っていたのは、そりゃ、最初に声をかけたのは、遊び相手を探すためだった。でも未来に会うたびに、どんどん好きになっていった。止められなかった。特別だった。正直今でも、他の女と未来のどこが違うのか、わからない。でも、今回の騒動で、強く実感したんだ。未来を失いたくないって……。
運命の、相手だって」
未来が息を呑む。
運命の相手、それは、未来が度々口にした言葉。
もう出会えないのではないかと、諦めにも似た存在だった。
ようやく、出会えたのだ。
探し求めていた運命の相手に。
万感の思いだった。
ふと見上げると、隣の高柳が、泣いていることに気づいた。
つられて、未来まで泣き出してしまう。
「なんで泣いてるのよ。冬真」
「泣いてない。未来こそ、泣いてるじゃん」
乱暴に涙を拭うと、高柳は恥ずかしそうに、赤くなった顔を背ける。
「未来、本当に俺でいいの?イチからのスタートじゃない、ゼロからやり直すことになるけど」
「それくらい、覚悟してる。ゼロなのは私も一緒だし」
「未来となら、やり直せる。未来……」
「ん?」
足もとのバッグに手を伸ばした高柳は、小さな箱を未来に差し出す。
未来に緊張が走る。
「俺と、結婚してもらえますか?」
改まった口調で、箱を開け、高柳は照明に光る指輪を取り出した。
夢のような光景だった。
運命の相手にプロポーズされる。
長年憧れ続けたその奇跡が、現実として自分の前に広がっている。
未来は、震えながら左手を差し出した。
高柳がゆっくり指輪を未来の左手薬指に嵌めていく。
高柳の手も、緊張で汗ばみ、震えていた。
指輪を、照明にかざす。
子どものころから思い描いていた夢を、ようやく叶えることができた。
あまりに幸福に満たされて、肺がいっぱいになり、呼吸がうまくできない。
未来は泣き笑いの顔になっていった。
「よろしくお願いします」
3月17日(日) 馴染みのカフェにて
『はーん。で、結局うまくいっちゃったんだ』
未来は、結婚指輪をチカにみせつけるようにかざしながら、満面の笑みでうなずいた。
「これ以上の幸せはないよ。とうとう念願の結婚。縁結びの神様は、本当に願いを叶えてくれるんだね。初詣行ってよかったなあ。お礼に行かないとね」
『でもさ、アンタたち、ふたりとも職を失ったわけでしょ?生活はどうするの?』
「冬真ね、劇団に入ることになったの」
『劇団?』
「冬真が子どものころ所属してた劇団のひとが、声かけてくれて、今は舞台出演に向けて稽古中。
冬真の演技は格別だから、役者辞めないですんで、本当によかった。
冬真にはどうしても演技を続けてほしかったし、そう考えてたひとが、私だけじゃないってわかって心強かった。
生活は苦しいけど、私も、次の職場がみつかるまでは日雇いのバイト続けて、資金を貯めて、冬真と一緒に住む家をみつけるつもり」
『まだなにも決まってないわけね。スタートラインにも立ってないじゃない。本当にそんなことで大丈夫なの?高柳さんに甲斐性があるのかしら?』
「大丈夫だよ。貢ぐことには慣れてる。チカも知ってるでしょ。冬真が、役者として大成するのを、私は命がけで支える。誰よりも近くで彼が仕事に没頭できる環境を整えてあげるの。今は、彼の夢が私の夢」
『命がけ……。大げさねえ』
チカは、コーヒーをひとくち飲んでから、遠い目をカフェの窓の向こうへ送る。
『ま、頑張んなさいよ、気が済むまで。マイナスからのスタートで、生活は苦しいかもしれないけど、いつか、アンタの願い通り、高柳冬真って役者の実力が認められるといいわね』
「うん。本当、そう思う。私も冬真も、まだ発展途上。力を合わせて、どんな困難もふたりで乗り越えていけるよ」
『何度きいたんだかねえ、そのセリフ。また浮気相手募集されて棄てられるんじゃないの?治ってんのかしらねえ、高柳さんの浮気グセ。今はお互い盲目になってるけど、やっぱり違うって棄てられないようにね。
ま、そうなったら、また不幸話きかせてよ。
酒の肴にするからさ。アンタの不幸話に勝る肴はないからね』
「相変わらず趣味悪いなあ。運命の恋人に二言はありません。もう一生チカには美味しい酒の肴はありません。残念でした」
『だからさあ、何度きかせるのよ、そのセリフ。もうきき飽きたって。
やっぱり不安になってきたわ。
また同じ繰り返しになる予感が、ぷんぷんするわよ』
「縁起でもないこといわないでよ。結婚は決まったことなんだから、次はないの!遊んで棄てられるの繰り返しだった過去の恋愛は、冬真と出会うためにあったの。だから、繰り返しはもうありません!」
じっと未来を眺めていたチカの口元が、ふっと緩んだ。
『いじめるのもこれくらいにしておくか。
未来、結婚、おめでとう』
はにかむように未来が柔らかく笑った。
「ありがとう。チカにこんな報告する日がくるとは思わなかったよ。本当に、私、結婚するんだなあ。ふふっ」
『気色悪い笑い方しないでよ。ご祝儀は弾むかあ』
「あ、それ助かる。今は少しでもお金がほしいところだから」
『生活費を渡すわけじゃないわよ!ひとを金づるみたいに……』
「えー、ちょっとくらいいいじゃない。チカ、稼いでるのに使い道ないでしょ?人助けだと思ってさ」
『冗談じゃない!ようやくアンタが結婚して、お役御免になったっていうのに、なんでまだアンタの生活の面倒みなきゃいけないのよ。あたしを見習って自立しなさい』
「ケチだなあ、チカは」
『ケチで結構。で、籍はいつ入れるの?』
「まずは新潟の実家にふたりで挨拶に行こうって話してる。お母さんには、迷惑とか心配とか、いっぱいかけたし、安心させてあげなきゃねって。仕事が軌道に乗って、落ち着いたら籍入れようって。だから、まだ少し先の話になりそうかな」
『その間になにもないといいわね』
「今度こそうまくいってほしいけどね。上がって下がってのジェットコースターはもううんざり」
『ま、ここまでくれば大丈夫でしょ。あたしのためにもちゃんと結婚してよ』
「はいはい。ちゃんとお嫁さんになります」
『お嫁さん!似合わないわね、アンタ!』
けたけたと愉快そうにチカが笑う。
未来もつられて笑いながら、「本当だね」と返した。
穏やかな時間が、未来の横を通り過ぎていった。