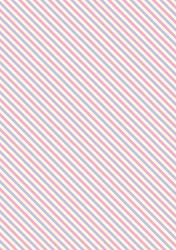それは高校卒業を控えた冬のこと。
俺の受験や、息吹の東京行きの日程を考えると、もう俺の部屋でごろごろできる日も限られてきたな、という頃合いだった。
いつものように遊ぶ約束をして、俺は部屋で息吹を待っていた。
朝からその年初めての雪が降っていた。
俺たちが生れて以来大雪が降ったことはなかったから、約束を取りやめようとは俺も息吹も考えなかった。
あと数日もない、という気持ちも作用してたんだと思う。
あの、なんでもない幸福を共有できる時間が。
息吹の家がある駅前から、山際にある俺の家に向かう道中には、幹線道路があった。一緒にポットを買いに行った家電量販店がある、あの通りだ。
そこは、頻繁に長距離トラックが通る道でもある。
その日思いがけない大雪で、納期の決まっているドライバーは焦っていた。装備もなかった。
信号機にも雪が積もり、視界は悪く――
いろいろな不運が重なった結果だった。
俺は受験に失敗した。
息吹のいない毎日を、どう過ごしたのか、あまり記憶もない。
それでも、夏の終わり頃には再び勉強を始めた。息吹の死が、俺の人生を歪めたことになってはいけないと思ったからだ。いざ再開してみると、勉強はとても役立った。
なにかに没頭していれば、後悔にさいなまれないで済む。
そしてその年の初雪の日、息吹は俺の前に現れたのだ。
参考書に埋もれる俺を見て「頑張ってるなー。じゃあ俺は頑張ってる奴の横で漫画読もっと」といつもの調子で言った息吹は、事故の日から買い足してなかった雑誌を読んで、
「……こいつ、こんなとこで死ぬとか聞いてない……っ!」
と、盛大に泣いた。
以来、毎年初雪の日になると、息吹は俺の元にやってくる。
夢中になると他のことが目に入らなくなる奴のことだ。今でも「東京に行く前に最後に遊ぼうぜ」という約束のこと以外、覚えていないんだと思う。
だから俺は、毎年、最後の日がくり返せるように、細工してしまう。
それは誰にも――息吹のお母さんにも言っていないことだった。
自分が死んだことに気がつけていないのなら、教えてやるのが本当はあいつのためなんだろうか?
あの世のシステムが俺にはよくわからないけど、俺との最後の約束なんて忘れてしまったほうが、いわゆる「成仏」できたりするんだろうか。
あれから俺は無事大学にも合格した。新しいことを勉強した。バイトしたり、サークルに入ったり、彼女も作った。来年にはいよいよ就職だ。
息吹の知らない俺がどんどん増えているのに、俺はまだあの日にとらわれている。
なにか特別なことをするわけでもないのに心地いい。そんな時間を、手放せずにいる。
迷惑をかけているのは、ばかなのは、俺のほうなのかもしれない。
けして足跡の残らない後ろ姿を、俺はいつまでも見送っていた。
〈了〉