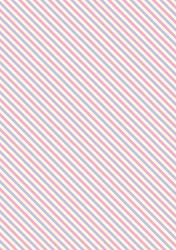◇◇◇
ぐすっと鼻をすする音がして、俺は思い出の中から現実に呼び戻される。
音の出所は、こたつに肩まで潜り込んで週刊漫画雑誌を読んでいる息吹だ。
「……こいつ、こんなとこで死ぬとか聞いてない……っ!」
「その漫画そのあとも主要キャラほとんど死ぬけど」とは俺は言わず、黙って箱ティッシュを差し出してやる。息吹はこっちも見ずにティッシュを引き抜いて、ずびびっと豪快に鼻をかむ。
あの雑誌もずいぶんくたびれてきたけど、捨てられるのはいつになるだろうか。
他愛もないことを話して、ゲームをやる。
「え、ちょと待っておまえ俺が来ないうちにめちゃくちゃやりこんだ?」
という問いには「センスだよ」と返す。
息吹が俺のカップ麺置き場を漁りだしたときには、ひやっとした。
幸い、今年出た味はもう喰ったあとだった。例のポットからお湯を注ぎ、スタンダードな味のカップ麺を作って、一緒にすすった。
だいたいいつもこんなふうに過ごしていた。特別なことをなにもしなくても、楽しく、心地良い時間。
かつては、永遠に続くと思っていた時間。
「んじゃ、そろそろ帰るわ」
数時間いつものようにごろごろしたあと、息吹はそう言って、ふたたび鼻先までぐるぐるとマフラーを巻き付けた。
「おう、……気をつけてな」
またな、と言っていいのかわからず、そう差し替えた。たしか去年もそうしたと思う。
息吹は離れの玄関を出て、ぐるっと庭を回り込み、公道からうちまで上ってくる私道に出る。
俺は手つかずのまま伸びてしまったカップ麺が乗ったこたつを出、窓辺に立った。
雪はもうやんでいたが、舗装されていない私道の表面を覆う程度には積もっている。
息吹が俺に気がついて、笑顔を向ける。手を振ってやると、息吹も振り替えし、また歩いて行く。
その後ろ姿を見送りながら、俺はスマホを取り出した。
呼び出したのは息吹のお母さんの番号だ。
「今年も来ました。で、今帰りました」
挨拶もそこそこに本題に入っても、お母さんは驚いた様子もない。このやりとりをするのも何度目かだったから。
『そう……』
伝わってくる呟きは、微かに湿っている。それを払拭するかのように、続く言葉の響きは明るい。
『もう、あの子ったら、ほんとばか。死んでまで勇生くんに迷惑かけてほんとにごめんね』
「迷惑だなんて」
応じながら再び窓の外に視線を移す。少しずつ遠ざかる息吹の背中。昔何度もそうやって見送った背中。
昔と違うのは、去って行くその足下の雪の上に、足跡が残らないこと、だった。