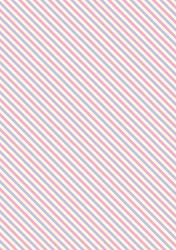中学も高校も同じところに通った。
相変わらず学年で一番背が高く、目つきが悪くなりがちな俺と、背が低く童顔で人なつこい、ポメラニアンみたいな息吹。人からは「デコボココンビ」なんて呼ばれていたようだ。
息吹は、高校を卒業したら東京の理美容の専門学校に通って美容師になり、母親を助けるのだと公言してはばからなかった。
家が美容院なのをいいことに、もう自分を実験台にメッシュやカラーリングを試したりしていたから、だいたい髪色は金。元々校則のゆるい高校だったし、教師も生徒も息吹のそんなキャラクターを理解して、大目に見られていた。母親を助ける男の子、というものの年寄りウケは抜群だ。
叔父さんが引き上げていったことでめでたく俺の部屋になった離れに、最初に泊まったのも息吹だった。
それからはもう、ほぼ入り浸りだ。なにしろずっといるから、コーヒーを飲んだり、カップ麺を喰ったりする。そういうとき「母屋にいちいち行くのめんどくせえな」と俺がこぼすと、じゃあ半分ずつ出し合って湯沸かしポットを買おうということになった。
田舎のことだ。幹線通りまで行けば、家電、スーパー、ドラッグストア、本屋やカラオケにボーリングまでぎゅっとまとめられた場所がある。
俺たちはなけなしの小遣いを握りしめ、自転車でそこへ向かった。
ポットなんて、それまでは台所の隅に当たり前にあるものだったから、相場もまったくわかっていなかったのだが、予算内でそこそこいいものが買えた。むしろ少し余った。
「ゲーム見たあと本屋行く? 前の続き、出てなかったっけ?」
当然のように俺たちは漫画も折半で共有していたのだ。
息吹がポットの箱を嬉しそうに抱えたままエスカレーターへ駆けていくのを「こけんなよー」と追っていたとき、声をかけられた。
「勇生くん!」
夏休みの間だけしたバイトの先輩だった。地元の女子大生。やけに短いスカートで、小走りに近寄ってくる。
「買い物?」
ゆるく巻いた髪を耳元にかけながら、彼女が訊ねる。はい、と応じると「私も!」と身を乗り出してきた。いやまあ、ここで会ったからにはそういうことだと思うけど。
彼女も言ってしまってから思い当たったのだろう。照れ隠しのように笑って、ふたたび長い髪をいじる。
「このあとみんなでボーリングなんだけど、勇生くんも行かない? この間、来てくれなかったし」
そういえばそんなことがあった。バイトの打ち上げとかいって。
でも、みんなの予定をすり合わせたらそうなったのかなんなのか、指定された日程は俺のバイト最終日じゃなくて別日だった。
バイトのついでならともかく、わざわざ出ていくのが面倒だったから、適当な理由をつけて断ったのだ。
「みんな」と言われた背後に控える人たちは、大学の友だちだろうか。
「勇生ーー?」
俺がいつまで経っても上がってこないからだろう。息吹がふたたびエスカレーターで下りてきた。彼女の姿に気がつくと、
「……ども」
と頭を下げる。
「どした?」
息吹は俺を見上げる。
「ボーリング誘われてた」
事実をそのまま告げただけだったのに、なぜか彼女を取り巻く空気が強張った気がした。背後に控える「みんな」さんが、くすりと笑う。
その笑いに含まれる、微かだけれどたしかに意地の悪い響き。俺は察した。
こいつら今、息吹を値踏みしたな。
砂でも噛んだようなざらっとした不快感が、口の中に広がる。
図体がでかいと、気がつくことがある。
遺伝子の気まぐれでたまたまそう生まれついただけだというのに、やっぱりそれは「生き物として強い」のだ。
もっと言うなら「雄として強い」。
中学、下手すると小学校高学年辺りから自分が「恋愛対象」として見られやすいのだと感じていた。高校生になってからはなおさらだ。
バイトの打ち上げなんていうのも口実で、大人びていると言われる高校生を呼び出して、からかってやろうくらいに思っていたんだろう。わざわざ別日になったのはそういうことだったのだと、今頃になって腑に落ちていた。
ここで偶然に出会って仕切り直しと考えたんだろう。
だけど、息吹はいらないと、切り捨てた。
もちろんこういうことを「モテ」と受け止めたっていいんだろう。選ばれたのだと。
でも、だめだ。
ーーおまえらごときが、息吹をジャッジできると思うなよ。
「帰るぞ、息吹」
俺が言うと、息吹は「え?」と声をあげ、俺と彼女たちの顔を交互に見た。本当にポメラニアンが困ってるみたいな仕草だった。
俺の離れに帰り、早速ポットを箱から取り出す。
取り出して俺たちは「おー」といい、蓋を装着して「おー」と言い、電源を入れても「おー」と言った。無事お湯が沸いたときには拍手までしたのだが、カップ麺の包装をむいている最中に、息吹がこんなことを言い出した。
「これ、牛乳で作ると美味いってほんとかな?」
「やってみるか」
母屋に行って、母ちゃんに「ちゃんと洗いなさいよ!」とどやされながら小鍋で牛乳を沸かし、カップ麺を作った。
「うまい」
「うまいな……」
喰い終わったところで俺たちは顔を見合わせる。
「「結局ポットのお湯使わなかったじゃん!!!!!」」
カップ麺が胃から逆流してくるほど笑い転げた。
その日の寝入りばな。俺に背を向けて丸まっていた息吹にぽそりと名前を呼ばれた。
「勇生」
「んー?」
「ありがと」
なにが、と俺は訊ねなかった。