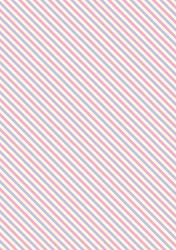「びびったー、新しい宗教のお祈りのポーズかなんかかと思った」
そう言いながら、息吹は鼻先までぐるぐる巻いていたマフラーをはずし、こたつに潜り込んだ。髪は相変わらずの金髪だ。耳には、それもトレードマークの、いくつものピアス。
「そんなトンチキな宗教あるかよ」
「どっかの国になかった? ぐるぐる回転しながらお祈りするの」
「それで叶えられるのは願い事じゃなくて三半規管の強化だけだろ」
言い捨てると、息吹はふっと笑った。俺も笑った。話の内容より、こういう会話のテンポが別段気を遣わなくてもぴったり合うという心地よさに。
◇◇◇
息吹が小学三年生で転校してきたとき、俺は奴をてっきり女の子だと思った。
顔の造作がずば抜けて女っぽかったというわけではない。髪が背中の真ん中に届くほど長かったからだ。
一昔前の、田舎町の話だ。もちろん息吹のそんな姿はすぐにいじめの対象になった。「オカマ」だの「ヘンタイ」だの、子供の安直な考えで心ない言葉が日々投げつけられた。
息吹は体も小さかったから、田舎で日々野山を駆け回っている大柄な子供にちょっと押されでもすれば、簡単に転んでしまう。
毎日そんなふうにいじめられて、転ばされて、その髪に草や落ち葉がくっついても、息吹は髪を切ろうとしなかった。
俺は、そんな奴の態度が不思議でたまらなかった。
だって、たかが髪だ。
たかが髪でそんなに嫌な目に遭うのを我慢するなんて、おかしなことじゃないか?
高校生になると俺の部屋になった離れだが、当時は叔父さんが居候していた。離れというのはそれだけで秘密基地めいているものだ。だから俺はよく叔父さんの元へ遊びに行っていた。
叔父さんは大手メーカーのエンジニア。都会に家族を置いてこっちの工場へ単身赴任していた。叔父さんは、俺との遊びの合間にときどき会社の愚痴をこぼした。エンジニアとして来たのに、リストラ対象を選ばされるのはしんどいとかなんとか。
大人の世界は色々大変らしい。
そんな環境だったからか、俺はクラスの奴らのことをどこか冷めた目で見ていた。よく言えば大人びている。悪くいえば、可愛げのない子供。
そんな俺からしてみれば、息吹をいじめる奴らも、髪なんかにこだわって奴らにいじめの材料を与える息吹も、等しくうっとうしい存在だった。
俺と息吹の席は隣だったから、息吹の席にいじめっ子が集まってくると、がつがつ机に当たられたりして、迷惑でもある。
俺はある日訊ねていた。
「なんで髪伸ばしてんの?」
もちろん、子供ながらに、言外に「迷惑だから切ってくれ」という思いを滲ませて。
「へあどねーしょん」
息吹が口にした言葉は、始め、俺の中でうまく形にならなかった。
たぶん、給食で見たことのないものが出たときみたいな顔をしてしまってたんだろう。息吹は「ヘアドネーションって言って、病気の人に髪の毛をあげるんだよ」と続けた。
息吹の母親は美容師だった。東京で修行して、両親の実家の元床屋を綺麗に改築し、駅前で美容院をやっている。
そしてヘアドネーションとは、がんなどの病気の治療薬の副作用で髪が抜けてしまう人たちのウィッグに使う髪を提供すること。息吹の母の店は、この辺りでは珍しい、その取次店なのだという。
だからからかわれても怒らなかったのかと俺が訊ねると、息吹は「怒る?」と目を瞬いた。
「そっか、そういうの、忘れてた」
「もうちょとでヘアドネーションできるから、それで頭がいっぱいだった」
――そう、奴は言ったのだ。
俺は心底驚いた。
怒るのを忘れる? そんなことあるのかよ、と。
俺たちくらいの年頃の男子にとって、怒りは最強の手段だった。学校で怒れば女子か教師が仲裁に入ってくれるし、家でなら、両親のどちらかが機嫌を取ってくれる。
けれど息吹は、それをあっさり「忘れてた」という。
クラスの男子の中で誰よりも小さい息吹が、俺にはこのとき誰よりも大きく思えた。不可解で、だけど不思議に惹きつけられる存在に。
以来、俺は息吹と親しくするようになった。
小学生の頃から、俺は背だけは誰よりも高い。おかげでいじめ対象にはならなかったから、そんな俺といつも一緒に行動することで、息吹へのいじめも柔らいでいった。
無事必要な長さになると、息吹は髪をばっさり切って登校した。
そこで先生からヘアドネーションについて初めて聞かされた連中の顔は見物だったし、女子の何人かは息吹の母親の店に行って、髪を切った。