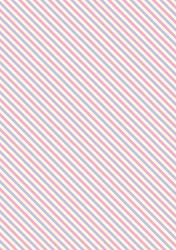「さて、と」
なんとか彼女をなだめすかして送り出し、俺は部屋を見渡した。
雪は降っているが、窓を開けて換気する。
薄く引き延ばした綿みたいな雪が、ふわふわとゆっくり、けれど絶え間なく空から落ちてきている。確実に積もるやつだ。あの日と同じに。
「灰皿と、チューハイの缶と、マグもか」
空き缶や、彼女の使ったマグやグラスをひとまとめにして母屋に運ぶ。俺の部屋は庭の一角に建てられた離れなのだ。
「ちょっと勇生、あんたはまた置きっぱなしにして!」
「あとで洗うから!」
母ちゃんの当然の小言に、洗面所でひげを剃りながら怒鳴り返す。
剃り終えて終えて震えながらまた部屋に戻る頃には、雪はもう地面を覆い尽くしていた。母屋との行き来に使っているサンダルの足跡が、くっきりとつく。
彼女の置いていった細々とした化粧品、服をひとつにまとめてベッドの下に放り込む。入れ違いにプラケースを引っ張り出し、中に入れてあった一世代前のゲーム機を出し、最新のものはしまった。
大学の教材と雑誌を、背表紙が見えないようにしてカラーボックスにねじ込む。漫画は最新の数冊を引き抜いて隠す。ぴりっと指先に痛みが走った。
「い……っ」
やった。慌てるから紙で切ってしまった。たしか去年もやった。痛えんだよな、これ。でもやらないわけにはいかない。
この辺は特にあいつの目に触れさせてはいけないのだ。
「おっと」
ここまでやってカレンダーをはずすのを忘れてた。あほだ。慌ててはずしてくるくる巻き、映画ポスターをまとめて突っ込んである段ボールに紛れ込ませた。
「あとはこれか……」
押し入れから引っ張り出した高校のジャージ。さすがに身長は当時と変わらないけど、筋トレを始めた腕周りなんかはパツパツだ。
「そうだはんてん! はんてんを上から着れば……」
俺は再び雪の中母屋に走り、父ちゃんのはんてんをひっつかんで戻った。
「あー、太腿もきっつい……」
上半身は高校の芋ジャーに袢纏、下半身はパンツ一丁。片足立ちになって、きついジャージになんとか足を通そうともがいてよろける。
どこからどう見ても間抜けな姿をさらしているとき、部屋のドアが開いた。
「……なにやってんの?」
立っているのは、息吹。俺の親友だ。