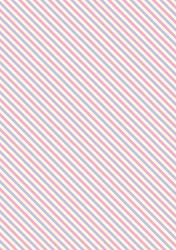「ね、外、雪だよ。初雪」
明け方、もぞもぞ起き出した彼女が少し興奮した声で言った。
誕生日にねだられた、なんとかピケのもこもこしたルームウェアを着ている体を引き寄せる。
「まだ早いだろ。もう少し寝――」
いつもの週末のように言いかけて、はたと気づいた。
初雪?
「きゃっ、なにもう、急に起き上がって」
「雪? 初雪?」
「だからさっきからそう言って」
可愛らしく頬を膨らます彼女の両腕を掴んで告げる。
「危ないから、積もる前に帰ったほうがいい」
俺の口調は、よっぽど切羽詰まっていたらしい。彼女は逆に笑った。
「大丈夫だよー。どうせ明日も休みだし、ごろごろしてたらやむよ。だいたいこの辺でそんなに積もったのって、三年? 四年? 前のあの日だけでしょ?」
「――いいから、早く」
今日は駄目だ。初雪の日は駄目なのだ。
あいつが、約束を果たしに来る日なのだから。