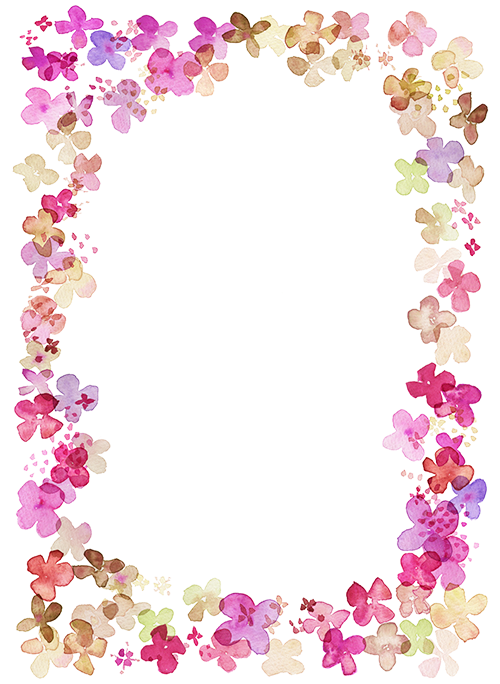意識の裏側で、思いだしたことがある。
――今は休ませてほしい。ほんの少しだけでいいから。
両親が亡くなって二週間、あてもなくさまよった撫子は希望を失って倒れた。
歩くことも食べることも諦めて、生きることさえ投げ出そうとしていた。
そこに白い猫が通りかかった。
それは撫子が幼い頃からたびたび目にした綺麗な毛並みの猫だった。
借金から逃げるために両親とあちこち転々としたはずの撫子が、なぜかどこに行っても出会った不思議な猫。
今考えてみれば、あの猫はオーナーだったのだと思う。
――君に今あげたパンに免じて、あの世ではもうちょっとマシな生活ができるように頼んでもらえないかな。
撫子はオーナーに願い事をしてコッペパンをあげた。それをオーナーは食べた。
あれはオーナーが撫子の願い事を受け入れるという約束だったのだろう。
――死にたくなければ、私の妻になりなさい。
オーナーは肉体を離れた撫子の魂に、「あの世でのマシな生活」を与えようとしてくれた。オーナーにできる限り最上の生活を送った。オーナーの妻という立場で、彼が心血を注いで作り上げたキャット・ステーション・ホテルの生活だった。
コッペパン一つで、オーナーは撫子が一生かかっても手に入れられないほどのものをくれた。
オーナーは多少強引に撫子の魂を連れていった。撫子を言いくるめたところもあった。
でもオーナーは、撫子の投げやりな願い事に最大限の誠意を返した。
そんな相手を裏切ってまで生き返る理由を、撫子はまだみつけていない。
家族も友達も頼りになる者もいない世界に一人だけ放り出されて、私は本当にやっていけるんだろうか?
正直自信がなかった。大見栄切ってあの世を飛び出したくせに、自分の弱さを笑いたくなる。
無意識に暗闇の中へ伸ばした手は空を切った。
それでも撫子がつかむものを探して手を伸ばしていたら、その手を誰かがつかんだ。
その手は撫子の手を包み込んで、力強く握り返す。
父さん、母さん? 撫子は暗闇に問いかける。
両親はもういない。撫子は一人のはずで、誰かに頼るなんてもう許されない。
知らず撫子の頬を流れていた涙を、その手は拭いとる。
――何をぐずぐずしているんです。裏切るなら徹底的にやりなさい
ぺち、と軽く頬を叩かれる。
――こんなことで負けるほど、あなたは弱くないでしょう。
聞き覚えのある声が告げて、撫子から遠ざかっていく。
「待ってください、オーナー……!」
自分の声で目が覚めた。
撫子の視界に、白い天井が広がった。
「撫子さん! 撫子さん!」
どこか遠くで、人の声が聞こえる。
「先生! 意識が戻りました……!」
にわかに様々なものが撫子の中に飛び込んでくる。
人の足音も、消毒液の匂いも、飾り気のない四角い景色も、確かな感触を持って存在している。
ここは生の世界だ。
撫子は手をゆっくりと上げて頬に触れる。
涙が乾いた跡に、撫子は微かな温もりを感じていた。
――今は休ませてほしい。ほんの少しだけでいいから。
両親が亡くなって二週間、あてもなくさまよった撫子は希望を失って倒れた。
歩くことも食べることも諦めて、生きることさえ投げ出そうとしていた。
そこに白い猫が通りかかった。
それは撫子が幼い頃からたびたび目にした綺麗な毛並みの猫だった。
借金から逃げるために両親とあちこち転々としたはずの撫子が、なぜかどこに行っても出会った不思議な猫。
今考えてみれば、あの猫はオーナーだったのだと思う。
――君に今あげたパンに免じて、あの世ではもうちょっとマシな生活ができるように頼んでもらえないかな。
撫子はオーナーに願い事をしてコッペパンをあげた。それをオーナーは食べた。
あれはオーナーが撫子の願い事を受け入れるという約束だったのだろう。
――死にたくなければ、私の妻になりなさい。
オーナーは肉体を離れた撫子の魂に、「あの世でのマシな生活」を与えようとしてくれた。オーナーにできる限り最上の生活を送った。オーナーの妻という立場で、彼が心血を注いで作り上げたキャット・ステーション・ホテルの生活だった。
コッペパン一つで、オーナーは撫子が一生かかっても手に入れられないほどのものをくれた。
オーナーは多少強引に撫子の魂を連れていった。撫子を言いくるめたところもあった。
でもオーナーは、撫子の投げやりな願い事に最大限の誠意を返した。
そんな相手を裏切ってまで生き返る理由を、撫子はまだみつけていない。
家族も友達も頼りになる者もいない世界に一人だけ放り出されて、私は本当にやっていけるんだろうか?
正直自信がなかった。大見栄切ってあの世を飛び出したくせに、自分の弱さを笑いたくなる。
無意識に暗闇の中へ伸ばした手は空を切った。
それでも撫子がつかむものを探して手を伸ばしていたら、その手を誰かがつかんだ。
その手は撫子の手を包み込んで、力強く握り返す。
父さん、母さん? 撫子は暗闇に問いかける。
両親はもういない。撫子は一人のはずで、誰かに頼るなんてもう許されない。
知らず撫子の頬を流れていた涙を、その手は拭いとる。
――何をぐずぐずしているんです。裏切るなら徹底的にやりなさい
ぺち、と軽く頬を叩かれる。
――こんなことで負けるほど、あなたは弱くないでしょう。
聞き覚えのある声が告げて、撫子から遠ざかっていく。
「待ってください、オーナー……!」
自分の声で目が覚めた。
撫子の視界に、白い天井が広がった。
「撫子さん! 撫子さん!」
どこか遠くで、人の声が聞こえる。
「先生! 意識が戻りました……!」
にわかに様々なものが撫子の中に飛び込んでくる。
人の足音も、消毒液の匂いも、飾り気のない四角い景色も、確かな感触を持って存在している。
ここは生の世界だ。
撫子は手をゆっくりと上げて頬に触れる。
涙が乾いた跡に、撫子は微かな温もりを感じていた。