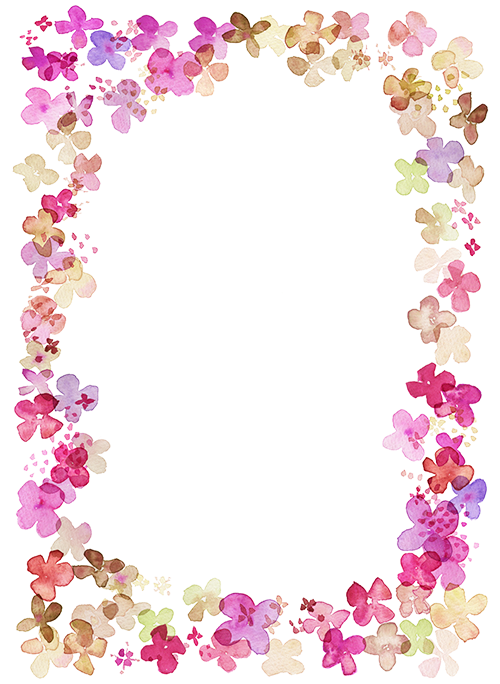オーナーと撫子、それから撫子の両親は、来た時と同じような天井の低い列車で駅を後にした。
笛の音が響いて、ゆっくりと列車が駅舎を離れる。
「オーナーと撫子さんに送ってもらえるなんてね」
「いいのかしら? 他のお客様と不公平にならない?」
向かい側で寄りそって座っている両親に、オーナーはいつも通り完璧な支配人の笑顔で答える。
「仕事で終着駅に向かう用もありますから。いくつか名所をご案内がてら参りましょう」
「それは楽しみだ」
「お宅のホテルのサービスは至れり尽くせりね」
父は母の方を振り向いて付け加える。
「桃子が喜んでくれれば僕はどこでもいいんだけど」
「あら、私は亮さんが楽しければそれでいいわ」
うふふあははと笑い合う両親に、撫子は頭を押さえる。
そうだった。両親はこういう人たちだった。
何をするのも楽しそうで、見ているこっちが胸焼けするくらいいちゃいちゃしている。
「ピクニックとは少し違うのでは」
「休暇は楽しむものだよ? ねえ桃子」
「初めて伊豆に旅行した時のことを思い出すわ。あの時は寝袋に入って一晩じゅう語り合ったわね」
「ああ、懐かしいな」
二人の記憶はどんなささいなことでも覚えていても、娘のことはからっと忘れてしまうくらい、二人の世界を展開する。
「初めて手をつないだのは文化祭の後夜祭だったね」
「夕陽が眩しかったわ。あんな綺麗な景色はきっと一生忘れないって思ったわね」
「僕もそう思ったよ。桃子とはいつも同じものを見てる」
二人でにこにこしながら思い出話にふける姿が切ないと思ったのは最初だけで、列車に乗って数刻で撫子はあきらめの境地に達する。
「オーナー、すみませんね。こういう人たちなんです」
オーナーの猫耳に口を寄せてこっそり告げる。
「存じております」
「あ、そうでしたか」
知られていたのはちょっとどきっとした。
「じゃあ借金大魔王だってこともご存じですか?」
オーナーは猫目を細めて小さくうなずく。撫子は深く息をついて続ける。
「人を疑うことを知らないんですよね。それで何度だまされたことか」
撫子が向かい側でぼやいていても、両親は構わず自分たちの会話に没頭している。
「生命の危険を感じて私が無理やり借金取りから逃げようと説得しなきゃ、もっと早死にしてましたよ。ええ」
実に貧しかった記憶が蘇ってきて、撫子は遠い目をする。
生きていた頃は一日二食食べられたらいい方だった。四畳一間以上の部屋に住んだことがない。冬に水道と電気が止められて震えながら眠ったことも数えきれないほどある。
「まあいいんですけど。慣れればどこも都でしたから」
ところが撫子は記憶に残る限り病気一つしたことがないし、両親も健康そのものだった。
「年にしては達観しましたね」
「はは。落ち込む暇があったら働いてましたから」
一応褒め言葉と受け取っておいて、撫子は向かい側を見やる。
「能天気な両親のおかげですよ、たぶん」
生活は苦しかった。でも両親と一緒に過ごした日々は楽しかった。
両親はいつも二人でくっついていて自分を忘れているのではと思う時もあったが、とにかく優しくて憎めない人たちだったから。
本当に死んじゃったのかな。撫子は苦笑して両親を見る。
こうして旅行にはしゃいでいる二人を見ていると、これはただの夢のようにも思えてくる。
撫子が目を細めて考えに沈んでいたら、オーナーは小声で言った。
「ご両親は死を受け入れていて、休暇の申請を許された数少ない人間です。誇れることですよ」
何かオーナーが言いよどんだ気配を感じて、撫子は問い返す。
「うん? 何か言おうとなさったでしょう。どうぞ言ってください。今更ですから」
撫子は笑いながら袖をつついた。オーナーは首を横に振る。
「気になるじゃないですか。言ってくださいよー」
ぐいぐいとオーナーの袖を引いてみても、彼の鋼鉄のような笑顔は崩れない。
「大人は言葉を選ぶものです」
「それって私が子どもってことですか? いやそうですけど、だったらちょっとくらいヒントをくれたっていいじゃないですか」
撫子たちが言い合っていると、向かい側から声がかかる。
「素敵なカップルだね」
「見本にしたいわ」
おっとりと言われて、撫子は返す言葉に困った。
列車はおしゃべりの邪魔にならない程度にゴトンゴトンと音を立てて、線路の上を走っていく。
撫子たちは他愛もないことを話しながら、淡い光の中で列車に揺られていた。
「あれ?」
少し外の景色が明るくなってきたことに気付いて、撫子は窓の外を見やる。
「そろそろ停留所です」
オーナーに教えられてまもなく、ブレーキがかかったのがわかった。ゆっくりと速度が落ちて行く列車に、車掌のアナウンスがかかる。
「まもなく山上駅です。しばらく停車いたします。ごゆっくりどうぞ」
時間を全く気にしていないのがあの世らしいな。撫子はそんなことを思う。
オーナーは持ってきたバスケットを持ち上げて言う。
「景色が綺麗なので外で食事にしませんか?」
「いいね」
「行きましょう」
両親もそれに乗って、撫子たちは列車から降りた。
駅の名前の通り、外はまさに山の上だった。
斜面には色とりどりの花が咲き乱れて、谷間には透明な湖がある。遠くには山々がそびえたち、赤く紅葉した木々が豊かにしげっていた。
「やあ、絶景ですね。空も明るいような?」
「ここは死出の世界でも昼に近い場所ですので。左から春、夏、秋になっています。頂上からは冬も見えますよ」
プラットホームに隣接した芝生には、いろいろな動物たちが座り込んで談笑していた。ここは展望台のようなものらしい。
オーナーは芝生にシートを引いて、バスケットからサンドイッチや果物を出して並べる。
「見てごらん、桃子。あれは君の花だね」
「あら、本当。亮さんの花がないのが残念ね」
「君と名前を共有している花があることが奇跡みたいなものだよ」
「まあ」
両親は景色を見ているのかそうでないのかわからない会話を繰り広げて笑っている。花の名前の方が先にあるんでしょうがと撫子は心の中で突っ込んだが、言ってもまったく意味はない。
のどかな光景が広がっていた。まさか生きていた頃、あの世で景色を楽しみながらランチを取るとは思ってもみなかった。
動物たちも喧嘩することなく談笑しているし、両親は生きていた頃と変わりなく能天気だし、景色は綺麗で空気は澄んでいる。
やっぱり自分は死んだんだろうな。撫子はなんとなくそんなことを思う。
死んだからこんなに平和なんだ。天国というのは、きっとこういう場所のことを言うのだろうから。
「道があるわね。まだ上に行けるの?」
「ええ。森林浴を楽しみながら頂上へ向かう道です。時間は十分ありますからご案内いたしましょうか?」
オーナーが両親に告げると、父が返す。
「僕はせっかくのランチボックスを頂きたいな。桃子は行っておいでよ」
父は撫子に視線を向けて首を傾ける。
「撫子さんも一緒に食べない?」
「ええ、もちろん頂きます」
基本的に食欲が最優先の撫子だった。生きていた頃にはその日の食事を確保することを目標にしていたから、綺麗なものや面白いものより食べ物が大好きだ。
「では奥様をご案内いたします」
オーナーは一瞬猫目を細めてから、母と共に山道に向かっていった。
「やっぱりおいしいですねぇ」
死出の世界に来てからは食べ物に不自由はしていないが、やっぱり生きていた頃に染みついたものはそう簡単には消えない。
撫子は次から次へとランチボックスに手を伸ばす。オーナーがいたら食い意地が張っていると冷笑が繰り出されるところだが、父は穏やかに微笑んでいるだけだ。
「いっぱい食べなさい」
その温かな眼差しが、生前の父と重なった。年齢は変わっていても、父の本質は変わっていないことを証明するように。
撫子はふと手を置いて頭を下げる。
「拇印の件はありがとうございました。けど、水島さんはどうして私のことをご存じだったのですか?」
撫子は気になっていたことを問いかけた。父は何でもないことのように答える。
「撫子さんのことは前から知っていたよ。猫以外の従業員は珍しかったから、名前を訊いてみたんだ。そうしたら「撫子」だってわかって、ますます親しみがわいてね」
父は山道の方をみやりながら微笑む。
「桃子と、娘が生まれたら「撫子」って名前にしようと話していたから。まだ生まれていない娘に会ったような気分なんだよ」
……ううん、父さん。私は本当にあなたの娘だよ。
撫子は思って、その一言を喉まで上らせた。
だけど撫子は口をつぐんだ。魂を洗う休暇を過ごす内に撫子の記憶が消えたなら、それを無理に思い出させてどうするのだろう?
父は撫子に視線を投げかけて問う。
「ねえ、あのホテルは猫の従業員ばかりだったのに、どうして君は働いていたの? 君は人間だろう?」
撫子ははっと我に返って言う。
「あはは……まあいろいろありまして。アルバイトです」
苦笑しながら答えると、父は目を細める。
「一生懸命働いていて微笑ましかったよ。君は気配りがうまいし、応対の姿勢もいい」
「褒めすぎですよ」
撫子は頬をかいて照れる。
「キャット・ステーション・ホテルは従業員の皆さんのレベルが高いんです。皆さんの様子を見て真似していただけですよ」
職場環境に何の不満もない。働いていて楽しいと胸を張って言える。
父は微笑んで、つと首を傾げる。
「君はずいぶん若いらしいけど、どうしてこの世界に来たの?」
撫子は視線をさまよわせながら、ぽつりと言う。
「さあ。よく覚えていないんですけど、コッペパンが死因みたいで」
「コッペパン?」
「ええ」
そしてパンが原因ということは、食中毒か喉に詰まらせたかどちらかだろう。まさかパンに滑って転んだとは思えない。
「死んじゃったものは仕方ないですから。最近は考えることもやめています」
撫子は空を仰いで深呼吸した。
空気が澄んでいて心地いい。空は青くないが、ほのかな光に満ちていて安心できる。
撫子はこの光景を、夢に見ていた気がする。生きていた間どこかでこの世界とつながっていたのか、もしかしたら生まれる前に見たのか。
「僕もそう思う」
父は笑って撫子に同意した。
「失ったものは仕方ないからこの世界で何か楽しもうと思っていたら、休暇の申請ができるって言われて」
「休暇が認められるのは人間ではなかなか珍しいらしいですよ。欲がないんですね」
それは生前から知っていた。父も母も何かを強く欲しがることなく、そこにある生活を過ごしていくことを喜んだ。
「僕は十分楽しんだからね。これ以上なんて、もうなかったよ」
父はそう言って、撫子の隣で空を仰いだ。
空を仰ぐのは人間の特性だろうかと撫子は思った。
誰だって遠く離れた場所をうかがいたくなる。でも今を受け入れられるかで、意地汚くも潔くもなる。
「幸せでしたか?」
撫子の問いかけに、父は迷うことなくうなずいた。
「とてもね」
二人で景色を見ながらランチを楽しんだ。その時間は二人の関係が親子だと名前がついていないだけで、生きていた頃の団らんと何も変わりがなかった。
笛の音が響いて、ゆっくりと列車が駅舎を離れる。
「オーナーと撫子さんに送ってもらえるなんてね」
「いいのかしら? 他のお客様と不公平にならない?」
向かい側で寄りそって座っている両親に、オーナーはいつも通り完璧な支配人の笑顔で答える。
「仕事で終着駅に向かう用もありますから。いくつか名所をご案内がてら参りましょう」
「それは楽しみだ」
「お宅のホテルのサービスは至れり尽くせりね」
父は母の方を振り向いて付け加える。
「桃子が喜んでくれれば僕はどこでもいいんだけど」
「あら、私は亮さんが楽しければそれでいいわ」
うふふあははと笑い合う両親に、撫子は頭を押さえる。
そうだった。両親はこういう人たちだった。
何をするのも楽しそうで、見ているこっちが胸焼けするくらいいちゃいちゃしている。
「ピクニックとは少し違うのでは」
「休暇は楽しむものだよ? ねえ桃子」
「初めて伊豆に旅行した時のことを思い出すわ。あの時は寝袋に入って一晩じゅう語り合ったわね」
「ああ、懐かしいな」
二人の記憶はどんなささいなことでも覚えていても、娘のことはからっと忘れてしまうくらい、二人の世界を展開する。
「初めて手をつないだのは文化祭の後夜祭だったね」
「夕陽が眩しかったわ。あんな綺麗な景色はきっと一生忘れないって思ったわね」
「僕もそう思ったよ。桃子とはいつも同じものを見てる」
二人でにこにこしながら思い出話にふける姿が切ないと思ったのは最初だけで、列車に乗って数刻で撫子はあきらめの境地に達する。
「オーナー、すみませんね。こういう人たちなんです」
オーナーの猫耳に口を寄せてこっそり告げる。
「存じております」
「あ、そうでしたか」
知られていたのはちょっとどきっとした。
「じゃあ借金大魔王だってこともご存じですか?」
オーナーは猫目を細めて小さくうなずく。撫子は深く息をついて続ける。
「人を疑うことを知らないんですよね。それで何度だまされたことか」
撫子が向かい側でぼやいていても、両親は構わず自分たちの会話に没頭している。
「生命の危険を感じて私が無理やり借金取りから逃げようと説得しなきゃ、もっと早死にしてましたよ。ええ」
実に貧しかった記憶が蘇ってきて、撫子は遠い目をする。
生きていた頃は一日二食食べられたらいい方だった。四畳一間以上の部屋に住んだことがない。冬に水道と電気が止められて震えながら眠ったことも数えきれないほどある。
「まあいいんですけど。慣れればどこも都でしたから」
ところが撫子は記憶に残る限り病気一つしたことがないし、両親も健康そのものだった。
「年にしては達観しましたね」
「はは。落ち込む暇があったら働いてましたから」
一応褒め言葉と受け取っておいて、撫子は向かい側を見やる。
「能天気な両親のおかげですよ、たぶん」
生活は苦しかった。でも両親と一緒に過ごした日々は楽しかった。
両親はいつも二人でくっついていて自分を忘れているのではと思う時もあったが、とにかく優しくて憎めない人たちだったから。
本当に死んじゃったのかな。撫子は苦笑して両親を見る。
こうして旅行にはしゃいでいる二人を見ていると、これはただの夢のようにも思えてくる。
撫子が目を細めて考えに沈んでいたら、オーナーは小声で言った。
「ご両親は死を受け入れていて、休暇の申請を許された数少ない人間です。誇れることですよ」
何かオーナーが言いよどんだ気配を感じて、撫子は問い返す。
「うん? 何か言おうとなさったでしょう。どうぞ言ってください。今更ですから」
撫子は笑いながら袖をつついた。オーナーは首を横に振る。
「気になるじゃないですか。言ってくださいよー」
ぐいぐいとオーナーの袖を引いてみても、彼の鋼鉄のような笑顔は崩れない。
「大人は言葉を選ぶものです」
「それって私が子どもってことですか? いやそうですけど、だったらちょっとくらいヒントをくれたっていいじゃないですか」
撫子たちが言い合っていると、向かい側から声がかかる。
「素敵なカップルだね」
「見本にしたいわ」
おっとりと言われて、撫子は返す言葉に困った。
列車はおしゃべりの邪魔にならない程度にゴトンゴトンと音を立てて、線路の上を走っていく。
撫子たちは他愛もないことを話しながら、淡い光の中で列車に揺られていた。
「あれ?」
少し外の景色が明るくなってきたことに気付いて、撫子は窓の外を見やる。
「そろそろ停留所です」
オーナーに教えられてまもなく、ブレーキがかかったのがわかった。ゆっくりと速度が落ちて行く列車に、車掌のアナウンスがかかる。
「まもなく山上駅です。しばらく停車いたします。ごゆっくりどうぞ」
時間を全く気にしていないのがあの世らしいな。撫子はそんなことを思う。
オーナーは持ってきたバスケットを持ち上げて言う。
「景色が綺麗なので外で食事にしませんか?」
「いいね」
「行きましょう」
両親もそれに乗って、撫子たちは列車から降りた。
駅の名前の通り、外はまさに山の上だった。
斜面には色とりどりの花が咲き乱れて、谷間には透明な湖がある。遠くには山々がそびえたち、赤く紅葉した木々が豊かにしげっていた。
「やあ、絶景ですね。空も明るいような?」
「ここは死出の世界でも昼に近い場所ですので。左から春、夏、秋になっています。頂上からは冬も見えますよ」
プラットホームに隣接した芝生には、いろいろな動物たちが座り込んで談笑していた。ここは展望台のようなものらしい。
オーナーは芝生にシートを引いて、バスケットからサンドイッチや果物を出して並べる。
「見てごらん、桃子。あれは君の花だね」
「あら、本当。亮さんの花がないのが残念ね」
「君と名前を共有している花があることが奇跡みたいなものだよ」
「まあ」
両親は景色を見ているのかそうでないのかわからない会話を繰り広げて笑っている。花の名前の方が先にあるんでしょうがと撫子は心の中で突っ込んだが、言ってもまったく意味はない。
のどかな光景が広がっていた。まさか生きていた頃、あの世で景色を楽しみながらランチを取るとは思ってもみなかった。
動物たちも喧嘩することなく談笑しているし、両親は生きていた頃と変わりなく能天気だし、景色は綺麗で空気は澄んでいる。
やっぱり自分は死んだんだろうな。撫子はなんとなくそんなことを思う。
死んだからこんなに平和なんだ。天国というのは、きっとこういう場所のことを言うのだろうから。
「道があるわね。まだ上に行けるの?」
「ええ。森林浴を楽しみながら頂上へ向かう道です。時間は十分ありますからご案内いたしましょうか?」
オーナーが両親に告げると、父が返す。
「僕はせっかくのランチボックスを頂きたいな。桃子は行っておいでよ」
父は撫子に視線を向けて首を傾ける。
「撫子さんも一緒に食べない?」
「ええ、もちろん頂きます」
基本的に食欲が最優先の撫子だった。生きていた頃にはその日の食事を確保することを目標にしていたから、綺麗なものや面白いものより食べ物が大好きだ。
「では奥様をご案内いたします」
オーナーは一瞬猫目を細めてから、母と共に山道に向かっていった。
「やっぱりおいしいですねぇ」
死出の世界に来てからは食べ物に不自由はしていないが、やっぱり生きていた頃に染みついたものはそう簡単には消えない。
撫子は次から次へとランチボックスに手を伸ばす。オーナーがいたら食い意地が張っていると冷笑が繰り出されるところだが、父は穏やかに微笑んでいるだけだ。
「いっぱい食べなさい」
その温かな眼差しが、生前の父と重なった。年齢は変わっていても、父の本質は変わっていないことを証明するように。
撫子はふと手を置いて頭を下げる。
「拇印の件はありがとうございました。けど、水島さんはどうして私のことをご存じだったのですか?」
撫子は気になっていたことを問いかけた。父は何でもないことのように答える。
「撫子さんのことは前から知っていたよ。猫以外の従業員は珍しかったから、名前を訊いてみたんだ。そうしたら「撫子」だってわかって、ますます親しみがわいてね」
父は山道の方をみやりながら微笑む。
「桃子と、娘が生まれたら「撫子」って名前にしようと話していたから。まだ生まれていない娘に会ったような気分なんだよ」
……ううん、父さん。私は本当にあなたの娘だよ。
撫子は思って、その一言を喉まで上らせた。
だけど撫子は口をつぐんだ。魂を洗う休暇を過ごす内に撫子の記憶が消えたなら、それを無理に思い出させてどうするのだろう?
父は撫子に視線を投げかけて問う。
「ねえ、あのホテルは猫の従業員ばかりだったのに、どうして君は働いていたの? 君は人間だろう?」
撫子ははっと我に返って言う。
「あはは……まあいろいろありまして。アルバイトです」
苦笑しながら答えると、父は目を細める。
「一生懸命働いていて微笑ましかったよ。君は気配りがうまいし、応対の姿勢もいい」
「褒めすぎですよ」
撫子は頬をかいて照れる。
「キャット・ステーション・ホテルは従業員の皆さんのレベルが高いんです。皆さんの様子を見て真似していただけですよ」
職場環境に何の不満もない。働いていて楽しいと胸を張って言える。
父は微笑んで、つと首を傾げる。
「君はずいぶん若いらしいけど、どうしてこの世界に来たの?」
撫子は視線をさまよわせながら、ぽつりと言う。
「さあ。よく覚えていないんですけど、コッペパンが死因みたいで」
「コッペパン?」
「ええ」
そしてパンが原因ということは、食中毒か喉に詰まらせたかどちらかだろう。まさかパンに滑って転んだとは思えない。
「死んじゃったものは仕方ないですから。最近は考えることもやめています」
撫子は空を仰いで深呼吸した。
空気が澄んでいて心地いい。空は青くないが、ほのかな光に満ちていて安心できる。
撫子はこの光景を、夢に見ていた気がする。生きていた間どこかでこの世界とつながっていたのか、もしかしたら生まれる前に見たのか。
「僕もそう思う」
父は笑って撫子に同意した。
「失ったものは仕方ないからこの世界で何か楽しもうと思っていたら、休暇の申請ができるって言われて」
「休暇が認められるのは人間ではなかなか珍しいらしいですよ。欲がないんですね」
それは生前から知っていた。父も母も何かを強く欲しがることなく、そこにある生活を過ごしていくことを喜んだ。
「僕は十分楽しんだからね。これ以上なんて、もうなかったよ」
父はそう言って、撫子の隣で空を仰いだ。
空を仰ぐのは人間の特性だろうかと撫子は思った。
誰だって遠く離れた場所をうかがいたくなる。でも今を受け入れられるかで、意地汚くも潔くもなる。
「幸せでしたか?」
撫子の問いかけに、父は迷うことなくうなずいた。
「とてもね」
二人で景色を見ながらランチを楽しんだ。その時間は二人の関係が親子だと名前がついていないだけで、生きていた頃の団らんと何も変わりがなかった。