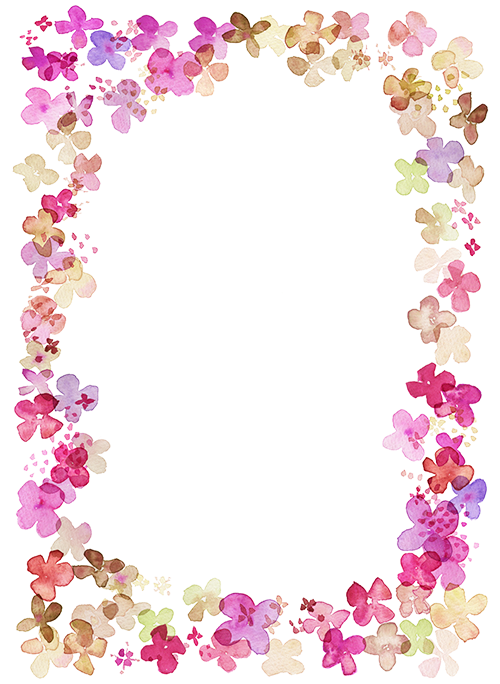フィンとルイに拇印をもらってから、撫子は部屋を出て従業員を探しに行った。
ヴィンセントの言う通り、ホテルの中は変化が始まっていた。
「女将はルームサービスなど日本の宿でされてはならんとおっしゃっていたぞ」
「納得できん。お客様が希望されているならいいじゃないか」
あちこちでサービスや設備について口論がされて、提供するか否かでもめている。
これなら拇印がもらえるかもしれない。撫子は期待に胸を熱くして声をかける。
「すみません。今ホテルの改装を止めるために女将の権限を凍結する運動をしているのですが」
「え?」
ただ、問題は撫子がホテルの従業員ではないことらしかった。
「申し訳ありません、お客様。女将は宿の主でございますから」
どんなにもめていてもお客様には汚いところは見せず、かつマイルドに接するのがキャット・ステーション・ホテルの従業員だ。撫子が拇印の提供を求めても、すべて丁重に断られた。
「参ったな」
手当たり次第に頼んでみたが、どうにも残り二人の従業員の拇印が貰えない。
「ヴィンセントさんと一緒に頼んでもらった方がよかったかな……でも改装も止めてもらわないと」
ぼやきながらフロントを通り過ぎて玄関までやって来る。
「あ、撫子様!」
ぴょこんと耳を動かして撫子のところまで駆けてきたのはチャーリーだった。
「何か御用はありませんか?」
嬉しそうに尻尾を振って首を傾けながら問いかけてくる。
撫子は疲れていたので、投げやりに言った。
「何も言わずにこの書類に拇印をくれると嬉しいな」
思わずぽつりとつぶやいてから、撫子は苦笑する。
「はは。ごめん、冗談。いくら君でも」
「これでいいですか?」
「……って」
チャーリーはぺたりと自分の拇印を付けた委任状を撫子に返してくる。
「押してるー! 君、書類はちゃんと読んでからハンコ捺さなきゃ! だまされたらどうするんだ!」
思いがけず二人目の拇印が集まったが、彼の将来が心配になって叫んだ。
チャーリーはきょとんとして言った。
「僕はホテルの従業員になる時に、どんな時でもお客様の味方になりなさいって教わっていますから」
撫子がとっさに黙ると、チャーリーは屈託なく笑いながらふと首を傾げる。
「あれ、でもあの時のホテルの主は女将じゃなかったような?」
「チャーリー。その方の言う通りだ」
扉の向こう側に立っているヒューイが声をかけてくる。
「いくらお客様の頼み事といっても、冷静に判断して自分で対応を考えるのが一人前の従業員だろう。お前は考えなしすぎる」
「君、お兄さんよりしっかりしてるね」
時々どちらが兄なのか忘れる兄弟だった。撫子はその安定感に乾いた笑いをもらす。
「撫子様、その書面は何ですか?」
沈着冷静に訊ねてくるヒューイに、ああ彼にはごまかしは通用しないなと思う。
ちゃんと説明しよう。もしかしたらチャーリーの拇印もなしになってしまうかもしれないが、嘘をつくのはいけない。
「これはね……」
「何をしているのです」
言いかけた撫子の元に、鳥の羽音が聞こえた。
恐る恐る振り向く。そこには桜の模様の着物をまとった女将が立っていた。
「あなたは人間の……。当宿は人間の宿泊を認めません。退去なさい」
女将の厳しい口調に撫子の身がすくむ。
撫子はぎゅっと委任状を握り締めたまま後ずさった。
「何ですか、それは。お見せなさい」
女将が手を伸ばして委任状に手を触れると、それは電気を放つように女将の手を弾き返した。
「……まさか委任状? なんてこと!」
女将は血相を変えて翼を出す。
突風が吹き抜けて、撫子は玄関の扉に叩きつけられた。
「ぐっ!」
「放棄なさい。人間」
背中に走った痛みに体を縮めながら、撫子はきっと女将をにらみつける。
「いやだ!」
これは今自分にできる唯一のこと。手放してたまるものかと跳ねのける。
「小癪な……」
空気の流れが変わって、撫子が身構えた時だった。
撫子の前に誰かが立ちふさがる。風は撫子に触れることなく壁と扉を揺らしただけだった。
「……ヒューイ君?」
撫子の前に立ってヒューイが両手を広げていた。
守るように上げていた手を下げると、ヒューイは目を光らせて女将を見返す。
「お客様に危害を加えるのは、女将といえど許されることではありません」
断固とした非難の口調に、女将は冷えた声で言う。
「一門番が主に逆らうのですか」
「当宿の真の主はお客様です」
ヒューイはグレーの瞳で女将を見据えて告げる。
「僕の真の主もお客様です。そのお客様に危害を加える上司には従いません。どうぞ僕の名前をお消しください」
にらみあいがしばらく続いて、先に目を逸らしたのは女将だった。
翼を出して飛び去って行く女将を見送ってから、ヒューイは撫子に振り向く。
「君が真面目なのは知ってるけど、あんまり危ないことしちゃだめだよ」
撫子が思わずヒューイに言ったら、彼は一拍黙った。
「その言葉、そっくりそのままお返しします」
ヒューイはまっすぐに撫子を見て言った。
「僕は契約した主の言葉を繰り返しただけです。お客様に危害を加えるならば主にさえ従う必要はないと」
「君と契約した?」
撫子は目を見開いて言う。
「君、オーナーのこと覚えてるの?」
「育てていただいた方のことは忘れません。チャーリーもそうです」
撫子が振り向くと、チャーリーはこくんとうなずき返す。
ヒューイは撫子の持っている委任状に目を向けて言う。
「ただ僕らはお客様に最高の休暇を提供できる方であれば、主が誰であっても構わないと思うだけです。あなたにはそれができますか?」
撫子はヒューイの意図を察して、彼をじっと見返した。
「ホテルにふさわしい主を取り戻したいんだ。君の力を貸してほしい」
ヒューイは猫目を細めて思案顔をすると、やがて一つうなずいた。
ヴィンセントの言う通り、ホテルの中は変化が始まっていた。
「女将はルームサービスなど日本の宿でされてはならんとおっしゃっていたぞ」
「納得できん。お客様が希望されているならいいじゃないか」
あちこちでサービスや設備について口論がされて、提供するか否かでもめている。
これなら拇印がもらえるかもしれない。撫子は期待に胸を熱くして声をかける。
「すみません。今ホテルの改装を止めるために女将の権限を凍結する運動をしているのですが」
「え?」
ただ、問題は撫子がホテルの従業員ではないことらしかった。
「申し訳ありません、お客様。女将は宿の主でございますから」
どんなにもめていてもお客様には汚いところは見せず、かつマイルドに接するのがキャット・ステーション・ホテルの従業員だ。撫子が拇印の提供を求めても、すべて丁重に断られた。
「参ったな」
手当たり次第に頼んでみたが、どうにも残り二人の従業員の拇印が貰えない。
「ヴィンセントさんと一緒に頼んでもらった方がよかったかな……でも改装も止めてもらわないと」
ぼやきながらフロントを通り過ぎて玄関までやって来る。
「あ、撫子様!」
ぴょこんと耳を動かして撫子のところまで駆けてきたのはチャーリーだった。
「何か御用はありませんか?」
嬉しそうに尻尾を振って首を傾けながら問いかけてくる。
撫子は疲れていたので、投げやりに言った。
「何も言わずにこの書類に拇印をくれると嬉しいな」
思わずぽつりとつぶやいてから、撫子は苦笑する。
「はは。ごめん、冗談。いくら君でも」
「これでいいですか?」
「……って」
チャーリーはぺたりと自分の拇印を付けた委任状を撫子に返してくる。
「押してるー! 君、書類はちゃんと読んでからハンコ捺さなきゃ! だまされたらどうするんだ!」
思いがけず二人目の拇印が集まったが、彼の将来が心配になって叫んだ。
チャーリーはきょとんとして言った。
「僕はホテルの従業員になる時に、どんな時でもお客様の味方になりなさいって教わっていますから」
撫子がとっさに黙ると、チャーリーは屈託なく笑いながらふと首を傾げる。
「あれ、でもあの時のホテルの主は女将じゃなかったような?」
「チャーリー。その方の言う通りだ」
扉の向こう側に立っているヒューイが声をかけてくる。
「いくらお客様の頼み事といっても、冷静に判断して自分で対応を考えるのが一人前の従業員だろう。お前は考えなしすぎる」
「君、お兄さんよりしっかりしてるね」
時々どちらが兄なのか忘れる兄弟だった。撫子はその安定感に乾いた笑いをもらす。
「撫子様、その書面は何ですか?」
沈着冷静に訊ねてくるヒューイに、ああ彼にはごまかしは通用しないなと思う。
ちゃんと説明しよう。もしかしたらチャーリーの拇印もなしになってしまうかもしれないが、嘘をつくのはいけない。
「これはね……」
「何をしているのです」
言いかけた撫子の元に、鳥の羽音が聞こえた。
恐る恐る振り向く。そこには桜の模様の着物をまとった女将が立っていた。
「あなたは人間の……。当宿は人間の宿泊を認めません。退去なさい」
女将の厳しい口調に撫子の身がすくむ。
撫子はぎゅっと委任状を握り締めたまま後ずさった。
「何ですか、それは。お見せなさい」
女将が手を伸ばして委任状に手を触れると、それは電気を放つように女将の手を弾き返した。
「……まさか委任状? なんてこと!」
女将は血相を変えて翼を出す。
突風が吹き抜けて、撫子は玄関の扉に叩きつけられた。
「ぐっ!」
「放棄なさい。人間」
背中に走った痛みに体を縮めながら、撫子はきっと女将をにらみつける。
「いやだ!」
これは今自分にできる唯一のこと。手放してたまるものかと跳ねのける。
「小癪な……」
空気の流れが変わって、撫子が身構えた時だった。
撫子の前に誰かが立ちふさがる。風は撫子に触れることなく壁と扉を揺らしただけだった。
「……ヒューイ君?」
撫子の前に立ってヒューイが両手を広げていた。
守るように上げていた手を下げると、ヒューイは目を光らせて女将を見返す。
「お客様に危害を加えるのは、女将といえど許されることではありません」
断固とした非難の口調に、女将は冷えた声で言う。
「一門番が主に逆らうのですか」
「当宿の真の主はお客様です」
ヒューイはグレーの瞳で女将を見据えて告げる。
「僕の真の主もお客様です。そのお客様に危害を加える上司には従いません。どうぞ僕の名前をお消しください」
にらみあいがしばらく続いて、先に目を逸らしたのは女将だった。
翼を出して飛び去って行く女将を見送ってから、ヒューイは撫子に振り向く。
「君が真面目なのは知ってるけど、あんまり危ないことしちゃだめだよ」
撫子が思わずヒューイに言ったら、彼は一拍黙った。
「その言葉、そっくりそのままお返しします」
ヒューイはまっすぐに撫子を見て言った。
「僕は契約した主の言葉を繰り返しただけです。お客様に危害を加えるならば主にさえ従う必要はないと」
「君と契約した?」
撫子は目を見開いて言う。
「君、オーナーのこと覚えてるの?」
「育てていただいた方のことは忘れません。チャーリーもそうです」
撫子が振り向くと、チャーリーはこくんとうなずき返す。
ヒューイは撫子の持っている委任状に目を向けて言う。
「ただ僕らはお客様に最高の休暇を提供できる方であれば、主が誰であっても構わないと思うだけです。あなたにはそれができますか?」
撫子はヒューイの意図を察して、彼をじっと見返した。
「ホテルにふさわしい主を取り戻したいんだ。君の力を貸してほしい」
ヒューイは猫目を細めて思案顔をすると、やがて一つうなずいた。