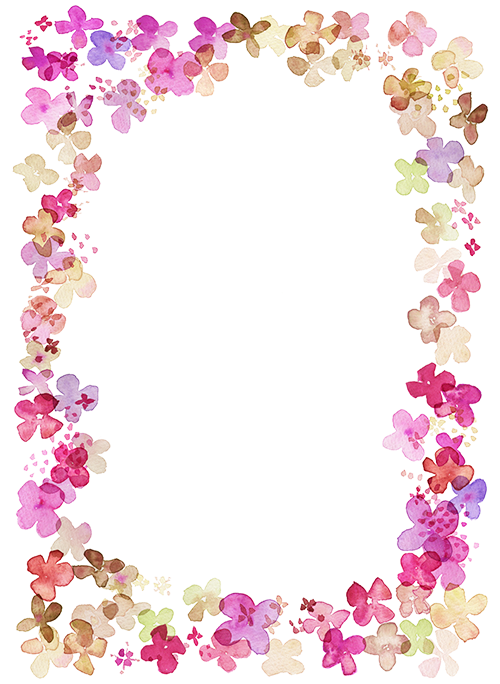肩を揺さぶられる感覚に、深い海の中から引っ張り上げられるような覚醒感があった。
撫子が目を開くと、そこには心配そうなヴィンセントの顔があった。
「返事がなかったので入らせて頂きました。どこか具合でも?」
撫子はオーナーのベッドで仰向けになっていた。床に寝転んだ覚えはないから、ヴィンセントが運んでくれたのだろう。
ヴィンセントの助けを借りながら体を起こして、辺りを見回す。
「夢を……」
オーナーの部屋に白いスクリーンはない。いつも掃除に来ている通りのオーナーの部屋だ。
撫子は右手が熱くなる感触に、手をぐっと握りしめる。
「夢にするもんか」
撫子は顔を上げてヴィンセントを見返す。
「副オーナーの紙をお持ちではありませんか? それで委任状を作るんです」
撫子の言葉に、ヴィンセントははっと息を呑む。
「どうしてそれを? いえ、私もそれを探して一応お持ちしたのですが、書き方を忘れてしまって」
「私が書けます!」
首を傾げて撫子を見るヴィンセントに、撫子はうなずく。
「ペンはありますか?」
ヴィンセントは戸惑う素振りを見せたが、すぐに懐に手を入れて一枚の巻物とペンを取り出した。
一見してみると何の変哲もないただの紙だった。ペンにも細工がしてある様子はない。
「神様、お願いします」
だけどこれが神から交付された由緒正しい紙だというなら、それに賭けてみたい。
撫子は何の神かわからないながら手を合わせて、ペン先を紙につける。
「我、宿主に、異……を、となえし、もの」
まぶたの裏の記憶と幼いオーナーの手のぬくもりが蘇る。
うなりながら、撫子は小学生が初めて漢字を書くような拙い字を書き始めた。
「宿は客人の作りしもの。遠方からやって来た旅人のよりどころ。私有にあらず」
声に出して字を読むと、さっぱりわからなかったはずの言葉が生きたものに感じられてくる。
遠くから来たなら、楽しいところで過ごしたい。安心するところで眠りたい。撫子もやって来た一人だからわかる。
目を閉じれば幼いオーナーが撫子の右手を握っていて、撫子に教えてくれる。
ほら、簡単なことでしょう。オーナーが笑う声が聞こえる気がする。
「キャット・ステーション・ホテル」
撫子はミミズがのたくったような字で署名を記した。
副オーナーの紙はふいに光って、返事をするように「キャット・ステーション・ホテル」の透かし字を浮かび上がらせた。
「……これは、オーケイって返事?」
撫子が恐る恐る紙を裏返して確かめると、ヴィンセントが笑顔になる。
「すばらしいです、撫子様」
「いや、まだまだ安心するのは早いです。従業員三名とお客様三名の拇印をもらわないと……」
撫子は紙の下の方を指さす。
「とりあえずヴィンセントさんの拇印をください」
「もちろんです」
ヴィンセントが人差し指で触れると、そこにかわいい猫の手のマークが現れた。
拇印ってこういうものだっけ? 撫子は多少納得できなかったが、何はともあれ一歩前進だった。
「でも従業員のみんなはオーナーのことを忘れてるんですよね? あと二つはどうしたらいいんでしょうか」
「朗報がありますよ」
ヴィンセントは頬をほころばせて言う。
「女将に従わない従業員が増えているのです。長年オーナーのやり方に従ってきた従業員は、無意識に異変に気付いているのだと思います」
「それなら拇印が貰えるかもしれませんね!」
撫子は拇印を提供してくれそうな従業員を頭の中で探しつつ、元気よく立ち上がる。
「問題はお客様ですけど」
言いかけたところで、来訪のベルが鳴った。
撫子とヴィンセントは顔を見合わせて、玄関の方に急ぐ。
「撫子? ここってオーナーの部屋じゃなかったか?」
来訪者は寄宿学生風少年と英国紳士、フィンとルイだった。
フィンはいぶかしげに問う。
「オーナーはどこに行ったんだ?」
「えっ? フィン様はオーナーを覚えておいでで?」
「当たり前だろう」
「あ、もしかして」
従業員名簿は従業員にしか効果がないらしかった。オーナーの名前が消されたからといってお客様の記憶からは消えない。
フィンは頭からぷりぷりと湯気を吹き出しながら言う。
「突然エレベーターをなくしたりレストランを閉めたり、一体何を始めたのか苦情を言いに来た。なぜか女将とかいう雀が出張っているし、従業員はオーナーなど知らないと言うし。客の迷惑も考えろっていうんだ」
つらつらと文句を並べるフィンに、兄のルイが笑いを含んだ声をかける。
「フィンが一番気にいらないのはプールを閉めたことだろ。最近水浴びが楽しくて仕方ないところだもんな」
「兄さん!」
水が嫌いだったフィンは、いつの間にかプールの常連になっていたらしい。撫子はちょっと驚いてまじまじとフィンを見た。
フィンは撫子に視線に気づいたのか慌てて言う。
「そうじゃなくて! このホテルもまあ悪くないと最近思ってたのに、今更失望させるなってことを言いたいんだ」
「ありがとうございます!」
撫子はぺこりと頭を下げて言う。
「戻ったらオーナーによく伝えておきます。あ、あと、それなら」
撫子はばっと顔を上げた。
「もし今のホテルに不満を持っていらっしゃるなら……」
撫子は慌てて、委任状を取り出して二人に説明を始めたのだった。
撫子が目を開くと、そこには心配そうなヴィンセントの顔があった。
「返事がなかったので入らせて頂きました。どこか具合でも?」
撫子はオーナーのベッドで仰向けになっていた。床に寝転んだ覚えはないから、ヴィンセントが運んでくれたのだろう。
ヴィンセントの助けを借りながら体を起こして、辺りを見回す。
「夢を……」
オーナーの部屋に白いスクリーンはない。いつも掃除に来ている通りのオーナーの部屋だ。
撫子は右手が熱くなる感触に、手をぐっと握りしめる。
「夢にするもんか」
撫子は顔を上げてヴィンセントを見返す。
「副オーナーの紙をお持ちではありませんか? それで委任状を作るんです」
撫子の言葉に、ヴィンセントははっと息を呑む。
「どうしてそれを? いえ、私もそれを探して一応お持ちしたのですが、書き方を忘れてしまって」
「私が書けます!」
首を傾げて撫子を見るヴィンセントに、撫子はうなずく。
「ペンはありますか?」
ヴィンセントは戸惑う素振りを見せたが、すぐに懐に手を入れて一枚の巻物とペンを取り出した。
一見してみると何の変哲もないただの紙だった。ペンにも細工がしてある様子はない。
「神様、お願いします」
だけどこれが神から交付された由緒正しい紙だというなら、それに賭けてみたい。
撫子は何の神かわからないながら手を合わせて、ペン先を紙につける。
「我、宿主に、異……を、となえし、もの」
まぶたの裏の記憶と幼いオーナーの手のぬくもりが蘇る。
うなりながら、撫子は小学生が初めて漢字を書くような拙い字を書き始めた。
「宿は客人の作りしもの。遠方からやって来た旅人のよりどころ。私有にあらず」
声に出して字を読むと、さっぱりわからなかったはずの言葉が生きたものに感じられてくる。
遠くから来たなら、楽しいところで過ごしたい。安心するところで眠りたい。撫子もやって来た一人だからわかる。
目を閉じれば幼いオーナーが撫子の右手を握っていて、撫子に教えてくれる。
ほら、簡単なことでしょう。オーナーが笑う声が聞こえる気がする。
「キャット・ステーション・ホテル」
撫子はミミズがのたくったような字で署名を記した。
副オーナーの紙はふいに光って、返事をするように「キャット・ステーション・ホテル」の透かし字を浮かび上がらせた。
「……これは、オーケイって返事?」
撫子が恐る恐る紙を裏返して確かめると、ヴィンセントが笑顔になる。
「すばらしいです、撫子様」
「いや、まだまだ安心するのは早いです。従業員三名とお客様三名の拇印をもらわないと……」
撫子は紙の下の方を指さす。
「とりあえずヴィンセントさんの拇印をください」
「もちろんです」
ヴィンセントが人差し指で触れると、そこにかわいい猫の手のマークが現れた。
拇印ってこういうものだっけ? 撫子は多少納得できなかったが、何はともあれ一歩前進だった。
「でも従業員のみんなはオーナーのことを忘れてるんですよね? あと二つはどうしたらいいんでしょうか」
「朗報がありますよ」
ヴィンセントは頬をほころばせて言う。
「女将に従わない従業員が増えているのです。長年オーナーのやり方に従ってきた従業員は、無意識に異変に気付いているのだと思います」
「それなら拇印が貰えるかもしれませんね!」
撫子は拇印を提供してくれそうな従業員を頭の中で探しつつ、元気よく立ち上がる。
「問題はお客様ですけど」
言いかけたところで、来訪のベルが鳴った。
撫子とヴィンセントは顔を見合わせて、玄関の方に急ぐ。
「撫子? ここってオーナーの部屋じゃなかったか?」
来訪者は寄宿学生風少年と英国紳士、フィンとルイだった。
フィンはいぶかしげに問う。
「オーナーはどこに行ったんだ?」
「えっ? フィン様はオーナーを覚えておいでで?」
「当たり前だろう」
「あ、もしかして」
従業員名簿は従業員にしか効果がないらしかった。オーナーの名前が消されたからといってお客様の記憶からは消えない。
フィンは頭からぷりぷりと湯気を吹き出しながら言う。
「突然エレベーターをなくしたりレストランを閉めたり、一体何を始めたのか苦情を言いに来た。なぜか女将とかいう雀が出張っているし、従業員はオーナーなど知らないと言うし。客の迷惑も考えろっていうんだ」
つらつらと文句を並べるフィンに、兄のルイが笑いを含んだ声をかける。
「フィンが一番気にいらないのはプールを閉めたことだろ。最近水浴びが楽しくて仕方ないところだもんな」
「兄さん!」
水が嫌いだったフィンは、いつの間にかプールの常連になっていたらしい。撫子はちょっと驚いてまじまじとフィンを見た。
フィンは撫子に視線に気づいたのか慌てて言う。
「そうじゃなくて! このホテルもまあ悪くないと最近思ってたのに、今更失望させるなってことを言いたいんだ」
「ありがとうございます!」
撫子はぺこりと頭を下げて言う。
「戻ったらオーナーによく伝えておきます。あ、あと、それなら」
撫子はばっと顔を上げた。
「もし今のホテルに不満を持っていらっしゃるなら……」
撫子は慌てて、委任状を取り出して二人に説明を始めたのだった。