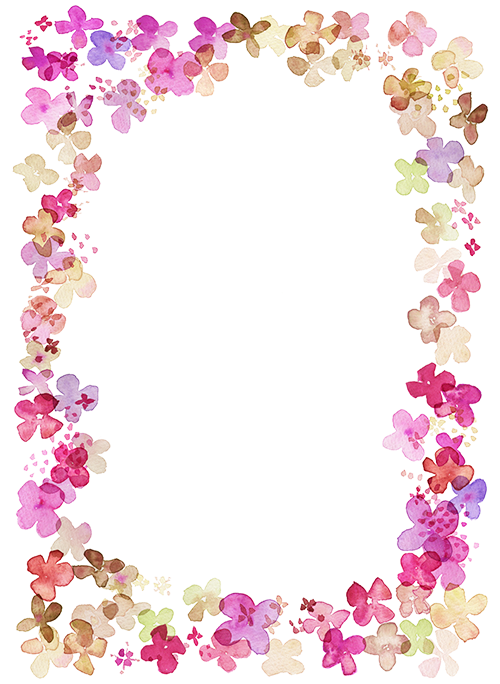建設途中のホテルの中のフロントの台を前にして、撫子はうめき声を上げていた。
「これ、本当に全部覚えなきゃいけないんですか?」
「当たり前です。この程度暗記できなければ代理なんて許されません」
キャットが台に乗せた書面には、まるで呪文のような記号がひたすら並んでいる。
「難しすぎますよ! せめてコピーください」
「委任状は複製不可です。第一過去から物を持っていくことはできません」
「ううう」
わかっている。生前真面目に勉強してこなかったツケだ。
いや、違うかもと思った。撫子の平凡な人生に、こんな呪文を覚える機会なんて百年生きてもなかったかもしれない。
「なんでもっと簡単な文字にしないんですか」
「古代から使われている由緒正しい共通文字ですから。お上が変えようとされなかったのでこれがずっと使われています」
「エリート教育は庶民にははた迷惑です」
「あなたの頭が足らないだけなんじゃないですか?」
幼少の頃のオーナーは言葉をオブラートに包まない分、容赦がないようだ。
「もっと難しいことは他にあります。委任状には従業員三名とお客様三名の同意が必要です。オーナーに異を唱えるのですから、従業員とお客様の意思に沿っていないといけません」
「サインでもしてもらうんですか?」
「拇印で足ります。死出の世界では文字が書ける者は一部ですから」
だったらどうして委任状の文面自体にこんな小難しい文字を要求するのか。あの世のお上は理不尽だと思った。
「紙と六名分の拇印が揃ったら、「代理権発動」と宣言してください。現在のオーナーの権限が凍結されて、あなたにオーナーの権限が移ります。ただ……」
キャットは猫目を細めてうなる。
「権限は与えられてもあなたはオーナーとしての教育を受けていないので、力が使いこなせないかもしれません。たとえば瞬間移動の能力は、元々の体が瞬時に移動するだけの力を持っているからできるんです」
「なるほど」
撫子も瞬間移動はできる気がしなかったので、納得した。あれは身体能力の突出している猫の従業員だからこそできるものらしかった。
「まあ、がんばります」
撫子は頭をかいて暗記作業に戻る。
「どうしました?」
撫子の顔を側でじっと見ているキャットが気になったので、視線を文面に落としたまま問いかける。
キャットはぷいと顔を背けて言った。
「いいえ。別に」
「何か思ったことがあったら言ってくださいよ。オーナーに皮肉言われるのは慣れてますから」
撫子は繰り返し書きとりをしながら言う。頭では覚えられなくても、手が覚えてくれることを期待した。
「キャットー。見てみて、これがエレベーターよ!」
先代の声にキャットが顔を上げる。
撫子も目を向けると、アニマル的特徴を持った人たちがフロントの隣に機械を設置しているところだった。
「エレベーターって、万博で出ていた昇降機のことですか? 日本にはまだないでしょう」
エレベーターはいつ頃に来たものだっただろうか。撫子は考えたが、たぶん百年くらいは前なのだろう。
「どこまで西洋かぶれしたホテルを作るつもりなんですか。この間雀の女将にも馬鹿にされたのに。ここは日本のお客様がほとんどなんですよ」
おやと撫子は思う。この頃はキャットが雀の女将の意見を気にしている素振りがある。
「ホテルは生活空間であると同時に非日常でなくちゃ」
うっとりした口調で先代は言う。
「生きていた頃に夢見ていたような憧れの生活を提供するのよ。それでこそ魂の休暇だと思わない?」
撫子は先代の言葉になるほどと思った。
ただの日常なら生きている内に十分経験している。あの世でくらい非日常を味わいたい。
「僕は多分にオーナーの趣味が含まれていると思いますが。従業員を全員猫で揃えるつもりだとか」
「それくらいの遊び心はいいじゃないの。ね、撫子さん?」
「そうですね。暮らし心地のいいホテルに仕上がっていましたよ」
「ほら」
ふいにキャットが何かに引っ張られるように動く。
「何ですか」
「庭も見に行きましょ」
「撫子はどうするんです。まだ暗記できていませんよ」
「一緒に来てもらえばいいじゃない。キャットの将来の奥さんには、ここの良さをいろいろ知ってもらわなきゃ」
「わ」
手首をぎゅっと握られる感触があった。たぶん先代が掴んだのだろう。
「見物しないと損よ」
今遊んでいる場合ではないのですが。そんな言葉は喉の奥で消えた。
目の前の白いスクリーンに吸い込まれると、そこは噴水を中心とした庭園だった。
色とりどりの薔薇が咲き乱れる光景が圧巻だった。撫子は思わずペンを取り落とす。
「ここは英国風の庭。あっちが和風で、向こうが……」
ただしいろいろ混ざっている。砂と苔で出来た和風の庭がすぐ隣にあるし、その向こうには彫刻だらけの美術館の庭みたいになっている。
キャットは呆れたように言う。
「統一性がなくてみっともないですよ。考えたことを全部実行するのはやめてください」
「だって作りたいんだもの」
キャットはあくまで冷ややかだが、先代は楽しそうだ。笑い声が行ったり来たりして、庭をあちこち歩き回っているのがわかる。
「ゴンドラも作ったの。空から見られるように」
「また突拍子もない」
「さ、行きましょ。撫子さんも」
キャットがまた引っ張られる動きをする。キャットは不機嫌そうに眉をひそめた。
目の前に白いスクリーンが現れて中に入ると、また場面が変わる。
先代が撫子とキャットに見せてくれたのは、ゴンドラだったり厨房だったり倉庫だったりした。
「先代は発明家だったのですか?」
エレベーターもない頃の日本人とは思えない新しさが溢れていたので、撫子は不思議になった。
「そうなりたかったの。私は二十歳前に死んだから、あっちの世界を思い出しながら勉強して考えたの」
「すごいですね。一人でよくここまで」
「一人じゃないわ。死出の世界で勧誘した従業員の皆がいるし」
キャットが何かを振り払うような仕草をする。
「ちょっと。頭撫でないでください」
「次期オーナーの教育もやりがいがあるしね」
最初は抵抗していたが、やがてキャットは諦めて頭を撫でられるままになっていた。微笑ましくなって撫子は目を細める。
「暗記しなくていいんですか、撫子。僕はその程度ひとめで覚えられましたよ」
「あなたのような神童と一緒にしないで頂きたいです」
とはいえ自分の能力の低さを悔やんでも仕方がない。
撫子はキャットが貸してくれたメモを見ながら、委任状の書きとりを再開する。
何度書いても意味がわからない。書いた直後から混乱する。
だけどこれができないとホテルを取り返せない。そう思うと、ひたすら手を動かすしかなかった。
「大体こんなことをしなくても、未来の僕は自分でホテルを取り返しますよ」
「まあきっとそうですけど、そうなんですけど」
撫子はちゃんとした理屈が思い浮かばないながらも、目を白黒させて言う。
「ホテルに土足で上がり込んだ女将に、何とか仕返しをしたいのかも……いや、それはオーナーの思いじゃなくて私の個人的なものですけど、きっとオーナーだってそう思ってくれるはず。はは、わからなくなってきました」
難しすぎて説明する言葉が尻すぼみになる。
頬をかいて黙った撫子を見て、キャットは一言つぶやく。
「お馬鹿」
顔を上げた撫子の目に映ったのは、いつか見たような優しい眼差しだった。
キャットは同情でももちろん軽蔑でもなく、不思議な温かみを持って撫子に笑いかける。
「ほら、いいですか」
思わず手を止めた撫子の手にキャットは自分の手を重ねて、ゆっくりと動かし始める。
「我、宿主に、異を、唱えし、者」
言い聞かせるように文言を区切りながら、キャットは撫子の手と共に委任状の文句を記す。
「ここに、宿主を、代理する、ことを、宣言、する。撫子。……もう一度」
キャットの動きに合わせて手を動かすと、自然と言葉が手に染みついていくような気がした。
撫子の手を取って、キャットは繰り返し委任状の文句を書き記す。
「字が下手でも読みづらくても、異を唱える意思がお上に伝わればいいんです」
「はい」
「もう一度、最初から」
いつしか撫子は、キャットが手を離していることに気付いていた。
「ホテルは建てた者の意思を受け継いでいますから。その意思を形にすれば、ホテルが力を貸してくれます」
次第に薄れていく意識の中、キャットが言う。
「オーナーの意思を忘れないでください」
見えなくなっていく紙を目に焼き付けるようにして、撫子は手を動かし続けた。
「これ、本当に全部覚えなきゃいけないんですか?」
「当たり前です。この程度暗記できなければ代理なんて許されません」
キャットが台に乗せた書面には、まるで呪文のような記号がひたすら並んでいる。
「難しすぎますよ! せめてコピーください」
「委任状は複製不可です。第一過去から物を持っていくことはできません」
「ううう」
わかっている。生前真面目に勉強してこなかったツケだ。
いや、違うかもと思った。撫子の平凡な人生に、こんな呪文を覚える機会なんて百年生きてもなかったかもしれない。
「なんでもっと簡単な文字にしないんですか」
「古代から使われている由緒正しい共通文字ですから。お上が変えようとされなかったのでこれがずっと使われています」
「エリート教育は庶民にははた迷惑です」
「あなたの頭が足らないだけなんじゃないですか?」
幼少の頃のオーナーは言葉をオブラートに包まない分、容赦がないようだ。
「もっと難しいことは他にあります。委任状には従業員三名とお客様三名の同意が必要です。オーナーに異を唱えるのですから、従業員とお客様の意思に沿っていないといけません」
「サインでもしてもらうんですか?」
「拇印で足ります。死出の世界では文字が書ける者は一部ですから」
だったらどうして委任状の文面自体にこんな小難しい文字を要求するのか。あの世のお上は理不尽だと思った。
「紙と六名分の拇印が揃ったら、「代理権発動」と宣言してください。現在のオーナーの権限が凍結されて、あなたにオーナーの権限が移ります。ただ……」
キャットは猫目を細めてうなる。
「権限は与えられてもあなたはオーナーとしての教育を受けていないので、力が使いこなせないかもしれません。たとえば瞬間移動の能力は、元々の体が瞬時に移動するだけの力を持っているからできるんです」
「なるほど」
撫子も瞬間移動はできる気がしなかったので、納得した。あれは身体能力の突出している猫の従業員だからこそできるものらしかった。
「まあ、がんばります」
撫子は頭をかいて暗記作業に戻る。
「どうしました?」
撫子の顔を側でじっと見ているキャットが気になったので、視線を文面に落としたまま問いかける。
キャットはぷいと顔を背けて言った。
「いいえ。別に」
「何か思ったことがあったら言ってくださいよ。オーナーに皮肉言われるのは慣れてますから」
撫子は繰り返し書きとりをしながら言う。頭では覚えられなくても、手が覚えてくれることを期待した。
「キャットー。見てみて、これがエレベーターよ!」
先代の声にキャットが顔を上げる。
撫子も目を向けると、アニマル的特徴を持った人たちがフロントの隣に機械を設置しているところだった。
「エレベーターって、万博で出ていた昇降機のことですか? 日本にはまだないでしょう」
エレベーターはいつ頃に来たものだっただろうか。撫子は考えたが、たぶん百年くらいは前なのだろう。
「どこまで西洋かぶれしたホテルを作るつもりなんですか。この間雀の女将にも馬鹿にされたのに。ここは日本のお客様がほとんどなんですよ」
おやと撫子は思う。この頃はキャットが雀の女将の意見を気にしている素振りがある。
「ホテルは生活空間であると同時に非日常でなくちゃ」
うっとりした口調で先代は言う。
「生きていた頃に夢見ていたような憧れの生活を提供するのよ。それでこそ魂の休暇だと思わない?」
撫子は先代の言葉になるほどと思った。
ただの日常なら生きている内に十分経験している。あの世でくらい非日常を味わいたい。
「僕は多分にオーナーの趣味が含まれていると思いますが。従業員を全員猫で揃えるつもりだとか」
「それくらいの遊び心はいいじゃないの。ね、撫子さん?」
「そうですね。暮らし心地のいいホテルに仕上がっていましたよ」
「ほら」
ふいにキャットが何かに引っ張られるように動く。
「何ですか」
「庭も見に行きましょ」
「撫子はどうするんです。まだ暗記できていませんよ」
「一緒に来てもらえばいいじゃない。キャットの将来の奥さんには、ここの良さをいろいろ知ってもらわなきゃ」
「わ」
手首をぎゅっと握られる感触があった。たぶん先代が掴んだのだろう。
「見物しないと損よ」
今遊んでいる場合ではないのですが。そんな言葉は喉の奥で消えた。
目の前の白いスクリーンに吸い込まれると、そこは噴水を中心とした庭園だった。
色とりどりの薔薇が咲き乱れる光景が圧巻だった。撫子は思わずペンを取り落とす。
「ここは英国風の庭。あっちが和風で、向こうが……」
ただしいろいろ混ざっている。砂と苔で出来た和風の庭がすぐ隣にあるし、その向こうには彫刻だらけの美術館の庭みたいになっている。
キャットは呆れたように言う。
「統一性がなくてみっともないですよ。考えたことを全部実行するのはやめてください」
「だって作りたいんだもの」
キャットはあくまで冷ややかだが、先代は楽しそうだ。笑い声が行ったり来たりして、庭をあちこち歩き回っているのがわかる。
「ゴンドラも作ったの。空から見られるように」
「また突拍子もない」
「さ、行きましょ。撫子さんも」
キャットがまた引っ張られる動きをする。キャットは不機嫌そうに眉をひそめた。
目の前に白いスクリーンが現れて中に入ると、また場面が変わる。
先代が撫子とキャットに見せてくれたのは、ゴンドラだったり厨房だったり倉庫だったりした。
「先代は発明家だったのですか?」
エレベーターもない頃の日本人とは思えない新しさが溢れていたので、撫子は不思議になった。
「そうなりたかったの。私は二十歳前に死んだから、あっちの世界を思い出しながら勉強して考えたの」
「すごいですね。一人でよくここまで」
「一人じゃないわ。死出の世界で勧誘した従業員の皆がいるし」
キャットが何かを振り払うような仕草をする。
「ちょっと。頭撫でないでください」
「次期オーナーの教育もやりがいがあるしね」
最初は抵抗していたが、やがてキャットは諦めて頭を撫でられるままになっていた。微笑ましくなって撫子は目を細める。
「暗記しなくていいんですか、撫子。僕はその程度ひとめで覚えられましたよ」
「あなたのような神童と一緒にしないで頂きたいです」
とはいえ自分の能力の低さを悔やんでも仕方がない。
撫子はキャットが貸してくれたメモを見ながら、委任状の書きとりを再開する。
何度書いても意味がわからない。書いた直後から混乱する。
だけどこれができないとホテルを取り返せない。そう思うと、ひたすら手を動かすしかなかった。
「大体こんなことをしなくても、未来の僕は自分でホテルを取り返しますよ」
「まあきっとそうですけど、そうなんですけど」
撫子はちゃんとした理屈が思い浮かばないながらも、目を白黒させて言う。
「ホテルに土足で上がり込んだ女将に、何とか仕返しをしたいのかも……いや、それはオーナーの思いじゃなくて私の個人的なものですけど、きっとオーナーだってそう思ってくれるはず。はは、わからなくなってきました」
難しすぎて説明する言葉が尻すぼみになる。
頬をかいて黙った撫子を見て、キャットは一言つぶやく。
「お馬鹿」
顔を上げた撫子の目に映ったのは、いつか見たような優しい眼差しだった。
キャットは同情でももちろん軽蔑でもなく、不思議な温かみを持って撫子に笑いかける。
「ほら、いいですか」
思わず手を止めた撫子の手にキャットは自分の手を重ねて、ゆっくりと動かし始める。
「我、宿主に、異を、唱えし、者」
言い聞かせるように文言を区切りながら、キャットは撫子の手と共に委任状の文句を記す。
「ここに、宿主を、代理する、ことを、宣言、する。撫子。……もう一度」
キャットの動きに合わせて手を動かすと、自然と言葉が手に染みついていくような気がした。
撫子の手を取って、キャットは繰り返し委任状の文句を書き記す。
「字が下手でも読みづらくても、異を唱える意思がお上に伝わればいいんです」
「はい」
「もう一度、最初から」
いつしか撫子は、キャットが手を離していることに気付いていた。
「ホテルは建てた者の意思を受け継いでいますから。その意思を形にすれば、ホテルが力を貸してくれます」
次第に薄れていく意識の中、キャットが言う。
「オーナーの意思を忘れないでください」
見えなくなっていく紙を目に焼き付けるようにして、撫子は手を動かし続けた。