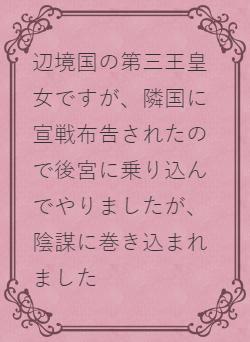昔から雪鈴には、石の声が聞こえていた。
けれど信じてくれたのは、病床にあった祖母だけ。
祖母の話では、雪鈴の白い髪と紅い目の色。そして石の声を聞く力は、曾祖母譲りのものだと教えられた。
雪鈴の産まれた北の地域では昔から石の神が信じられており、その神託を受ける巫女は白髪紅瞳で生まれてくるのだという。
だが最近では信仰する者は減り、巫女の伝承すら忘れられてしまった。
雪鈴の家族も神や巫女の話など信じておらず、まして石の声が聞こえるなどと真顔で言う娘を気味悪がった。
亡くなる際に祖母は「余計な事は言わない方がよい」と処世術を教えてくれたので、後宮に来てからこの不思議な力の事は、誰にも話さずにいたのである。
しかし次期皇后となる姫君が偽物を身につけている方が恥だと思った雪鈴は、美麗の髪で輝く青い宝石を指さして進言した。
すぐに信じてもらえると思わなかったが、仮にも美麗は正妃候補である。宝物庫の役人を呼んで鑑定されると思いきや、突如大声で怒鳴りしたのだ。
当然取り巻き達も美麗に習い、「無礼だ」とか「非常識な女だ」と口々に罵る。
気が付いたときには雪鈴は「嘘をつき、簪を奪おうとした大罪人」にされていて、更には官長が呼ばれ、雪鈴はその日のうちに寵姫の住まいから立ち退くよう命じられたのである。
まだ正式には決まっていないが、雪鈴は寵姫候補から外されたも同じだった。
「後宮でやっていける自信なかったし。まあいいか」
一族は落胆するだろうけど、二度と会うこともない人達だから特に気
にしてない。
なにより楽しい思い出なんてなかったから、後宮に送られるのだと知ったときには内心ほっとしたほどだ。
「あの、雪鈴様。正式な沙汰がくだったら……私もお供してよろしいですか?」
「京が良ければ、かまわないわよ。でも私といたら、ろくなことにならないけどいいの?」
「商家の出の私を庇ってくださったご恩は、一生忘れませんよ。どうかこれからも、御側で恩返しさせてください」
雪鈴より年下の京は、女官見習いとして後宮に入った娘だ。
学舎での成績が良かったので特別に推挙されたと聞いている。だが女官は貴族の家系が殆どだ。
そんな後ろ盾のない京は格好のいじめの対象となった。
理不尽な扱いを受けていたところに偶々雪鈴が通りかかり、正式な側仕えの女官として召し上げたという経緯がある。
「正妃候補の美麗様に無礼を働いた罪、って女官長は言ってたけど。どんな罰がくだるか京は知ってる?」
「後宮の刑法では、余り例がないのですが……まだ正妃も決まってませんし、皇帝のお渡りもない以上、後宮の女子は全員清い身。となると、高位の貴族に下げ渡される可能性が高いですね」
「下げ渡される……」
呟く雪鈴が己が未来を悲観したと勘違いした京が、慌てて付け加えた。
「あ、でも雪鈴様の場合は、正妻として望まれて後宮を出る事になると思いますよ。寵姫候補の中でも、上位でしたし。何より雪鈴様はお美しいから、引く手あまたですよ」
「ああ、うん。でも別に、愛人とかでいいんだけとね。その方が気楽だし」
正直なところ、顔も知らない皇帝の寵姫になるのも、見知らぬ貴族に下げ渡されるのも体して変わらないと思う。
「食事と寝床がもらえて、時々散歩に出られる自由があれば十分よ」
「欲がなさ過ぎますよ」
過酷な故郷の生活に比べれば、都に来られただけでも有り難い。貴族であっても北国の冬は凍えるし、食事だって作物の育ちが悪ければ飢えるのだ。
特に家族の中で孤立していた雪鈴は、ほぼ民と同様の生活をしていたので、この隙間風の吹き込む部屋だって十分すぎる屋敷なのである。
(期待はせず、静かに暮らそう。ね、白露)
雪鈴は帯の間から透明な宝玉を取り出す。水晶のように透明だが、水晶とはまた違う石なのだと祖母は教えてくれた。