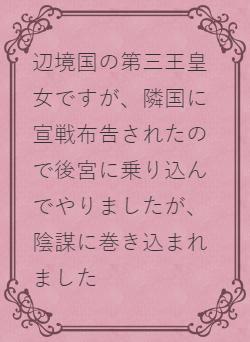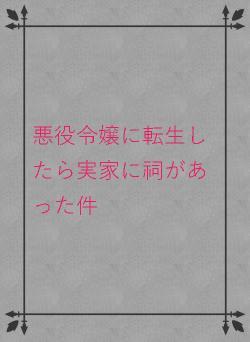メニュー
この作家の他の作品
表紙を見る
中華風のファンタジーです。辺境国に産まれた美蘭(みらん)は、国を守る為に大国の後宮に潜入しますが次期皇帝の月冥(げつめい)に見つかってしまい絶体絶命?
命を賭して故国を守ろうと奮闘する美蘭は、運命を切り開いていきます。
表紙を見る
元ネタ知りません。「祠」「破壊」の文字が気になったので、勢いで書きました。
「祠」「ホコラ」などは使い分けなので誤字ではありません。
表紙を見る
高位貴族である湖家の娘、春鈴はとある事情で後宮の厨で下女として働いていた。春鈴は「鳳凰憑き」と呼ばれる特別な能力を持っている。ある日の夜、ふらりと現れた学生と思われる青年・青嵐の「愚痴聞き」をしたのだが、彼は「自分は皇帝だ」などと言い出して……。
「1話だけ大賞」エントリー作品
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…
濡れ衣を着せられて後宮の端に追いやられた底辺姫。異能も容姿も気味悪がられてますが、これ巫女の証なんです
を読み込んでいます