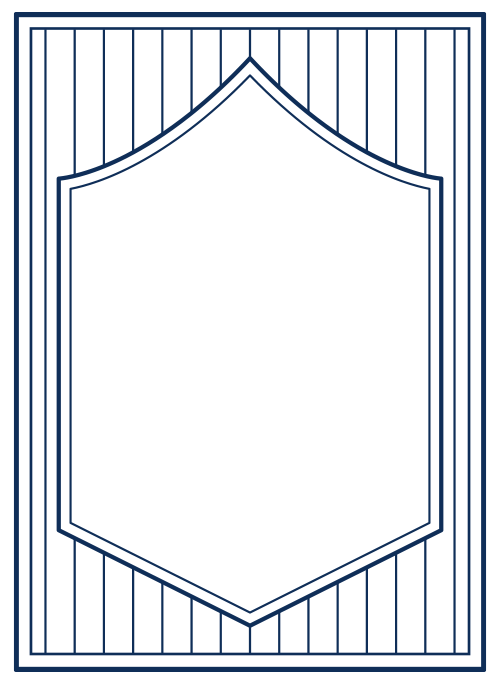「いや、俺は。……勘弁してくれ」
幻夜がまた、痛みをこらえるような顔をして目を逸らす。その表情を見て、沙和ははたと思い至った。さっき、外の石畳を歩いたときに見たのとおなじだ。
「それは、わたしに触れられないから……? さっきも、ひょっとして転んだわたしを助けようとしてくださいましたか?」
「辰野に聞いたのか。怯えさせるから黙ってろと言ったのに……」
幻夜が軽く舌打ちした。やっぱりそうだったのかと腑に落ち、沙和は慌てて手をひらひら振る。
「怖くないですよ、わたし。助けようとしてくださったのも嬉しいです」
「けっきょくなにもできなかった。嬉しがるな」
「幻夜さまのお気持ちが嬉しいんです。ありがとうございます」
「……そうか」
幻夜は一瞬、顔を逸らした。けれど、その耳がほんのり赤いと沙和が思ったときにはもう、平静な顔に戻っていた。
「で、わかってるならかんざしは辰野につけてもらえ」
沙和は少し考え、かぶりを振った。
「幻夜さまにつけてほしいです。……お嫌でなければ。お願いします、髪だけなら触れられるかもしれませんし」
「くだらないことを考えてないで、もう遅いから寝ろ」
「やってみるだけですから」
重ねて頼みこむと、幻夜が深々とため息をついた。
「……わかった。気味悪がっても知らないからな。そこに座れ」
沙和は幻夜に言われたとおり、居間のソファに腰掛ける。
幻夜がうしろに回る気配が感じられた。足音だってする。触れられないだなんて信じられない。
かんざしの先が髪にそっと挿し入れられた。
「やはり……沙和の髪には触れられんな」
幻夜はそれきり手を止める。沙和は明るく続けた。
「ではわたしが挿しますから、幻夜さまも手伝ってくださいませんか?」
「おいっ、沙和。しようのないことをするな」
沙和は、離れていこうとするかんざしを髪に押しつけた。幻夜が声を荒げる。
沙和からは見えないし、感じられることもないけれど、沙和の手は幻夜の手に重なって――というより、幻夜の手を突き抜けているのかもしれない。
沙和はしばらくそうしてからそっと手を離す。けれど、先端を挿しただけのかんざしは落ちなかった。
幻夜が押さえてくれているのだ。
「力加減は大丈夫か? 頭に突き刺さってないだろうな?」
かんざしには触れられても、沙和の頭に触れられないからだろう。幻夜が心なしか不安げにする。
「ちょうどいい感じです。えっと、ここからどうしたらいいですか?」
「……こうだ、耳の髪をとって——」
かんざしを押さえたまま、耳元で幻夜が指示していく。今になって、近すぎる距離にいたたまれなくなる。
そんな沙和とは裏腹に、幻夜は平然とした口調で沙和の手を誘導する。
おかげで今度は、耳の上に作った小さなお団子にかんざしを挿すことができた。
「できました……! 幻夜さま、できましたよ!」
「言わなくても見えてる」
「幻夜さまが挿してくださったんですよ!」
「俺が?」
「ええ、ありがとうございます! どうですか?」
沙和は声を弾ませてうしろをふり向く。
至近距離で幻夜と目が合ったとたん、幻夜がぱっと顔を逸らした。
「……近い」
「あっ、すみません」
沙和は前に向き直った。幻夜は、近すぎるのを好まないのかもしれない。だったら、さっきも不快だったのではないか、と沙和は気を引きしめた。
「よく似合ってる。こんな俺でも、少しはできることがあるらしい」
「幻夜さまは、わたしにたくさんのことをしてくださってます。少し、だなんて謙遜ですよ」
沙和は髪型が崩れないよう、かんざしにそっと手をやる。
もうそこには幻夜の手はないだろうけれど、心なしかぬくもりが残っている気がする。
「このまま、外したくないです」
「そうか」
幻夜が耳をほんのり赤くする。
沙和の心まで、あたたかく灯った気がした。
幻夜がまた、痛みをこらえるような顔をして目を逸らす。その表情を見て、沙和ははたと思い至った。さっき、外の石畳を歩いたときに見たのとおなじだ。
「それは、わたしに触れられないから……? さっきも、ひょっとして転んだわたしを助けようとしてくださいましたか?」
「辰野に聞いたのか。怯えさせるから黙ってろと言ったのに……」
幻夜が軽く舌打ちした。やっぱりそうだったのかと腑に落ち、沙和は慌てて手をひらひら振る。
「怖くないですよ、わたし。助けようとしてくださったのも嬉しいです」
「けっきょくなにもできなかった。嬉しがるな」
「幻夜さまのお気持ちが嬉しいんです。ありがとうございます」
「……そうか」
幻夜は一瞬、顔を逸らした。けれど、その耳がほんのり赤いと沙和が思ったときにはもう、平静な顔に戻っていた。
「で、わかってるならかんざしは辰野につけてもらえ」
沙和は少し考え、かぶりを振った。
「幻夜さまにつけてほしいです。……お嫌でなければ。お願いします、髪だけなら触れられるかもしれませんし」
「くだらないことを考えてないで、もう遅いから寝ろ」
「やってみるだけですから」
重ねて頼みこむと、幻夜が深々とため息をついた。
「……わかった。気味悪がっても知らないからな。そこに座れ」
沙和は幻夜に言われたとおり、居間のソファに腰掛ける。
幻夜がうしろに回る気配が感じられた。足音だってする。触れられないだなんて信じられない。
かんざしの先が髪にそっと挿し入れられた。
「やはり……沙和の髪には触れられんな」
幻夜はそれきり手を止める。沙和は明るく続けた。
「ではわたしが挿しますから、幻夜さまも手伝ってくださいませんか?」
「おいっ、沙和。しようのないことをするな」
沙和は、離れていこうとするかんざしを髪に押しつけた。幻夜が声を荒げる。
沙和からは見えないし、感じられることもないけれど、沙和の手は幻夜の手に重なって――というより、幻夜の手を突き抜けているのかもしれない。
沙和はしばらくそうしてからそっと手を離す。けれど、先端を挿しただけのかんざしは落ちなかった。
幻夜が押さえてくれているのだ。
「力加減は大丈夫か? 頭に突き刺さってないだろうな?」
かんざしには触れられても、沙和の頭に触れられないからだろう。幻夜が心なしか不安げにする。
「ちょうどいい感じです。えっと、ここからどうしたらいいですか?」
「……こうだ、耳の髪をとって——」
かんざしを押さえたまま、耳元で幻夜が指示していく。今になって、近すぎる距離にいたたまれなくなる。
そんな沙和とは裏腹に、幻夜は平然とした口調で沙和の手を誘導する。
おかげで今度は、耳の上に作った小さなお団子にかんざしを挿すことができた。
「できました……! 幻夜さま、できましたよ!」
「言わなくても見えてる」
「幻夜さまが挿してくださったんですよ!」
「俺が?」
「ええ、ありがとうございます! どうですか?」
沙和は声を弾ませてうしろをふり向く。
至近距離で幻夜と目が合ったとたん、幻夜がぱっと顔を逸らした。
「……近い」
「あっ、すみません」
沙和は前に向き直った。幻夜は、近すぎるのを好まないのかもしれない。だったら、さっきも不快だったのではないか、と沙和は気を引きしめた。
「よく似合ってる。こんな俺でも、少しはできることがあるらしい」
「幻夜さまは、わたしにたくさんのことをしてくださってます。少し、だなんて謙遜ですよ」
沙和は髪型が崩れないよう、かんざしにそっと手をやる。
もうそこには幻夜の手はないだろうけれど、心なしかぬくもりが残っている気がする。
「このまま、外したくないです」
「そうか」
幻夜が耳をほんのり赤くする。
沙和の心まで、あたたかく灯った気がした。