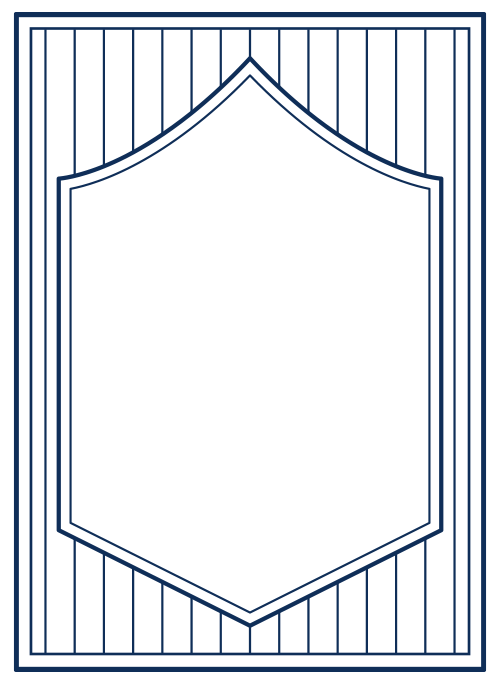「これくらい、大丈夫です。村でもときどき転んでいましたから。あの、幻夜さま……?」
「……悪い」
幻夜のほうが、なぜか痛みを覚えたみたいに眉を寄せている。その拳はきつく握りこまれており、沙和は首をかしげた。
「なにかありましたか? ……そうだ、お腹空いてらっしゃいませんか? 夕食、あたためますね」
行きましょう、と沙和が言えば幻夜も歩みを再開する。暗くかげった表情が気になり、沙和は意識して声を明るくした。
「辰野さんが、今夜はオムライスというものを作ってくれました。オムライスってふしぎな見た目ですね。ご飯と卵が反乱を起こしてるみたいで」
「……それは、失敗作だな」
「そうなんですか? でも楽しかったです。わたしもいつか、作れるようになりたい」
辰野とふたり、これが西洋の食事らしいとおっかなびっくりスプーンなるものを使った。辰野は家の主人と女中が一緒に食事だなんてとんでもないと言い張ったけれど、沙和だって主人というわけでもない。むしろ女中に近いほうだから、と無理やり一緒に座卓を囲んだ。
西洋の味は、正直なところ沙和にはよくわからなかったけれど、首をかしげながらもひとと食べる食事は楽しかった。
「辰野だけは見本にするなよ」
幻夜が顔をしかめて釘を刺す。理由はわからなかったけれど、声の調子はいつもの幻夜だったからそれだけでほっとした。
離れに運ぶ労を気遣ってくれたらしく、幻夜は食事を主屋で取ると言う。沙和は幻夜とともに主屋に寄った。幻夜は、顔を能面のようにして「ご飯と卵が反乱中」のオムライスを食べる。その顔がなんだか可笑しくて、沙和はお茶をのみながらずっと幻夜を見ていた。
夕食後、離れに下がると、幻夜が髪に差していたかんざしを抜いて沙和に渡した。白銀の髪がさらりとシャツに落ちる。
「その着物に似合うだろう。これをやる。手を出せ」
反射的に手を出すと、繊細なガラス細工のついた黒漆のかんざしを手に乗せられる。沙和は焦った。
「でも、これは幻夜さまので」
「いずれ沙和にぴったりなものを買ってやる。それまでの間に合わせだ」
「いえ! わたしは新しいものを買っていただくより、これがいいです。いただいてよいのですか?」
「いいから渡してるんだが?」
「大事にします! 素敵な贈り物をありがとうございます……!」
「贈り物ってほどじゃないがな。つけてみてくれ」
「はいっ」
ところが、髪の長さが足りないのと、これまで髪飾りなど与えられたことがなかったので扱いかたがわからないのとで、うまく挿せずに落ちてしまう。
焦って何度も挑戦するが結果はおなじで、沙和はうなだれた。
「すみません……」
「なんで沙和が謝るんだ。辰野を起こしてつけさせるか」
「でももう夜も遅いですし……」
声がしおれかけたが、沙和はふと思いついて幻夜のシャツを引っ張った。
「幻夜さまがつけてくださるわけには、いきませんか?」
「……悪い」
幻夜のほうが、なぜか痛みを覚えたみたいに眉を寄せている。その拳はきつく握りこまれており、沙和は首をかしげた。
「なにかありましたか? ……そうだ、お腹空いてらっしゃいませんか? 夕食、あたためますね」
行きましょう、と沙和が言えば幻夜も歩みを再開する。暗くかげった表情が気になり、沙和は意識して声を明るくした。
「辰野さんが、今夜はオムライスというものを作ってくれました。オムライスってふしぎな見た目ですね。ご飯と卵が反乱を起こしてるみたいで」
「……それは、失敗作だな」
「そうなんですか? でも楽しかったです。わたしもいつか、作れるようになりたい」
辰野とふたり、これが西洋の食事らしいとおっかなびっくりスプーンなるものを使った。辰野は家の主人と女中が一緒に食事だなんてとんでもないと言い張ったけれど、沙和だって主人というわけでもない。むしろ女中に近いほうだから、と無理やり一緒に座卓を囲んだ。
西洋の味は、正直なところ沙和にはよくわからなかったけれど、首をかしげながらもひとと食べる食事は楽しかった。
「辰野だけは見本にするなよ」
幻夜が顔をしかめて釘を刺す。理由はわからなかったけれど、声の調子はいつもの幻夜だったからそれだけでほっとした。
離れに運ぶ労を気遣ってくれたらしく、幻夜は食事を主屋で取ると言う。沙和は幻夜とともに主屋に寄った。幻夜は、顔を能面のようにして「ご飯と卵が反乱中」のオムライスを食べる。その顔がなんだか可笑しくて、沙和はお茶をのみながらずっと幻夜を見ていた。
夕食後、離れに下がると、幻夜が髪に差していたかんざしを抜いて沙和に渡した。白銀の髪がさらりとシャツに落ちる。
「その着物に似合うだろう。これをやる。手を出せ」
反射的に手を出すと、繊細なガラス細工のついた黒漆のかんざしを手に乗せられる。沙和は焦った。
「でも、これは幻夜さまので」
「いずれ沙和にぴったりなものを買ってやる。それまでの間に合わせだ」
「いえ! わたしは新しいものを買っていただくより、これがいいです。いただいてよいのですか?」
「いいから渡してるんだが?」
「大事にします! 素敵な贈り物をありがとうございます……!」
「贈り物ってほどじゃないがな。つけてみてくれ」
「はいっ」
ところが、髪の長さが足りないのと、これまで髪飾りなど与えられたことがなかったので扱いかたがわからないのとで、うまく挿せずに落ちてしまう。
焦って何度も挑戦するが結果はおなじで、沙和はうなだれた。
「すみません……」
「なんで沙和が謝るんだ。辰野を起こしてつけさせるか」
「でももう夜も遅いですし……」
声がしおれかけたが、沙和はふと思いついて幻夜のシャツを引っ張った。
「幻夜さまがつけてくださるわけには、いきませんか?」