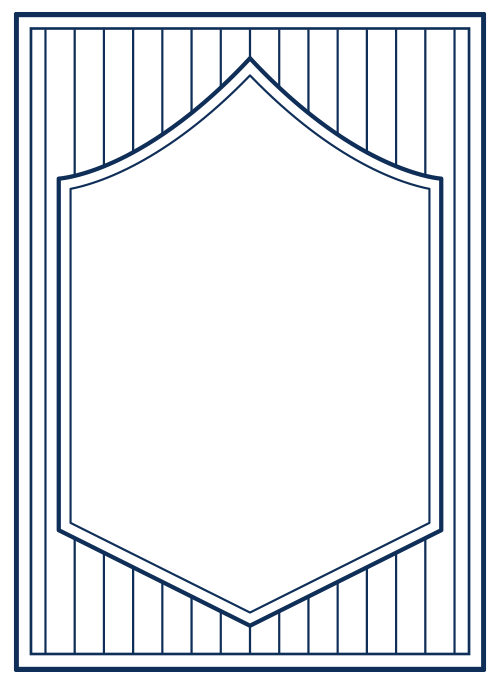「なあ、鎮守の神も村人も、身内もおまえを見捨てたんだろ。おまえも捨ててしまえ」
「捨てる……」
困惑して眉を下げると、青年が突然がしがしと首の裏をかいた。
「悪い。物言いががさつだとよく注意されるんだが、直らん。癖だと思え」
ばつが悪そうに頭を下げられ、沙和は慌てて首を横に振った。
たしかに粗野だとは思ったけれど、青年の言い方はちっとも不快じゃない。図星をつかれたから困惑しただけだ。
「なあ、名前はなんていうんだ?」
「沙和といいます」
「俺は幻夜だ。沙和、村を捨てて俺のところに来ればいい」
「それってやっぱり……死ねという意味でしょうか?」
「あのなあ!」
声を荒げた幻夜に、沙和は肩をすくめる。幻夜はふたたび首の裏をかき、落ち着こうとしてか深々と息を吐いた。
「片足を冥府に突っこんじゃあいるが、俺は生きた人間だ。帝都に家もある。これまでよりも、よい暮らしを保証してやる。沙和を死なせたり見捨てたりすることもない。約束する」
「でも、どうしてわたしを拾ってくださるのですか?」
「沙和を助けてやりたい。それが理由じゃおかしいか」
「いえ、でも」
沙和は艶のない乾いた髪をつまんだ。先週、叔母に切られたので、肩先ほどの長さしかない。
頬にも触れてみたが、髪とおなじでカサついている。手足を見れば、棒のようだ。
初対面の相手に気に入られる要素なんてどこにもない。
沙和は首をひねったけれど、幻夜はそれ以上は説明が面倒だとばかり「そういうわけだから」とぞんざいに締めくくった。
「この世でいちばん大切にしてやる。沙和は、村で疎まれながら巫女のままでいるか、俺に大切にされて幸せに生きるか。どちらにするか決めろ」
「わたしが決めて……いいのですか?」
「なんだその妙な顔は。当然だろ」
「ちょっと……驚いてしまいました」
誰かに沙和自身の意思を聞かれるなんて、初めてだったのだ。
沙和は胸がとくりと鳴るのを感じた。
冥府の番人だと名乗る、この世ならざるほどの美青年。怪しむ要素は満載といっていいはずなのに、沙和はこの短時間で幻夜のことを信じ始めていた。
きっと、幻夜の目に嘘がなかったから。
「俺を選べよ、沙和。後悔はさせない」
答えは、頭で考えるより先にするりと口をついた。
「では……よろしくお願いします」
「ああ」
冥府に向かう最後の死者の姿が川から見えなくなるのを待って、幻夜が背を向ける。沙和も幻夜についていく。
きっと、この選択は正しいという予感がする。
沙和は生まれて初めて、胸が高鳴るのを自覚した。
「捨てる……」
困惑して眉を下げると、青年が突然がしがしと首の裏をかいた。
「悪い。物言いががさつだとよく注意されるんだが、直らん。癖だと思え」
ばつが悪そうに頭を下げられ、沙和は慌てて首を横に振った。
たしかに粗野だとは思ったけれど、青年の言い方はちっとも不快じゃない。図星をつかれたから困惑しただけだ。
「なあ、名前はなんていうんだ?」
「沙和といいます」
「俺は幻夜だ。沙和、村を捨てて俺のところに来ればいい」
「それってやっぱり……死ねという意味でしょうか?」
「あのなあ!」
声を荒げた幻夜に、沙和は肩をすくめる。幻夜はふたたび首の裏をかき、落ち着こうとしてか深々と息を吐いた。
「片足を冥府に突っこんじゃあいるが、俺は生きた人間だ。帝都に家もある。これまでよりも、よい暮らしを保証してやる。沙和を死なせたり見捨てたりすることもない。約束する」
「でも、どうしてわたしを拾ってくださるのですか?」
「沙和を助けてやりたい。それが理由じゃおかしいか」
「いえ、でも」
沙和は艶のない乾いた髪をつまんだ。先週、叔母に切られたので、肩先ほどの長さしかない。
頬にも触れてみたが、髪とおなじでカサついている。手足を見れば、棒のようだ。
初対面の相手に気に入られる要素なんてどこにもない。
沙和は首をひねったけれど、幻夜はそれ以上は説明が面倒だとばかり「そういうわけだから」とぞんざいに締めくくった。
「この世でいちばん大切にしてやる。沙和は、村で疎まれながら巫女のままでいるか、俺に大切にされて幸せに生きるか。どちらにするか決めろ」
「わたしが決めて……いいのですか?」
「なんだその妙な顔は。当然だろ」
「ちょっと……驚いてしまいました」
誰かに沙和自身の意思を聞かれるなんて、初めてだったのだ。
沙和は胸がとくりと鳴るのを感じた。
冥府の番人だと名乗る、この世ならざるほどの美青年。怪しむ要素は満載といっていいはずなのに、沙和はこの短時間で幻夜のことを信じ始めていた。
きっと、幻夜の目に嘘がなかったから。
「俺を選べよ、沙和。後悔はさせない」
答えは、頭で考えるより先にするりと口をついた。
「では……よろしくお願いします」
「ああ」
冥府に向かう最後の死者の姿が川から見えなくなるのを待って、幻夜が背を向ける。沙和も幻夜についていく。
きっと、この選択は正しいという予感がする。
沙和は生まれて初めて、胸が高鳴るのを自覚した。