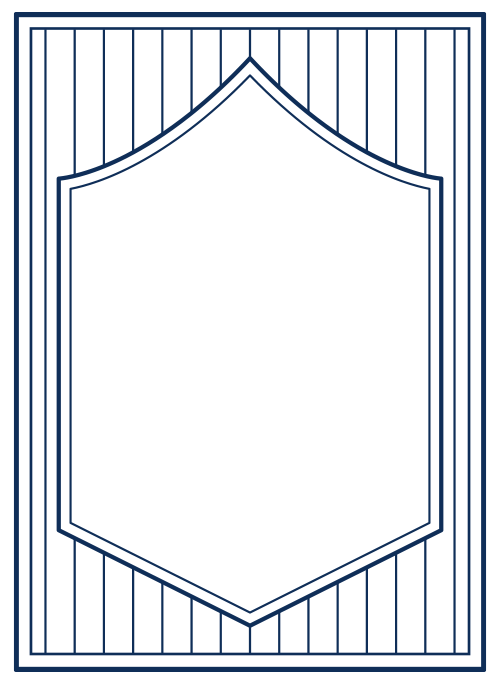*
気づいたときには、幻夜の意識は体から離れてさまよっていた。
下を向くと、自分の体がぴくりとも動かずに横たわっている。目はぴたりと閉じられ、唇には血の気がない。詰襟の服は、袖口が擦れて糸がほつれている。
鏡越しでもないのに、自分で自分の顔が見えている。
意味がわからない。
『なんだよこれ! なんだよ、俺どうなってんだ!?』
『——お前は死ぬんだよ』
どこからともなく声が響き、幻夜は見下ろしていた自分の体から目を離して、周囲を見回した。
どこかの川原だった。
水の流れは細く急で、両側を挟む山あいを縫うように流れている。川原には水の流れによって運ばれてきたのだろう、角の取れた石がごろごろと転がっている。
しかし、人気はない。
『あんたは誰だ? どこにいる』
『核がないのに、生きがいいね』
『いいから答えろ』
『死ねば嫌でもわかるよ。って、どうせもうすぐだし教えてあげよう。ここは冥府に続く道だよ』
人を食った笑いが響いた。男とも女とも判別のつかない、中性的な声だった。
『冥府? なぜ俺は死ぬ? 核ってなんだ?』
『ああもう、うるさいね。お前はとある神に、魂の核を取られたんだよ。そして核がないからここにいる』
『なぜそんなことになった? 魂の核と魂は違うのか?』
『いちいち私に説明させようとしないで、思い出してごらんよ……って、核がないから無理か』
そう言いながらも、その何者かは幻夜の現状については教える気があるらしかった。
核とは、魂の中心にある芯のようなものらしい。その人間を形成する大元となる部分。
『核だけが取られるのは、異例中の異例だね。たいていの人間は、魂そのものが弱って死ぬわけだから』
『あんたがやったのか?』
『まさか。そんな低俗な遊び、神しかやらないよ』
頭の中で誰か皮肉っぽく笑う。雰囲気からすると、声の主は冥府の何者かではないか。
『さあて、いくら生きがよくともそろそろ限界だろう。おいで』
『嫌だね、俺はまだ死にたくない。あんたの言いぶりからすると、核とやらが取られただけでは死なないのだろう? 核を返してもらう。どこにある?』
『さあね。興味がない』
『ならどうすりゃいいんだよ!?』
『ふむ、そうだね。では私とひとつ契約をしよう。お前が核を取り戻すまで、冥府の番人として働くのはどう? そのあいだ、私はお前が死ぬのは見逃してやる』
『冥府の番人? 死ぬのとおなじじゃないか』
『いいや、違うよ。人間として生きればいい。ただし少々制約はつくけれどね』
『……俺が核を取り戻せば、普通の人間に戻れるんだな?』
『そのときこそ死ぬんじゃないかな』
『話が違う!』
幻夜が声を荒げると、声の主がすっと冷気をまとわせた。
『わかってないようだから、言ってあげよう。お前は核が取られただけでは死なないと思っているようだけれど、普通に死ぬよ? 勘違いだよ? 普通と異なるのは、死ぬまでに少しばかり冥府への道で迷うくらい。だから私が迎えにきてやったんだ』
迎えにきたと言うわりに、声の主の姿は見えない。
『私が死ぬのを見逃すとはつまり、お前は終わりなき生を生きるということだよ。核を取り戻さない限り、お前は死ねない』
『卑劣だろうが……!』
終わりなき生を、と言うからには、神から核を取り戻すのはほぼ不可能なのかもしれない。
幻夜としても、ただの人間である自分が神と渡り合える自信はない。
そもそも、なぜ神が一介の人間の魂の一部を取ったのかも不明だが。
『なら、このまま死ぬ? どっちでもいいよ』
気づいたときには、幻夜の意識は体から離れてさまよっていた。
下を向くと、自分の体がぴくりとも動かずに横たわっている。目はぴたりと閉じられ、唇には血の気がない。詰襟の服は、袖口が擦れて糸がほつれている。
鏡越しでもないのに、自分で自分の顔が見えている。
意味がわからない。
『なんだよこれ! なんだよ、俺どうなってんだ!?』
『——お前は死ぬんだよ』
どこからともなく声が響き、幻夜は見下ろしていた自分の体から目を離して、周囲を見回した。
どこかの川原だった。
水の流れは細く急で、両側を挟む山あいを縫うように流れている。川原には水の流れによって運ばれてきたのだろう、角の取れた石がごろごろと転がっている。
しかし、人気はない。
『あんたは誰だ? どこにいる』
『核がないのに、生きがいいね』
『いいから答えろ』
『死ねば嫌でもわかるよ。って、どうせもうすぐだし教えてあげよう。ここは冥府に続く道だよ』
人を食った笑いが響いた。男とも女とも判別のつかない、中性的な声だった。
『冥府? なぜ俺は死ぬ? 核ってなんだ?』
『ああもう、うるさいね。お前はとある神に、魂の核を取られたんだよ。そして核がないからここにいる』
『なぜそんなことになった? 魂の核と魂は違うのか?』
『いちいち私に説明させようとしないで、思い出してごらんよ……って、核がないから無理か』
そう言いながらも、その何者かは幻夜の現状については教える気があるらしかった。
核とは、魂の中心にある芯のようなものらしい。その人間を形成する大元となる部分。
『核だけが取られるのは、異例中の異例だね。たいていの人間は、魂そのものが弱って死ぬわけだから』
『あんたがやったのか?』
『まさか。そんな低俗な遊び、神しかやらないよ』
頭の中で誰か皮肉っぽく笑う。雰囲気からすると、声の主は冥府の何者かではないか。
『さあて、いくら生きがよくともそろそろ限界だろう。おいで』
『嫌だね、俺はまだ死にたくない。あんたの言いぶりからすると、核とやらが取られただけでは死なないのだろう? 核を返してもらう。どこにある?』
『さあね。興味がない』
『ならどうすりゃいいんだよ!?』
『ふむ、そうだね。では私とひとつ契約をしよう。お前が核を取り戻すまで、冥府の番人として働くのはどう? そのあいだ、私はお前が死ぬのは見逃してやる』
『冥府の番人? 死ぬのとおなじじゃないか』
『いいや、違うよ。人間として生きればいい。ただし少々制約はつくけれどね』
『……俺が核を取り戻せば、普通の人間に戻れるんだな?』
『そのときこそ死ぬんじゃないかな』
『話が違う!』
幻夜が声を荒げると、声の主がすっと冷気をまとわせた。
『わかってないようだから、言ってあげよう。お前は核が取られただけでは死なないと思っているようだけれど、普通に死ぬよ? 勘違いだよ? 普通と異なるのは、死ぬまでに少しばかり冥府への道で迷うくらい。だから私が迎えにきてやったんだ』
迎えにきたと言うわりに、声の主の姿は見えない。
『私が死ぬのを見逃すとはつまり、お前は終わりなき生を生きるということだよ。核を取り戻さない限り、お前は死ねない』
『卑劣だろうが……!』
終わりなき生を、と言うからには、神から核を取り戻すのはほぼ不可能なのかもしれない。
幻夜としても、ただの人間である自分が神と渡り合える自信はない。
そもそも、なぜ神が一介の人間の魂の一部を取ったのかも不明だが。
『なら、このまま死ぬ? どっちでもいいよ』