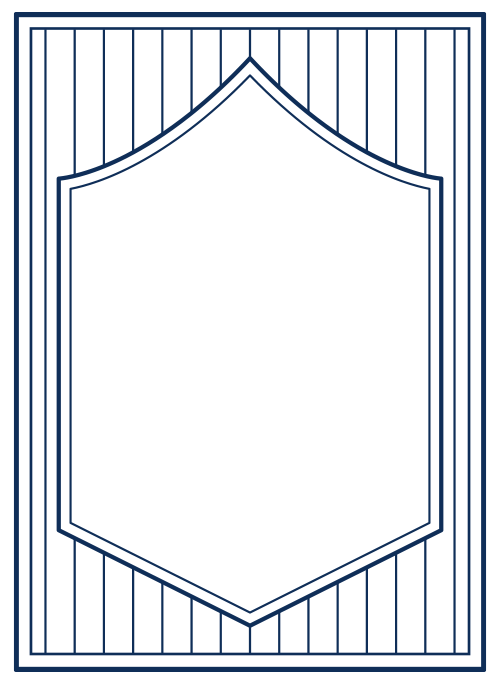「沙和の言うとおりだ。鎮守の神はお前たちに愛想を尽かして、霧谷を出ていった。だがな、お前たちが不作だと偽り、収穫をせしめている事実は筒抜けだ」
「ひぃ、な、なぜそんなことまで……!」
叔母の顔がみるみる青ざめる。どうやら、幻夜の言葉は真実らしかった。
「お前たちが誰を怒らせたのか、よくよくその身に刻んでおけ。あの村は鎮守の神ではなく、冥府の主が監視している」
「そんな! お、お許しを……!」
叔母は地面を這いつくばって進むと、幻夜の足首をつかもうとした。
ところが、その手はスーツを着た幻夜の足を素通りした。
「今後、沙和にはいっさい手を出すな。もし手を出したら、そのときはそこの娘共々、お前を冥府に送ってやる」
「ひぃ……っ!」
叔母の表情が凍りついたかと思うと、地面にひざをついた。
幻夜の冷え切った目を前に、叔母は這々のていで美綾を引っ張ると人力車を駆けさせて帰っていった。
「あらあら、旦那様も沙和様も、玄関先でどうされたんですか? お出かけですか?」
放心していた沙和をわれに返らせたのは、買い物から戻ってきた辰野だった。
「ああ、そうだな。俺も珍しく早く帰れたことだから、少し散歩でもしてくるか。……沙和」
「あっ、はい!」
歩きだした幻夜を沙和も追いかける。
夕暮れどきの空は、幻夜に拾われた日を思い出させる。大通りに出れば、ガス灯が点くところだった。
その中を、家路を急ぐ人々や人力車、馬車が砂埃を上げながら行き交う。沙和たちもそぞろ歩く。
「鎮守様の件、気づいてたんだな」
「もしかしてと思っただけです。幻夜さまも辰野さまも、わたしの意思を汲んでくださって……初めて、鎮守様が呼びかけに応じてくださらないのには、なにか理由があるのでは、と思って。でも幻夜さまはどうして?」
「ああ、鎮守様に成り代わって霧谷の社にいるあやかしから、俺に連絡があってな。村長の家のやつらが、収穫を独占しているのもそいつから聞いた」
「ええっ、あやかしが鎮守様の……ふりをしてたということですか?」
思いもよらなかった事実に目をみはると、幻夜がうなずいてふっと笑った。その手が、沙和の髪のかんざしを撫でる。
かんざし越しに頭を撫でられるのに似た感覚をわずかに覚え、沙和は幻夜の実体をたしかめられたように思った。
「ああ。沙和にもいつか会わせる。……沙和が無事でよかった」
「ありがとうございます。幻夜さまに、また救っていただきました」
沙和が立ち止まって頭を下げると、幻夜のほうが神妙な顔をした。
「救われたというなら、俺のほうだ。昔……瀕死になった俺を助けてくれたのは、沙和なんだ」
「わたしが……?」
幻夜は沙和を見つめ、目元をやわらかくゆるめた。
「沙和がまだ幼いころだ。覚えてないだろ。俺は沙和のおかげで、こっちに戻ってこられた。――俺は一度、ある神に魂の核を奪われたんだ」
「ひぃ、な、なぜそんなことまで……!」
叔母の顔がみるみる青ざめる。どうやら、幻夜の言葉は真実らしかった。
「お前たちが誰を怒らせたのか、よくよくその身に刻んでおけ。あの村は鎮守の神ではなく、冥府の主が監視している」
「そんな! お、お許しを……!」
叔母は地面を這いつくばって進むと、幻夜の足首をつかもうとした。
ところが、その手はスーツを着た幻夜の足を素通りした。
「今後、沙和にはいっさい手を出すな。もし手を出したら、そのときはそこの娘共々、お前を冥府に送ってやる」
「ひぃ……っ!」
叔母の表情が凍りついたかと思うと、地面にひざをついた。
幻夜の冷え切った目を前に、叔母は這々のていで美綾を引っ張ると人力車を駆けさせて帰っていった。
「あらあら、旦那様も沙和様も、玄関先でどうされたんですか? お出かけですか?」
放心していた沙和をわれに返らせたのは、買い物から戻ってきた辰野だった。
「ああ、そうだな。俺も珍しく早く帰れたことだから、少し散歩でもしてくるか。……沙和」
「あっ、はい!」
歩きだした幻夜を沙和も追いかける。
夕暮れどきの空は、幻夜に拾われた日を思い出させる。大通りに出れば、ガス灯が点くところだった。
その中を、家路を急ぐ人々や人力車、馬車が砂埃を上げながら行き交う。沙和たちもそぞろ歩く。
「鎮守様の件、気づいてたんだな」
「もしかしてと思っただけです。幻夜さまも辰野さまも、わたしの意思を汲んでくださって……初めて、鎮守様が呼びかけに応じてくださらないのには、なにか理由があるのでは、と思って。でも幻夜さまはどうして?」
「ああ、鎮守様に成り代わって霧谷の社にいるあやかしから、俺に連絡があってな。村長の家のやつらが、収穫を独占しているのもそいつから聞いた」
「ええっ、あやかしが鎮守様の……ふりをしてたということですか?」
思いもよらなかった事実に目をみはると、幻夜がうなずいてふっと笑った。その手が、沙和の髪のかんざしを撫でる。
かんざし越しに頭を撫でられるのに似た感覚をわずかに覚え、沙和は幻夜の実体をたしかめられたように思った。
「ああ。沙和にもいつか会わせる。……沙和が無事でよかった」
「ありがとうございます。幻夜さまに、また救っていただきました」
沙和が立ち止まって頭を下げると、幻夜のほうが神妙な顔をした。
「救われたというなら、俺のほうだ。昔……瀕死になった俺を助けてくれたのは、沙和なんだ」
「わたしが……?」
幻夜は沙和を見つめ、目元をやわらかくゆるめた。
「沙和がまだ幼いころだ。覚えてないだろ。俺は沙和のおかげで、こっちに戻ってこられた。――俺は一度、ある神に魂の核を奪われたんだ」