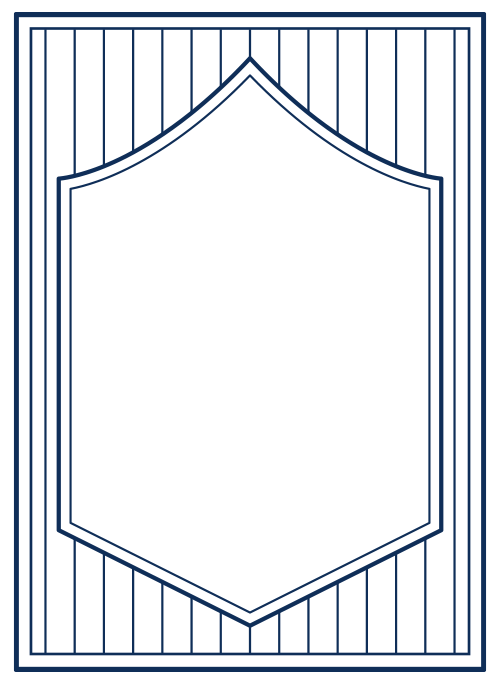祈祷を続けても沙和の体に鎮守の神は降りなかった。
長いあいだ、沙和はそれを自分の無能ゆえだと思ってきた。
だが祈祷の際に感じたのは、鎮守の神とはなにか別の気配だったのだ。
「なっ……! 言うに事欠いて、そんな嘘をついて言い逃れ? 性根がここまで腐ってるとはね!」
芯からの怒りに燃えた目で、叔母がふたたび沙和の腕をつかむ。沙和はたちまち、人力車の停まるほうへと引きずられた。
「離して! 痛っ、離してください!」
訴えても、ますますきつく腕をつかまれるだけ。沙和はとっさに美綾を見たけれど、返ってきたのはなんの感情もない視線だけだった。
叔母の手の爪が手首に食いこむ。沙和は振りほどくこともできずに身を縮めた。
ところが、そのときだった。
「ぎゃあぁっ……!」
叔母がやにわに呻き声を上げ、額を押さえて地面にうずくまった。
「お母様っ」
倒れた叔母に駆け寄った美綾が、おろおろと沙和を見やる。叔母の額からは血が筋を作って流れていた。そのそばには小石が転がっている。叔母の額に当たったのは、それらしかった。
沙和は呆然として、足音のしたほうへ目を向けた。
「幻夜さま!」
いつのまに帰ってきたのか、幻夜が沙和に向かって歩いてくるところだった。沙和は弾かれたように、幻夜に駆け寄った。
「間に合ったな。物に触れられれば、俺にもやれることはある。だろう?」
「はい……!」
幻夜がやわらかな笑みで、沙和に手を差し伸べる。
その手に伸ばした手が触れることはないものの、沙和は幻夜の隣に収まった。
肩の力がふっと抜けていく。
幻夜は沙和が隣に立つのをたしかめると、一転して表情を険しくした。
長いあいだ、沙和はそれを自分の無能ゆえだと思ってきた。
だが祈祷の際に感じたのは、鎮守の神とはなにか別の気配だったのだ。
「なっ……! 言うに事欠いて、そんな嘘をついて言い逃れ? 性根がここまで腐ってるとはね!」
芯からの怒りに燃えた目で、叔母がふたたび沙和の腕をつかむ。沙和はたちまち、人力車の停まるほうへと引きずられた。
「離して! 痛っ、離してください!」
訴えても、ますますきつく腕をつかまれるだけ。沙和はとっさに美綾を見たけれど、返ってきたのはなんの感情もない視線だけだった。
叔母の手の爪が手首に食いこむ。沙和は振りほどくこともできずに身を縮めた。
ところが、そのときだった。
「ぎゃあぁっ……!」
叔母がやにわに呻き声を上げ、額を押さえて地面にうずくまった。
「お母様っ」
倒れた叔母に駆け寄った美綾が、おろおろと沙和を見やる。叔母の額からは血が筋を作って流れていた。そのそばには小石が転がっている。叔母の額に当たったのは、それらしかった。
沙和は呆然として、足音のしたほうへ目を向けた。
「幻夜さま!」
いつのまに帰ってきたのか、幻夜が沙和に向かって歩いてくるところだった。沙和は弾かれたように、幻夜に駆け寄った。
「間に合ったな。物に触れられれば、俺にもやれることはある。だろう?」
「はい……!」
幻夜がやわらかな笑みで、沙和に手を差し伸べる。
その手に伸ばした手が触れることはないものの、沙和は幻夜の隣に収まった。
肩の力がふっと抜けていく。
幻夜は沙和が隣に立つのをたしかめると、一転して表情を険しくした。