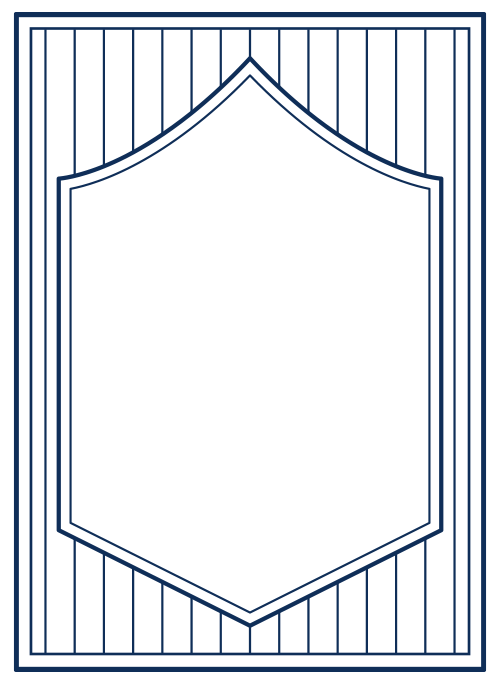叔母の視線は逃げるように沙和の顔から逸れたが、可憐な花が織られた品のある着物に向いたとたん鬼の形相になった。
「なによ、その高そうな着物! あんたにまったく似合わないわ! 下女のくせにそんなものを着せてもらって、どうやってこの家に取り入ったの? 相手は誰、言いなさい」
「それはお答え——」
できません、と言うより先に、頬に熱い痛みが走った。
覚えのある平手打ちの痛みに、沙和は顔をしかめる。
「私たちが育ててやった恩も忘れて、ずいぶん偉くなったようだね。言いなさい」
恩を持ちだされては逆らえるわけもない。沙和はおののきながら、幻夜の苗字を口にした。
「……高階、様が」
「高階? ってあの、華族様かい!? たしか当主はまだ若くて独身だったと華族年鑑にも載っていたっけね。……こりゃ、あたしにも運が向いたってことだね。美綾」
叔母は人力車に向かって声を張った。
「降りて、この家で待ってなさい。母は、沙和を」
沙和の腕が強くつかまれた。
「——村に戻してから、ここに戻るわ。お母様と一緒に、高階様にご挨拶しましょう。沙和が巫女に戻れば、万事うまく収まるわね。美綾にとっても、これ以上ない良縁ができたわ」
叔母はさもすでに決まったことのように言い、派手な赤の紅を引いた唇を上げた。
「行くわよ、沙和。元はといえば、お前がいなくなったせいで迷惑したんだから、当然これくらいはするわよね?」
つかまれた腕が引っ張られる。
けれど沙和はもう、村にいたころの沙和ではなかった。
沙和はその場に踏ん張り、叔母に反論した。
「それは叔母さまが、わたしを岩場から突き落としたからじゃないですか……!」
「おかしなことを言い出すのは、やめなさい! 義務を放棄するためにデタラメを言うなんて、許されないわよ」
車を降りた美綾に聞かせたくないからだろう、叔母は沙和よりも大きな声を張り上げる。
だけど沙和も、自分の意思を引っこめることはしなかった。
「叔母さまに突き落とされたわたしを、助けてくださったのは幻夜さまです。幻夜さまは『俺を選べ』とおっしゃってくださいました。だからわたしはもう、村には戻りません。叔母さまの言いなりにもなりません」
「お前を家に置いてやったというのに、美綾の幸せを邪魔する気? 村も、お前のせいで未だに不作続きだ。こんなことなら、お前なんか引き取るんじゃなかったよ」
「それでも、こればかりは譲れません」
たとえ下女だとしか思われていなくても、美綾に幸せになってほしいという気持ちに嘘偽りはない。
村のことだって、毎日のように役立たずだとなじられたり、突き落とされなければ、きっと今でも気にしていた。
けれど、もう駄目なのだ。
沙和の心は一度折れてしまった。その心を救いあげてくれたのは幻夜だった。
だから幻夜だけは。
どれほど美綾を大事に思っていても……譲れない。
沙和は思い切り身を引き、叔母の腕から逃れた。
「わたしは、幻夜さまを選びました。あのかたのいらっしゃらない場所には、戻りません。それに……っ」
沙和は大きく息を吸いこんだ。
これまで口を開けば頬を叩かれてきたために、言えなかったこと。
自分の無能を棚に上げるようで、疑問が浮かぶたびに必死で否定してきたこと。
「霧谷の村に鎮守様は……いらっしゃらないのでは、ないでしょうか……?」
「なによ、その高そうな着物! あんたにまったく似合わないわ! 下女のくせにそんなものを着せてもらって、どうやってこの家に取り入ったの? 相手は誰、言いなさい」
「それはお答え——」
できません、と言うより先に、頬に熱い痛みが走った。
覚えのある平手打ちの痛みに、沙和は顔をしかめる。
「私たちが育ててやった恩も忘れて、ずいぶん偉くなったようだね。言いなさい」
恩を持ちだされては逆らえるわけもない。沙和はおののきながら、幻夜の苗字を口にした。
「……高階、様が」
「高階? ってあの、華族様かい!? たしか当主はまだ若くて独身だったと華族年鑑にも載っていたっけね。……こりゃ、あたしにも運が向いたってことだね。美綾」
叔母は人力車に向かって声を張った。
「降りて、この家で待ってなさい。母は、沙和を」
沙和の腕が強くつかまれた。
「——村に戻してから、ここに戻るわ。お母様と一緒に、高階様にご挨拶しましょう。沙和が巫女に戻れば、万事うまく収まるわね。美綾にとっても、これ以上ない良縁ができたわ」
叔母はさもすでに決まったことのように言い、派手な赤の紅を引いた唇を上げた。
「行くわよ、沙和。元はといえば、お前がいなくなったせいで迷惑したんだから、当然これくらいはするわよね?」
つかまれた腕が引っ張られる。
けれど沙和はもう、村にいたころの沙和ではなかった。
沙和はその場に踏ん張り、叔母に反論した。
「それは叔母さまが、わたしを岩場から突き落としたからじゃないですか……!」
「おかしなことを言い出すのは、やめなさい! 義務を放棄するためにデタラメを言うなんて、許されないわよ」
車を降りた美綾に聞かせたくないからだろう、叔母は沙和よりも大きな声を張り上げる。
だけど沙和も、自分の意思を引っこめることはしなかった。
「叔母さまに突き落とされたわたしを、助けてくださったのは幻夜さまです。幻夜さまは『俺を選べ』とおっしゃってくださいました。だからわたしはもう、村には戻りません。叔母さまの言いなりにもなりません」
「お前を家に置いてやったというのに、美綾の幸せを邪魔する気? 村も、お前のせいで未だに不作続きだ。こんなことなら、お前なんか引き取るんじゃなかったよ」
「それでも、こればかりは譲れません」
たとえ下女だとしか思われていなくても、美綾に幸せになってほしいという気持ちに嘘偽りはない。
村のことだって、毎日のように役立たずだとなじられたり、突き落とされなければ、きっと今でも気にしていた。
けれど、もう駄目なのだ。
沙和の心は一度折れてしまった。その心を救いあげてくれたのは幻夜だった。
だから幻夜だけは。
どれほど美綾を大事に思っていても……譲れない。
沙和は思い切り身を引き、叔母の腕から逃れた。
「わたしは、幻夜さまを選びました。あのかたのいらっしゃらない場所には、戻りません。それに……っ」
沙和は大きく息を吸いこんだ。
これまで口を開けば頬を叩かれてきたために、言えなかったこと。
自分の無能を棚に上げるようで、疑問が浮かぶたびに必死で否定してきたこと。
「霧谷の村に鎮守様は……いらっしゃらないのでは、ないでしょうか……?」