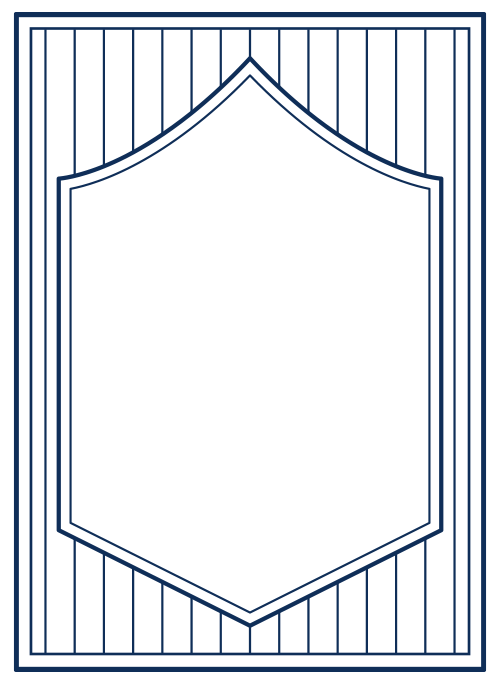それから一週間ほど経ったときだった。
辰野が買い物に出かけたあいだ、沙和は屋敷の前を掃き清めようと外に出た。
なにかしていないと落ち着かない性分なのは、村で暮らしていたときの名残かもしれない。
沙和はしばらく通りを掃いていたが、目の前を過ぎる人力車が立てた砂埃に咳きこむ。人力車は沙和の前を過ぎた少し先で停まった。
「呉服屋の主人から聞いて見にきてみれば、あんただったなんて……! こんなところで生きてたの? しぶとい子」
人力車から着物姿の女性が降り、こちらに向かってくる。顔を上げた沙和は目をみはった。
「奥方様……どうして」
「なによその目。私がここにいちゃおかしい? 美綾を嫁に行かせるなら、帝都に限るでしょうよ」
叔母が人力車をふり返る。つられて沙和もそちらを見れば、美綾が座席から身を乗りだして手を振った。降りてこないのは、沙和が「下女」だからか。
沙和はしばらく美綾の愛らしい手を名残惜しく見ていたが、美綾の着物が派手に装飾された振袖であるのに気づいた。
「嫁って、美綾はまだ七つでは……」
「だからでしょうが! あんたの次に巫女にするはずだった娘が、駆け落ちしていなくなったんだもの。美綾にいつお鉢が回ってくるかわからないじゃないのよ! 巫女になんてなってみなさい。美綾は一生、鎮守様の贄も同然じゃないの。そんなこと美綾にはぜったいにさせないわ」
複雑な思いで聞く沙和に頓着せず、叔母はまくし立てる。
「今のうちに、帝都のいいお家と縁を結ばせないと。七つといっても婚約はできるでしょ。見合い写真用に、帝都でいちばんの呉服屋で、あの子に着物を仕立ててやったわ。なのにあの店員ったら、帝都いちばんの美人の接客をしたと言って……」
叔母が沙和を舐め回すように凝視する。その表情がみるみる歪んだ。
沙和は、幻夜に拾われてからの三ヶ月ほどで見違えるほどに美しくなっていた。毎日、手をかけた食事のおかげで肌の色つやはよく、髪も絹のような光沢を帯びている。
沙和が元から持っていた清楚な美しさが、幻夜の手によって見事に花開いていた。
辰野が買い物に出かけたあいだ、沙和は屋敷の前を掃き清めようと外に出た。
なにかしていないと落ち着かない性分なのは、村で暮らしていたときの名残かもしれない。
沙和はしばらく通りを掃いていたが、目の前を過ぎる人力車が立てた砂埃に咳きこむ。人力車は沙和の前を過ぎた少し先で停まった。
「呉服屋の主人から聞いて見にきてみれば、あんただったなんて……! こんなところで生きてたの? しぶとい子」
人力車から着物姿の女性が降り、こちらに向かってくる。顔を上げた沙和は目をみはった。
「奥方様……どうして」
「なによその目。私がここにいちゃおかしい? 美綾を嫁に行かせるなら、帝都に限るでしょうよ」
叔母が人力車をふり返る。つられて沙和もそちらを見れば、美綾が座席から身を乗りだして手を振った。降りてこないのは、沙和が「下女」だからか。
沙和はしばらく美綾の愛らしい手を名残惜しく見ていたが、美綾の着物が派手に装飾された振袖であるのに気づいた。
「嫁って、美綾はまだ七つでは……」
「だからでしょうが! あんたの次に巫女にするはずだった娘が、駆け落ちしていなくなったんだもの。美綾にいつお鉢が回ってくるかわからないじゃないのよ! 巫女になんてなってみなさい。美綾は一生、鎮守様の贄も同然じゃないの。そんなこと美綾にはぜったいにさせないわ」
複雑な思いで聞く沙和に頓着せず、叔母はまくし立てる。
「今のうちに、帝都のいいお家と縁を結ばせないと。七つといっても婚約はできるでしょ。見合い写真用に、帝都でいちばんの呉服屋で、あの子に着物を仕立ててやったわ。なのにあの店員ったら、帝都いちばんの美人の接客をしたと言って……」
叔母が沙和を舐め回すように凝視する。その表情がみるみる歪んだ。
沙和は、幻夜に拾われてからの三ヶ月ほどで見違えるほどに美しくなっていた。毎日、手をかけた食事のおかげで肌の色つやはよく、髪も絹のような光沢を帯びている。
沙和が元から持っていた清楚な美しさが、幻夜の手によって見事に花開いていた。