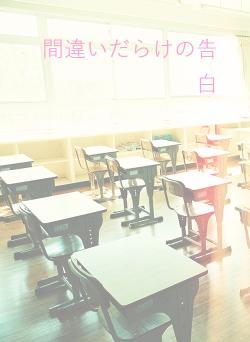「ずいぶんと躾けがなっていない姑娘が来たものだ」
玉座は細やかな龍の金細工が施され、人が一人で座るのには似つかわしくないほどの大きさだった。
そして玉座の両脇にはずらりと妃たちが左右対称に並ばされている。
皇帝に近いほど彼女たちの装飾品も漢服も豪華であり、遠くなればなるほど地味になっていくところを見ると、おそらく近い順に身分が高いってことね。
そんな玉座にふさわしくないほど、皇帝はご立腹だった。
まぁそれもそのはずなんだけどね。
怯え、衰弱しきった娘が送り届けられると思っていたのだろうが、私は勝手知ったるとばかりに牛車が到着するとすぐにそこから飛び出したのだから。
目的はお手洗いとお水。
城の造りというのは、構造上どこも似たような造りになっている。
だからその場にいた者たちを無視し、強引にでも場所を見つけることが出来た。
そして散々皇帝を待たせた挙句、今に至るという。
だってねぇ。私、我慢とか嫌いだし? それに全部が思い通りに行くとか思ってるあたりが許せないのよね。
「お待たせしてしまって申し訳ありません皇帝陛下。ですがここまでくる間に御者に休憩もさせてもらえず、みすぼらしいまま陛下にお会いするわけにもいかなかったので……。そうですよね、御妃様方?」
私はわざとの妃たちに声をかけた。同じ状況を強いられた彼女たちなら、私の言いたいことが分かるわよね。
でも彼女たちは皇帝の顔色を伺うようにちらちらと見ているだけで、誰も声を発しようとはしない。
そうみると、関係性が良く分かる気がする。
まぁ初めから良好な夫婦関係なんて無理だとは分かっていたけど。ホント大概だなぁ。
「ここにいる妃たちはどれもお前と違って従順な者たちしかおらぬわ」
「まぁ。では私は毛色の違う猫娘々という感じですね」
「よく回る口だな」
「にゃーと鳴いている方が可愛いですか?」
中身を知りもしないで、強引に娶ろうとするからでしょう。自業自得よ。当面、扱いずらいくらいに思っていただかないと。
簡単に屈してあげたりなんてしないんだから。
「これは本格的に躾けないとダメだな。どこに嫁いできたのかと言うことをしっかりと叩き込んでやるわ」
「まぁ、皇帝陛下自ら私に構って下さるのですね。嬉しいですわ」
こっちだって嫁ぎたくて嫁いできたわけじゃないのよ。そんな風に睨んだところで、私には効果はないから。
ただ涼やかな顔で微笑み返せば、ますます皇帝の顔は赤くなっていった。
青筋まで立てる様子に、妃たちはソワソワし始める。
「桜綾翁主、この方は偉大なる皇帝陛下にて夫となるお方なのですよ。そんな風にわざと怒らせるような真似はおやめください」
いたたまれなくなったのか、皇帝に一番近い妃が声を上げた。この方はおそらく皇后陛下なのかな。
歳としては一番陛下に近い気がする。
彼女は震えているものの、明らかにその目はやめた方がいいと私に訴えかけていた。
後宮にも優しい方がいる。それだけで少しは気が楽になる気がした。
私だって別に陛下を刺激したいわけではないし、このまま後宮で生きていくのなら怒らすのが得策じゃないことなど分かってはいる。
でも無理して結婚した先に、不幸しかないのにそのまま生きていたくなんてない。そう思えてしまうのだもの。
もちろん前回みたいに次があるなんて限らないし、私は私でしかないから出来れば長生きはしたいけど。
苦痛の中で長生きしても楽しくないんだもん。
これはある意味、転生の弊害といってもいいわね。
「私は私として思ったままを口にしていたのですが、不快にさせてしまったのならば平に謝罪させていただきますわ」
「本当に分からないようだな」
玉座からずかずかと音がしそうなほど大股で、皇帝は私に近づいてきた。
背は私の頭一つ分ほど大きく、ガタイもいい。齢60を超えていると思えないほど、茶色く焼けた肌は艶やかだ。
しかしその赤みががかった黒い瞳はかけらほども笑ってなどいない。
そしてその太い腕を振り上げ、私の頬をそのまま叩いた。
大きな、そしてやや高い音が室内に響き渡る。
「いっっっつつたぁーーーい」
しびれるような感覚に、耳の奥にキーンという甲高い音が鳴り響く。
私はそのまま横に吹き飛ぶように倒れ込む。
焼けつくような、と表現がぴったりくるほど叩かれた頬が痛い。
頬だけじゃなく頭もだ。
最低。本当に最低。よりによって手を上げるだなんて。
私は皇帝を見上げ、睨みつけた。
玉座は細やかな龍の金細工が施され、人が一人で座るのには似つかわしくないほどの大きさだった。
そして玉座の両脇にはずらりと妃たちが左右対称に並ばされている。
皇帝に近いほど彼女たちの装飾品も漢服も豪華であり、遠くなればなるほど地味になっていくところを見ると、おそらく近い順に身分が高いってことね。
そんな玉座にふさわしくないほど、皇帝はご立腹だった。
まぁそれもそのはずなんだけどね。
怯え、衰弱しきった娘が送り届けられると思っていたのだろうが、私は勝手知ったるとばかりに牛車が到着するとすぐにそこから飛び出したのだから。
目的はお手洗いとお水。
城の造りというのは、構造上どこも似たような造りになっている。
だからその場にいた者たちを無視し、強引にでも場所を見つけることが出来た。
そして散々皇帝を待たせた挙句、今に至るという。
だってねぇ。私、我慢とか嫌いだし? それに全部が思い通りに行くとか思ってるあたりが許せないのよね。
「お待たせしてしまって申し訳ありません皇帝陛下。ですがここまでくる間に御者に休憩もさせてもらえず、みすぼらしいまま陛下にお会いするわけにもいかなかったので……。そうですよね、御妃様方?」
私はわざとの妃たちに声をかけた。同じ状況を強いられた彼女たちなら、私の言いたいことが分かるわよね。
でも彼女たちは皇帝の顔色を伺うようにちらちらと見ているだけで、誰も声を発しようとはしない。
そうみると、関係性が良く分かる気がする。
まぁ初めから良好な夫婦関係なんて無理だとは分かっていたけど。ホント大概だなぁ。
「ここにいる妃たちはどれもお前と違って従順な者たちしかおらぬわ」
「まぁ。では私は毛色の違う猫娘々という感じですね」
「よく回る口だな」
「にゃーと鳴いている方が可愛いですか?」
中身を知りもしないで、強引に娶ろうとするからでしょう。自業自得よ。当面、扱いずらいくらいに思っていただかないと。
簡単に屈してあげたりなんてしないんだから。
「これは本格的に躾けないとダメだな。どこに嫁いできたのかと言うことをしっかりと叩き込んでやるわ」
「まぁ、皇帝陛下自ら私に構って下さるのですね。嬉しいですわ」
こっちだって嫁ぎたくて嫁いできたわけじゃないのよ。そんな風に睨んだところで、私には効果はないから。
ただ涼やかな顔で微笑み返せば、ますます皇帝の顔は赤くなっていった。
青筋まで立てる様子に、妃たちはソワソワし始める。
「桜綾翁主、この方は偉大なる皇帝陛下にて夫となるお方なのですよ。そんな風にわざと怒らせるような真似はおやめください」
いたたまれなくなったのか、皇帝に一番近い妃が声を上げた。この方はおそらく皇后陛下なのかな。
歳としては一番陛下に近い気がする。
彼女は震えているものの、明らかにその目はやめた方がいいと私に訴えかけていた。
後宮にも優しい方がいる。それだけで少しは気が楽になる気がした。
私だって別に陛下を刺激したいわけではないし、このまま後宮で生きていくのなら怒らすのが得策じゃないことなど分かってはいる。
でも無理して結婚した先に、不幸しかないのにそのまま生きていたくなんてない。そう思えてしまうのだもの。
もちろん前回みたいに次があるなんて限らないし、私は私でしかないから出来れば長生きはしたいけど。
苦痛の中で長生きしても楽しくないんだもん。
これはある意味、転生の弊害といってもいいわね。
「私は私として思ったままを口にしていたのですが、不快にさせてしまったのならば平に謝罪させていただきますわ」
「本当に分からないようだな」
玉座からずかずかと音がしそうなほど大股で、皇帝は私に近づいてきた。
背は私の頭一つ分ほど大きく、ガタイもいい。齢60を超えていると思えないほど、茶色く焼けた肌は艶やかだ。
しかしその赤みががかった黒い瞳はかけらほども笑ってなどいない。
そしてその太い腕を振り上げ、私の頬をそのまま叩いた。
大きな、そしてやや高い音が室内に響き渡る。
「いっっっつつたぁーーーい」
しびれるような感覚に、耳の奥にキーンという甲高い音が鳴り響く。
私はそのまま横に吹き飛ぶように倒れ込む。
焼けつくような、と表現がぴったりくるほど叩かれた頬が痛い。
頬だけじゃなく頭もだ。
最低。本当に最低。よりによって手を上げるだなんて。
私は皇帝を見上げ、睨みつけた。