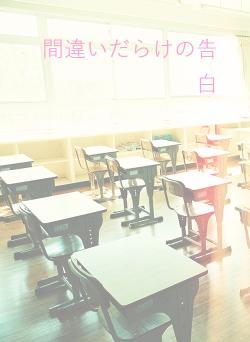私は首に回される腕にわざと力を入れて掴みつつ、意識を下に集中する。
そして私の頭の上で口論する彼らの意識が私から離れた瞬間、思い切り特製の靴で皇帝を踏みつけた。
この国には本来ない、靴。
前の世界で私が大好きで履いていた、ピンヒールだ。
動きやすいし、スラッと見えるからわざわざ特注で作ってもらったのよね。
まさかこんな風に役立つ時が来るだなんて、思ってもみなかった。
「ぐぁぁぁぁぁぁ! な、な、にをする!」
急に訪れた痛みから私を締める腕を緩めた瞬間、今度はみぞおちに、肘を食らわせる。
「ごっふぉっ! がっ、がっっっ」
皇帝がよろけたのを確認すると、私はその場から這いつくばって転げるように逃げ出す。
前世の私、グッドジョブすぎ。護身術って、ホントに役立つのね。
「今だ! 狂王を捕獲しろ!」
剣を高く掲げた皇子の言葉に呼応した兵士たちが、一気に皇帝の元へとなだれ込んだ。
さすがの数に抵抗は無理だと理解した皇帝は腕を上げ、項垂れるように肩を落とした。
「大丈夫か、翁主殿?」
「大丈夫そうに見えますか? 手を貸していただけるとありがたいのですが殿下」
「もう今日から皇帝だがな」
不敵な笑みを浮かべながら、私に手を差し伸べた。
今日から皇帝か。まぁそうよね。
これだけの兵士を動かし、現皇帝を倒しちゃったんだから。
あ、でも、ということは私はこのままお役御免って感じじゃない?
やだー。またあのぬくぬく生活に復活できるし。やっぱり今世はついてる~。
「んで、あんたが皇后だ」
「は?」
思わず真顔で私は言葉を返す。
「あはははは、おい、その顔。さすがに不敬罪だと思うぞ」
顔と言われても鏡ないし。
鏡なくても今自分がどれだけ嫌そうな顔をしてしまったかは分かるけど。
にしてもこの人何言ってるの状態なんだもの。仕方ないでしょう。
好色皇帝の妃という最悪の展開から外れたっていうのに、誰が好き好んでこの人の妃になんてならなきゃいけないのよ。
しかも皇后ですって。帝国の国母とか、権力はあっても、ただ面倒なだけじゃない。
私はぬくぬくしていきたいだけで、別に権力が欲しいワケじゃないのよ。
ぜーーーーーーったいに嫌だし。
「元々、殿下のお父上であらせられる方と婚姻を結ぶ予定だった私と婚約をなさるおつもりなのですか?」
要約。あなたの義母になる予定だったのに、なんで私と結婚するとか言ってるのよ。って、意味通じるわよね。
しかしどれだけ言葉を返しても、まるで珍獣でも見るかのような目で、殿下は私を見ている。
「どーせ、どこかに嫁ぐとこになるんだ。それなら俺にしとけ」
「ですから、そこにメリット……お得な点はあるんですか?」
「あははは。お前、本当に面白いな。あのジジイを踏みつけたとこからして最高だ。まさか、皇后になれと言われて損得勘定を持ち出すとは」
殿下という身分を感じさせないほど、感情のままに笑う彼を見ていると、そんなに嫌いではない自分がいるのも確かだった。
どうせどこかに嫁ぐ。確かに、それはそうだ。
いつかなんて、今回みたいにあっという間に来てしまうだろうし、その時もきっと自分での選択肢はないのよね。
それなら少しでもいい方がいいに決まっている。
「他の妃はもうけず、皇后ただ一人を据えると誓おう。あんなジジイみたいなことはしないさ」
「……私、結構、好き勝手させてもらいますけど?」
「まぁ、皇后としての務めさえ果たしてくれればそこは構わない」
「……」
「不自由はさせないぞ」
「あとでどうだったとか、裏切るのはナシですよ?」
「あはははは。あんな大胆な攻撃をされたら困るからな。裏切らないさ」
「な、それは! も、もう……」
攻撃って。あの場面では仕方ないでしょう。だいたい、それのおかげでこうして簡単に皇帝を捕らえることが出来たのに。
もっと褒めてくれたっていいのに。
「でもだからこそ俺の妃にしたい。こんないい女、他には見たことないからな」
「な、な、な! ぅーーーー」
殿下の言葉に、顔が火照っていくのが分かる。
褒めて欲しかったけど、こんな風にストレートに言われることには慣れてないのよ。
しかも女性っぽさじゃなくて、強さを褒められるだなんて……。なんか、いろいろ反則だわ。
こういうのも吊り橋効果って言うのかしらね。
「分かりました。あなたのただ一人の妃となりましょう」
この手を取ることが良き未来なのかどうかは分からない。
大体、前世だって結婚運とか一ミリもなかったわけだし。
でも分からないからこそ、賭けてみることにした。
この皇帝らしからぬ皇帝となる彼に。
そして彼を選ぶ私の運に。
それに私は自分の幸せを諦める気などまったくないから。
遠くで鳥が高らかに鳴いていた。
彼の即位が行われたと同時に、私が皇后になったのはそれからすぐのことだったーー
そして私の頭の上で口論する彼らの意識が私から離れた瞬間、思い切り特製の靴で皇帝を踏みつけた。
この国には本来ない、靴。
前の世界で私が大好きで履いていた、ピンヒールだ。
動きやすいし、スラッと見えるからわざわざ特注で作ってもらったのよね。
まさかこんな風に役立つ時が来るだなんて、思ってもみなかった。
「ぐぁぁぁぁぁぁ! な、な、にをする!」
急に訪れた痛みから私を締める腕を緩めた瞬間、今度はみぞおちに、肘を食らわせる。
「ごっふぉっ! がっ、がっっっ」
皇帝がよろけたのを確認すると、私はその場から這いつくばって転げるように逃げ出す。
前世の私、グッドジョブすぎ。護身術って、ホントに役立つのね。
「今だ! 狂王を捕獲しろ!」
剣を高く掲げた皇子の言葉に呼応した兵士たちが、一気に皇帝の元へとなだれ込んだ。
さすがの数に抵抗は無理だと理解した皇帝は腕を上げ、項垂れるように肩を落とした。
「大丈夫か、翁主殿?」
「大丈夫そうに見えますか? 手を貸していただけるとありがたいのですが殿下」
「もう今日から皇帝だがな」
不敵な笑みを浮かべながら、私に手を差し伸べた。
今日から皇帝か。まぁそうよね。
これだけの兵士を動かし、現皇帝を倒しちゃったんだから。
あ、でも、ということは私はこのままお役御免って感じじゃない?
やだー。またあのぬくぬく生活に復活できるし。やっぱり今世はついてる~。
「んで、あんたが皇后だ」
「は?」
思わず真顔で私は言葉を返す。
「あはははは、おい、その顔。さすがに不敬罪だと思うぞ」
顔と言われても鏡ないし。
鏡なくても今自分がどれだけ嫌そうな顔をしてしまったかは分かるけど。
にしてもこの人何言ってるの状態なんだもの。仕方ないでしょう。
好色皇帝の妃という最悪の展開から外れたっていうのに、誰が好き好んでこの人の妃になんてならなきゃいけないのよ。
しかも皇后ですって。帝国の国母とか、権力はあっても、ただ面倒なだけじゃない。
私はぬくぬくしていきたいだけで、別に権力が欲しいワケじゃないのよ。
ぜーーーーーーったいに嫌だし。
「元々、殿下のお父上であらせられる方と婚姻を結ぶ予定だった私と婚約をなさるおつもりなのですか?」
要約。あなたの義母になる予定だったのに、なんで私と結婚するとか言ってるのよ。って、意味通じるわよね。
しかしどれだけ言葉を返しても、まるで珍獣でも見るかのような目で、殿下は私を見ている。
「どーせ、どこかに嫁ぐとこになるんだ。それなら俺にしとけ」
「ですから、そこにメリット……お得な点はあるんですか?」
「あははは。お前、本当に面白いな。あのジジイを踏みつけたとこからして最高だ。まさか、皇后になれと言われて損得勘定を持ち出すとは」
殿下という身分を感じさせないほど、感情のままに笑う彼を見ていると、そんなに嫌いではない自分がいるのも確かだった。
どうせどこかに嫁ぐ。確かに、それはそうだ。
いつかなんて、今回みたいにあっという間に来てしまうだろうし、その時もきっと自分での選択肢はないのよね。
それなら少しでもいい方がいいに決まっている。
「他の妃はもうけず、皇后ただ一人を据えると誓おう。あんなジジイみたいなことはしないさ」
「……私、結構、好き勝手させてもらいますけど?」
「まぁ、皇后としての務めさえ果たしてくれればそこは構わない」
「……」
「不自由はさせないぞ」
「あとでどうだったとか、裏切るのはナシですよ?」
「あはははは。あんな大胆な攻撃をされたら困るからな。裏切らないさ」
「な、それは! も、もう……」
攻撃って。あの場面では仕方ないでしょう。だいたい、それのおかげでこうして簡単に皇帝を捕らえることが出来たのに。
もっと褒めてくれたっていいのに。
「でもだからこそ俺の妃にしたい。こんないい女、他には見たことないからな」
「な、な、な! ぅーーーー」
殿下の言葉に、顔が火照っていくのが分かる。
褒めて欲しかったけど、こんな風にストレートに言われることには慣れてないのよ。
しかも女性っぽさじゃなくて、強さを褒められるだなんて……。なんか、いろいろ反則だわ。
こういうのも吊り橋効果って言うのかしらね。
「分かりました。あなたのただ一人の妃となりましょう」
この手を取ることが良き未来なのかどうかは分からない。
大体、前世だって結婚運とか一ミリもなかったわけだし。
でも分からないからこそ、賭けてみることにした。
この皇帝らしからぬ皇帝となる彼に。
そして彼を選ぶ私の運に。
それに私は自分の幸せを諦める気などまったくないから。
遠くで鳥が高らかに鳴いていた。
彼の即位が行われたと同時に、私が皇后になったのはそれからすぐのことだったーー