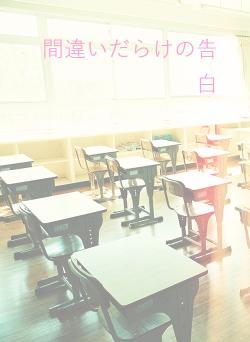「ああ、それは空気だと思えばいい」
「えええ」
「陛下、さすがに空気は酷くないですか?」
「なんだ空燕。さっきまで借りてきた猫のような顔をしていたくせに」
「そりゃあ、他の者たちの目がありますからね」
先ほどと同一人物なのかというくらいの、変わりようね。あからさまに空燕と呼ばれた宦官は、不機嫌さを隠そうとはしない。
あきらかに、皇帝とその妃に対する対応ではない気がするのだけど、こんなものなのかしら。それにこんなに不敬極まりない態度をとっても、陛下は気にもかけていないし。
そして空燕は私をやや怪訝そうに見たあと、近くにあった椅子をとり、ドカっと腰かけた。
「オレも聞きたいとこでしたよ。どうしてその娘が皇后なのですか」
「なんだ。おまえまで不服なのか」
「不服ではないですが……。仮にもその娘は平民。見目が気に入っただけなら、側妃でいいではないですか」
やや私を蔑むような目。ああ、そうね。これよ。いつでも人々が私を見てきた目だ。普通はそう。こういう反応なのよね。陛下が違うだけで。
「それにですよ? 何も属性も色もない人間を後宮に入れるだなんて」
「……そうですね」
心の中が冷や水を浴びたように、冷静になっていくのが自分でも手に取るようにわかった。この人に言われたくても知っている。自分がこの世界でどういう人間なのか、なんて。
ほんの少し、ただの一瞬でも浮かれそうになった自分がむしろ恥ずかしい。馬鹿ね、私。
「空燕、言い残すコトはそれだけか?」
「言いたいことではなく、言い残すって、いくらなんでも不穏すぎるでしょう陛下」
「自分が言った言葉の意味を考えろ」
「私なら気にしません。本当のことですから」
「……すみません。言い過ぎました」
頭をかきながら、空燕は私に頭を下げた。
「先ほども言ったが、俺は妃に力など求めてはいない」
「陛下ほどの力がおありになる方でしたら、確かにそうでしょう。ですが、家臣からしたらそうではないのではないですか?」
私は空燕を見た。彼の言いたいことは最もだ。陛下は良くても、周りがそんなことを認めるわけがない。例え私に力があったとしても、所詮は平民。平民の娘が皇后になったなんて話は今まで聞いたことがなかった。
「お世継ぎのことや、他の豪族などの兼ね合いもございましょう」
「オレもそれが言いたかったんです。力のない娘が後宮に入れば、荒れることは目に見えています。それにあいつらは確実に標的として狙ってくるでしょう。そうなったらどうするんです」
全面否定かと思ったんだけど、空燕の言葉はいつもの人たちと少し違う気がした。言い方は確かに武骨ではあるけど、私への気遣いが今はそこはかとなく感じられる。
「そこはおまえたちが上手くやればいいことだ。それに俺がそんなことを放っておくと?」
「目が行き届くのには限界があるというのです……」
「それは痛いほどわかっているさ。だが、次はない」
二人の会話の中身までは分からないけど、目が行き届かず誰かが亡くなったか何かだということは察すれる。後宮は伏魔殿といわれるほど、女たちの争いが絶えないというし。
私では確かに皇后の座は荷が重すぎる。せめて自分を守る力がないと、ココでは生き残れないかもしれないのね。そこまで考えて、私はなぜか自分の考えに笑いがこみ上げてきてしまった。
「えええ」
「陛下、さすがに空気は酷くないですか?」
「なんだ空燕。さっきまで借りてきた猫のような顔をしていたくせに」
「そりゃあ、他の者たちの目がありますからね」
先ほどと同一人物なのかというくらいの、変わりようね。あからさまに空燕と呼ばれた宦官は、不機嫌さを隠そうとはしない。
あきらかに、皇帝とその妃に対する対応ではない気がするのだけど、こんなものなのかしら。それにこんなに不敬極まりない態度をとっても、陛下は気にもかけていないし。
そして空燕は私をやや怪訝そうに見たあと、近くにあった椅子をとり、ドカっと腰かけた。
「オレも聞きたいとこでしたよ。どうしてその娘が皇后なのですか」
「なんだ。おまえまで不服なのか」
「不服ではないですが……。仮にもその娘は平民。見目が気に入っただけなら、側妃でいいではないですか」
やや私を蔑むような目。ああ、そうね。これよ。いつでも人々が私を見てきた目だ。普通はそう。こういう反応なのよね。陛下が違うだけで。
「それにですよ? 何も属性も色もない人間を後宮に入れるだなんて」
「……そうですね」
心の中が冷や水を浴びたように、冷静になっていくのが自分でも手に取るようにわかった。この人に言われたくても知っている。自分がこの世界でどういう人間なのか、なんて。
ほんの少し、ただの一瞬でも浮かれそうになった自分がむしろ恥ずかしい。馬鹿ね、私。
「空燕、言い残すコトはそれだけか?」
「言いたいことではなく、言い残すって、いくらなんでも不穏すぎるでしょう陛下」
「自分が言った言葉の意味を考えろ」
「私なら気にしません。本当のことですから」
「……すみません。言い過ぎました」
頭をかきながら、空燕は私に頭を下げた。
「先ほども言ったが、俺は妃に力など求めてはいない」
「陛下ほどの力がおありになる方でしたら、確かにそうでしょう。ですが、家臣からしたらそうではないのではないですか?」
私は空燕を見た。彼の言いたいことは最もだ。陛下は良くても、周りがそんなことを認めるわけがない。例え私に力があったとしても、所詮は平民。平民の娘が皇后になったなんて話は今まで聞いたことがなかった。
「お世継ぎのことや、他の豪族などの兼ね合いもございましょう」
「オレもそれが言いたかったんです。力のない娘が後宮に入れば、荒れることは目に見えています。それにあいつらは確実に標的として狙ってくるでしょう。そうなったらどうするんです」
全面否定かと思ったんだけど、空燕の言葉はいつもの人たちと少し違う気がした。言い方は確かに武骨ではあるけど、私への気遣いが今はそこはかとなく感じられる。
「そこはおまえたちが上手くやればいいことだ。それに俺がそんなことを放っておくと?」
「目が行き届くのには限界があるというのです……」
「それは痛いほどわかっているさ。だが、次はない」
二人の会話の中身までは分からないけど、目が行き届かず誰かが亡くなったか何かだということは察すれる。後宮は伏魔殿といわれるほど、女たちの争いが絶えないというし。
私では確かに皇后の座は荷が重すぎる。せめて自分を守る力がないと、ココでは生き残れないかもしれないのね。そこまで考えて、私はなぜか自分の考えに笑いがこみ上げてきてしまった。