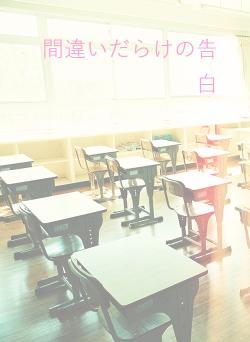陛下は私を荷物を担ぐように肩に乗せた。何が起きたのかなど、まったく分からない。しかも身じろぎして抗議した私を、陛下は抱きなおしただけで辞める気などないようだった。
広場にいた全員の視線が私に突き刺さる。
「陛下! お、お話を聞いていただけませんでしょうか?」
私のすぐ隣で傅いていた女の子が、声を上げた。確か隣は陛下と同じ火属性。しかも最前列にいるってことは、上位の色の子ってことよね。
「なんだ」
小春日和な陽気が、一瞬にして凍り付く。それほどまでに陛下の声は低かった。先ほどまでの陛下の表情や声色とは明らかに異なる。
声を上げた女の子も、思わず顔を上げて陛下を見上げていた。そのあまりの蒼白さに、こっちまで気の毒に思えるほどだわ。
「そその娘は……最前列にはおりますが……その、力がなく。陛下が何か……その」
「この俺が勘違いをしたと言いたいのか?」
「いいいいえ、そうではなく! ただただ心配で」
「お前ごときが、俺の何を心配すると?」
「あの、それはその……」
女の子が声を上げるたびに、どんどんと気温が下がって行くようだった。陛下の眉間にあるシワも、運河のように深くなっていく。私が選ばれたことへの戸惑いと、陛下を心配してのことなんだろうけど。
元々、気安く殿上人に声をかけていいわけもない。しかも今帝は身内すら殺した血塗られ皇帝とまで言われる方。身分を考えたら、到底意見なんて出来ないはずなのに。
「俺はこの娘を皇后とする。これは決定事項だ。力がなんだとか言っていたな。俺は自分の妃に力を求めるほど、弱くはないつもりだ」
そうね……。陛下は霊力の中で最も強い金色の色を持つほど。この何百年、金色を持つモノなんて現れたことがないって聞いたことがあるわ。
それほどの力があるんだもの。普通ならば妃に力を~は確かに求めないでしょうね。
「それでもまだ、俺に意見をする者はいるか?」
陛下は広場を見渡した。皆下を向き、誰一人声を上げようとする者はいなかった。でもだからこそ、私は陛下の行動が気になってしまった。
なんで私なのか。確かに陛下に力のある妃など必要はない。だからといって、それが私を選ぶ理由になんてなりはしない。力がいらないと力がない者を選ぶということは別に同じコトではないから。
「……陛下、どうして私を選んで下さったのかお聞きしてもよろしいですか?」
もう誰も声をあげないと思っていたのか、陛下はややキョトンとした顔をしていた。
広場にいた全員の視線が私に突き刺さる。
「陛下! お、お話を聞いていただけませんでしょうか?」
私のすぐ隣で傅いていた女の子が、声を上げた。確か隣は陛下と同じ火属性。しかも最前列にいるってことは、上位の色の子ってことよね。
「なんだ」
小春日和な陽気が、一瞬にして凍り付く。それほどまでに陛下の声は低かった。先ほどまでの陛下の表情や声色とは明らかに異なる。
声を上げた女の子も、思わず顔を上げて陛下を見上げていた。そのあまりの蒼白さに、こっちまで気の毒に思えるほどだわ。
「そその娘は……最前列にはおりますが……その、力がなく。陛下が何か……その」
「この俺が勘違いをしたと言いたいのか?」
「いいいいえ、そうではなく! ただただ心配で」
「お前ごときが、俺の何を心配すると?」
「あの、それはその……」
女の子が声を上げるたびに、どんどんと気温が下がって行くようだった。陛下の眉間にあるシワも、運河のように深くなっていく。私が選ばれたことへの戸惑いと、陛下を心配してのことなんだろうけど。
元々、気安く殿上人に声をかけていいわけもない。しかも今帝は身内すら殺した血塗られ皇帝とまで言われる方。身分を考えたら、到底意見なんて出来ないはずなのに。
「俺はこの娘を皇后とする。これは決定事項だ。力がなんだとか言っていたな。俺は自分の妃に力を求めるほど、弱くはないつもりだ」
そうね……。陛下は霊力の中で最も強い金色の色を持つほど。この何百年、金色を持つモノなんて現れたことがないって聞いたことがあるわ。
それほどの力があるんだもの。普通ならば妃に力を~は確かに求めないでしょうね。
「それでもまだ、俺に意見をする者はいるか?」
陛下は広場を見渡した。皆下を向き、誰一人声を上げようとする者はいなかった。でもだからこそ、私は陛下の行動が気になってしまった。
なんで私なのか。確かに陛下に力のある妃など必要はない。だからといって、それが私を選ぶ理由になんてなりはしない。力がいらないと力がない者を選ぶということは別に同じコトではないから。
「……陛下、どうして私を選んで下さったのかお聞きしてもよろしいですか?」
もう誰も声をあげないと思っていたのか、陛下はややキョトンとした顔をしていた。