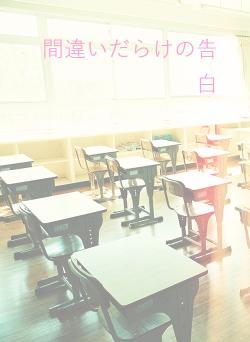あれほどまでにおしゃべりをしていた女の子たちも口を閉じ、その場で傅く。
あああ、これだと皇帝陛下の顔見れないわね。でも一人だけ顔を上げるのはさすがに不敬罪となってしまうわ。諦めて下を向いたままの私たちの間を皇帝陛下と宦官らしき人が通りすぎていく。
「よく集まって下さいました。これより、陛下直々にお妃候補を選んで行きます。お声をかけられた方は、この後後宮へ移動となります」
陛下が直接選ぶだなんて、なんかすごいわね。選定っていうから、お偉い様たちが勝手に決めるものなのかと思っていたけど、今帝はそうではないみたい。
ここに並ぶのも身分とか一切の忖度もなかったし。実力重視って感じなのかな。ああ、でも顔の好みとかも……って、下向いてたら分からないわね。
「ただお妃候補に選ばれなかった方でも、その後の女官選定がございますのでその場でしばらくお待ちください」
女官ねぇ。下級女官でも、衣食住は確か保証されるのよね。私みたいな身寄りのない者には最適なのだろうけど、力がないからなぁ。選ばれることはないだろうけど、さすがに王妃様が選ばれる瞬間は顔が見れそうね。
帝国でただ一人、金色の力を持つ皇帝陛下。ある意味私とは真逆の存在だから、どんな方だろうって興味があったのよね。
「ではこれより陛下が皆さんのところを回られます。お声をかけられるまではそのままで居て下さい」
みんな息をひそめているのか、木靴のようなコツコツという陛下の歩く音だけが広場に響き渡っていた。
普段から緊張とは無縁の私ですら、息をするのを忘れてしまいそうになる。そしてその時間は長いものだったのか、ほんのわずかな時間だったのか。そんな感覚すらおかしくなるほどの時、ふと陛下の足が私の前で止まった。
えっと?
私の前にも後ろにも誰もいない。だって属性なしは私だけだもの。それなのに陛下が私の前に立つ意味って何があるのかしら。しかしそう思う私の頭の上で、陛下と宦官の小声での話し声が途切れ途切れに聞こえてくる。
私だけが一人だったのが気になったのね、きっと。ため息をつきたくなる気持ちを抑えつつ、頭に突き刺さる視線がなくなるのをただじっと待った。
大丈夫。どうせいつものことよ。好奇の目も、笑い声も……。
「うむ。そうだな……この娘にしよう」
短くそう言った皇帝は、広場の一番隅で小さくなっていた私を軽々と担ぐ。
「えええ?」
自分でも何が起こったのか理解できず、思わす私は素っ頓狂な声を上げてしまった。
あああ、これだと皇帝陛下の顔見れないわね。でも一人だけ顔を上げるのはさすがに不敬罪となってしまうわ。諦めて下を向いたままの私たちの間を皇帝陛下と宦官らしき人が通りすぎていく。
「よく集まって下さいました。これより、陛下直々にお妃候補を選んで行きます。お声をかけられた方は、この後後宮へ移動となります」
陛下が直接選ぶだなんて、なんかすごいわね。選定っていうから、お偉い様たちが勝手に決めるものなのかと思っていたけど、今帝はそうではないみたい。
ここに並ぶのも身分とか一切の忖度もなかったし。実力重視って感じなのかな。ああ、でも顔の好みとかも……って、下向いてたら分からないわね。
「ただお妃候補に選ばれなかった方でも、その後の女官選定がございますのでその場でしばらくお待ちください」
女官ねぇ。下級女官でも、衣食住は確か保証されるのよね。私みたいな身寄りのない者には最適なのだろうけど、力がないからなぁ。選ばれることはないだろうけど、さすがに王妃様が選ばれる瞬間は顔が見れそうね。
帝国でただ一人、金色の力を持つ皇帝陛下。ある意味私とは真逆の存在だから、どんな方だろうって興味があったのよね。
「ではこれより陛下が皆さんのところを回られます。お声をかけられるまではそのままで居て下さい」
みんな息をひそめているのか、木靴のようなコツコツという陛下の歩く音だけが広場に響き渡っていた。
普段から緊張とは無縁の私ですら、息をするのを忘れてしまいそうになる。そしてその時間は長いものだったのか、ほんのわずかな時間だったのか。そんな感覚すらおかしくなるほどの時、ふと陛下の足が私の前で止まった。
えっと?
私の前にも後ろにも誰もいない。だって属性なしは私だけだもの。それなのに陛下が私の前に立つ意味って何があるのかしら。しかしそう思う私の頭の上で、陛下と宦官の小声での話し声が途切れ途切れに聞こえてくる。
私だけが一人だったのが気になったのね、きっと。ため息をつきたくなる気持ちを抑えつつ、頭に突き刺さる視線がなくなるのをただじっと待った。
大丈夫。どうせいつものことよ。好奇の目も、笑い声も……。
「うむ。そうだな……この娘にしよう」
短くそう言った皇帝は、広場の一番隅で小さくなっていた私を軽々と担ぐ。
「えええ?」
自分でも何が起こったのか理解できず、思わす私は素っ頓狂な声を上げてしまった。