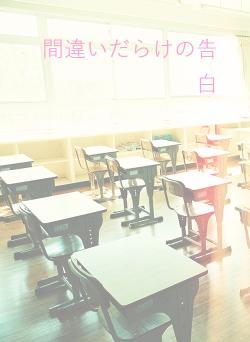「ああ、まだ生きていたのね」
村の中を歩く私を見つけた大姐たちがちらちらとこちらを見ながら、決して小さくはない声で陰口をたたいた。
まだ十七になったばかりの身寄りもない娘に言う言葉ではないことぐらい、学がない私でも分かる。分かるけど、この国にとって絶対的なモノ……。
「気味の悪い色なしなんて……」
「本当よね。あんなのがこの村に住み着いてるせいで、この村はどんどん貧しくなる一方さ」
色なし。そう……それこそが、私がここで虐げられる原因だ。
「この国で霊力の色すらもない人間なんて、とっとと追い出せばいいものを」
「本当だわ。聞いたこともない。力も色も持たぬものなど」
この国の者は少なからず霊力を持つ。霊力は四つの属性に分かれており、力の強さはその色によって表された。属性に最強はないけど、金色が一番強いんだっけ。
でも私はそのどの属性も持っていなければ、色すらない無色。つまりは何の力も持たない異質な存在でしかなかった。
「……すみません阿姨、その御触書が見たいのですが」
「ああ、やだやた。無色に声をかけられちまったよ。寿命が縮まったらどうしてくれるんだい!」
すでに80は超えてるだろうに、まだ寿命とか気にしていたのね。
意外だわ。私だったら、こんな風に力のないものに嫌味をネチネチ言い続けてまで長生きするのとか、絶対に嫌なんだけど。まぁ、きっとこれも考え方の違いね。
「申し訳ありません。村長より必ず読むようにと言われてここまで来たもので」
「村長も何を考えてるのやら。息子に代変わりしてから、感じが悪いったらありゃしない」
「まぁでも今回の御触書は仕方ないんじゃないんかい? 何せ、世代替わりした皇帝からのモノだろう」
「確かに皇帝に逆らうなどしたら、こんなちんけな村など一晩で焼かれてしまうからね」
「ああ、恐ろしや恐ろしや」
私からしたら、十分あんたたちの方が恐ろしいけどね。だいたい、村が焼かれたって死ななさそうだし。それに村長も村長よ。
婆さん二人から見たら若いかもしれないけど、ゆうに私の親の年齢を超えてるのよ。最近になって馴れ馴れしく家にやってきたりしてさ。魂胆が開け透けて見えてるのよね。爺さんの妾になんて絶対にならないんだから。
村の中を歩く私を見つけた大姐たちがちらちらとこちらを見ながら、決して小さくはない声で陰口をたたいた。
まだ十七になったばかりの身寄りもない娘に言う言葉ではないことぐらい、学がない私でも分かる。分かるけど、この国にとって絶対的なモノ……。
「気味の悪い色なしなんて……」
「本当よね。あんなのがこの村に住み着いてるせいで、この村はどんどん貧しくなる一方さ」
色なし。そう……それこそが、私がここで虐げられる原因だ。
「この国で霊力の色すらもない人間なんて、とっとと追い出せばいいものを」
「本当だわ。聞いたこともない。力も色も持たぬものなど」
この国の者は少なからず霊力を持つ。霊力は四つの属性に分かれており、力の強さはその色によって表された。属性に最強はないけど、金色が一番強いんだっけ。
でも私はそのどの属性も持っていなければ、色すらない無色。つまりは何の力も持たない異質な存在でしかなかった。
「……すみません阿姨、その御触書が見たいのですが」
「ああ、やだやた。無色に声をかけられちまったよ。寿命が縮まったらどうしてくれるんだい!」
すでに80は超えてるだろうに、まだ寿命とか気にしていたのね。
意外だわ。私だったら、こんな風に力のないものに嫌味をネチネチ言い続けてまで長生きするのとか、絶対に嫌なんだけど。まぁ、きっとこれも考え方の違いね。
「申し訳ありません。村長より必ず読むようにと言われてここまで来たもので」
「村長も何を考えてるのやら。息子に代変わりしてから、感じが悪いったらありゃしない」
「まぁでも今回の御触書は仕方ないんじゃないんかい? 何せ、世代替わりした皇帝からのモノだろう」
「確かに皇帝に逆らうなどしたら、こんなちんけな村など一晩で焼かれてしまうからね」
「ああ、恐ろしや恐ろしや」
私からしたら、十分あんたたちの方が恐ろしいけどね。だいたい、村が焼かれたって死ななさそうだし。それに村長も村長よ。
婆さん二人から見たら若いかもしれないけど、ゆうに私の親の年齢を超えてるのよ。最近になって馴れ馴れしく家にやってきたりしてさ。魂胆が開け透けて見えてるのよね。爺さんの妾になんて絶対にならないんだから。