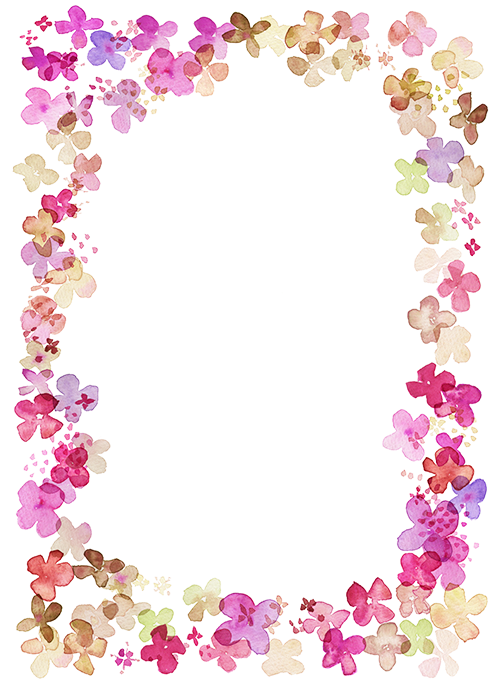透はしばらく居間で待っていたが、玄関で押し問答している麻美が気になって腰を上げた。
冷気を遮断する引き戸を開けると、見知らぬ男と麻美が向き合っていた。近所にはいない顔だと透が訝しみながら見やると、その男は透を一瞥する。
目が合った瞬間、男は凍てつくような眼差しを透に向けた。
「こんにちは」
次の瞬間にはにっこりと笑って、気さくに挨拶をしてくる。
「日高宗太です。あなたが片桐透さん?」
男の年は透と同じくらいで、モデルのような長身痩躯をしていた。涼やかな目鼻立ちを優しげな微笑みで彩って軽く首を傾げる様は、なかなか絵になる。
ただ目だけは全く笑っていない。それに気づいて、透は警戒心を抱いた。
「ええ。日高ということは、麻美さんの親戚の方ですか」
「夫です」
つと透が眉をひそめると、麻美が振り向いて言う。
「その冗談はやめてって言ってる、兄さん」
「ああ、ごめんごめん」
彼は悪びれずにくすくすと笑って、笑みを収めて透を見る。
「でも彼がお前の夫だというのも、全然笑えない冗談だよ」
「それは冗談じゃないの。籍もちゃんと入ってる」
「麻美」
彼の声は優しい呼びかけだったのに、麻美はびくりと肩を震わせる。
「兄さんが嫌いになった?」
「そういう意味じゃ、ないの」
宗太は後ずさった麻美の腕に手を伸ばす。
「じゃあ言うことを聞きなさい。帰るんだ」
「……待ってください」
宗太の手を押しやって、透は麻美の前に出た。
「嫌いじゃないなら言うことを聞けというのは、ちょっと乱暴ではないですか」
割り込んだ透を見やって、宗太は冷えた声を出す。
「あなたはこの子のことをよく知らないでしょう。麻美は昔から、時々現実逃避をする。そういう時は引き戻してやらないといけないんです」
「昔はそうだったかもしれませんが、今の麻美さんは大人です」
透は部屋の中を示して告げる。
「どうぞお入りになって、座って話してください」
透の言葉に、麻美が切羽詰まった声で遮った。
「だめ。兄さん、今すぐ帰って」
「麻美さん?」
気遣わしげに呼んだ透にも気づかず、麻美は早口で言葉を吐き出す。
「兄さんは嫌い。家族にも二度と会いたくない。ほっといて」
透はそこに頑なな麻美の感情をみつけて口をつぐむ。
透が宗太を振り向くと、宗太は青ざめて立っていた。
「……麻美?」
宗太は信じられないものを見る目で麻美を見下ろす。
「兄さんにそんなこと言ったことないじゃないか。麻美、どうした? 話して」
「帰って!」
麻美は叩きつけるように叫んで、両手で宗太の胸を押しやる。
後は宗太が何を言っても、麻美は「帰って」以外に一言も話さなかった。ただ宗太を扉の外に押し出そうとする麻美に、透は見かねて言った。
「日高さん、携帯番号と宿泊先を教えて頂けますか。ひとまず今日はお互い頭を冷やすことにして、明日こちらから伺わせて頂きます」
宗太もこれ以上は麻美が何も話さないと理解したのか、仕方なさそうに手帳を取り出す。
宗太は手帳を破いてペンを走らせると、透にメモを渡す。
宗太は扉の外に出ると、途方に暮れた顔で麻美を見やる。
「麻美。兄さんは心配だから来ただけだ」
目を逸らしたままの麻美に、宗太はそっと告げる。
「本当だよ。だから帰ってきて」
踵を返して、宗太は自分から扉を閉めた。
透はうつむいたまま立ちすくむ麻美に振り向いて、中を示す。
「中に入って座ろう。……話をゆっくり聞くから」
透が肩に触れても、麻美は全身を強張らせて口を引き結んでいた。
麻美が話し出すには、ずいぶんと時間がかかった。
おせち料理の準備のために代わる代わる台所に立ちながら、いつもとは逆で透から話しかける。
二日ほどかけてゆっくり準備しようと話していたのだが、作業ばかりしていたらその日の夕方の内におせち料理は完成した。
「……話してもいいのかな」
麻美がようやく小声で切り出したのは夜になってからで、透は振り向く。
「麻美さんが話したいなら聞くよ」
透はお茶を淹れて持ってくる。
二人で向き合ってテーブルの前に座った頃、ようやく麻美は息をついて話し出した。
「年が離れてたからか、兄さんはずっと子どもみたいに私を扱ってた」
麻美がテーブルの木目をみつめる眼差しは、頼りなさげだった。
「泣けば抱っこしてくれて、傷つきそうになったらそういうものから私を遠ざけてくれた。優しい兄さん」
透はそんな麻美の表情を眺めながら問う。
「それならどうして、麻美さんはそんなに悲しそうなの」
麻美は喉につっかえたようにごくりと息を呑む。
そのまま麻美は押し黙った。透は話し出す気配も失われたのを感じる。
透は立ち上がって麻美の隣に座る。その背中を抱くと、強張った麻美の背をさすった。
それに促されるように麻美はゆっくりと力を抜いて、喉を動かした。
「……一度だけ、叩かれた」
ようやく麻美から零れ落ちた言葉に、透はぴくりと反応した。
「兄さんの仕事が忙しくなって、顔も合わせない日々が数か月続いたある時、一回だけ。兄さんはすぐ我に返って、いっぱい謝ってくれた」
自分の手をじっと見下ろして、麻美はつぶやく。
「でもなんだかとても……兄さんが遠くに感じて」
目を歪めて、麻美は言葉を落とした。
「周りを見回したら、お父さんもお母さんもおばあちゃんもそう見えた。兄さんも家族もそこにいるのに、それは海の向こうの風景を見てるみたいだった」
頭を片手で押さえて、麻美は苦しそうにつぶやく。
「家族だって変わっていく。ずっと同じなんて、ない」
それでねと麻美は告げる。
「夢を見たくなったの。家族とつながっていた頃の思い出が見られたらと思って」
そう言ったきり、麻美は黙りこくった。
透は彼女の言葉が尽きたのを感じて問いかけた。
「今は、お兄さんと向かい合うことができない?」
透の言葉に、麻美は申し訳なさそうにうなずいた。
透は考え込んで、やがて静かにうなずき返した。
「わかった。明日は、僕だけで話をしに行くよ」
そう言って、透は目を伏せた。
翌日、透は早朝にゴミを出しに外に出た。
アパートの階段を下りて、そこで壁にもたれて立っている人影に気づく。
人影の正体は宗太だった。射るような目で透を眺めて、それから不自然なほどにこやかに笑う。
透は息を吸って問いかける。
「いつからいらっしゃったんですか?」
「一度は宿に戻りましたよ」
宗太はあまり答えにならない答えを返して、透に歩み寄る。
「麻美は?」
「まだお兄さんとは話せないと。ひとまず僕だけで話をさせてください。喫茶店にでも行きましょう」
「ふん……」
宗太は透を睨むように見たが、ぷいと踵を返して透に続いた。
透の職場近くの喫茶店に入ると、二人はコーヒーを一つずつ注文する。
宗太は透を見据えたまま、コーヒーに手もつけずに切り出す。
「麻美に何をしたんですか」
焦るように机を指先で叩いて、宗太は早口に言う。
「あの子は大人しい子なんです。何かのきっかけで家を出たのはともかく、家族にも黙って結婚するなんて考えられない。あの子の弱さにつけ込むのはよしてください」
透はその言葉を一通り聞いて、彼の感情に呑まれないように答える。
「この結婚は麻美さんと二人で決めたことです。僕は何も強制していません」
「信じられない。麻美は緊張して外食もできないような繊細な子ですよ」
「僕の知る麻美さんは、人と一緒に時間を過ごすのが好きなひとです。結構頑固なところもあります。日高さんが思われるほど、麻美さんは大人しくも弱くもないと思いますが」
「私たち家族は何十年もあの子と一緒にいたんですよ」
「何十年もすれば子どもは大人になります」
宗太の眼差しが一段と尖ったのを感じて、透は口調をゆっくりに変える。
「僕は喧嘩がしたいわけじゃありません。ただ知って頂きたいんです」
「知る?」
「麻美さんは今は戻れないと言っていました。叩かれたときの衝撃が消えてないんです」
宗太はそれを聞いて、頭をくしゃくしゃとかきまぜる。
焦燥に駆られたように宗太は声を荒らげる。
「叩いたのは本当に悪かった。それはあの子に言った通りです。でも麻美は今でも私たちの大切な家族ですし、帰ってきてほしいんです」
必死の眼差しを向ける宗太の前で、透は黙った。
透は深く息をついて口を開く。
「……いつでも、どんなときでも一緒にいることが家族ではないと思います」
宗太は怪訝な顔をして透を見る。
「孤独の陸に上りたいときもある。一人でいたいときがある」
「あの子を一人にはさせておけません」
「無理に連れ戻しても、麻美さんはまた出て行ってしまうでしょう」
断言した透に、宗太は息を呑んだ。
言葉に詰まった宗太の前で、透は頭を下げた。
「でも麻美さんを一人にはしません。僕が側にいます。それを知ってください」
透は黙って頭を下げ続ける。
宗太はしばらく透をみつめて、やがて砕けた調子でつぶやいた。
「君は麻美に同情してるのか」
その言葉に、透は顔を上げて困ったように眉を寄せた。
「同情では、こんなに長く一緒に暮らせないと思います」
透は視線を動かして、また宗太を見る。
透はくすぐったそうに笑って言った。
「僕も最初はただ、一人が嫌だったんです。でもその相手が麻美さんだったから、こんな優しい時間を重ねられた」
透は表情を和らげてゆっくりと告げる。
「麻美さんが好きです」
宗太は今にも掴みかかろうとするように透を睨んだが、それを自分で制するように深く息をついた。
宗太はテーブルの上で拳を強く握りしめる。
「俺が麻美を一人前だと認めてやらなかったから、認めてくれる君のところに行ったんだろうか」
宗太はようやくコーヒーに口をつける。
「……あんなに小さかったのにな」
宗太は悔しそうに、どこか安堵するようにつぶやいた。
「お聞きした通り、いいお兄さんですね」
「君が知るもんか。今もあの子は変わらず、俺たちの家族だ」
宗太はため息をついて、少しやけになったようにコーヒーを飲み干した。
冷気を遮断する引き戸を開けると、見知らぬ男と麻美が向き合っていた。近所にはいない顔だと透が訝しみながら見やると、その男は透を一瞥する。
目が合った瞬間、男は凍てつくような眼差しを透に向けた。
「こんにちは」
次の瞬間にはにっこりと笑って、気さくに挨拶をしてくる。
「日高宗太です。あなたが片桐透さん?」
男の年は透と同じくらいで、モデルのような長身痩躯をしていた。涼やかな目鼻立ちを優しげな微笑みで彩って軽く首を傾げる様は、なかなか絵になる。
ただ目だけは全く笑っていない。それに気づいて、透は警戒心を抱いた。
「ええ。日高ということは、麻美さんの親戚の方ですか」
「夫です」
つと透が眉をひそめると、麻美が振り向いて言う。
「その冗談はやめてって言ってる、兄さん」
「ああ、ごめんごめん」
彼は悪びれずにくすくすと笑って、笑みを収めて透を見る。
「でも彼がお前の夫だというのも、全然笑えない冗談だよ」
「それは冗談じゃないの。籍もちゃんと入ってる」
「麻美」
彼の声は優しい呼びかけだったのに、麻美はびくりと肩を震わせる。
「兄さんが嫌いになった?」
「そういう意味じゃ、ないの」
宗太は後ずさった麻美の腕に手を伸ばす。
「じゃあ言うことを聞きなさい。帰るんだ」
「……待ってください」
宗太の手を押しやって、透は麻美の前に出た。
「嫌いじゃないなら言うことを聞けというのは、ちょっと乱暴ではないですか」
割り込んだ透を見やって、宗太は冷えた声を出す。
「あなたはこの子のことをよく知らないでしょう。麻美は昔から、時々現実逃避をする。そういう時は引き戻してやらないといけないんです」
「昔はそうだったかもしれませんが、今の麻美さんは大人です」
透は部屋の中を示して告げる。
「どうぞお入りになって、座って話してください」
透の言葉に、麻美が切羽詰まった声で遮った。
「だめ。兄さん、今すぐ帰って」
「麻美さん?」
気遣わしげに呼んだ透にも気づかず、麻美は早口で言葉を吐き出す。
「兄さんは嫌い。家族にも二度と会いたくない。ほっといて」
透はそこに頑なな麻美の感情をみつけて口をつぐむ。
透が宗太を振り向くと、宗太は青ざめて立っていた。
「……麻美?」
宗太は信じられないものを見る目で麻美を見下ろす。
「兄さんにそんなこと言ったことないじゃないか。麻美、どうした? 話して」
「帰って!」
麻美は叩きつけるように叫んで、両手で宗太の胸を押しやる。
後は宗太が何を言っても、麻美は「帰って」以外に一言も話さなかった。ただ宗太を扉の外に押し出そうとする麻美に、透は見かねて言った。
「日高さん、携帯番号と宿泊先を教えて頂けますか。ひとまず今日はお互い頭を冷やすことにして、明日こちらから伺わせて頂きます」
宗太もこれ以上は麻美が何も話さないと理解したのか、仕方なさそうに手帳を取り出す。
宗太は手帳を破いてペンを走らせると、透にメモを渡す。
宗太は扉の外に出ると、途方に暮れた顔で麻美を見やる。
「麻美。兄さんは心配だから来ただけだ」
目を逸らしたままの麻美に、宗太はそっと告げる。
「本当だよ。だから帰ってきて」
踵を返して、宗太は自分から扉を閉めた。
透はうつむいたまま立ちすくむ麻美に振り向いて、中を示す。
「中に入って座ろう。……話をゆっくり聞くから」
透が肩に触れても、麻美は全身を強張らせて口を引き結んでいた。
麻美が話し出すには、ずいぶんと時間がかかった。
おせち料理の準備のために代わる代わる台所に立ちながら、いつもとは逆で透から話しかける。
二日ほどかけてゆっくり準備しようと話していたのだが、作業ばかりしていたらその日の夕方の内におせち料理は完成した。
「……話してもいいのかな」
麻美がようやく小声で切り出したのは夜になってからで、透は振り向く。
「麻美さんが話したいなら聞くよ」
透はお茶を淹れて持ってくる。
二人で向き合ってテーブルの前に座った頃、ようやく麻美は息をついて話し出した。
「年が離れてたからか、兄さんはずっと子どもみたいに私を扱ってた」
麻美がテーブルの木目をみつめる眼差しは、頼りなさげだった。
「泣けば抱っこしてくれて、傷つきそうになったらそういうものから私を遠ざけてくれた。優しい兄さん」
透はそんな麻美の表情を眺めながら問う。
「それならどうして、麻美さんはそんなに悲しそうなの」
麻美は喉につっかえたようにごくりと息を呑む。
そのまま麻美は押し黙った。透は話し出す気配も失われたのを感じる。
透は立ち上がって麻美の隣に座る。その背中を抱くと、強張った麻美の背をさすった。
それに促されるように麻美はゆっくりと力を抜いて、喉を動かした。
「……一度だけ、叩かれた」
ようやく麻美から零れ落ちた言葉に、透はぴくりと反応した。
「兄さんの仕事が忙しくなって、顔も合わせない日々が数か月続いたある時、一回だけ。兄さんはすぐ我に返って、いっぱい謝ってくれた」
自分の手をじっと見下ろして、麻美はつぶやく。
「でもなんだかとても……兄さんが遠くに感じて」
目を歪めて、麻美は言葉を落とした。
「周りを見回したら、お父さんもお母さんもおばあちゃんもそう見えた。兄さんも家族もそこにいるのに、それは海の向こうの風景を見てるみたいだった」
頭を片手で押さえて、麻美は苦しそうにつぶやく。
「家族だって変わっていく。ずっと同じなんて、ない」
それでねと麻美は告げる。
「夢を見たくなったの。家族とつながっていた頃の思い出が見られたらと思って」
そう言ったきり、麻美は黙りこくった。
透は彼女の言葉が尽きたのを感じて問いかけた。
「今は、お兄さんと向かい合うことができない?」
透の言葉に、麻美は申し訳なさそうにうなずいた。
透は考え込んで、やがて静かにうなずき返した。
「わかった。明日は、僕だけで話をしに行くよ」
そう言って、透は目を伏せた。
翌日、透は早朝にゴミを出しに外に出た。
アパートの階段を下りて、そこで壁にもたれて立っている人影に気づく。
人影の正体は宗太だった。射るような目で透を眺めて、それから不自然なほどにこやかに笑う。
透は息を吸って問いかける。
「いつからいらっしゃったんですか?」
「一度は宿に戻りましたよ」
宗太はあまり答えにならない答えを返して、透に歩み寄る。
「麻美は?」
「まだお兄さんとは話せないと。ひとまず僕だけで話をさせてください。喫茶店にでも行きましょう」
「ふん……」
宗太は透を睨むように見たが、ぷいと踵を返して透に続いた。
透の職場近くの喫茶店に入ると、二人はコーヒーを一つずつ注文する。
宗太は透を見据えたまま、コーヒーに手もつけずに切り出す。
「麻美に何をしたんですか」
焦るように机を指先で叩いて、宗太は早口に言う。
「あの子は大人しい子なんです。何かのきっかけで家を出たのはともかく、家族にも黙って結婚するなんて考えられない。あの子の弱さにつけ込むのはよしてください」
透はその言葉を一通り聞いて、彼の感情に呑まれないように答える。
「この結婚は麻美さんと二人で決めたことです。僕は何も強制していません」
「信じられない。麻美は緊張して外食もできないような繊細な子ですよ」
「僕の知る麻美さんは、人と一緒に時間を過ごすのが好きなひとです。結構頑固なところもあります。日高さんが思われるほど、麻美さんは大人しくも弱くもないと思いますが」
「私たち家族は何十年もあの子と一緒にいたんですよ」
「何十年もすれば子どもは大人になります」
宗太の眼差しが一段と尖ったのを感じて、透は口調をゆっくりに変える。
「僕は喧嘩がしたいわけじゃありません。ただ知って頂きたいんです」
「知る?」
「麻美さんは今は戻れないと言っていました。叩かれたときの衝撃が消えてないんです」
宗太はそれを聞いて、頭をくしゃくしゃとかきまぜる。
焦燥に駆られたように宗太は声を荒らげる。
「叩いたのは本当に悪かった。それはあの子に言った通りです。でも麻美は今でも私たちの大切な家族ですし、帰ってきてほしいんです」
必死の眼差しを向ける宗太の前で、透は黙った。
透は深く息をついて口を開く。
「……いつでも、どんなときでも一緒にいることが家族ではないと思います」
宗太は怪訝な顔をして透を見る。
「孤独の陸に上りたいときもある。一人でいたいときがある」
「あの子を一人にはさせておけません」
「無理に連れ戻しても、麻美さんはまた出て行ってしまうでしょう」
断言した透に、宗太は息を呑んだ。
言葉に詰まった宗太の前で、透は頭を下げた。
「でも麻美さんを一人にはしません。僕が側にいます。それを知ってください」
透は黙って頭を下げ続ける。
宗太はしばらく透をみつめて、やがて砕けた調子でつぶやいた。
「君は麻美に同情してるのか」
その言葉に、透は顔を上げて困ったように眉を寄せた。
「同情では、こんなに長く一緒に暮らせないと思います」
透は視線を動かして、また宗太を見る。
透はくすぐったそうに笑って言った。
「僕も最初はただ、一人が嫌だったんです。でもその相手が麻美さんだったから、こんな優しい時間を重ねられた」
透は表情を和らげてゆっくりと告げる。
「麻美さんが好きです」
宗太は今にも掴みかかろうとするように透を睨んだが、それを自分で制するように深く息をついた。
宗太はテーブルの上で拳を強く握りしめる。
「俺が麻美を一人前だと認めてやらなかったから、認めてくれる君のところに行ったんだろうか」
宗太はようやくコーヒーに口をつける。
「……あんなに小さかったのにな」
宗太は悔しそうに、どこか安堵するようにつぶやいた。
「お聞きした通り、いいお兄さんですね」
「君が知るもんか。今もあの子は変わらず、俺たちの家族だ」
宗太はため息をついて、少しやけになったようにコーヒーを飲み干した。