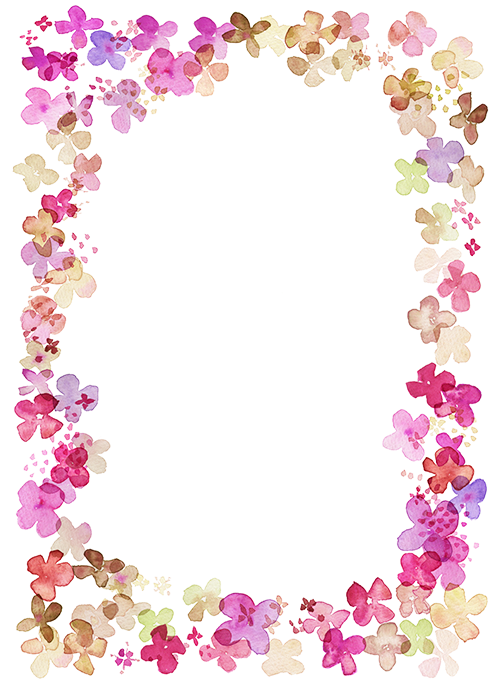楼ヶ町に冬がやって来た。
雪はめったに降らないが、畑に真っ白な霜が降りるようになった。枯葉は細かく散って風にまぎれて、木々は枝だけになっていく。
朝夕と冷えるようになったから、日中の限られた時間しか町の人は外に出てこない。麻美と透も、自然と家にこもりがちになった。
楼ヶ町には会社といえるほど大きなものはないから、年末は決算に急ぐことがなく静かなものだ。休みの前半で年越しの準備をして、後はそれぞれの家でのんびりと過ごす。
年末休みの初日、麻美と透は駅前に出て年越しの買い物をした。掃除道具や締め飾り、おせち料理やお雑煮の材料、二人で買っても両手にいっぱいだった。
家に帰ったら大掃除を始める。麻美はいつもより念入りに水回りの手入れをして、透はすす払いや窓ふきをして、二人で布団やカーテンを干した。
「もうここで半年以上暮らしてきたんだね」
昼下がり、休憩の合間に二人で熱いお茶を飲む。
透の言葉に、麻美はうなずいて言う。
「お互い病気もなく過ごしてこられてよかった」
「うん」
掃除に汗をかいたから、お茶が体に染み渡るようだった。
窓の外の山を見上げながら、透がぽつりとつぶやく。
「……たぶんお正月くらいに、高台で蜃気楼が見られるよ」
麻美は瞬きも忘れて透を見上げる。
それから目を伏せて、麻美は迷うように言った。
「そうなの。でも……もしかしたら見に行かないかも」
透は黙って横目で麻美を見る。
「夢は見られたから、これ以上探さなくてもいいかなって思うの」
透は考える素振りを見せたが、やがてうなずく。
「麻美さんがそう言うなら」
「うん。ありがとう」
麻美は立ち上がってマグカップを片付けに行った。
二人のマグカップは、いつの間にか互いの家から持ってきたものではなく、こちらに来てから麻美がフリーマーケットで買ったものになっている。
透の淡いブルーのマグカップと、麻美の淡いピンクのカップはおそろいだ。
「こっちはそろそろ捨てようかな」
麻美がそう言って分別回収の袋を持ってくる。その袋の中に、麻美の前のマグカップがあった。
マグカップだけではない。服や靴、本も袋に入っている。半年間生活すれば、余分なものも出てくる。
「大丈夫?」
けれど透の口から心配の言葉が零れ落ちた。彼は言ってから、気まずそうに目を逸らす。
透がもう一度目を戻したとき、麻美は困ったように微笑んでいた。
「全部残しておくわけにはいかないから」
「そう、だね」
透は掃除に戻ったが、麻美は彼が部屋の隅に置いた処分用の袋を気にしているのを感じていた。
麻美が以前から持ってきたものを手放す時、透は心配そうな目をする。結婚した初日にダイヤモンドのペンダントを透に渡した時からそうだった。
麻美が楼ヶ町に来る前の生活を捨てたがっていることを、きっと透は気づいている。
透は優しい人だと思う。そんな人に、麻美自身まだ整理がついていないことを話すことはできなかった。
「今晩高校の部活仲間と食事に行ってくる。遅くなるから、夕食は一人で食べてくれる?」
考え事をしていて、麻美は透の言葉に反応が遅れた。
透が誰かと食事に行くのは珍しい。酒が飲めない透はこの年頃の青年にしては珍しく、飲み会といったものに参加することはめったになかった。
「うん。楽しんできて」
麻美が振り向いて告げると、透はうなずく。
二人の距離の取り方は、もう学んだはずだったのに……麻美は少しだけ寂しく感じた。
闇の中で、騒々しい声が聞こえる。
怒鳴るような激しい声もあれば、甲高い笑い声もある。
まただ。麻美は体を小さくして布団を被った。
朝になれば大丈夫。そう思って、早く寝付くために麻美は心の中から余計な考えを振り払う。
でも足音が近づいてきて、麻美は布団の中で肩を跳ねさせた。
扉が開かれる。誰かが部屋に入ってくる。
揺さぶられて、呂律の回らない声で呼ばれる。
鼻をついた匂いに、麻美の中の体温がすべて抜けていく気がした。
体温をなくした空っぽの体を引きずって、麻美は部屋の外に飛び出す。
どこもかしこも同じ匂いがする。嗅ぐたび吐き気がする、麻美にとって大嫌いな匂いが家中に満ちている。
めまいがして、麻美は数歩よろめいた。
どこで、どうやって夜を明かしたのかは覚えていない。
「……麻美、怒っているか」
振り向くと、ぼやけた視界の中で父が立っていた。
「お父さん。酔って帰るのはやめて」
麻美が掠れた声で告げると、父は困ったように返した。
「仕方ない。付き合いだから」
麻美はうつむいて、仕方ないと口の中でつぶやいた。
その言葉を何度となく心で反芻しているうち、麻美の意識は黒く濁っていった。
扉が叩かれる音がして、麻美は真夜中に目を覚ました。
時計を見ると深夜の一時で、眠りについてからまだ二時間も経っていない。
麻美は透が帰ってきたのだろうかと玄関に急ぐ。
扉を開け放った時、覚えのある嫌な匂いがした。
玄関の向こうには、透と彼を支える同級生らしい男性がいた。
「すみません。透に酒飲ましちゃって」
ぐったりして言葉もない透に肩を貸しながら、青年は苦笑交じりに言う。
「奥さん?」
麻美は立ちすくむ。体温が失われて、足元から力が抜けていくようだった。
透たちを中に通そうともしない麻美に、青年は苦笑を深めた。
「怒るのはわかりますけど、付き合いだからしょうがないでしょ」
重いのか、彼は早く中に通してほしそうに促す。
それでも麻美は動かなかった。動けないというのが正しかった。
赤くなった透の顔、濁った目、漂うアルコールの匂い、そういうものすべてが、麻美の意識を濁らせていく。
「浮気したわけでもないし、ちょっと酒飲んだくらいでそう……」
意識が完全に沈む前に、麻美の防衛本能が動いた。
「ちょ、奥さん!」
透と青年を押しやるようにして、麻美は外に飛び出した。
深夜の暗黒に温度はなく、道は氷を踏むようにいびつな音がする。一歩踏み出すたびに違う世界に入って行きそうで、それが怖くて、同時にそれでいいと思った。
あの匂いに満ちた世界には、もう戻りたくない。
ただその一心で、麻美は真冬の最中を駆け続けた。
数刻の後に辿りついたのは、麻美の職場の隣にある院長の家だった。年末でどこも店は閉じていて、頼りにできるのは彼女だけだった。
年末の夜分に突然押しかけたことを詫びる麻美に、院長は気にしないでと言って迎え入れてくれた。
「寒かったでしょう。これでも飲んで」
一人暮らしの院長は、広々としたリビングに麻美を通してお茶を出してくれる。
「旦那さんと喧嘩でもした?」
そっとかけられた問いかけに、麻美はうつむいて話し始めた。
院長は相槌を打ちながら、麻美の話を聞いてくれる。
床暖房で部屋は暖かく、お茶が麻美の内側から熱を取り戻してくれる。
「透さんが酔って帰ってきただけで、その場にいられなくなって」
冷静に考えればそれだけのことだったと、麻美は院長の前で恥ずかしくなる。
院長は頬に手を当てて思案すると、ううん、と口を開く。
「許せないことはあるわ。良い悪いじゃないの」
麻美は顔を上げる。院長は穏やかな眼差しで麻美をみつめていた。
「妥協するかしないかはあなたたちで決めることよ。誰にも、仕方ないだなんて言えないの」
麻美の頭をぽんぽんと叩いて、院長は微笑む。
「今日は泊まっていっていいけど。明日になったら、透さんの話を聞いてあげなさいね」
麻美はうなずいて、その日は院長の家に泊まった。
夜の間に、院長に透から電話があったらしい。麻美は朝食の席でそれを聞いた。
翌日の昼前、透が院長宅を訪れた。
酔いは抜けているようだったが、気分が悪そうで顔に血の気がなかった。まだ時折ふらついていて、麻美は慌てて駆け寄る。
「透さん。家で休んでて」
「まず謝らせてほしいんだ」
「家で聞くから」
「ごめん」
謝罪を繰り返す透に、麻美は言う。
「一緒に帰りましょう」
そう告げた麻美に、透は安堵したように肩から力を抜いた。
帰宅の道中、透は苦々しい口調で話してくれた。
「高校の部活は唯一、人と一緒にスポーツをした時だったから。ついその仲間と久しぶりに会って嬉しくて、勧められるままに飲んでしまった」
透は帰るなり倒れるように横になった。まだ何も食べていなかったらしく、麻美がおかゆを作って枕元に持っていく。
「本当にごめん。麻美さんは酔っぱらいが大嫌いなのはわかってたのに」
麻美が貼った冷却シートを押さえて、透は顔を苦しそうに歪める。
麻美ははっと息を呑んで問いかける。
「どうしてわかったの?」
「お見合いの時に僕がお酒を飲まないって聞いて、すごくほっとした顔をしてた」
麻美は思わず苦笑いをする。そんなにわかりやすい反応をしていたなんて、初めて知った。
「私こそごめんなさい。酔って苦しかった透さんを残して飛び出すなんて」
「ん……うん。あれは確かに効いたな」
透は自分の頭を押さえて髪をくしゃくしゃと混ぜると、言葉を重ねる。
「だからもう二度としないって約束する」
透はおかゆのお椀をテーブルに置いて言う。
「……許してほしい」
深く頭を下げた透に、麻美は黙った。
空になったマグカップに水を入れて持ってくると、麻美はそれを透に差し出す。
「透さんが謝るほど、そんな深刻なことじゃないの」
透はマグカップを受け取って、水を喉に通す音が聞こえた。
「私、お父さんがよく酔って帰ってくる人で」
透は黙って言葉の先を待つ。それに促されて、麻美は続けた。
「何度頼んでもそれを直してくれないから、私の言葉は永遠に届かないような気がして、人と暮らすのが嫌になった。……それが家を出たきっかけ」
麻美はうつむいて自嘲気味に言う。
「人は自分の望むようにしてくれるわけじゃないから、仕方ないのにね」
「でも麻美さんは許せなかった」
顔を上げると、透はまっすぐな目で麻美を見ていた。
「そうなったら一緒には暮らせないよ。当たり前のことだ」
透はまた頭を下げる。
「僕は麻美さんと暮らしていきたい。だから謝るし、直す」
麻美は泣き笑いのような顔で、透の肩に頬を寄せた。
まだお酒の匂いがした。でも麻美は、もうそれを感じても視界が暗くなるような絶望感を抱かずに済んだ。
透の食事を手伝って、一日看病に付き合った。
麻美は母のことを思い出していた。酔って帰る父を、母だって不愉快そうに見ていた。それでも父を許して看病したのは、母は自分より父と一緒にいたい気持ちが強かったからなのだろう。
愛情というのは、どこまで相手のことを許せるかなのかもしれない。
夕方には透の具合もだいぶよくなった。麻美たちは一緒におせち料理の準備を始める。
こんぶ巻を作りながら、透は話を始める。
「家を出たきっかけがお父さんのことだっていうのはわかった。でも麻美さんが実家に帰りたがらないのは、他に理由があると思う」
麻美は向かいの席で栗を剥きながら苦笑した。
「そうだね。もう話さなきゃ……」
麻美が答えようとしたとき、ふいにインターホンが鳴る。
麻美は慌てて立ち上がって言った。
「座ってて。たぶんお向かいの足立さん。煮豆をくれるって言ってくださったから」
反射的に立ち上がろうとした透を制して、麻美は玄関に向かう。
扉を開いた途端に差し込む逆光がまぶしすぎて、麻美は目を閉じてしまった。
「……麻美」
その声を聞いて、麻美は真夏の日差しの中に引きずり出されたような気分がした。
目を開けばカッターシャツ姿の、背の高い男性が立っていた。黒い目が射抜くように麻美を見ている。
硬直した麻美の前で、涼やかな面立ちがくしゃりと歪む。
次の瞬間、麻美は彼の腕の中にいた。
「帰るぞ」
泣く直前のような声で言われて、麻美は立ちすくんだ。
懐かしさと愛情に挟まれた時間が、麻美の中に戻って来ていた。
雪はめったに降らないが、畑に真っ白な霜が降りるようになった。枯葉は細かく散って風にまぎれて、木々は枝だけになっていく。
朝夕と冷えるようになったから、日中の限られた時間しか町の人は外に出てこない。麻美と透も、自然と家にこもりがちになった。
楼ヶ町には会社といえるほど大きなものはないから、年末は決算に急ぐことがなく静かなものだ。休みの前半で年越しの準備をして、後はそれぞれの家でのんびりと過ごす。
年末休みの初日、麻美と透は駅前に出て年越しの買い物をした。掃除道具や締め飾り、おせち料理やお雑煮の材料、二人で買っても両手にいっぱいだった。
家に帰ったら大掃除を始める。麻美はいつもより念入りに水回りの手入れをして、透はすす払いや窓ふきをして、二人で布団やカーテンを干した。
「もうここで半年以上暮らしてきたんだね」
昼下がり、休憩の合間に二人で熱いお茶を飲む。
透の言葉に、麻美はうなずいて言う。
「お互い病気もなく過ごしてこられてよかった」
「うん」
掃除に汗をかいたから、お茶が体に染み渡るようだった。
窓の外の山を見上げながら、透がぽつりとつぶやく。
「……たぶんお正月くらいに、高台で蜃気楼が見られるよ」
麻美は瞬きも忘れて透を見上げる。
それから目を伏せて、麻美は迷うように言った。
「そうなの。でも……もしかしたら見に行かないかも」
透は黙って横目で麻美を見る。
「夢は見られたから、これ以上探さなくてもいいかなって思うの」
透は考える素振りを見せたが、やがてうなずく。
「麻美さんがそう言うなら」
「うん。ありがとう」
麻美は立ち上がってマグカップを片付けに行った。
二人のマグカップは、いつの間にか互いの家から持ってきたものではなく、こちらに来てから麻美がフリーマーケットで買ったものになっている。
透の淡いブルーのマグカップと、麻美の淡いピンクのカップはおそろいだ。
「こっちはそろそろ捨てようかな」
麻美がそう言って分別回収の袋を持ってくる。その袋の中に、麻美の前のマグカップがあった。
マグカップだけではない。服や靴、本も袋に入っている。半年間生活すれば、余分なものも出てくる。
「大丈夫?」
けれど透の口から心配の言葉が零れ落ちた。彼は言ってから、気まずそうに目を逸らす。
透がもう一度目を戻したとき、麻美は困ったように微笑んでいた。
「全部残しておくわけにはいかないから」
「そう、だね」
透は掃除に戻ったが、麻美は彼が部屋の隅に置いた処分用の袋を気にしているのを感じていた。
麻美が以前から持ってきたものを手放す時、透は心配そうな目をする。結婚した初日にダイヤモンドのペンダントを透に渡した時からそうだった。
麻美が楼ヶ町に来る前の生活を捨てたがっていることを、きっと透は気づいている。
透は優しい人だと思う。そんな人に、麻美自身まだ整理がついていないことを話すことはできなかった。
「今晩高校の部活仲間と食事に行ってくる。遅くなるから、夕食は一人で食べてくれる?」
考え事をしていて、麻美は透の言葉に反応が遅れた。
透が誰かと食事に行くのは珍しい。酒が飲めない透はこの年頃の青年にしては珍しく、飲み会といったものに参加することはめったになかった。
「うん。楽しんできて」
麻美が振り向いて告げると、透はうなずく。
二人の距離の取り方は、もう学んだはずだったのに……麻美は少しだけ寂しく感じた。
闇の中で、騒々しい声が聞こえる。
怒鳴るような激しい声もあれば、甲高い笑い声もある。
まただ。麻美は体を小さくして布団を被った。
朝になれば大丈夫。そう思って、早く寝付くために麻美は心の中から余計な考えを振り払う。
でも足音が近づいてきて、麻美は布団の中で肩を跳ねさせた。
扉が開かれる。誰かが部屋に入ってくる。
揺さぶられて、呂律の回らない声で呼ばれる。
鼻をついた匂いに、麻美の中の体温がすべて抜けていく気がした。
体温をなくした空っぽの体を引きずって、麻美は部屋の外に飛び出す。
どこもかしこも同じ匂いがする。嗅ぐたび吐き気がする、麻美にとって大嫌いな匂いが家中に満ちている。
めまいがして、麻美は数歩よろめいた。
どこで、どうやって夜を明かしたのかは覚えていない。
「……麻美、怒っているか」
振り向くと、ぼやけた視界の中で父が立っていた。
「お父さん。酔って帰るのはやめて」
麻美が掠れた声で告げると、父は困ったように返した。
「仕方ない。付き合いだから」
麻美はうつむいて、仕方ないと口の中でつぶやいた。
その言葉を何度となく心で反芻しているうち、麻美の意識は黒く濁っていった。
扉が叩かれる音がして、麻美は真夜中に目を覚ました。
時計を見ると深夜の一時で、眠りについてからまだ二時間も経っていない。
麻美は透が帰ってきたのだろうかと玄関に急ぐ。
扉を開け放った時、覚えのある嫌な匂いがした。
玄関の向こうには、透と彼を支える同級生らしい男性がいた。
「すみません。透に酒飲ましちゃって」
ぐったりして言葉もない透に肩を貸しながら、青年は苦笑交じりに言う。
「奥さん?」
麻美は立ちすくむ。体温が失われて、足元から力が抜けていくようだった。
透たちを中に通そうともしない麻美に、青年は苦笑を深めた。
「怒るのはわかりますけど、付き合いだからしょうがないでしょ」
重いのか、彼は早く中に通してほしそうに促す。
それでも麻美は動かなかった。動けないというのが正しかった。
赤くなった透の顔、濁った目、漂うアルコールの匂い、そういうものすべてが、麻美の意識を濁らせていく。
「浮気したわけでもないし、ちょっと酒飲んだくらいでそう……」
意識が完全に沈む前に、麻美の防衛本能が動いた。
「ちょ、奥さん!」
透と青年を押しやるようにして、麻美は外に飛び出した。
深夜の暗黒に温度はなく、道は氷を踏むようにいびつな音がする。一歩踏み出すたびに違う世界に入って行きそうで、それが怖くて、同時にそれでいいと思った。
あの匂いに満ちた世界には、もう戻りたくない。
ただその一心で、麻美は真冬の最中を駆け続けた。
数刻の後に辿りついたのは、麻美の職場の隣にある院長の家だった。年末でどこも店は閉じていて、頼りにできるのは彼女だけだった。
年末の夜分に突然押しかけたことを詫びる麻美に、院長は気にしないでと言って迎え入れてくれた。
「寒かったでしょう。これでも飲んで」
一人暮らしの院長は、広々としたリビングに麻美を通してお茶を出してくれる。
「旦那さんと喧嘩でもした?」
そっとかけられた問いかけに、麻美はうつむいて話し始めた。
院長は相槌を打ちながら、麻美の話を聞いてくれる。
床暖房で部屋は暖かく、お茶が麻美の内側から熱を取り戻してくれる。
「透さんが酔って帰ってきただけで、その場にいられなくなって」
冷静に考えればそれだけのことだったと、麻美は院長の前で恥ずかしくなる。
院長は頬に手を当てて思案すると、ううん、と口を開く。
「許せないことはあるわ。良い悪いじゃないの」
麻美は顔を上げる。院長は穏やかな眼差しで麻美をみつめていた。
「妥協するかしないかはあなたたちで決めることよ。誰にも、仕方ないだなんて言えないの」
麻美の頭をぽんぽんと叩いて、院長は微笑む。
「今日は泊まっていっていいけど。明日になったら、透さんの話を聞いてあげなさいね」
麻美はうなずいて、その日は院長の家に泊まった。
夜の間に、院長に透から電話があったらしい。麻美は朝食の席でそれを聞いた。
翌日の昼前、透が院長宅を訪れた。
酔いは抜けているようだったが、気分が悪そうで顔に血の気がなかった。まだ時折ふらついていて、麻美は慌てて駆け寄る。
「透さん。家で休んでて」
「まず謝らせてほしいんだ」
「家で聞くから」
「ごめん」
謝罪を繰り返す透に、麻美は言う。
「一緒に帰りましょう」
そう告げた麻美に、透は安堵したように肩から力を抜いた。
帰宅の道中、透は苦々しい口調で話してくれた。
「高校の部活は唯一、人と一緒にスポーツをした時だったから。ついその仲間と久しぶりに会って嬉しくて、勧められるままに飲んでしまった」
透は帰るなり倒れるように横になった。まだ何も食べていなかったらしく、麻美がおかゆを作って枕元に持っていく。
「本当にごめん。麻美さんは酔っぱらいが大嫌いなのはわかってたのに」
麻美が貼った冷却シートを押さえて、透は顔を苦しそうに歪める。
麻美ははっと息を呑んで問いかける。
「どうしてわかったの?」
「お見合いの時に僕がお酒を飲まないって聞いて、すごくほっとした顔をしてた」
麻美は思わず苦笑いをする。そんなにわかりやすい反応をしていたなんて、初めて知った。
「私こそごめんなさい。酔って苦しかった透さんを残して飛び出すなんて」
「ん……うん。あれは確かに効いたな」
透は自分の頭を押さえて髪をくしゃくしゃと混ぜると、言葉を重ねる。
「だからもう二度としないって約束する」
透はおかゆのお椀をテーブルに置いて言う。
「……許してほしい」
深く頭を下げた透に、麻美は黙った。
空になったマグカップに水を入れて持ってくると、麻美はそれを透に差し出す。
「透さんが謝るほど、そんな深刻なことじゃないの」
透はマグカップを受け取って、水を喉に通す音が聞こえた。
「私、お父さんがよく酔って帰ってくる人で」
透は黙って言葉の先を待つ。それに促されて、麻美は続けた。
「何度頼んでもそれを直してくれないから、私の言葉は永遠に届かないような気がして、人と暮らすのが嫌になった。……それが家を出たきっかけ」
麻美はうつむいて自嘲気味に言う。
「人は自分の望むようにしてくれるわけじゃないから、仕方ないのにね」
「でも麻美さんは許せなかった」
顔を上げると、透はまっすぐな目で麻美を見ていた。
「そうなったら一緒には暮らせないよ。当たり前のことだ」
透はまた頭を下げる。
「僕は麻美さんと暮らしていきたい。だから謝るし、直す」
麻美は泣き笑いのような顔で、透の肩に頬を寄せた。
まだお酒の匂いがした。でも麻美は、もうそれを感じても視界が暗くなるような絶望感を抱かずに済んだ。
透の食事を手伝って、一日看病に付き合った。
麻美は母のことを思い出していた。酔って帰る父を、母だって不愉快そうに見ていた。それでも父を許して看病したのは、母は自分より父と一緒にいたい気持ちが強かったからなのだろう。
愛情というのは、どこまで相手のことを許せるかなのかもしれない。
夕方には透の具合もだいぶよくなった。麻美たちは一緒におせち料理の準備を始める。
こんぶ巻を作りながら、透は話を始める。
「家を出たきっかけがお父さんのことだっていうのはわかった。でも麻美さんが実家に帰りたがらないのは、他に理由があると思う」
麻美は向かいの席で栗を剥きながら苦笑した。
「そうだね。もう話さなきゃ……」
麻美が答えようとしたとき、ふいにインターホンが鳴る。
麻美は慌てて立ち上がって言った。
「座ってて。たぶんお向かいの足立さん。煮豆をくれるって言ってくださったから」
反射的に立ち上がろうとした透を制して、麻美は玄関に向かう。
扉を開いた途端に差し込む逆光がまぶしすぎて、麻美は目を閉じてしまった。
「……麻美」
その声を聞いて、麻美は真夏の日差しの中に引きずり出されたような気分がした。
目を開けばカッターシャツ姿の、背の高い男性が立っていた。黒い目が射抜くように麻美を見ている。
硬直した麻美の前で、涼やかな面立ちがくしゃりと歪む。
次の瞬間、麻美は彼の腕の中にいた。
「帰るぞ」
泣く直前のような声で言われて、麻美は立ちすくんだ。
懐かしさと愛情に挟まれた時間が、麻美の中に戻って来ていた。