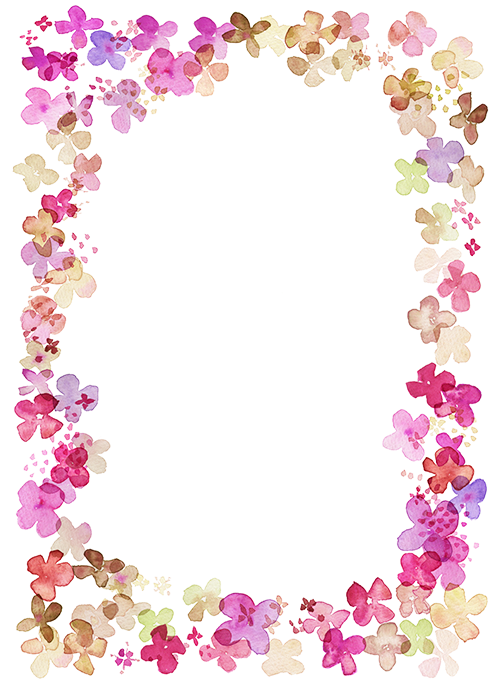もやがかかったような風景の中、麻美は立っていた。
かろうじてわかるのは、室内ということくらいだった。どこも色が混じりあって、触れようとすると崩れていってしまう。
まるで砂で作った家の中にいるみたい。麻美はそう思った。
声が聞こえた気がして、麻美は顔を上げる。
数歩先の椅子に誰かが座っている。その椅子がずいぶん高いところに見えて、麻美は自分の身長がいつもの半分ほどもないことに気づいた。
椅子に近づいて、麻美はその人の膝に顔を埋める。
「おかあさん」
言葉が形になるように、懐かしい匂いが麻美を包み込んだ。
麻美は頬に触れるぬくもりにまどろむ。
綿のTシャツとその下にある硬い肌の感触が、いつの間にか馴染み深くなっている。
見上げると、眠そうに目をまたたかせている透の顔があった。
外はすっかり太陽が昇っている。麻美は寝過ごしてしまったと思ったが、今日は休日だということに思い当る。
季節は夏の終わり。夕べは少し暑さが緩んで、そのありがたみを噛みしめるように二人は早々に床についたのだった。
やがてどちらともなく起き上がって身支度を始める。
「麻美さんが布団に入って来てること、起きるまで気づかなかった」
朝食の席で、透はまだ目を擦りながら言い出す。
その言葉に、麻美は苦笑して謝った。
「ごめんなさい。暑かった?」
「いいよ。最近はこれが普通だから」
二人が一緒に暮らし始めて、一つの季節が過ぎようとしていた。二人の話し方も砕けた調子になってきている。透の口数も、少し増えた気がする。
いくつかお互いのことも知るようになっていた。麻美はしょうゆ味が好きで透は辛いものが好き、麻美は夜更かしが苦手で透は朝が弱い、そういうことが生活している内にお互いに伝わるようになった。
「透さんって、オイルの匂いがする」
何気なくつぶやいた麻美に、透は自分の腕を持ち上げて鼻を近づけた。
「車ばかり触ってるからかな。気になる?」
「ううん。その匂い、好き」
透は黙って、その腕をどうしようかと迷うように動かしてからテーブルの上に戻した。
それから麻美がコーヒーを淹れてきて二人でそれを飲む。
湯気の中に沈黙が漂う。
数だけ数えるなら、お互い知らないことの方がたぶんずっと多い。それでも毎日は淡々と過ぎていく。
休日の午前中は、二人で掃除をする。午後はそれぞれ自由に過ごすと決めていた。
午後、麻美は喫茶店に行って本を読む。その日の気分で注文した飲み物を片手に、古書店で買ってきた本のページをめくる。
透が休日の午後にどうしているのか、麻美は知らなかった。透は家にいる時もあるし、出かけている時もある。
ただ麻美は三時を過ぎる頃には喫茶店を出て、町を散策することにしていた。そして狭い町だからか、家に帰るまでにどこかで透と合流する。
その日も麻美は喫茶店で本を読んで、移動スーパーで買い物をした。それで帰宅する途中、公営プールの前で透とばったり出会った。
透が肩に引っかけた袋からはバスタオルが覗いていた。短い黒髪が濡れていて、今さっきまで泳いでいたらしかった。
自然と二人で並んで歩き始めながら、麻美は問いかける。
「透さんは水泳が好きなの?」
「うん。黙々と体を動かすことが好きなんだ。人といるのは苦手だから、一人でできるスポーツばかりしてるけど」
駅前で道路が整備されているから、コンクリートの照り返しがきつかった。麻美は帽子を深く被り直す。
透は大丈夫だろうかと見上げた。だがすっかり日焼けした透は、夏の終わり程度の残光はそれほど辛くないようだった。
透は麻美の視線に気づいて問いかける。
「麻美さん、暑い?」
「そうね」
楼ヶ町は起伏の大きな土地だ。だから家同士の距離がずいぶんと離れていて、満足な道もないことが多い。
素直に答えた麻美に、透は言葉を続ける。
「持とうか」
透は麻美が下げていた買い物袋を手に取ろうとする。
「……大丈夫。これくらい自分で持てなくちゃ」
でも麻美はそう言って断った。
透は少し考え込んだようで、ちらと麻美を見てから前に向き直った。
家に着いたら透は洗濯物を取り込んで、麻美は夕食の支度を始めた。
冷しゃぶとオクラのサラダ、中華スープの晩御飯を、二人向き合って食べる。
「さっぱりしてておいしい」
透の言葉に、麻美はうなずく。
決まりを作ったわけではないが、夕食を作ってもらった方は一言感想を告げるようになっている。
「今晩は神社で縁日があるけど、行ってみる?」
「うん」
皿洗いをしながら透が投げかけた誘いに、麻美はうなずいた。
七時過ぎに神社に着いた時には、縁日は始まっていた。境内を下りた坂道には屋台が並んで、その前を人が行き交う。
水槽の中を熱帯魚が泳いでいくのを覗いているようだった。
薄闇の中を提灯が照らし出す淡い景色は幻想的だが、人のざわめきや食べ物の香りを感じると、ここが現実だと思い出す。
麻美と透は食事をするでもなく、屋台の出し物に参加するでもなく、ただ二人ぶらぶらと歩いていた。
ふいに雨が降り始めて、麻美は立ちすくむ。
「こっち」
透に呼ばれて、麻美と透は神社の大木の下に入る。そこには既に何人かが雨宿りをしていた。
「透?」
そうしたら透と同年代ほどの青年に声をかけられて、透が顔を上げる。
透は麻美に振り向いて、「高校の同級生」とつぶやくように教える。麻美は反射的に会釈をした。
青年は麻美を見やって、ちょっと動揺したように言った。
「あ、彼女?」
「妻だよ。一月くらい前に結婚した」
「えっ?」
彼は透の言葉に、身を引くようにして驚く。
「いつの間に? ていうか、そんな話全然聞いてないし」
「職場の上司にしか伝えてないから」
「おい、結婚ってそんな簡単なもんじゃないだろ。もっと周りにお披露目するとか」
何かに気づいたように彼は声をひそめる。
「まさかとは思うけど、お前、彼女の両親にも挨拶してない?」
「ああ」
「そりゃ駄目だろ!」
その辺りで、麻美は言葉を挟もうと決めた。
「いいんです。お互いよく話はしてます」
少し強引に拒絶した麻美を、透はちらと見る。
青年はまた驚いて目を見開いた。
「な、何か事情でも? あ、話したくないことなら訊かないけど」
「大丈夫です。そんな深刻なことじゃありません」
麻美は微笑んで、けれどそれ以上話そうとはしなかった。
線引きされたことに気づいたらしく、青年は気まずそうな顔になる。
「まあ最後は二人で決めることなんだろうけど。周りにお祝いする機会くらいは作ってくれてもいいんじゃないかなぁ」
彼はぽつりとつぶやいて、じゃあと言って去って行く。
雨はもう上がっていたが、二人だけはまだ木の下に立っていた。
二人は黙って境内の下で再開された縁日の様子を見ていた。
光があるところ、賑やかなところに人は集まる。だけど、麻美は木の下を動く気にならない。
「透さんは行ってきていいよ」
麻美は言外に自分はここに残ると伝える。
「ここがいいんだ」
透はそっけないほどにあっさりと答えて、また黙りこくる。
人がいなくなっても、ずいぶん長いこと、二人はそこに立っていた。
やがて人目を避けるように神社の裏手を回って、二人は帰って行った。
和室に布団を二つ並べて、透と麻美は床につく。
「実は今朝、夢を見たの」
麻美の声を聞いて、透は麻美の方に体を向ける。
「お母さんの膝に顔を埋めたの。ただそれだけ」
「いい夢だった?」
暗闇の中にため息をつくようにして、麻美は息を細く吐き出す。
「それができたのは幼い頃だけだから。今は見られない光景を見たのは、いいことなのか悪いことなのか」
「麻美さんはどう思ったの?」
麻美は天井を眺めながら黙ると、口元を綻ばせる。
「……嬉しかった」
言ってから実感が迫ってきて、麻美の口から言葉が次々と溢れる。
「お母さんに持ってる感情は一つじゃない。弟が生まれてからは弟に掛かりきりで、寂しい思いをしたこともたくさんある。でも懐かしいって気持ちは、切ないけど温かい」
透は暗闇の中で麻美を探すように目を細めて言う。
「それならきっといい夢だね」
「うん。透さんがおまじないをしてくれたおかげだね。ありがとう」
麻美と透は手探りでお互いの手をみつけた。
また沈黙が立ち込める中で、透は切り出す。
「最近思う。麻美さんは、独り立ちがしたかったんだなって」
それを聞いて麻美は苦笑いを浮かべる。
「意地を張ってるって、よく言われた。可愛げがない、とも」
「いいんじゃないかな。僕はよく、面白味がないって言われたし」
透は生真面目な口調で続ける。
「でも一人ではいたくなかった。麻美さんもそう見える」
きっと透でない他の誰かが同じことを言ったなら、麻美は苛立っただろうと思った。
独り立ちはしたい。でも、一人ではいたくない。
甘えたくない。けれど寄り添いたい。
「それでいいんだよ」
矛盾するような二つの願い事なのに、透と一緒にいるとどちらも満たされた。
麻美は手を伸ばして、透の頭にそっと触れる。
「そうだね。……透さんも、いい夢が見られますように」
自然と麻美も透におまじないをかけていた。
「ありがとう」
透は目を閉じて息を漏らす。
透が笑ったことに気づいて、麻美も安らいだ気持ちで眠りについた。
かろうじてわかるのは、室内ということくらいだった。どこも色が混じりあって、触れようとすると崩れていってしまう。
まるで砂で作った家の中にいるみたい。麻美はそう思った。
声が聞こえた気がして、麻美は顔を上げる。
数歩先の椅子に誰かが座っている。その椅子がずいぶん高いところに見えて、麻美は自分の身長がいつもの半分ほどもないことに気づいた。
椅子に近づいて、麻美はその人の膝に顔を埋める。
「おかあさん」
言葉が形になるように、懐かしい匂いが麻美を包み込んだ。
麻美は頬に触れるぬくもりにまどろむ。
綿のTシャツとその下にある硬い肌の感触が、いつの間にか馴染み深くなっている。
見上げると、眠そうに目をまたたかせている透の顔があった。
外はすっかり太陽が昇っている。麻美は寝過ごしてしまったと思ったが、今日は休日だということに思い当る。
季節は夏の終わり。夕べは少し暑さが緩んで、そのありがたみを噛みしめるように二人は早々に床についたのだった。
やがてどちらともなく起き上がって身支度を始める。
「麻美さんが布団に入って来てること、起きるまで気づかなかった」
朝食の席で、透はまだ目を擦りながら言い出す。
その言葉に、麻美は苦笑して謝った。
「ごめんなさい。暑かった?」
「いいよ。最近はこれが普通だから」
二人が一緒に暮らし始めて、一つの季節が過ぎようとしていた。二人の話し方も砕けた調子になってきている。透の口数も、少し増えた気がする。
いくつかお互いのことも知るようになっていた。麻美はしょうゆ味が好きで透は辛いものが好き、麻美は夜更かしが苦手で透は朝が弱い、そういうことが生活している内にお互いに伝わるようになった。
「透さんって、オイルの匂いがする」
何気なくつぶやいた麻美に、透は自分の腕を持ち上げて鼻を近づけた。
「車ばかり触ってるからかな。気になる?」
「ううん。その匂い、好き」
透は黙って、その腕をどうしようかと迷うように動かしてからテーブルの上に戻した。
それから麻美がコーヒーを淹れてきて二人でそれを飲む。
湯気の中に沈黙が漂う。
数だけ数えるなら、お互い知らないことの方がたぶんずっと多い。それでも毎日は淡々と過ぎていく。
休日の午前中は、二人で掃除をする。午後はそれぞれ自由に過ごすと決めていた。
午後、麻美は喫茶店に行って本を読む。その日の気分で注文した飲み物を片手に、古書店で買ってきた本のページをめくる。
透が休日の午後にどうしているのか、麻美は知らなかった。透は家にいる時もあるし、出かけている時もある。
ただ麻美は三時を過ぎる頃には喫茶店を出て、町を散策することにしていた。そして狭い町だからか、家に帰るまでにどこかで透と合流する。
その日も麻美は喫茶店で本を読んで、移動スーパーで買い物をした。それで帰宅する途中、公営プールの前で透とばったり出会った。
透が肩に引っかけた袋からはバスタオルが覗いていた。短い黒髪が濡れていて、今さっきまで泳いでいたらしかった。
自然と二人で並んで歩き始めながら、麻美は問いかける。
「透さんは水泳が好きなの?」
「うん。黙々と体を動かすことが好きなんだ。人といるのは苦手だから、一人でできるスポーツばかりしてるけど」
駅前で道路が整備されているから、コンクリートの照り返しがきつかった。麻美は帽子を深く被り直す。
透は大丈夫だろうかと見上げた。だがすっかり日焼けした透は、夏の終わり程度の残光はそれほど辛くないようだった。
透は麻美の視線に気づいて問いかける。
「麻美さん、暑い?」
「そうね」
楼ヶ町は起伏の大きな土地だ。だから家同士の距離がずいぶんと離れていて、満足な道もないことが多い。
素直に答えた麻美に、透は言葉を続ける。
「持とうか」
透は麻美が下げていた買い物袋を手に取ろうとする。
「……大丈夫。これくらい自分で持てなくちゃ」
でも麻美はそう言って断った。
透は少し考え込んだようで、ちらと麻美を見てから前に向き直った。
家に着いたら透は洗濯物を取り込んで、麻美は夕食の支度を始めた。
冷しゃぶとオクラのサラダ、中華スープの晩御飯を、二人向き合って食べる。
「さっぱりしてておいしい」
透の言葉に、麻美はうなずく。
決まりを作ったわけではないが、夕食を作ってもらった方は一言感想を告げるようになっている。
「今晩は神社で縁日があるけど、行ってみる?」
「うん」
皿洗いをしながら透が投げかけた誘いに、麻美はうなずいた。
七時過ぎに神社に着いた時には、縁日は始まっていた。境内を下りた坂道には屋台が並んで、その前を人が行き交う。
水槽の中を熱帯魚が泳いでいくのを覗いているようだった。
薄闇の中を提灯が照らし出す淡い景色は幻想的だが、人のざわめきや食べ物の香りを感じると、ここが現実だと思い出す。
麻美と透は食事をするでもなく、屋台の出し物に参加するでもなく、ただ二人ぶらぶらと歩いていた。
ふいに雨が降り始めて、麻美は立ちすくむ。
「こっち」
透に呼ばれて、麻美と透は神社の大木の下に入る。そこには既に何人かが雨宿りをしていた。
「透?」
そうしたら透と同年代ほどの青年に声をかけられて、透が顔を上げる。
透は麻美に振り向いて、「高校の同級生」とつぶやくように教える。麻美は反射的に会釈をした。
青年は麻美を見やって、ちょっと動揺したように言った。
「あ、彼女?」
「妻だよ。一月くらい前に結婚した」
「えっ?」
彼は透の言葉に、身を引くようにして驚く。
「いつの間に? ていうか、そんな話全然聞いてないし」
「職場の上司にしか伝えてないから」
「おい、結婚ってそんな簡単なもんじゃないだろ。もっと周りにお披露目するとか」
何かに気づいたように彼は声をひそめる。
「まさかとは思うけど、お前、彼女の両親にも挨拶してない?」
「ああ」
「そりゃ駄目だろ!」
その辺りで、麻美は言葉を挟もうと決めた。
「いいんです。お互いよく話はしてます」
少し強引に拒絶した麻美を、透はちらと見る。
青年はまた驚いて目を見開いた。
「な、何か事情でも? あ、話したくないことなら訊かないけど」
「大丈夫です。そんな深刻なことじゃありません」
麻美は微笑んで、けれどそれ以上話そうとはしなかった。
線引きされたことに気づいたらしく、青年は気まずそうな顔になる。
「まあ最後は二人で決めることなんだろうけど。周りにお祝いする機会くらいは作ってくれてもいいんじゃないかなぁ」
彼はぽつりとつぶやいて、じゃあと言って去って行く。
雨はもう上がっていたが、二人だけはまだ木の下に立っていた。
二人は黙って境内の下で再開された縁日の様子を見ていた。
光があるところ、賑やかなところに人は集まる。だけど、麻美は木の下を動く気にならない。
「透さんは行ってきていいよ」
麻美は言外に自分はここに残ると伝える。
「ここがいいんだ」
透はそっけないほどにあっさりと答えて、また黙りこくる。
人がいなくなっても、ずいぶん長いこと、二人はそこに立っていた。
やがて人目を避けるように神社の裏手を回って、二人は帰って行った。
和室に布団を二つ並べて、透と麻美は床につく。
「実は今朝、夢を見たの」
麻美の声を聞いて、透は麻美の方に体を向ける。
「お母さんの膝に顔を埋めたの。ただそれだけ」
「いい夢だった?」
暗闇の中にため息をつくようにして、麻美は息を細く吐き出す。
「それができたのは幼い頃だけだから。今は見られない光景を見たのは、いいことなのか悪いことなのか」
「麻美さんはどう思ったの?」
麻美は天井を眺めながら黙ると、口元を綻ばせる。
「……嬉しかった」
言ってから実感が迫ってきて、麻美の口から言葉が次々と溢れる。
「お母さんに持ってる感情は一つじゃない。弟が生まれてからは弟に掛かりきりで、寂しい思いをしたこともたくさんある。でも懐かしいって気持ちは、切ないけど温かい」
透は暗闇の中で麻美を探すように目を細めて言う。
「それならきっといい夢だね」
「うん。透さんがおまじないをしてくれたおかげだね。ありがとう」
麻美と透は手探りでお互いの手をみつけた。
また沈黙が立ち込める中で、透は切り出す。
「最近思う。麻美さんは、独り立ちがしたかったんだなって」
それを聞いて麻美は苦笑いを浮かべる。
「意地を張ってるって、よく言われた。可愛げがない、とも」
「いいんじゃないかな。僕はよく、面白味がないって言われたし」
透は生真面目な口調で続ける。
「でも一人ではいたくなかった。麻美さんもそう見える」
きっと透でない他の誰かが同じことを言ったなら、麻美は苛立っただろうと思った。
独り立ちはしたい。でも、一人ではいたくない。
甘えたくない。けれど寄り添いたい。
「それでいいんだよ」
矛盾するような二つの願い事なのに、透と一緒にいるとどちらも満たされた。
麻美は手を伸ばして、透の頭にそっと触れる。
「そうだね。……透さんも、いい夢が見られますように」
自然と麻美も透におまじないをかけていた。
「ありがとう」
透は目を閉じて息を漏らす。
透が笑ったことに気づいて、麻美も安らいだ気持ちで眠りについた。