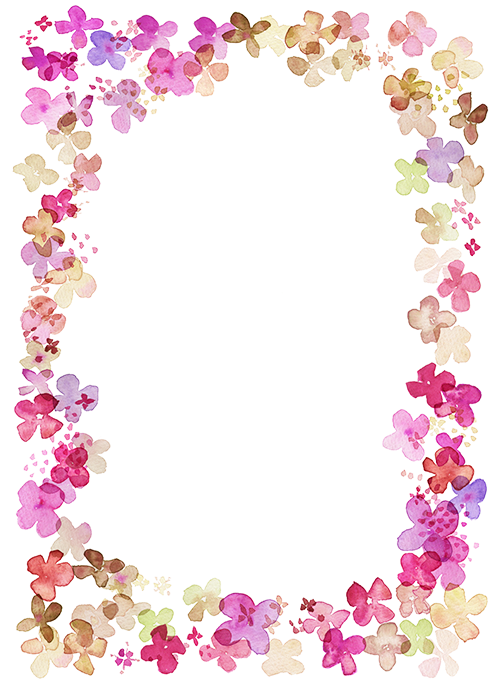麻美が楼ヶ町に引っ越してきたのは、六月の終わりのことだった。
山間に畑と小さな工房が点在する楼ヶ町は、蜃気楼が見える町として評判だった。もっとも麻美がやって来た頃は蜃気楼が発生する季節ではなく、蜃気楼を除けばこの町はどこにでもある田舎町だった。
ただ、高台から覗き込んだ楼ヶ町はぽつねんとしていて、雨に霞んで何もかもが淡く見えた。
ここがいい。麻美は微笑んで、けぶる雨を頬に受けながら天を仰いだ。
アパートを借りて、グループホームの職員の仕事に就いた。慌ただしく、暮らしが始まった。
そうして一月が過ぎる頃、麻美は透と知り合った。
楼ヶ町の自動車整備工場で働く透は、大柄で無口な青年だった。世話焼きの麻美の上司と、やはり世話焼きの透の上司が計らって、二人はお見合いをすることになった。
麻美は二十一歳で、透は二十八歳。似合いだろうと上司たちは勧めたが、今の時代お互い結婚を焦るほどの年でもない。
透の上司が話したところによれば、透は自分で家事もできて継ぐべき家業もないらしい。
この人はたぶん、結婚を急いでいない。そう思えたことがかえって、麻美を安心させた。
お見合いの日も雨が降っていた。
透は口数が少なく、二人きりになってからもしばらく無言で懐石をつついていた。
「……麻美さんは」
ふいに低い声で切り出した透に、麻美は首を傾げる。
「あまりしゃべりませんね」
麻美は少し考える。迷いながら、思った通りのことをそのまま答える。
「得意ではなくて」
沈黙が流れる。
麻美はその間が不愉快ではなかった。透のまとう温度は麻美に近くて、それが麻美を安心させた。
透は体格がいいからか、あっという間に食事を平らげてしまっていた。その中で梅酒のグラスだけは手もつけずに残っているのに気づいて、麻美は問いかける。
「透さんは梅酒が嫌いですか?」
「僕、お酒は飲めないんです」
また沈黙が流れる。そして半刻ほどが過ぎる。
透は決心したようにうなずいて口を開いた。
「僕と、結婚を前提にお付き合いして頂けませんか」
麻美は箸を置いて、テーブルの向こうへ言葉を投げかける。
「お付き合いの時間は必要ですか?」
首を傾げた透に、麻美はそっと告げる。
「私はすぐに結婚しても構いません」
透は黒々とした目でじっと麻美をみつめて、一拍だけ考え込んだように見えた。
「……では、結婚しましょう」
にこりともせずに透は告げた。
駆け引きもなく、突き放すでもない。初めて見た楼ヶ町のように輪郭が淡くぼやけて混ざっているような、不思議な一体感が二人の間にあった。
「はい」
それが心地よくて、麻美は微笑んでうなずいた。
麻美と透が婚姻届を出したのは、それから三日の後のことだった。
お見合いの紹介をした上司たちさえ少し時間を置いたらと勧めたが、二人は町役場へ行った足でお互いの新居も探しに行った。
築三十年の2LDK、家賃は七万円。前の住人の家具が残っているし、二人暮らしならそれで十分生活できるだろうと、二つ返事で契約を決めた。
また三日の後、麻美と透は新居に引っ越してきた。
二人とも黙々と荷ほどきをする。荷物といえるほどのものはなかった。透は段ボール一つ分、麻美に至っては三日分ほどのトラベルセット程度だった。
透はふいに麻美の方に顔を向けて言う。
「そろそろ食事に行きませんか」
一時間ほどで荷物は片付いていて、麻美もうなずいた。
「透さん、何か食べたいものは?」
「喫茶店くらいで大丈夫です」
外に出て二人、畑の隙間にねじこんだような曲がりくねった道を歩く。
太陽はまだ低いところにあった。時折、お年寄りがゆっくりとすれ違っていく。
二人は透の職場のすぐ近くにある喫茶店に入る。
時間帯が早いからか、メニューは朝食セットだけだった。それを注文すると、コーヒーとゆで卵とサンドイッチが出てくる。
カップを温めてあるからか、コーヒーからは白い湯気が立ち上る。麻美はほろ苦い香りと共に湯気を吸いこんで息をつく。
「透さんは、ここにはよく来るんですか?」
麻美が声をかけたのは、食事も半ばに入っていた頃だった。
透はいや、と声を上げて答える。
「ここに来たのは二度目です。昼はいつも宅配のお弁当ですから、外食というのもほとんどなくて」
「休日は?」
「買っておいたパンに残り物を挟んで、という感じです」
透は淡く笑って付け加えた。
「けど、これからは二人ですから。もうちょっとがんばります」
麻美も苦笑して、私もがんばりますとうなずき返した。
透はそれきりほとんど話さず、麻美が話すのに相槌を打っている程度だった。そのテンポが、麻美にはちょうどよかった。
喫茶店を出た時には、太陽は高く昇っていた。
山間に家々や木立が並ぶ。初めて見た楼ヶ町の景色は絵の具を混ぜ合わせたように現実味がなかったが、眩しい太陽の元だとどこもくっきりしていて生活感が溢れる。
「ここで本当に見えるんでしょうか」
ぽつりとつぶやいた麻美に、透は振り向く。
「蜃気楼が見たいですか?」
麻美の問いかけは何もかも足りない言葉だったのに、透の返事は麻美の心を読み取ったみたいに的確だった。
麻美はうなずこうとして口をつぐむ。
黙りこくった麻美に、透はそれ以上追及しようとしなかった。
「見える季節になったら教えますよ。そんなに遠くない未来に見えます」
透はそう告げて、先に立って帰路を辿り始めた。
昼からは雑貨屋で生活に必要なものを買い足して、スーパーで三日分ほどの食材を買ってきた。
家に戻ってからは二人で掃除をした。特にお互い相談したわけではなかったが、麻美は風呂場とトイレ掃除、透は窓拭きや床拭きを始めた。
それが終わったら、透は夕食の下ごしらえに取り掛かった。包丁の使い方や手際の良さから、聞いた通り透は自炊ができるようだった。
「いただきます」
食卓には豚のしょうが焼きと芋サラダ、味噌汁が並んでいた。
麻美は箸を取って夕食を口にする。透もテーブルの向かい側で食べ始める。
「おいしいです」
「よかった」
麻美の感想も、透の返答もそれだけだった。
お見合いの時以上に会話が少ない。でも少しだけ笑った透が、麻美を温かい気持ちにさせた。
今度は麻美が夕食の後片付けをして、麻美たちはお互いの家から持ってきたそれぞれのマグカップにお茶を淹れる。
麻美は窓から入り込む風を感じながら言った。
「朝食は私が作りますね」
「いつもじゃなくていいですよ。順々に」
透はそう答えて、食事のこと、掃除のこと、ゴミ出しのこと、そういう話を淡々と二人で相談した。
お茶を飲み終わると、麻美は先にお風呂を使った。
その後透がお風呂に入っている間、麻美は窓辺に座って空を眺めていた。
夏の宵は暮れゆくのが遅く、ゆるゆると更けていく。
「冷えますよ」
見上げると、透がカーディガンを差し出していた。お礼を言って麻美がそれを受け取ると、透も隣に座る。
フローリングに二人で座り込んで、しばらく無言で空を眺める。
薄暗がりに溶けていきそうな、そんな錯覚を抱いた時だった。
ふいに透が口を開く。
「何を探しているんですか?」
外は新月の夜だった。
麻美は息を吸い込んで、透に振り向きながら言った。
「また夢を見たくてここに来ました」
透は相槌を打つ代わりに、麻美をみつめた。
麻美は立ち上がって戸棚に向かうと、そこから小袋を取り出す。
袋の中から現れたのはペンダントだった。細かい銀の鎖の先に、雫のような小さな宝石がついている。
「私が就職する時、母が譲ってくれたものです。小さいけれど、本物のダイヤモンドだそうです」
麻美はペンダントを両手の上に乗せて目を伏せる。
「幼い頃の私は病気がちで、よく悪夢にうなされました。そんな私に、母がおまじないをしてくれたんです。「このペンダントを枕元に置いて眠ればいい夢が見られる」と言って」
視線を上げて、麻美は透を見上げる。
「そうしたら本当にいい夢が見られました。信じやすい子どもだったのだと思います」
麻美は微笑んで、すぐにそれを寂しい笑みに塗り替える。
「……でもいつからか、夢を見なくなりました」
麻美は口の端を下げて、ため息をつく。
「ある日思い立って、夢の見られるような場所を探しに行っていたんです」
「それで楼ヶ町に?」
「ええ」
麻美はうなずいて窓の外を見やる。
「話に聞いていた蜃気楼は見られませんでした。でも雨の中で見た楼ヶ町は本当に、夢の中のようでしたから」
ぽつりとつぶやいた麻美の横で、透は黙った。
麻美はふいに言葉を切り出した。
「……これは透さんに渡しておきます」
麻美は透にペンダントを差し出す。
「代わりに蜃気楼を、隣で見てください」
透は迷うように麻美を見たが、やがてペンダントを受け取った。
麻美もそれ以上話そうとはせず、二人の間に沈黙が横たわる。
やがて空になった麻美のカップを手に取って、透は二人分のマグカップを片付けに行く。
二人は和室に布団を並べて敷いて、それぞれの布団に横になった。
暗がりの中、麻美はぼんやりと天井を眺めていた。
「麻美さん」
透の低い声が麻美の耳を打つ。
「僕にも探し物があります」
麻美は体を横に向けて、透の方をみつめる。
「沈黙を分かち合える時間。麻美さんの中に、僕は探し物をみつけられそうなんです。だから」
ふわりと空気が動いた。麻美の頭に、透の大きな手が触れる。
「麻美さんが、いい夢を見られますように。……これは僕からのおまじない」
透は麻美の頭をそっと撫でる。無骨な撫で方だが、それはとても優しかった。
麻美は透の手を取って微笑んだ。透もその手を握り返す。
淡い暗闇の中、二人は眠りに落ちて行った。
山間に畑と小さな工房が点在する楼ヶ町は、蜃気楼が見える町として評判だった。もっとも麻美がやって来た頃は蜃気楼が発生する季節ではなく、蜃気楼を除けばこの町はどこにでもある田舎町だった。
ただ、高台から覗き込んだ楼ヶ町はぽつねんとしていて、雨に霞んで何もかもが淡く見えた。
ここがいい。麻美は微笑んで、けぶる雨を頬に受けながら天を仰いだ。
アパートを借りて、グループホームの職員の仕事に就いた。慌ただしく、暮らしが始まった。
そうして一月が過ぎる頃、麻美は透と知り合った。
楼ヶ町の自動車整備工場で働く透は、大柄で無口な青年だった。世話焼きの麻美の上司と、やはり世話焼きの透の上司が計らって、二人はお見合いをすることになった。
麻美は二十一歳で、透は二十八歳。似合いだろうと上司たちは勧めたが、今の時代お互い結婚を焦るほどの年でもない。
透の上司が話したところによれば、透は自分で家事もできて継ぐべき家業もないらしい。
この人はたぶん、結婚を急いでいない。そう思えたことがかえって、麻美を安心させた。
お見合いの日も雨が降っていた。
透は口数が少なく、二人きりになってからもしばらく無言で懐石をつついていた。
「……麻美さんは」
ふいに低い声で切り出した透に、麻美は首を傾げる。
「あまりしゃべりませんね」
麻美は少し考える。迷いながら、思った通りのことをそのまま答える。
「得意ではなくて」
沈黙が流れる。
麻美はその間が不愉快ではなかった。透のまとう温度は麻美に近くて、それが麻美を安心させた。
透は体格がいいからか、あっという間に食事を平らげてしまっていた。その中で梅酒のグラスだけは手もつけずに残っているのに気づいて、麻美は問いかける。
「透さんは梅酒が嫌いですか?」
「僕、お酒は飲めないんです」
また沈黙が流れる。そして半刻ほどが過ぎる。
透は決心したようにうなずいて口を開いた。
「僕と、結婚を前提にお付き合いして頂けませんか」
麻美は箸を置いて、テーブルの向こうへ言葉を投げかける。
「お付き合いの時間は必要ですか?」
首を傾げた透に、麻美はそっと告げる。
「私はすぐに結婚しても構いません」
透は黒々とした目でじっと麻美をみつめて、一拍だけ考え込んだように見えた。
「……では、結婚しましょう」
にこりともせずに透は告げた。
駆け引きもなく、突き放すでもない。初めて見た楼ヶ町のように輪郭が淡くぼやけて混ざっているような、不思議な一体感が二人の間にあった。
「はい」
それが心地よくて、麻美は微笑んでうなずいた。
麻美と透が婚姻届を出したのは、それから三日の後のことだった。
お見合いの紹介をした上司たちさえ少し時間を置いたらと勧めたが、二人は町役場へ行った足でお互いの新居も探しに行った。
築三十年の2LDK、家賃は七万円。前の住人の家具が残っているし、二人暮らしならそれで十分生活できるだろうと、二つ返事で契約を決めた。
また三日の後、麻美と透は新居に引っ越してきた。
二人とも黙々と荷ほどきをする。荷物といえるほどのものはなかった。透は段ボール一つ分、麻美に至っては三日分ほどのトラベルセット程度だった。
透はふいに麻美の方に顔を向けて言う。
「そろそろ食事に行きませんか」
一時間ほどで荷物は片付いていて、麻美もうなずいた。
「透さん、何か食べたいものは?」
「喫茶店くらいで大丈夫です」
外に出て二人、畑の隙間にねじこんだような曲がりくねった道を歩く。
太陽はまだ低いところにあった。時折、お年寄りがゆっくりとすれ違っていく。
二人は透の職場のすぐ近くにある喫茶店に入る。
時間帯が早いからか、メニューは朝食セットだけだった。それを注文すると、コーヒーとゆで卵とサンドイッチが出てくる。
カップを温めてあるからか、コーヒーからは白い湯気が立ち上る。麻美はほろ苦い香りと共に湯気を吸いこんで息をつく。
「透さんは、ここにはよく来るんですか?」
麻美が声をかけたのは、食事も半ばに入っていた頃だった。
透はいや、と声を上げて答える。
「ここに来たのは二度目です。昼はいつも宅配のお弁当ですから、外食というのもほとんどなくて」
「休日は?」
「買っておいたパンに残り物を挟んで、という感じです」
透は淡く笑って付け加えた。
「けど、これからは二人ですから。もうちょっとがんばります」
麻美も苦笑して、私もがんばりますとうなずき返した。
透はそれきりほとんど話さず、麻美が話すのに相槌を打っている程度だった。そのテンポが、麻美にはちょうどよかった。
喫茶店を出た時には、太陽は高く昇っていた。
山間に家々や木立が並ぶ。初めて見た楼ヶ町の景色は絵の具を混ぜ合わせたように現実味がなかったが、眩しい太陽の元だとどこもくっきりしていて生活感が溢れる。
「ここで本当に見えるんでしょうか」
ぽつりとつぶやいた麻美に、透は振り向く。
「蜃気楼が見たいですか?」
麻美の問いかけは何もかも足りない言葉だったのに、透の返事は麻美の心を読み取ったみたいに的確だった。
麻美はうなずこうとして口をつぐむ。
黙りこくった麻美に、透はそれ以上追及しようとしなかった。
「見える季節になったら教えますよ。そんなに遠くない未来に見えます」
透はそう告げて、先に立って帰路を辿り始めた。
昼からは雑貨屋で生活に必要なものを買い足して、スーパーで三日分ほどの食材を買ってきた。
家に戻ってからは二人で掃除をした。特にお互い相談したわけではなかったが、麻美は風呂場とトイレ掃除、透は窓拭きや床拭きを始めた。
それが終わったら、透は夕食の下ごしらえに取り掛かった。包丁の使い方や手際の良さから、聞いた通り透は自炊ができるようだった。
「いただきます」
食卓には豚のしょうが焼きと芋サラダ、味噌汁が並んでいた。
麻美は箸を取って夕食を口にする。透もテーブルの向かい側で食べ始める。
「おいしいです」
「よかった」
麻美の感想も、透の返答もそれだけだった。
お見合いの時以上に会話が少ない。でも少しだけ笑った透が、麻美を温かい気持ちにさせた。
今度は麻美が夕食の後片付けをして、麻美たちはお互いの家から持ってきたそれぞれのマグカップにお茶を淹れる。
麻美は窓から入り込む風を感じながら言った。
「朝食は私が作りますね」
「いつもじゃなくていいですよ。順々に」
透はそう答えて、食事のこと、掃除のこと、ゴミ出しのこと、そういう話を淡々と二人で相談した。
お茶を飲み終わると、麻美は先にお風呂を使った。
その後透がお風呂に入っている間、麻美は窓辺に座って空を眺めていた。
夏の宵は暮れゆくのが遅く、ゆるゆると更けていく。
「冷えますよ」
見上げると、透がカーディガンを差し出していた。お礼を言って麻美がそれを受け取ると、透も隣に座る。
フローリングに二人で座り込んで、しばらく無言で空を眺める。
薄暗がりに溶けていきそうな、そんな錯覚を抱いた時だった。
ふいに透が口を開く。
「何を探しているんですか?」
外は新月の夜だった。
麻美は息を吸い込んで、透に振り向きながら言った。
「また夢を見たくてここに来ました」
透は相槌を打つ代わりに、麻美をみつめた。
麻美は立ち上がって戸棚に向かうと、そこから小袋を取り出す。
袋の中から現れたのはペンダントだった。細かい銀の鎖の先に、雫のような小さな宝石がついている。
「私が就職する時、母が譲ってくれたものです。小さいけれど、本物のダイヤモンドだそうです」
麻美はペンダントを両手の上に乗せて目を伏せる。
「幼い頃の私は病気がちで、よく悪夢にうなされました。そんな私に、母がおまじないをしてくれたんです。「このペンダントを枕元に置いて眠ればいい夢が見られる」と言って」
視線を上げて、麻美は透を見上げる。
「そうしたら本当にいい夢が見られました。信じやすい子どもだったのだと思います」
麻美は微笑んで、すぐにそれを寂しい笑みに塗り替える。
「……でもいつからか、夢を見なくなりました」
麻美は口の端を下げて、ため息をつく。
「ある日思い立って、夢の見られるような場所を探しに行っていたんです」
「それで楼ヶ町に?」
「ええ」
麻美はうなずいて窓の外を見やる。
「話に聞いていた蜃気楼は見られませんでした。でも雨の中で見た楼ヶ町は本当に、夢の中のようでしたから」
ぽつりとつぶやいた麻美の横で、透は黙った。
麻美はふいに言葉を切り出した。
「……これは透さんに渡しておきます」
麻美は透にペンダントを差し出す。
「代わりに蜃気楼を、隣で見てください」
透は迷うように麻美を見たが、やがてペンダントを受け取った。
麻美もそれ以上話そうとはせず、二人の間に沈黙が横たわる。
やがて空になった麻美のカップを手に取って、透は二人分のマグカップを片付けに行く。
二人は和室に布団を並べて敷いて、それぞれの布団に横になった。
暗がりの中、麻美はぼんやりと天井を眺めていた。
「麻美さん」
透の低い声が麻美の耳を打つ。
「僕にも探し物があります」
麻美は体を横に向けて、透の方をみつめる。
「沈黙を分かち合える時間。麻美さんの中に、僕は探し物をみつけられそうなんです。だから」
ふわりと空気が動いた。麻美の頭に、透の大きな手が触れる。
「麻美さんが、いい夢を見られますように。……これは僕からのおまじない」
透は麻美の頭をそっと撫でる。無骨な撫で方だが、それはとても優しかった。
麻美は透の手を取って微笑んだ。透もその手を握り返す。
淡い暗闇の中、二人は眠りに落ちて行った。