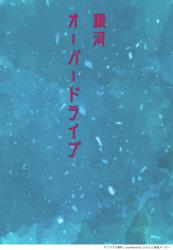いざ、始まってしまえばパーティーはとても楽しいものだった。友美が用意してくれた肉やパスタ、スイーツの数々は美味しくて、ついつい食べこんでしまった。それはこの場にいる全員に言えることで、みんな「美味しい」と口を揃えて用意されたものを食べていた。
「どう、美味しい?」
友美が明るい調子で声をかけてきた。
「美味しいよ」
「良かった。用意した甲斐があったよ」
「どうやって、こんな量を用意したの?」
「週一でお手伝いさんが私の様子を見に来るんだけど、昨日来てくれたから手伝ってもらった」
「へえ、そうなんだ」
「二人で用意するの大変だったから、喜んでもらえて嬉しい」
「え、二人?」
私は思わず質問していた。この時、友美の表情が一瞬だけ曇ったような気がした。それでも、彼女はすぐに明るい調子に戻ってこう答えた。
「私の両親、仕事が忙しくてさ。いつも家に居ないんだよね。だから、普段は一人で過ごしているんだ」
「そうなんだ、知らなかった、よ……」
「いいの、由香里には今まで全然言ってなかったもん。そんな、暗い顔しなくても大丈夫だよ」
私はいつの間にか暗い顔をしていたようだった。その訳は、彼女も大変なのだなと思ったことと、それまで彼女がこの事を伝えてくれなかったことのショックが混じったからかもしれない。それと同時に、ああ、私は彼女に頼られていなんだなと直感的に思った。ちょっぴり傷ついた。直後、彼女は別の友達に呼ばれて向こうへと行ってしまった。
この頃の私は友美のことを不信に思う反面、心のどこかで頼ろうとしていたのだと思う。それはなぜか。なぜなら、私は独りだと思っていたからだ。いくら表ではいろんな交流や仲間がいようと、裏にどうしても満たされない気持ちがあった。私は寂しかった。
パーティーが続いている中、私は幾人かとの新しい出会いがあった。
「こんにちは。はじめましてかな?」
「はじめまして……」
「あ、私は桜木かりんっていうの。友美の中学の同級生」
「はぁ」
「よろしくね!」
「よろしく……」
桜木かりんはとてもお洒落な人だった。流行の色味のニットにダメージジーンズ。ニット帽に少し長めの黒髪。手にはドリンクの入ったグラス。同い年の高校生には見えなかった。彼女はすぐに私の横にあったソファーに座り込んだ。すると彼女は、私にも座るように促した。
「座ったら?」
「じゃあ、遠慮なく」
私もソファーに座る。かりんさんはグラスに入ったドリンクを一気に飲むと、私の方を向いた。私はなんだか照れた。
「友美は学校ではどうしているの?」
彼女に質問に私はどう答えて良いのか分からず、少し考えた。不自然に間が空く。少し焦って、私は答えを絞り出した。
「ええと、そうですね。彼女は普通に頑張ってますよ。友達のこととか、勉強のこととか」
かりんさんはそれを聞いて、神妙な表情で窓の方を見つめる。目は遠くを見ていた。
「そうか、友美、やっぱり頑張っちゃっているのか……」
「頑張っちゃってるとは、どういうことですか?」
友美が用意していた広間中に設置されているスピーカから、流行りのクリスマスソングが流れている。私とかりんさんにとっては場違いだったのだが、逆にそれが良かった。かりんさんは言葉を選ぶような感じで答えてくれた。
「彼女さ、私たちからしたら普通じゃないじゃん。両親のことなんか特にそうだって本人が昔言ってた。それで……」
「それで?」
「それで、普通になりたがっているの彼女は。だからこそ、友達を欲していんだと思うんだ」
「そうだったんだ…… 」
「でもさ、彼女は友達を欲している割には、友達のことを位づけしたり、突き放したり、ねちっこく攻撃したりしてた」
「どうして……」
「私にもよくわからない。でもそのせいで、倉持さんって人が相当傷ついてた」
「待って、倉持って、倉持咲のこと?」
この質問をした時、かりんさんはとても驚いたような顔をしていた。
「そう。あれ、友美と同じ高校だっけ?」
「そうです。友美は、倉持さんには近づくなって言っていました……」
「そうか……」
彼女はまた遠い目をした。何か思うところがあるような言い草だった。そういえば、私は友美と倉持咲がどうして面識があるのかを全然知らない。そう思った私は思い切って、彼女に尋ねた。
「あの、友美と倉持さんの間に何があったんですか?」
かりんさんはそれから一分ほど言葉に詰まった。周りは私たちの会話に全然気付いてる様子はなく、私たちの間にはただ静寂があった。やがて、彼女はひそひそ声で事情を話してくれた。
「昔は、友美も倉持さんも仲が良かったんだ。だけどさ、二人の間になにか大きな出来事があったみたいで、それから友美は彼女のことを周到に攻撃するようになった。仲間外れにしたり、無視したり」
「そんな……」
「それで、倉持さん、その事が相当こたえちゃったみたいで、病院に通うようになったみたい。そして、倉持さんはなぜか折りたたみ式のナイフを持ち歩くようになったの」
「折りたたみ式のナイフ?」
かりんさんはジェスチャーで手のひら程の大きさだと教えてくれた。
「倉持さんは、何かに怯えるようになって、それから少し荒っぽくなった。中二の時なんかはたまに机とか椅子を蹴っ飛ばしてた」
「そんなに」
「一見すると怖いでしょうけど、あれは彼女にとって必要なことになってしまったんだと思う。ああやって、物に当たっておかないと心の平穏が保てない感じ」
私はなんて言えば良いのかわからなくなった。今度はこっちが返す言葉に詰まる。それを見たかりんさんは立ち上がって、水を持ってきてくれた。
「ありがとうございます」
「いいの。こっちこそいろいろ話してごめんね。せっかくのパーティーの場でするような話題じゃなかった。ごめんなさい」
「いいえ。でも、おかげで友美と倉持さんの関係が少しはわかった気がします。少し前から気にはなっていたので」
「それなら、良かったよ」
彼女の表情は心なしかさっきよりも明るくなっていた。直後、向こうのほうからかりんさんの友達らしき人たちがやってきて「ねえ、ケーキ食べない?」と彼女を誘った。彼女は「喜んで」と返事をする。すると友達たちは「じゃあ、向こうで待ってる」と言って離れていった。
「じゃあ、また今度お話ししましょう」
「はい」
「ありがとうね」
「こちらこそ、ありがとうございます」
別れの挨拶を交わして、かりんさんは友達たちのいる向こうの方へと歩いていった。
私は大きなテーブルの上に並べられているケーキを一つとって、ソファーへと腰掛けた。ケーキをフォークで切り分けて、口へと運ぶ。私はケーキを食べながら考えてみた。友美はどうして、友達を求めておきながらいじめたりしているのだろうか。どうしたら彼女のことw助けられるのだろうか? もっと言えば、友美のせいで傷ついてしまったという倉持咲のこともどうしたら助けられるのか。助けるという言葉はもしかしたら上から目線な表現だとすぐに思い返す。じゃあ、どうやったら二人は仲直りできるのだろうかと改めて考える。私には友達と呼べる人はいないが、あの二人に何かをしてやりたいと浅はかながらに思った。どうしたら良いんだろうか。つい考えてしまう。二人を仲直りさせたところで、私には何の得もないのに。それでも、そうしなくちゃと心の中で感じた。だけど、私にはそれを実行に移す勇気はなかった。その場の勢いで、考えてはみたが、まず私にはこのことに踏み込む覚悟がないことに気づいた。それから、もし、それで私も無視されたら、今度は私が友美のピラミッドから蹴落とされてしまう。そうなったら、今度は私の方が辛くなるかもしれない。怖かった。私はこの時、自分が誰かに嫌われることが怖いことに気付いた。私は何もできそうにないと思った。やるせなくなって、ケーキをソファーの上に置いて、ため息をした。
それからパーティーは一時間ほど続いた。お客さんたちはいまだに騒いでいる。隣に家が無いだけあって、近所に迷惑になっているのではないかという不安はあまりなかった。私も気持ちを切り替えて、パーティーを楽しんだ。ケーキーをもっと食べてみたり、真希ちゃんらと他愛もない会話をしてみたりした。それでも、このパーティーへの違和感は払拭しきれなかった。そういえば、友美はどこにいるのだろうか。少なくとも十分前からこの広間には居ない。興味本位で私は友美を探してみることにした。広間を出て少し歩いて、部屋を探す。静かなリビング、散らかったキッチン、どれも私の家から比べれば羨ましくなるほどに綺麗で広かったが、そこには居なかった。仕方なく私はこれまた大きな二階へとつながる階段で上へと上がることにした。
「おじゃまします……」
二階へと上がると、廊下の途中で扉が七つ程あった。おそらくのこれらの扉のどれかの向こうに友美はいる。私は扉を一つ一つノックして確かめることにした。
一つ目の扉はハズレだった。特に反応がない。二つ目を叩いてみたが、これも応答なし。三つ目も四つ目もだめだった。
「どこだろう……」
五つ目の扉を叩く。すると、扉の向こうから、
「誰?」
と声がした。
「あ、由香里だけど。どこにいるのかなと思って探してた」
「あ、ごめんごめん。今、パーティー最大の見せ場の用意してるから、下で待っていて!」
彼女は扉ごしにいつも通りの明るい声で話していた。
「わかった。じゃあ、下で待ってる」
私はこの時、倉持さんのことも話して見ようかと考えたが、いざ実際に話しかける勇気はなかった。元来た道を歩き始める。彼女は何をしているのだろうか。でも、みんなを楽しませようと準備をしているのだということは理解した。
下へと戻ると、みんなはまだまだこれからと言わんばかりに思い思いに盛り上がっていた。様子を見ていると彼女らはこの刹那を精一杯生きているのかもしれない。不思議とそう思える。私もそれに混ざろうと思って、輪に入った。とても楽しかった。しばらくすると友美が戻ってきた。手には大きな何かを抱えている。
「じゃあ、クリスマスパーティー恒例のビンゴ大会を始めるよ!」
彼女は大きな声で高らかにこう告げた。
「どう、美味しい?」
友美が明るい調子で声をかけてきた。
「美味しいよ」
「良かった。用意した甲斐があったよ」
「どうやって、こんな量を用意したの?」
「週一でお手伝いさんが私の様子を見に来るんだけど、昨日来てくれたから手伝ってもらった」
「へえ、そうなんだ」
「二人で用意するの大変だったから、喜んでもらえて嬉しい」
「え、二人?」
私は思わず質問していた。この時、友美の表情が一瞬だけ曇ったような気がした。それでも、彼女はすぐに明るい調子に戻ってこう答えた。
「私の両親、仕事が忙しくてさ。いつも家に居ないんだよね。だから、普段は一人で過ごしているんだ」
「そうなんだ、知らなかった、よ……」
「いいの、由香里には今まで全然言ってなかったもん。そんな、暗い顔しなくても大丈夫だよ」
私はいつの間にか暗い顔をしていたようだった。その訳は、彼女も大変なのだなと思ったことと、それまで彼女がこの事を伝えてくれなかったことのショックが混じったからかもしれない。それと同時に、ああ、私は彼女に頼られていなんだなと直感的に思った。ちょっぴり傷ついた。直後、彼女は別の友達に呼ばれて向こうへと行ってしまった。
この頃の私は友美のことを不信に思う反面、心のどこかで頼ろうとしていたのだと思う。それはなぜか。なぜなら、私は独りだと思っていたからだ。いくら表ではいろんな交流や仲間がいようと、裏にどうしても満たされない気持ちがあった。私は寂しかった。
パーティーが続いている中、私は幾人かとの新しい出会いがあった。
「こんにちは。はじめましてかな?」
「はじめまして……」
「あ、私は桜木かりんっていうの。友美の中学の同級生」
「はぁ」
「よろしくね!」
「よろしく……」
桜木かりんはとてもお洒落な人だった。流行の色味のニットにダメージジーンズ。ニット帽に少し長めの黒髪。手にはドリンクの入ったグラス。同い年の高校生には見えなかった。彼女はすぐに私の横にあったソファーに座り込んだ。すると彼女は、私にも座るように促した。
「座ったら?」
「じゃあ、遠慮なく」
私もソファーに座る。かりんさんはグラスに入ったドリンクを一気に飲むと、私の方を向いた。私はなんだか照れた。
「友美は学校ではどうしているの?」
彼女に質問に私はどう答えて良いのか分からず、少し考えた。不自然に間が空く。少し焦って、私は答えを絞り出した。
「ええと、そうですね。彼女は普通に頑張ってますよ。友達のこととか、勉強のこととか」
かりんさんはそれを聞いて、神妙な表情で窓の方を見つめる。目は遠くを見ていた。
「そうか、友美、やっぱり頑張っちゃっているのか……」
「頑張っちゃってるとは、どういうことですか?」
友美が用意していた広間中に設置されているスピーカから、流行りのクリスマスソングが流れている。私とかりんさんにとっては場違いだったのだが、逆にそれが良かった。かりんさんは言葉を選ぶような感じで答えてくれた。
「彼女さ、私たちからしたら普通じゃないじゃん。両親のことなんか特にそうだって本人が昔言ってた。それで……」
「それで?」
「それで、普通になりたがっているの彼女は。だからこそ、友達を欲していんだと思うんだ」
「そうだったんだ…… 」
「でもさ、彼女は友達を欲している割には、友達のことを位づけしたり、突き放したり、ねちっこく攻撃したりしてた」
「どうして……」
「私にもよくわからない。でもそのせいで、倉持さんって人が相当傷ついてた」
「待って、倉持って、倉持咲のこと?」
この質問をした時、かりんさんはとても驚いたような顔をしていた。
「そう。あれ、友美と同じ高校だっけ?」
「そうです。友美は、倉持さんには近づくなって言っていました……」
「そうか……」
彼女はまた遠い目をした。何か思うところがあるような言い草だった。そういえば、私は友美と倉持咲がどうして面識があるのかを全然知らない。そう思った私は思い切って、彼女に尋ねた。
「あの、友美と倉持さんの間に何があったんですか?」
かりんさんはそれから一分ほど言葉に詰まった。周りは私たちの会話に全然気付いてる様子はなく、私たちの間にはただ静寂があった。やがて、彼女はひそひそ声で事情を話してくれた。
「昔は、友美も倉持さんも仲が良かったんだ。だけどさ、二人の間になにか大きな出来事があったみたいで、それから友美は彼女のことを周到に攻撃するようになった。仲間外れにしたり、無視したり」
「そんな……」
「それで、倉持さん、その事が相当こたえちゃったみたいで、病院に通うようになったみたい。そして、倉持さんはなぜか折りたたみ式のナイフを持ち歩くようになったの」
「折りたたみ式のナイフ?」
かりんさんはジェスチャーで手のひら程の大きさだと教えてくれた。
「倉持さんは、何かに怯えるようになって、それから少し荒っぽくなった。中二の時なんかはたまに机とか椅子を蹴っ飛ばしてた」
「そんなに」
「一見すると怖いでしょうけど、あれは彼女にとって必要なことになってしまったんだと思う。ああやって、物に当たっておかないと心の平穏が保てない感じ」
私はなんて言えば良いのかわからなくなった。今度はこっちが返す言葉に詰まる。それを見たかりんさんは立ち上がって、水を持ってきてくれた。
「ありがとうございます」
「いいの。こっちこそいろいろ話してごめんね。せっかくのパーティーの場でするような話題じゃなかった。ごめんなさい」
「いいえ。でも、おかげで友美と倉持さんの関係が少しはわかった気がします。少し前から気にはなっていたので」
「それなら、良かったよ」
彼女の表情は心なしかさっきよりも明るくなっていた。直後、向こうのほうからかりんさんの友達らしき人たちがやってきて「ねえ、ケーキ食べない?」と彼女を誘った。彼女は「喜んで」と返事をする。すると友達たちは「じゃあ、向こうで待ってる」と言って離れていった。
「じゃあ、また今度お話ししましょう」
「はい」
「ありがとうね」
「こちらこそ、ありがとうございます」
別れの挨拶を交わして、かりんさんは友達たちのいる向こうの方へと歩いていった。
私は大きなテーブルの上に並べられているケーキを一つとって、ソファーへと腰掛けた。ケーキをフォークで切り分けて、口へと運ぶ。私はケーキを食べながら考えてみた。友美はどうして、友達を求めておきながらいじめたりしているのだろうか。どうしたら彼女のことw助けられるのだろうか? もっと言えば、友美のせいで傷ついてしまったという倉持咲のこともどうしたら助けられるのか。助けるという言葉はもしかしたら上から目線な表現だとすぐに思い返す。じゃあ、どうやったら二人は仲直りできるのだろうかと改めて考える。私には友達と呼べる人はいないが、あの二人に何かをしてやりたいと浅はかながらに思った。どうしたら良いんだろうか。つい考えてしまう。二人を仲直りさせたところで、私には何の得もないのに。それでも、そうしなくちゃと心の中で感じた。だけど、私にはそれを実行に移す勇気はなかった。その場の勢いで、考えてはみたが、まず私にはこのことに踏み込む覚悟がないことに気づいた。それから、もし、それで私も無視されたら、今度は私が友美のピラミッドから蹴落とされてしまう。そうなったら、今度は私の方が辛くなるかもしれない。怖かった。私はこの時、自分が誰かに嫌われることが怖いことに気付いた。私は何もできそうにないと思った。やるせなくなって、ケーキをソファーの上に置いて、ため息をした。
それからパーティーは一時間ほど続いた。お客さんたちはいまだに騒いでいる。隣に家が無いだけあって、近所に迷惑になっているのではないかという不安はあまりなかった。私も気持ちを切り替えて、パーティーを楽しんだ。ケーキーをもっと食べてみたり、真希ちゃんらと他愛もない会話をしてみたりした。それでも、このパーティーへの違和感は払拭しきれなかった。そういえば、友美はどこにいるのだろうか。少なくとも十分前からこの広間には居ない。興味本位で私は友美を探してみることにした。広間を出て少し歩いて、部屋を探す。静かなリビング、散らかったキッチン、どれも私の家から比べれば羨ましくなるほどに綺麗で広かったが、そこには居なかった。仕方なく私はこれまた大きな二階へとつながる階段で上へと上がることにした。
「おじゃまします……」
二階へと上がると、廊下の途中で扉が七つ程あった。おそらくのこれらの扉のどれかの向こうに友美はいる。私は扉を一つ一つノックして確かめることにした。
一つ目の扉はハズレだった。特に反応がない。二つ目を叩いてみたが、これも応答なし。三つ目も四つ目もだめだった。
「どこだろう……」
五つ目の扉を叩く。すると、扉の向こうから、
「誰?」
と声がした。
「あ、由香里だけど。どこにいるのかなと思って探してた」
「あ、ごめんごめん。今、パーティー最大の見せ場の用意してるから、下で待っていて!」
彼女は扉ごしにいつも通りの明るい声で話していた。
「わかった。じゃあ、下で待ってる」
私はこの時、倉持さんのことも話して見ようかと考えたが、いざ実際に話しかける勇気はなかった。元来た道を歩き始める。彼女は何をしているのだろうか。でも、みんなを楽しませようと準備をしているのだということは理解した。
下へと戻ると、みんなはまだまだこれからと言わんばかりに思い思いに盛り上がっていた。様子を見ていると彼女らはこの刹那を精一杯生きているのかもしれない。不思議とそう思える。私もそれに混ざろうと思って、輪に入った。とても楽しかった。しばらくすると友美が戻ってきた。手には大きな何かを抱えている。
「じゃあ、クリスマスパーティー恒例のビンゴ大会を始めるよ!」
彼女は大きな声で高らかにこう告げた。