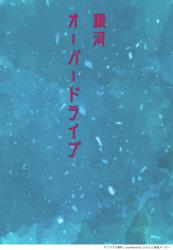十二月二五日、クリスマス。学校が冬休みに入っていたので、私は普段より遅い起床となった。この日、午後から友美の家でパーティーが開かれる。私は楽しみな気持ちと億劫な気持ちが混ざり合って、ブルーな気分になっていた。
「そうか、今日か」
私は部屋を出て、リビングへと出た。そこにはストレッチをしながらテレビを見ているパジャマ姿のお母さんの姿があった。お母さんはどうやらこの日、仕事は休みだったらしい。
「お、由香里おはよう」
「おはよう」
お母さんは既に朝食を食べていた。私は自分のご飯の用意を始める。パンを袋から出してトースターにして入れる。そうしていると、お母さんが話しかけてきた。
「そういえば、今日はクリスマスだね」
「そうだね」
「楽しんできなね」
「わかった……」
この日、友美の家でのパーティーに私も出るということは、数日前にお母さんに伝えていた。お母さんは、せっかくだからと前日にお菓子を買ってくれた。それは友美に渡すための物で、とても嬉しかったのだが何だか気が重くなった。パンをトースターで焼き始める。リビングに出て、改めてテーブルの上に置かれたお菓子が入った袋を見つめる。上手な説明はできないが、面倒くさいという漠然とした感情があった。私は、彼女と一応は友達である。だけど、そこまで深い間柄でもないと思っていた。
どうしてか、私は深い間柄の友達を作ることがいつからかできなかった。それは、見えない力関係や、読み取りきれない気持ちの数々がそうさせたのだとは思う。後になって考えれば私は、ただ純粋な友達が欲しかったのだ。気兼ねなく接せる、普通の友達。その人が私にはいないように思えた。どうしてそんな思考になったのか。もしかすると、錯覚や幻想、理想が幾らかはあるのだと思うが私の生の気持ちが願ったのだ。友達が欲しいのだと。
焼き終えたパンを皿に出す。バターを塗る。私はパンにはバターを塗って食べるのが好きだった。食べながらテレビを眺める。内容は先日から世の中をざわつかせているいじめが原因の事件だった。お母さんもテレビを見つめていた。コメンテーターやキャスターたちが相変わらず合っているのか、的外れなのかよくわからないことを言っている。改めて事件の内容を聞くと、男子生徒が複数の同級生からいじめられたことが原因で、いじめていた同級生をナイフで刺したのだった。幸い、刺された相手は軽傷だったようだが、男子生徒は警察署に連行された。その様子が、堂々と報じられている。世間や大人にはよほど衝撃だったようで、いろいろと騒いでいるみたいだった。お母さんも口を開けてその様子を見ていた。
「こんなことがあるのね」
「そうだね」
私は、こんなことがあり得る世界なのだと前々から思っていた。私たちはみんな、誰かに向けて鬱憤や不満、怒りを抱えている。だから、いつ、誰が、耐えきれなくなって何をしてもおかしくはないと思っていた。ただ、私の周りでそれが起きてないだけであって、世の中では頻繁に起こっているのだと感じていた。
パンを食べ終えて、服を着替えて、荷物をまとめた。パーティーは午後からなのでゆっくりと準備をする。あと一時間ほどで家を出ればいい。私は少しの間、部屋でゆっくりすることにした。好きなアーティストの音楽を聴いたり、動画サイトで流行っている動画を見たりした。そうしているうちに時間になったので、家を出ることにした。外は寒そうだったのでコートを身に纏う。リビングに出ると、テレビは東京とかで開かれているクリスマスイベントのことを伝えていた。綺麗なクリスマスツリーが画面に現れる。私は一瞬だけそれを見て、お母さんを探した。
「お母さん?」
「はい、何?」
洗面台の方から声がする。程なくして、お母さんがリビングに来た。
「じゃあ、行ってくるね」
「うん、気をつけて。あと、あれ、忘れないでね」
「あ、危なかった」
私は慌ててテーブルの上に置かれたままの袋を手に持った。それから、玄関に出てしゃがんで靴を履く。靴を履き終えて、立ち上がる。後ろを振り返ると、お母さんが立っていた。
「じゃあ、行ってきます」
「行ってらっしゃい!」
私は扉を開けて、外へ出た。階段を降りて、駐輪場へ向かう。予定の時間はまだ余裕があった。私は自転車の鍵を開錠する。それから、前面に取り付けられているカゴの中に袋を入れた。私は自転車に跨って、ゆっくりと漕ぎ出した。
友美の家は私の家から遠かった。そのため、街の中心部を抜ける必要があったので、私は中心部へと繋がる大通りに入った。道は少しだけ混んでいて通り抜けるのに時間がかかった。交差点に入り信号待ちをしていると、横の広場に大きなクリスマスツリーが飾ってあった。すぐそばでは子供たちが楽しそうに遊んでいる。私にもああいう時期があった。無邪気な心で友達と遊んでいられた、楽しい時間。ところが、今はどうだろうか? 私が純粋に楽しいと思えることは気づけば年月を経て減っていた。もっと言えば、その時間はこれからもどんどん減っていくのだろうなと諦めているところがあった。そう考えただけで、私は少しだけ悲しくなった。そう考えている間に信号は青になった。私は再び自転車を漕ぐ。
友美の家を探し当てるのは大変ではなかった。彼女から教えてもらっていた住所を地図アプリで検索をかけて事前に付近の様子をチェックしていたからだ。それと、友美の家は広かった。
石崎友美の家は、言うなれば西洋風のお屋敷だった。ブランコが一つ置かれている広い庭。季節の花が咲いている花壇。車が三台くらいは入りそうなガレージ。建物は二階建てで、広さはざっと見てバレーボールのコート二面分くらいはあるように思えた。
私は敷地内に入って、自転車が何台も置かれている場所に自分の自転車を並べた。この自転車たちはおそらく、友美が誘った仲間たちの物だろう。私は鍵をかけて、荷物をカゴから出して肩にかけた。玄関まで歩いて、インターホンを鳴らす。すると、すぐに応答があった。
「はーい」
「あ、佐野です」
「あー由香里! 今鍵を開けるからそこで待っていて」
友美の声だった。初めて彼女の家を訪れたせいなのか、なぜだか緊張してくる。程なくして、ドアの鍵が開けられた。扉が開くと、普段の私服とあまり変わらない姿の友美がいた。
「由香里! 待っていたよ」
「おじゃまします」
「どうぞ、どうぞ」
私は家の中に入った。玄関からして私の家よりも広かった。足元を見ると十人分くらいの靴が置かれており、横の方にも目を向けると数十足は入りそうな靴箱があった。靴を脱いで上がるとすぐに広い階段があった。周りには大きな花瓶や絵画が置かれている。私は彼女の住む世界はこんな所なのかと思った。
「広間は向こうよ。ついてきて」
友美の後ろを歩く。廊下にも高価そうな物がいくらか置かれていた。私は壁に掛けられていたバナナの絵を見つめる。この絵がいくらなのかは私にはわからなかったが、絵を見てお菓子を渡すことを思い出した。
「友美、ちょっと待って」
「どうしたの?」
彼女が足を止める。
「渡したい物が、あるんだ」
「なになに?」
気になるとでも言いたげな顔をして体ごとこちらを向いた。私は袋からお菓子を取り出して、彼女に見せた。
「このために用意したお菓子。どうぞ」
お菓子を差し出す。すると友美は嬉しそうにそれを受け取った。
「ありがとう! 嬉しい!」
「よかったよ。喜んでくれたようで」
彼女はそれを大事そうに抱えて、再び歩き始めた。私もついていく。
程なくして、広間へと入った。その広間はとても広く、モダンなデザインと家具で印象が統一され、洗練されていた。まるで、ドラマのセットのような空間で、私はまたしても驚いた。周りを見回すと、既に何人かの客人がいた。顔を見ると、真希ちゃんたち、バスケ部のチームメイトや、知らない顔の人もいて彼女の交流の広さを改めて意識した。
「本番はこれからだから、呼んでいる子がみんな来るまで待っていてね」
友美はそう言って、広間から出て行った。お菓子は彼女がそのまま持っていってしまった。みんなで食べることを想定していたのだがなと正直思った。おそらく、何かの準備をしに行ったのだ。私は誰も使っていないソファーにとりあえず座る。しばらく、窓の外を眺めていると、真希ちゃんが横に座ってきた。
「やあ、来たのね」
「まあね」
彼女は手に持ったガラスのコップを口につけて、中のジュースを一気に飲む。「ぷはあ」と言ってから彼女は小さい声で喋り始めた。
「このパーティー、色々な人がたくさん来てるけど、本当に友達だから来た人って何人いるのかな?」
その話に私は思わず小さな声で、聞き返した。
「どういうこと?」
「彼女さ、自分から声をかける方じゃん」
「それはそうだけど、それが何?」
「本当は、みんな逆らえないだけな気がしててさ。私だって、出ておかないと彼女に避けられるような気がしてさ……」
「それは、そうかもね……」
真希ちゃんの話に反論の余地はほとんど無かった。実際、これまで友美の意にそぐわないことをした人たちはみんな無視などをされていた。もしかすると、このパーティーに来ないという選択をした人たちはこのグループから外されてしまうのかもしれない。そんなことを考えると恐ろしいという言葉が浮かんできた。その瞬間、扉が開く音がした。私を含め全員が入り口の方を振り向く。そこには友美の姿があった。この部屋に静寂が訪れる。
「じゃあ、時間になったからパーティーを始めようか!」
彼女は拳を上げて朗らかにパーティーの始まりを宣言した。それに続いて、今度は私たちが「おー!」と言って、拳を上げたりした。
こうして、波乱のクリスマスパーティーが始まった。
「そうか、今日か」
私は部屋を出て、リビングへと出た。そこにはストレッチをしながらテレビを見ているパジャマ姿のお母さんの姿があった。お母さんはどうやらこの日、仕事は休みだったらしい。
「お、由香里おはよう」
「おはよう」
お母さんは既に朝食を食べていた。私は自分のご飯の用意を始める。パンを袋から出してトースターにして入れる。そうしていると、お母さんが話しかけてきた。
「そういえば、今日はクリスマスだね」
「そうだね」
「楽しんできなね」
「わかった……」
この日、友美の家でのパーティーに私も出るということは、数日前にお母さんに伝えていた。お母さんは、せっかくだからと前日にお菓子を買ってくれた。それは友美に渡すための物で、とても嬉しかったのだが何だか気が重くなった。パンをトースターで焼き始める。リビングに出て、改めてテーブルの上に置かれたお菓子が入った袋を見つめる。上手な説明はできないが、面倒くさいという漠然とした感情があった。私は、彼女と一応は友達である。だけど、そこまで深い間柄でもないと思っていた。
どうしてか、私は深い間柄の友達を作ることがいつからかできなかった。それは、見えない力関係や、読み取りきれない気持ちの数々がそうさせたのだとは思う。後になって考えれば私は、ただ純粋な友達が欲しかったのだ。気兼ねなく接せる、普通の友達。その人が私にはいないように思えた。どうしてそんな思考になったのか。もしかすると、錯覚や幻想、理想が幾らかはあるのだと思うが私の生の気持ちが願ったのだ。友達が欲しいのだと。
焼き終えたパンを皿に出す。バターを塗る。私はパンにはバターを塗って食べるのが好きだった。食べながらテレビを眺める。内容は先日から世の中をざわつかせているいじめが原因の事件だった。お母さんもテレビを見つめていた。コメンテーターやキャスターたちが相変わらず合っているのか、的外れなのかよくわからないことを言っている。改めて事件の内容を聞くと、男子生徒が複数の同級生からいじめられたことが原因で、いじめていた同級生をナイフで刺したのだった。幸い、刺された相手は軽傷だったようだが、男子生徒は警察署に連行された。その様子が、堂々と報じられている。世間や大人にはよほど衝撃だったようで、いろいろと騒いでいるみたいだった。お母さんも口を開けてその様子を見ていた。
「こんなことがあるのね」
「そうだね」
私は、こんなことがあり得る世界なのだと前々から思っていた。私たちはみんな、誰かに向けて鬱憤や不満、怒りを抱えている。だから、いつ、誰が、耐えきれなくなって何をしてもおかしくはないと思っていた。ただ、私の周りでそれが起きてないだけであって、世の中では頻繁に起こっているのだと感じていた。
パンを食べ終えて、服を着替えて、荷物をまとめた。パーティーは午後からなのでゆっくりと準備をする。あと一時間ほどで家を出ればいい。私は少しの間、部屋でゆっくりすることにした。好きなアーティストの音楽を聴いたり、動画サイトで流行っている動画を見たりした。そうしているうちに時間になったので、家を出ることにした。外は寒そうだったのでコートを身に纏う。リビングに出ると、テレビは東京とかで開かれているクリスマスイベントのことを伝えていた。綺麗なクリスマスツリーが画面に現れる。私は一瞬だけそれを見て、お母さんを探した。
「お母さん?」
「はい、何?」
洗面台の方から声がする。程なくして、お母さんがリビングに来た。
「じゃあ、行ってくるね」
「うん、気をつけて。あと、あれ、忘れないでね」
「あ、危なかった」
私は慌ててテーブルの上に置かれたままの袋を手に持った。それから、玄関に出てしゃがんで靴を履く。靴を履き終えて、立ち上がる。後ろを振り返ると、お母さんが立っていた。
「じゃあ、行ってきます」
「行ってらっしゃい!」
私は扉を開けて、外へ出た。階段を降りて、駐輪場へ向かう。予定の時間はまだ余裕があった。私は自転車の鍵を開錠する。それから、前面に取り付けられているカゴの中に袋を入れた。私は自転車に跨って、ゆっくりと漕ぎ出した。
友美の家は私の家から遠かった。そのため、街の中心部を抜ける必要があったので、私は中心部へと繋がる大通りに入った。道は少しだけ混んでいて通り抜けるのに時間がかかった。交差点に入り信号待ちをしていると、横の広場に大きなクリスマスツリーが飾ってあった。すぐそばでは子供たちが楽しそうに遊んでいる。私にもああいう時期があった。無邪気な心で友達と遊んでいられた、楽しい時間。ところが、今はどうだろうか? 私が純粋に楽しいと思えることは気づけば年月を経て減っていた。もっと言えば、その時間はこれからもどんどん減っていくのだろうなと諦めているところがあった。そう考えただけで、私は少しだけ悲しくなった。そう考えている間に信号は青になった。私は再び自転車を漕ぐ。
友美の家を探し当てるのは大変ではなかった。彼女から教えてもらっていた住所を地図アプリで検索をかけて事前に付近の様子をチェックしていたからだ。それと、友美の家は広かった。
石崎友美の家は、言うなれば西洋風のお屋敷だった。ブランコが一つ置かれている広い庭。季節の花が咲いている花壇。車が三台くらいは入りそうなガレージ。建物は二階建てで、広さはざっと見てバレーボールのコート二面分くらいはあるように思えた。
私は敷地内に入って、自転車が何台も置かれている場所に自分の自転車を並べた。この自転車たちはおそらく、友美が誘った仲間たちの物だろう。私は鍵をかけて、荷物をカゴから出して肩にかけた。玄関まで歩いて、インターホンを鳴らす。すると、すぐに応答があった。
「はーい」
「あ、佐野です」
「あー由香里! 今鍵を開けるからそこで待っていて」
友美の声だった。初めて彼女の家を訪れたせいなのか、なぜだか緊張してくる。程なくして、ドアの鍵が開けられた。扉が開くと、普段の私服とあまり変わらない姿の友美がいた。
「由香里! 待っていたよ」
「おじゃまします」
「どうぞ、どうぞ」
私は家の中に入った。玄関からして私の家よりも広かった。足元を見ると十人分くらいの靴が置かれており、横の方にも目を向けると数十足は入りそうな靴箱があった。靴を脱いで上がるとすぐに広い階段があった。周りには大きな花瓶や絵画が置かれている。私は彼女の住む世界はこんな所なのかと思った。
「広間は向こうよ。ついてきて」
友美の後ろを歩く。廊下にも高価そうな物がいくらか置かれていた。私は壁に掛けられていたバナナの絵を見つめる。この絵がいくらなのかは私にはわからなかったが、絵を見てお菓子を渡すことを思い出した。
「友美、ちょっと待って」
「どうしたの?」
彼女が足を止める。
「渡したい物が、あるんだ」
「なになに?」
気になるとでも言いたげな顔をして体ごとこちらを向いた。私は袋からお菓子を取り出して、彼女に見せた。
「このために用意したお菓子。どうぞ」
お菓子を差し出す。すると友美は嬉しそうにそれを受け取った。
「ありがとう! 嬉しい!」
「よかったよ。喜んでくれたようで」
彼女はそれを大事そうに抱えて、再び歩き始めた。私もついていく。
程なくして、広間へと入った。その広間はとても広く、モダンなデザインと家具で印象が統一され、洗練されていた。まるで、ドラマのセットのような空間で、私はまたしても驚いた。周りを見回すと、既に何人かの客人がいた。顔を見ると、真希ちゃんたち、バスケ部のチームメイトや、知らない顔の人もいて彼女の交流の広さを改めて意識した。
「本番はこれからだから、呼んでいる子がみんな来るまで待っていてね」
友美はそう言って、広間から出て行った。お菓子は彼女がそのまま持っていってしまった。みんなで食べることを想定していたのだがなと正直思った。おそらく、何かの準備をしに行ったのだ。私は誰も使っていないソファーにとりあえず座る。しばらく、窓の外を眺めていると、真希ちゃんが横に座ってきた。
「やあ、来たのね」
「まあね」
彼女は手に持ったガラスのコップを口につけて、中のジュースを一気に飲む。「ぷはあ」と言ってから彼女は小さい声で喋り始めた。
「このパーティー、色々な人がたくさん来てるけど、本当に友達だから来た人って何人いるのかな?」
その話に私は思わず小さな声で、聞き返した。
「どういうこと?」
「彼女さ、自分から声をかける方じゃん」
「それはそうだけど、それが何?」
「本当は、みんな逆らえないだけな気がしててさ。私だって、出ておかないと彼女に避けられるような気がしてさ……」
「それは、そうかもね……」
真希ちゃんの話に反論の余地はほとんど無かった。実際、これまで友美の意にそぐわないことをした人たちはみんな無視などをされていた。もしかすると、このパーティーに来ないという選択をした人たちはこのグループから外されてしまうのかもしれない。そんなことを考えると恐ろしいという言葉が浮かんできた。その瞬間、扉が開く音がした。私を含め全員が入り口の方を振り向く。そこには友美の姿があった。この部屋に静寂が訪れる。
「じゃあ、時間になったからパーティーを始めようか!」
彼女は拳を上げて朗らかにパーティーの始まりを宣言した。それに続いて、今度は私たちが「おー!」と言って、拳を上げたりした。
こうして、波乱のクリスマスパーティーが始まった。