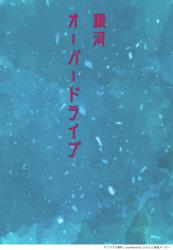私はどう答えたらいいのかわからず、言葉が詰まった。別に自分の身に何かがあったわけではないのに。それなのに、夕方の倉持咲とのことが気にかかっていた。リビングの中に静寂が訪れ、お母さんは何食わぬ顔で私のことを見つめる。自分の子供が何かに悩んだりしている時。その親というのはやはり、子供の異変に気づいているものなのだろうか。そんなことは私にはわからないが、私のお母さんはどうやら気づいたようだった。
「やっぱり、何かあったね」
「そんなこと、ないよ!」
咄嗟に声を張り上げた。認めたくない。倉持咲が放つ異質な何かに心が揺れていることなど、この時の私は認めたくは、なかった。
「そんなこと、ないからさ…… 。ほら、お菓子食べようよ」
お母さんは、私の顔を一瞬だけじろっと見た。
「まあ、何も言いたくないなら、言いたくなったら、その時は言ってよね。約束だよ」
「う、うん」
「それじゃあ、お菓子を食べよう」
それから、お母さんはすぐに表情を明るくして、お菓子を袋から取り出した。私は少しだけお母さんの言葉に安心感を覚えた。後になって、お母さんは「あの時は何も言っても由香里の心がぐちゃぐちゃになるだけになるだろうから、あれ以上は言わないようにしたの」と話してくれた。私のお母さんには、とても大きな愛があったのだとつくづく思う。
「じゃあ、食べようか」
「うん」
お母さんが買ってきたお菓子はパウンドケーキだった。二つの皿にそれぞれ一個ずつパウンドケーキが置かれている。
「いただきます」
私はケーキを食べた。この日のケーキはとても美味しかった。続いてお母さんもケーキを口に運んだ。
「美味しいわね」
「美味しい」
「買ってきてよかったわ」
「ありがとう」
「どういたしまして」
私は自然と笑っていた。お母さんも嬉しそうな顔をしていた。ある程度食べると、お母さんはこんなことを言った。
「お母さんはね。世の中に対してもう少し、悩んだり、傷ついたりすることがあったら、悩みが吹き飛んだり傷を乗り越えられたりするまで、思い切り休んでも良いんじゃないかなと思っているの」
突然の言葉に私は話に追いつけなかった。
「急にどうしてそんなこと言うの?」
「いやね。あなたが少しばかり苦しそうだから」
「え、全然そんなことないよ」
「まあ、あなたがそう思うなら、それでいいけど」
この会話はそこで途切れた。私はパウンドケーキを載せた皿をキッチンに移して、自分の部屋へと入った。すると、自分の荷物をリビングに置いてきてしまったことと、夕方から服を着替えてなかったことに気がついた。すぐにリビングに戻って荷物をとってから、部屋に戻って家着に着替えた。すると、お母さんに呼ばれて、いつも通り夕食作りの手伝いを頼まれた。お米を炊飯器に入れて、野菜をいくらか切って鍋に入れ込む。手伝いが終わって、部屋に戻った時、そういえば今日のご飯はなんだろうと思ったが、それ以上は深く考えずに、勉強用具を机の上に広げた。
勉強をしていると、スマホにメッセージアプリからの通知が届いた。メッセージの送り主は友美。グループチャットにそのメッセージは届いていた。
『再来週のクリスマス。午後から私の家でパーティーをしない?』
私は目を疑った。まさか、友美が倉持咲の言っていた通りにパーティーを開こうとしているとは。思わず、ごくりと唾を呑む。それから、立て続けにメンバーからの返事が届いた。
『オッケー、行く行く!』
『わかった〜』
『その日は北海道に旅行行くから無理〜 ごめんね』
『行けます!』
『行けそうにないよ。すまん!』
流れるように、素早くチャットが進んでいく。その中で私は何もメッセージを送れずにいる。すると、友美がチャットに戻ってきたようで、メンバーの一人一人に返事と相槌のメッセージを送り始めた。
『真希ちゃん、了解! 待ってるね』
『加奈〜 首を長ーくして待っているよ』
『きらりちゃん! それは残念…。帰ってきたらお土産ばなし聞かせてね』
『くるみー! 良かった! 嬉しい!』
『まどかちゃん、また今度おいでね!』
彼女の一人一人への返信が流れてゆく。画面を見つめる。私の勉強の手は完全に止まってしまった。どうしようと思っていた。理由はないが、ただなんとなく行くことが億劫だった。それと、倉持咲のことがどうしても引っ掛かっていた。悩む。悩んでいると、グループチャットに友美から私宛のメッセージが届いた。
『由香里はどうする? 来るんでしょ?』
私は慌てて、返事のメッセージを打ち込もうとした。だが、すぐに言葉が出てこなかった。いつもなら深く考えずに行くと言えていた。言えていたのに、この時ばかりは言えなかった。私の心の奥の奥には、本当はイエスもノーもなかったはずなのに、できればノーを突きつけてやりたい気分になっていた。そうしている間に、他のメンバーからも同じことを聞かれ始めた。
『由香里ちゃんもおいで! 楽しそうだよ』
『そうそう、来なよ〜』
『あれ、由香里ちゃん今、メッセージ見てないかな?』
『どうだろう? わかんない』
『とにかく、楽しそうね』
『そうだね。だから、由香里もおいでね!』
私は、本当は、この誘いを断ろうと、心のどこかで考えていた。だけど、だけど、私は、気づけば、脊髄反射で了承のメッセージを打ち込んで、送っていた。
『わかった。私も行くね!』
ああ、何を言っているのだろうか。考え直してメッセージの送信を取り消そうと思ったが、もう遅かった。
『良かった! 楽しみにしててね』
友美からだった。続いて、他のメンバーも了承の返事を送ってきた。
『おお、由香里も来てくれるようで良かった!』
『由香里も来るのね! 了解!』
『由香里、オッケー』
こうして、仲間たちから喜ばれることは嬉しい。だけど、彼女たちから送られてくるメッセージに私は少し、疲れてしまっていたのかもしれない。思わず、ため息が出た。
ご飯が出来上がったので、お母さんと一緒に食べる。今日の献立はシチューだった。無言で食べているとお母さんが何か気になるとでも言いたげな顔をしていた。
「どうしたの?」
「いや、また重たい顔をしてるなーと思って」
「大丈夫だよ」
気にせずにシチューを口に運ぶ。お母さんはスプーンを皿の上に置いた。
「いや、大丈夫じゃない顔をしている」
「大丈夫だって」
「そうには、見えないんだけどな」
部屋の中が無言になる。重たい空気が流れた。シチューを運ぶ手は完全に止まった。
「由香里は、心の奥の自分を封じ込めている。だから、とても心配なのだけど」
全くもってその通りだった。私は自分の気持ちを封じ込めている。図星だったので何も言えずに表情だけが崩れたような感覚だった。
「だからさ、もう少し心の声に従って生きてみたら、どうなの?」
お母さんの言葉は私の心の門に深く刺さった。だからこそもうこの場にいたくなくて、私は立ち上がった。シチューは半分くらい残っている。
「ごめん、今は、できない」
逃げるように自分の部屋へと歩き出す。
「由香里、ちょっと……」
お母さんのどこか引き止めたいようなそんな声が聞こえた。聞こえていたが、聞こえていないふりをして、部屋に戻り扉を閉じた。
私は部屋に入るなりベットの上に突っ込んだ。「心を閉ざしている」そんなことを言われて反発しない人間などこの世には居ないのではないか。私は急に泣きたいと思って、目を潤ませようとするが、なかなか目から涙は流れなかった。
「ううう……」
泣きたい気分なのに、泣けない。ベットの上に寝転がってそんなことを思った。
私はどうしても心を開けない。どうしてそうなったのかにテレビでよく聞くような壮絶なものは無い。代わりに、長年の小さくて些細なことたちが徐々に私の心をそうさせたのだと思う。こんなことを考えている私は疲れているのだろう。そう思ったので、一通り勉強を済ませると、私は早々にお風呂に入った。気持ちは沈んでいる。体も徐々に沈ませていく。口を水中に入れたせいで、ぶくぶくと泡が立つ。
お風呂を出て、髪を乾かす。歯を磨きながらテレビを眺める。偶然流れていたニュースは学校内で起こったいじめが原因の事件だった。私はただただ、その話題を話す、キャスターやコメンテータのことを見つめていた。彼らは「いじめをなくすには心のケアを……」とか、「学校がこうだからいじめは繰り返される」とか色々言っている。彼らは本当に私たちが置かれている状況をわかっているのだろうか。私たちですら、よく解っていないことなのに。
「なんだかなぁ」
ベットの上で私はそう呟いた。この日、私の違和感は大きく膨らんだ。なぜかと言われると、それは、倉持咲のせいなのだろうか。
私はまとまらない感情たちを押し込めて、毛布を被った。最初は眠れなかったが、十分以上すると眠りに落ちていた。
この時の私の気持ちはとても、とても、ぐちゃぐちゃだった。
「やっぱり、何かあったね」
「そんなこと、ないよ!」
咄嗟に声を張り上げた。認めたくない。倉持咲が放つ異質な何かに心が揺れていることなど、この時の私は認めたくは、なかった。
「そんなこと、ないからさ…… 。ほら、お菓子食べようよ」
お母さんは、私の顔を一瞬だけじろっと見た。
「まあ、何も言いたくないなら、言いたくなったら、その時は言ってよね。約束だよ」
「う、うん」
「それじゃあ、お菓子を食べよう」
それから、お母さんはすぐに表情を明るくして、お菓子を袋から取り出した。私は少しだけお母さんの言葉に安心感を覚えた。後になって、お母さんは「あの時は何も言っても由香里の心がぐちゃぐちゃになるだけになるだろうから、あれ以上は言わないようにしたの」と話してくれた。私のお母さんには、とても大きな愛があったのだとつくづく思う。
「じゃあ、食べようか」
「うん」
お母さんが買ってきたお菓子はパウンドケーキだった。二つの皿にそれぞれ一個ずつパウンドケーキが置かれている。
「いただきます」
私はケーキを食べた。この日のケーキはとても美味しかった。続いてお母さんもケーキを口に運んだ。
「美味しいわね」
「美味しい」
「買ってきてよかったわ」
「ありがとう」
「どういたしまして」
私は自然と笑っていた。お母さんも嬉しそうな顔をしていた。ある程度食べると、お母さんはこんなことを言った。
「お母さんはね。世の中に対してもう少し、悩んだり、傷ついたりすることがあったら、悩みが吹き飛んだり傷を乗り越えられたりするまで、思い切り休んでも良いんじゃないかなと思っているの」
突然の言葉に私は話に追いつけなかった。
「急にどうしてそんなこと言うの?」
「いやね。あなたが少しばかり苦しそうだから」
「え、全然そんなことないよ」
「まあ、あなたがそう思うなら、それでいいけど」
この会話はそこで途切れた。私はパウンドケーキを載せた皿をキッチンに移して、自分の部屋へと入った。すると、自分の荷物をリビングに置いてきてしまったことと、夕方から服を着替えてなかったことに気がついた。すぐにリビングに戻って荷物をとってから、部屋に戻って家着に着替えた。すると、お母さんに呼ばれて、いつも通り夕食作りの手伝いを頼まれた。お米を炊飯器に入れて、野菜をいくらか切って鍋に入れ込む。手伝いが終わって、部屋に戻った時、そういえば今日のご飯はなんだろうと思ったが、それ以上は深く考えずに、勉強用具を机の上に広げた。
勉強をしていると、スマホにメッセージアプリからの通知が届いた。メッセージの送り主は友美。グループチャットにそのメッセージは届いていた。
『再来週のクリスマス。午後から私の家でパーティーをしない?』
私は目を疑った。まさか、友美が倉持咲の言っていた通りにパーティーを開こうとしているとは。思わず、ごくりと唾を呑む。それから、立て続けにメンバーからの返事が届いた。
『オッケー、行く行く!』
『わかった〜』
『その日は北海道に旅行行くから無理〜 ごめんね』
『行けます!』
『行けそうにないよ。すまん!』
流れるように、素早くチャットが進んでいく。その中で私は何もメッセージを送れずにいる。すると、友美がチャットに戻ってきたようで、メンバーの一人一人に返事と相槌のメッセージを送り始めた。
『真希ちゃん、了解! 待ってるね』
『加奈〜 首を長ーくして待っているよ』
『きらりちゃん! それは残念…。帰ってきたらお土産ばなし聞かせてね』
『くるみー! 良かった! 嬉しい!』
『まどかちゃん、また今度おいでね!』
彼女の一人一人への返信が流れてゆく。画面を見つめる。私の勉強の手は完全に止まってしまった。どうしようと思っていた。理由はないが、ただなんとなく行くことが億劫だった。それと、倉持咲のことがどうしても引っ掛かっていた。悩む。悩んでいると、グループチャットに友美から私宛のメッセージが届いた。
『由香里はどうする? 来るんでしょ?』
私は慌てて、返事のメッセージを打ち込もうとした。だが、すぐに言葉が出てこなかった。いつもなら深く考えずに行くと言えていた。言えていたのに、この時ばかりは言えなかった。私の心の奥の奥には、本当はイエスもノーもなかったはずなのに、できればノーを突きつけてやりたい気分になっていた。そうしている間に、他のメンバーからも同じことを聞かれ始めた。
『由香里ちゃんもおいで! 楽しそうだよ』
『そうそう、来なよ〜』
『あれ、由香里ちゃん今、メッセージ見てないかな?』
『どうだろう? わかんない』
『とにかく、楽しそうね』
『そうだね。だから、由香里もおいでね!』
私は、本当は、この誘いを断ろうと、心のどこかで考えていた。だけど、だけど、私は、気づけば、脊髄反射で了承のメッセージを打ち込んで、送っていた。
『わかった。私も行くね!』
ああ、何を言っているのだろうか。考え直してメッセージの送信を取り消そうと思ったが、もう遅かった。
『良かった! 楽しみにしててね』
友美からだった。続いて、他のメンバーも了承の返事を送ってきた。
『おお、由香里も来てくれるようで良かった!』
『由香里も来るのね! 了解!』
『由香里、オッケー』
こうして、仲間たちから喜ばれることは嬉しい。だけど、彼女たちから送られてくるメッセージに私は少し、疲れてしまっていたのかもしれない。思わず、ため息が出た。
ご飯が出来上がったので、お母さんと一緒に食べる。今日の献立はシチューだった。無言で食べているとお母さんが何か気になるとでも言いたげな顔をしていた。
「どうしたの?」
「いや、また重たい顔をしてるなーと思って」
「大丈夫だよ」
気にせずにシチューを口に運ぶ。お母さんはスプーンを皿の上に置いた。
「いや、大丈夫じゃない顔をしている」
「大丈夫だって」
「そうには、見えないんだけどな」
部屋の中が無言になる。重たい空気が流れた。シチューを運ぶ手は完全に止まった。
「由香里は、心の奥の自分を封じ込めている。だから、とても心配なのだけど」
全くもってその通りだった。私は自分の気持ちを封じ込めている。図星だったので何も言えずに表情だけが崩れたような感覚だった。
「だからさ、もう少し心の声に従って生きてみたら、どうなの?」
お母さんの言葉は私の心の門に深く刺さった。だからこそもうこの場にいたくなくて、私は立ち上がった。シチューは半分くらい残っている。
「ごめん、今は、できない」
逃げるように自分の部屋へと歩き出す。
「由香里、ちょっと……」
お母さんのどこか引き止めたいようなそんな声が聞こえた。聞こえていたが、聞こえていないふりをして、部屋に戻り扉を閉じた。
私は部屋に入るなりベットの上に突っ込んだ。「心を閉ざしている」そんなことを言われて反発しない人間などこの世には居ないのではないか。私は急に泣きたいと思って、目を潤ませようとするが、なかなか目から涙は流れなかった。
「ううう……」
泣きたい気分なのに、泣けない。ベットの上に寝転がってそんなことを思った。
私はどうしても心を開けない。どうしてそうなったのかにテレビでよく聞くような壮絶なものは無い。代わりに、長年の小さくて些細なことたちが徐々に私の心をそうさせたのだと思う。こんなことを考えている私は疲れているのだろう。そう思ったので、一通り勉強を済ませると、私は早々にお風呂に入った。気持ちは沈んでいる。体も徐々に沈ませていく。口を水中に入れたせいで、ぶくぶくと泡が立つ。
お風呂を出て、髪を乾かす。歯を磨きながらテレビを眺める。偶然流れていたニュースは学校内で起こったいじめが原因の事件だった。私はただただ、その話題を話す、キャスターやコメンテータのことを見つめていた。彼らは「いじめをなくすには心のケアを……」とか、「学校がこうだからいじめは繰り返される」とか色々言っている。彼らは本当に私たちが置かれている状況をわかっているのだろうか。私たちですら、よく解っていないことなのに。
「なんだかなぁ」
ベットの上で私はそう呟いた。この日、私の違和感は大きく膨らんだ。なぜかと言われると、それは、倉持咲のせいなのだろうか。
私はまとまらない感情たちを押し込めて、毛布を被った。最初は眠れなかったが、十分以上すると眠りに落ちていた。
この時の私の気持ちはとても、とても、ぐちゃぐちゃだった。