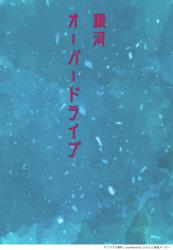それは突然だった。目的もなく外に出て街中を歩いていると見覚えのある顔を見かけた。その顔は、三年前に居なくなったはずの咲にそっくりだ。私は一体何が起きたのか理解が追いつかないでいる。思わず立ち止まってしまう。女性のことを見つめ続けているうちに向こうの方が私に気づいたようだった。彼女は私のそばまで駆け寄ってくる。
「あのー、私に何かご用でしょうか?」
彼女は恐る恐る聞いているという感じだ。私の方もどう答えて良いのかわからず何も言えずにいる。すると彼女は私の顔を少しだけ見た。
「何か幽霊でも見てるような顔ですが、大丈夫ですか?」
その通りだった。私はまるで咲の幽霊でも見てるような心地だ。だが、そんなことはあり得ない。
「そうですね……。すみません、あなたの顔が昔の友達にそっくりだったもので」
私は正直にこう答えることしかできなかった。彼女は一瞬だけ驚いたような表情を浮かべた。
「あ、なるほど。そういうことでしたか」
彼女はどうやら納得をしたようだ。私はいたたまれなくなってその場を後にしようと決めた。だが、歩き出そうとすると彼女は私の手を掴んだ。
「何するんですか!」
私は思わず声を荒らげる。
「ごめんなさい! ですが、せっかくですからお茶でもしませんか?」
そう提案されて、なぜだか私は首を縦に振っていた。
近くにあるカフェを見つけた私と彼女は、二人がけのテーブルで向かい合いながら椅子に座っている。彼女は要領よく注文を終えたところである。一方で私は何を頼もうか決まらなかったのでまだ考えている。そうしていると彼女はカバンの中から名刺入れを取り出した。
「そういえば、まだ名乗っていなかったですよね。私、こういう者です」
彼女は礼儀良く私に名刺を一枚差し出した。それを受け取ると、そこには「研究員 真澄咲良」と書いてあった。どうやら彼女、真澄さんは大きな研究機関の研究者のようだった。
「真澄咲良です。さっきからずっと聞けてなかったのですが、あなたの名前は?」
急に私の名前を聞かれて、私は一瞬だけ慌てた。
「佐野、佐野由香里です」
「由香里さんね。よろしくお願いします」
「よ、よろしくお願いします」
真澄さんはハキハキとしていて優しい人なのだなと思った。その一方で、私はつい小さい声で返事をしてしまう。
「私は名刺にも書いてある通り、星の研究をしています。由香里さんは何をしているんですか?」
「…… 無、無職です」
自信げに自らのことを紹介する真澄さんを見て私は自分のことを言うのが恥ずかしくなってしまった。だからほんの少しだけ自分が何もしていないことを言うのが躊躇われた。結果として、真澄さんの表情は何一つ変わらずにいた。
「そうなのですね」
なんだか、真澄さんに対して申し訳なくなってしまった。
「なんか、すみません……」
私は咄嗟に謝った。そうしたら真澄さんは私の目を真剣に見つめた。
「ええと、それは誰に謝っているのですか?」
「えっ」
真澄さんは私が考えていなかったようなことを言ってくれた。
「だって、無職だからといって謝るべきことは何一つないですよね」
「……そうですね」
しばし無言になる。それでも真澄さんは温かさのある真剣な目で私を見てくれた。だから、私は今まで思ってきたことをこの場で話しても良いのかもしれないと思った。
「あ、あの、私は実は友達があんまりいなくて、その、なんというか昔色々あったので……。もちろん今でも大事な友達は何人かいます。だけど、どうしても忘れられない友達が二人居て……」
私は勇気を出して声に出してみた。真澄さんはそれをちゃんと聞いてくれたように思えた。
「もしかして、そのうちの一人が私に似ているという友達ですか?」
真澄さんの問いに私は何も言わずに頷いた。
「その方々はどんな人だったんですか?」
促されるままに私は彼女のことを思い出しながら説明をした。
「不思議な、人たちでした。なんと形容したらいいのかわからない感じなんです。どこか悲しげで、苦しげで。恐ろしい物たちに苦しめられていて、自分たちの身を守るのに必死だった二人なのだと思います」
だめだ。私の中で当時のことを思い出してしまう。思い出して辛くなってしまう。でも、今言わなくちゃいけないような気がした。私はなんとか辛い気持ちを抑えた。
「だった。ということは今は?」
今は……。それは私にとって認めたくないことだった。認めなければ、咲はまだどこかで生きているような気がするから。だけど、認めるしかない。
「……二人とも死んでしまったんです。三年前に」
「まあ……」
「その二人は咲と友美っていうんです。それで、今でも、今でも見つかってないんです。咲の死体が」
私がそのことを話してから少々の間を置いて、真澄さんは口を開いた。
「二人はどうして、死んだのですか?」
私は当時のことをどこまで言えばいいのかを悩みながら答えた。
「……友美は咲に殺されたんです。でも、咲が本当に友美を殺そうとしてそうしたのかはもうわかりません。友美も咲も学校の中で同級生たちとの関係で苦しんでいました。それで二人とも心が壊れてしまって、どうしたら良いのかわからなくなったのかな……。咲は友美を死なせてしまったのを自分で許せなかったのだと思います。だから、最期は逃げて逃げて逃げた先で海に飛び込んでそれきりです……」
私は半ば泣きそうな顔でこのことを話していたと思う。真澄さんの顔すらも見れなかった。すると、真澄さんはこんなことを言った。
「あなたがその友達を大事にしていることは伝わりました。その方は多分、あなたにとってこれからも大事な存在であり続けると思います」
「私、私は二人のために何ができたんでしょうか。今でも考えてしまうんです」
「何ができたか、ですか」
「そうです。咲にはしたかったことがあったんです。結局それを果たすことはできませんでした。だから私は、今でも後悔しているんです。当時のことを……」
私の話を聞き終えると真澄さんは考えるような姿勢をとった。それから程なくして、答えは出た。
「二人がしたかったこと、二人に代わってあなたが叶えてあげたらどうですか? それはあなたのためにもなる気がします」
「……」
私は、私は真澄さんの提案に何も返す言葉が出なかった。
「由香里さん、私が思うにあなたは事の全てを一人で抱え過ぎてしまっています。だから、自分のことを蔑ろにしているんじゃないですか?」
その通りだった。私は全てを一人で抱え込もうと自分のことを蔑ろにした。だからこそ私の時間は止まったままだ。だが、自分ではこれ以外の方法が見つからなかった。見つからなかったのだ。真澄さんにこう言われて私は心の核にあるやるせなさを突かれたような気がした。
「由香里さん、もっと自分を大事にしてください。死んでしまった二人のためとは言いません。私自身があなたには自分を労って欲しいと思っているのです」
「それは、それはどうしてですか? どうして、初めて会った私にこんなことを言うんですか?」
「直感的に言うべきだと思いました。でも、話を聞いてたらわかりました。あなたはここまでずっと、苦しいことややるせないことに立ち向かっているのだと思うんです」
「もっと自分を大事にしてほしい」と言われて私は大事にできるほど器用な人間ではない。でも、私の心はもうぼろぼろで、だからこそ、このメッセージは心の奥底に痛いほど伝わった。
真澄さんは真剣に言ってくれた。私はなぜだか急に、今までずっと忘れて感じないようにしていた辛さややるせなさが溢れ出してきた。
何も言葉が出ない代わりに私は涙を流した。体の中にある全ての水分を使うんじゃないかと思う程の大量の涙を流した。それはしばらく止まらなかった。真澄さんは席を立って私の横で肩をさすってくれた。
「いつか、二人ができなかったことを叶えられる日が来ます。そうしたら、きっとあなたは自分を大事にできるようになると思うんです。まずは、ずっと抱えていた辛さをどうか、どうか手放してください。私からのお願いです」
真澄さんは全力で私のことを心配してくれた。私はいつから自分を蔑ろにしていたのだろう。もっと、もっと自分を大事にしたいとようやく思えた。この苦しさややるせなさは全てを一気に手放すことはできない。だけど、今少しだけ手放せたような気がした。
「あのー、私に何かご用でしょうか?」
彼女は恐る恐る聞いているという感じだ。私の方もどう答えて良いのかわからず何も言えずにいる。すると彼女は私の顔を少しだけ見た。
「何か幽霊でも見てるような顔ですが、大丈夫ですか?」
その通りだった。私はまるで咲の幽霊でも見てるような心地だ。だが、そんなことはあり得ない。
「そうですね……。すみません、あなたの顔が昔の友達にそっくりだったもので」
私は正直にこう答えることしかできなかった。彼女は一瞬だけ驚いたような表情を浮かべた。
「あ、なるほど。そういうことでしたか」
彼女はどうやら納得をしたようだ。私はいたたまれなくなってその場を後にしようと決めた。だが、歩き出そうとすると彼女は私の手を掴んだ。
「何するんですか!」
私は思わず声を荒らげる。
「ごめんなさい! ですが、せっかくですからお茶でもしませんか?」
そう提案されて、なぜだか私は首を縦に振っていた。
近くにあるカフェを見つけた私と彼女は、二人がけのテーブルで向かい合いながら椅子に座っている。彼女は要領よく注文を終えたところである。一方で私は何を頼もうか決まらなかったのでまだ考えている。そうしていると彼女はカバンの中から名刺入れを取り出した。
「そういえば、まだ名乗っていなかったですよね。私、こういう者です」
彼女は礼儀良く私に名刺を一枚差し出した。それを受け取ると、そこには「研究員 真澄咲良」と書いてあった。どうやら彼女、真澄さんは大きな研究機関の研究者のようだった。
「真澄咲良です。さっきからずっと聞けてなかったのですが、あなたの名前は?」
急に私の名前を聞かれて、私は一瞬だけ慌てた。
「佐野、佐野由香里です」
「由香里さんね。よろしくお願いします」
「よ、よろしくお願いします」
真澄さんはハキハキとしていて優しい人なのだなと思った。その一方で、私はつい小さい声で返事をしてしまう。
「私は名刺にも書いてある通り、星の研究をしています。由香里さんは何をしているんですか?」
「…… 無、無職です」
自信げに自らのことを紹介する真澄さんを見て私は自分のことを言うのが恥ずかしくなってしまった。だからほんの少しだけ自分が何もしていないことを言うのが躊躇われた。結果として、真澄さんの表情は何一つ変わらずにいた。
「そうなのですね」
なんだか、真澄さんに対して申し訳なくなってしまった。
「なんか、すみません……」
私は咄嗟に謝った。そうしたら真澄さんは私の目を真剣に見つめた。
「ええと、それは誰に謝っているのですか?」
「えっ」
真澄さんは私が考えていなかったようなことを言ってくれた。
「だって、無職だからといって謝るべきことは何一つないですよね」
「……そうですね」
しばし無言になる。それでも真澄さんは温かさのある真剣な目で私を見てくれた。だから、私は今まで思ってきたことをこの場で話しても良いのかもしれないと思った。
「あ、あの、私は実は友達があんまりいなくて、その、なんというか昔色々あったので……。もちろん今でも大事な友達は何人かいます。だけど、どうしても忘れられない友達が二人居て……」
私は勇気を出して声に出してみた。真澄さんはそれをちゃんと聞いてくれたように思えた。
「もしかして、そのうちの一人が私に似ているという友達ですか?」
真澄さんの問いに私は何も言わずに頷いた。
「その方々はどんな人だったんですか?」
促されるままに私は彼女のことを思い出しながら説明をした。
「不思議な、人たちでした。なんと形容したらいいのかわからない感じなんです。どこか悲しげで、苦しげで。恐ろしい物たちに苦しめられていて、自分たちの身を守るのに必死だった二人なのだと思います」
だめだ。私の中で当時のことを思い出してしまう。思い出して辛くなってしまう。でも、今言わなくちゃいけないような気がした。私はなんとか辛い気持ちを抑えた。
「だった。ということは今は?」
今は……。それは私にとって認めたくないことだった。認めなければ、咲はまだどこかで生きているような気がするから。だけど、認めるしかない。
「……二人とも死んでしまったんです。三年前に」
「まあ……」
「その二人は咲と友美っていうんです。それで、今でも、今でも見つかってないんです。咲の死体が」
私がそのことを話してから少々の間を置いて、真澄さんは口を開いた。
「二人はどうして、死んだのですか?」
私は当時のことをどこまで言えばいいのかを悩みながら答えた。
「……友美は咲に殺されたんです。でも、咲が本当に友美を殺そうとしてそうしたのかはもうわかりません。友美も咲も学校の中で同級生たちとの関係で苦しんでいました。それで二人とも心が壊れてしまって、どうしたら良いのかわからなくなったのかな……。咲は友美を死なせてしまったのを自分で許せなかったのだと思います。だから、最期は逃げて逃げて逃げた先で海に飛び込んでそれきりです……」
私は半ば泣きそうな顔でこのことを話していたと思う。真澄さんの顔すらも見れなかった。すると、真澄さんはこんなことを言った。
「あなたがその友達を大事にしていることは伝わりました。その方は多分、あなたにとってこれからも大事な存在であり続けると思います」
「私、私は二人のために何ができたんでしょうか。今でも考えてしまうんです」
「何ができたか、ですか」
「そうです。咲にはしたかったことがあったんです。結局それを果たすことはできませんでした。だから私は、今でも後悔しているんです。当時のことを……」
私の話を聞き終えると真澄さんは考えるような姿勢をとった。それから程なくして、答えは出た。
「二人がしたかったこと、二人に代わってあなたが叶えてあげたらどうですか? それはあなたのためにもなる気がします」
「……」
私は、私は真澄さんの提案に何も返す言葉が出なかった。
「由香里さん、私が思うにあなたは事の全てを一人で抱え過ぎてしまっています。だから、自分のことを蔑ろにしているんじゃないですか?」
その通りだった。私は全てを一人で抱え込もうと自分のことを蔑ろにした。だからこそ私の時間は止まったままだ。だが、自分ではこれ以外の方法が見つからなかった。見つからなかったのだ。真澄さんにこう言われて私は心の核にあるやるせなさを突かれたような気がした。
「由香里さん、もっと自分を大事にしてください。死んでしまった二人のためとは言いません。私自身があなたには自分を労って欲しいと思っているのです」
「それは、それはどうしてですか? どうして、初めて会った私にこんなことを言うんですか?」
「直感的に言うべきだと思いました。でも、話を聞いてたらわかりました。あなたはここまでずっと、苦しいことややるせないことに立ち向かっているのだと思うんです」
「もっと自分を大事にしてほしい」と言われて私は大事にできるほど器用な人間ではない。でも、私の心はもうぼろぼろで、だからこそ、このメッセージは心の奥底に痛いほど伝わった。
真澄さんは真剣に言ってくれた。私はなぜだか急に、今までずっと忘れて感じないようにしていた辛さややるせなさが溢れ出してきた。
何も言葉が出ない代わりに私は涙を流した。体の中にある全ての水分を使うんじゃないかと思う程の大量の涙を流した。それはしばらく止まらなかった。真澄さんは席を立って私の横で肩をさすってくれた。
「いつか、二人ができなかったことを叶えられる日が来ます。そうしたら、きっとあなたは自分を大事にできるようになると思うんです。まずは、ずっと抱えていた辛さをどうか、どうか手放してください。私からのお願いです」
真澄さんは全力で私のことを心配してくれた。私はいつから自分を蔑ろにしていたのだろう。もっと、もっと自分を大事にしたいとようやく思えた。この苦しさややるせなさは全てを一気に手放すことはできない。だけど、今少しだけ手放せたような気がした。