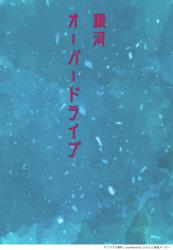佐伯くんと久しぶりに会ってから数日が経った。彼に言われた言葉を私はうまく理解できずにいる。もう少し労わるべきとはどういうことなのだろうか。私は背負っていかなきゃならないことがある。それは咲と友美のことだ。二人とも辛い思いを抱えてそれに耐えきれずにいなくなってしまった。その辛い思いを抱かせてしまったのは無意識のうちに辛いことを強いていた私であり、私は他の誰も背負ってはくれない全ての業を背負い続けるつもりである。そうでもしなきゃ、私はいなくなってしまった二人に顔向けができない。辛い道だとはわかっているつもりだ。それでも、それを知っているからこそ背負い続ける気でいる。
そう考えているうちにチャットアプリに久しぶりの着信があった。誰からだろうか。そう思ってスマホを開くと相手は真希ちゃんからだった。
『由香里ちゃん久しぶり! 突然だけど、もし良かったら今度会わない? 由香里ちゃんと久しぶりに会いたくなっちゃった笑』
このメッセージを読んでからすぐに次のメッセージが届いた。そこには希望の場所と彼女の都合が合う日時が記されていた。どの日時も私は空いていたのと、集合場所に指定されていたパスタ屋さんのチョイスにも異議はなかったので私はこの誘いを受けることにした。
真希ちゃんと会う当日。集合場所が少し遠かったので私は自転車を使うことにした。自転車を使うのはおおよそ一年振りだった。メンテナンスを少し怠っていたので、なんとなく走り心地が悪かったが、久しぶりに乗る自転車は気持ちが良かった。季節は冬になり道に沿って植えられている木々の葉は既に抜け落ちていた。季節は巡っている。私の気持ちなんて全く気にしないで巡り続けている。そう考えると友美と咲がいなくなった時点で私の時間は止まってしまったのだろう。あれからもう三年経つのかと思うと私にとって時の流れは早いような遅いような気がした。そんなことを考えながら自転車を漕ぎ続け、冷たい風は私の頬を切るように当たり続けていた。
やがて集合地点のパスタ屋さんに到着した。近くの停められそうな場所に自転車を置くと私はチャットアプリを確かめた。どうやら真希ちゃんは予定よりも数分遅れて来るらしい。仕方がないので外で待つことにした。
待っている間色々な人がここの前を通り過ぎていった。その人達の様子を観察しながら私はなんとなく寂しい気持ちになった。大した理由はないがなんとなく通り過ぎていった人々のような温かい日常は私には来ないような気がしてしまった。それは、なぜなのだろうか。私にはまだ真希ちゃんのような友達はいる。なのに私はいざという時に頼れる人が誰もいないような錯覚に陥っている。それが錯覚だとわかっているだけまだ自分のことをわかっている方なのかもしれない。それでもどうしてか私は独りぼっちだと思ってしまう自分がいる。
考え続けているとどんどん気持ちが沈んでしまったのでぼーっとしていると真希ちゃんがようやく現れた。
「由香里ちゃん、久しぶり!」
彼女の雰囲気は三年前からあまり変わっていない。けど、少しは大人っぽくなったような気がする。そう思うとまた少しだけ寂しくなった。私はその気持ちに蓋をして彼女に笑顔を向けた。
「久しぶり、真希ちゃん!」
「いつ振りだっけ?」
「おととし以来じゃない?」
「そっかー。なんかごめんね。二年も会えていなくて」
彼女は深く頭を下げた。
「どうしたの? そんな深刻にならなくても……」
「いや、私この二年間由香里ちゃんのことをほったらかしにしてたような気がして……。由香里ちゃん、この三年ずっと辛い気持ちを抱えているはずなのに、大事な時に力になることができなくてごめんなさい」
真希ちゃんはこのことをとても後悔しているように見えた。私は彼女の謝罪をどう受け取って良いのか、一瞬わからなくなってしまった。こういう理由で謝られるのは初めてだったからだ。考えに考えて私はようやく言葉を絞り出した。
「ありがとう。むしろ、ありがとうだよ。ずっと心配していてくれて」
頭を上げた彼女の目は嬉しそうに潤んでいた。
お互い落ち着いたところでようやく店内に入った。席に座ると私たちはすぐにメニュー表を開いた。
「何にする」
真希ちゃんがメニュー表を見ながら聞いてきた。
「そうだね、カルボナーラにするよ。そっちは?」
「私はペペロンチーノで」
「オッケー」
「じゃあ、注文するね」
そう言って彼女は店員さんを呼んだ。テキパキと注文を終えると私たちは明るい話をした。最近聴いている音楽のこととか、流行りのアニメの話で盛り上がった。
「私ね、今大学で心理学を勉強しているんだ」
アニメの話が終わったところで彼女はこんなことを言った。
「そうなんだ」
「そうそう。内容が難しくて大変だけど楽しいよ」
大変と彼女は言っていたが、それを言う彼女の顔は少し笑っていた。多分、彼女は充実した毎日を過ごしているのだろう。私は、それは良いことだと思えた。
「良かったね、充実している感じで」
「うん」
そうしていると注文していたカルボナーラとペペロンチーノが届いたので私たちは何も喋らずに食べた。何も喋らず黙々と食べたのは、この後話すことがなんとなく決まっていて、それは私達にとって一番辛いことだからだと思う。しばらくして私達はそれぞれのパスタを食べ終えた。
「ごちそうさま」
「ごちそうさまでした」
少しの間沈黙が続き、最終的に話を切り出したのは真希ちゃんの方からだった。
「あれからもうすぐ三年が経っちゃうんだね」
「そうだね……」
彼女は窓から見える店の外を眺め始めた。私もその方向を向いて外を見始めた。
「二人が死んじゃってからさ、私ずっと考えているんだ。人の心の脆さについて」
私はそれを聞いて、なぜ彼女は大学で心理学を学んでいるのかを理解できた。そうか、真希ちゃんは三年前どうしてあんなことになってしまったのかを心理学の力で少しでも理解しようとしているんだ。
「それでね、今勉強していることを使って少しでも、あんなことがもう起きないようにしたい。私はそのために今頑張っているんだ」
その強い意志に私は何も言うことができなかった。真希ちゃんはあの時感じたやるせなさや悲しみを力にして、他の誰かが同じ思いをしないために頑張っている。それなのに、それなのに一方で私は何もできずにただ生きているだけだ。頑張っている真希ちゃんを見て、生きているだけの自分が許せなくなる。私はようやく声を出せた。
「私はさ、自分が許せないや。あの時誰も助けられなかったのに、二人ともいなくなっちゃたのに。今何もしてない自分が許せない。真希ちゃんや他のみんなは進むべき道を見つけて進み続けているのに自分だけが時間から取り残されているような気がする。どうしたらいいんだろう。私にできそうなことはもう何もないのに、どうしても求めてしまうんだ、自分にできることを」
これを聞いた真希ちゃんは最初何と思ったのだろうか。彼女は飲みかけだった水を一口飲むと私の目を真っ直ぐに見つめてきた。
「数日前に佐伯くんから聞いたよ。由香里ちゃんがまだあのことで思い詰めているって。由香里ちゃん、お願いだから無茶はしないで」
「……」
この瞬間、どうして真希ちゃんが久しぶりに私と会おうとしたのか納得した。数日前に会った佐伯くんから私の様子を聞いたからなのだ。それで私に話を聞きたくなったのか。私はそれを理解したが、彼女が言った「無茶はしないで」という言葉に何も言えずにいる。
「由香里ちゃんがあの時のことをとても悔やんでいるのはわかる。だけど、今のあなたは死に向かいそうで怖いの。何もできないからって言っていつの間にか居なくなっていそうで、不安になってしまう。あなたにできることならまだたくさんあるはずなのに」
真希ちゃんは真剣な顔で言い切った。確かに、彼女の言う通りかもしれなかった。私は無意識のうちに心が死に向かっているのかもしれない。
「だから、お願い。死なないために生きていくためにあなた自身が望むことを見つけて。あなたまでいなくなったら、私はもう耐えられないから」
彼女の願いに私は首を縦に振るしかできなかった。だけど、生きていくために何を望んでいいのか私にはわからない。彼女は「ゆっくりでいいから探してみて」と話を付け加えてくれたけど、私にはそれを見つけられる自信がなかった。それから私達は近いうちにまた会う約束を交わして解散となった。
そう考えているうちにチャットアプリに久しぶりの着信があった。誰からだろうか。そう思ってスマホを開くと相手は真希ちゃんからだった。
『由香里ちゃん久しぶり! 突然だけど、もし良かったら今度会わない? 由香里ちゃんと久しぶりに会いたくなっちゃった笑』
このメッセージを読んでからすぐに次のメッセージが届いた。そこには希望の場所と彼女の都合が合う日時が記されていた。どの日時も私は空いていたのと、集合場所に指定されていたパスタ屋さんのチョイスにも異議はなかったので私はこの誘いを受けることにした。
真希ちゃんと会う当日。集合場所が少し遠かったので私は自転車を使うことにした。自転車を使うのはおおよそ一年振りだった。メンテナンスを少し怠っていたので、なんとなく走り心地が悪かったが、久しぶりに乗る自転車は気持ちが良かった。季節は冬になり道に沿って植えられている木々の葉は既に抜け落ちていた。季節は巡っている。私の気持ちなんて全く気にしないで巡り続けている。そう考えると友美と咲がいなくなった時点で私の時間は止まってしまったのだろう。あれからもう三年経つのかと思うと私にとって時の流れは早いような遅いような気がした。そんなことを考えながら自転車を漕ぎ続け、冷たい風は私の頬を切るように当たり続けていた。
やがて集合地点のパスタ屋さんに到着した。近くの停められそうな場所に自転車を置くと私はチャットアプリを確かめた。どうやら真希ちゃんは予定よりも数分遅れて来るらしい。仕方がないので外で待つことにした。
待っている間色々な人がここの前を通り過ぎていった。その人達の様子を観察しながら私はなんとなく寂しい気持ちになった。大した理由はないがなんとなく通り過ぎていった人々のような温かい日常は私には来ないような気がしてしまった。それは、なぜなのだろうか。私にはまだ真希ちゃんのような友達はいる。なのに私はいざという時に頼れる人が誰もいないような錯覚に陥っている。それが錯覚だとわかっているだけまだ自分のことをわかっている方なのかもしれない。それでもどうしてか私は独りぼっちだと思ってしまう自分がいる。
考え続けているとどんどん気持ちが沈んでしまったのでぼーっとしていると真希ちゃんがようやく現れた。
「由香里ちゃん、久しぶり!」
彼女の雰囲気は三年前からあまり変わっていない。けど、少しは大人っぽくなったような気がする。そう思うとまた少しだけ寂しくなった。私はその気持ちに蓋をして彼女に笑顔を向けた。
「久しぶり、真希ちゃん!」
「いつ振りだっけ?」
「おととし以来じゃない?」
「そっかー。なんかごめんね。二年も会えていなくて」
彼女は深く頭を下げた。
「どうしたの? そんな深刻にならなくても……」
「いや、私この二年間由香里ちゃんのことをほったらかしにしてたような気がして……。由香里ちゃん、この三年ずっと辛い気持ちを抱えているはずなのに、大事な時に力になることができなくてごめんなさい」
真希ちゃんはこのことをとても後悔しているように見えた。私は彼女の謝罪をどう受け取って良いのか、一瞬わからなくなってしまった。こういう理由で謝られるのは初めてだったからだ。考えに考えて私はようやく言葉を絞り出した。
「ありがとう。むしろ、ありがとうだよ。ずっと心配していてくれて」
頭を上げた彼女の目は嬉しそうに潤んでいた。
お互い落ち着いたところでようやく店内に入った。席に座ると私たちはすぐにメニュー表を開いた。
「何にする」
真希ちゃんがメニュー表を見ながら聞いてきた。
「そうだね、カルボナーラにするよ。そっちは?」
「私はペペロンチーノで」
「オッケー」
「じゃあ、注文するね」
そう言って彼女は店員さんを呼んだ。テキパキと注文を終えると私たちは明るい話をした。最近聴いている音楽のこととか、流行りのアニメの話で盛り上がった。
「私ね、今大学で心理学を勉強しているんだ」
アニメの話が終わったところで彼女はこんなことを言った。
「そうなんだ」
「そうそう。内容が難しくて大変だけど楽しいよ」
大変と彼女は言っていたが、それを言う彼女の顔は少し笑っていた。多分、彼女は充実した毎日を過ごしているのだろう。私は、それは良いことだと思えた。
「良かったね、充実している感じで」
「うん」
そうしていると注文していたカルボナーラとペペロンチーノが届いたので私たちは何も喋らずに食べた。何も喋らず黙々と食べたのは、この後話すことがなんとなく決まっていて、それは私達にとって一番辛いことだからだと思う。しばらくして私達はそれぞれのパスタを食べ終えた。
「ごちそうさま」
「ごちそうさまでした」
少しの間沈黙が続き、最終的に話を切り出したのは真希ちゃんの方からだった。
「あれからもうすぐ三年が経っちゃうんだね」
「そうだね……」
彼女は窓から見える店の外を眺め始めた。私もその方向を向いて外を見始めた。
「二人が死んじゃってからさ、私ずっと考えているんだ。人の心の脆さについて」
私はそれを聞いて、なぜ彼女は大学で心理学を学んでいるのかを理解できた。そうか、真希ちゃんは三年前どうしてあんなことになってしまったのかを心理学の力で少しでも理解しようとしているんだ。
「それでね、今勉強していることを使って少しでも、あんなことがもう起きないようにしたい。私はそのために今頑張っているんだ」
その強い意志に私は何も言うことができなかった。真希ちゃんはあの時感じたやるせなさや悲しみを力にして、他の誰かが同じ思いをしないために頑張っている。それなのに、それなのに一方で私は何もできずにただ生きているだけだ。頑張っている真希ちゃんを見て、生きているだけの自分が許せなくなる。私はようやく声を出せた。
「私はさ、自分が許せないや。あの時誰も助けられなかったのに、二人ともいなくなっちゃたのに。今何もしてない自分が許せない。真希ちゃんや他のみんなは進むべき道を見つけて進み続けているのに自分だけが時間から取り残されているような気がする。どうしたらいいんだろう。私にできそうなことはもう何もないのに、どうしても求めてしまうんだ、自分にできることを」
これを聞いた真希ちゃんは最初何と思ったのだろうか。彼女は飲みかけだった水を一口飲むと私の目を真っ直ぐに見つめてきた。
「数日前に佐伯くんから聞いたよ。由香里ちゃんがまだあのことで思い詰めているって。由香里ちゃん、お願いだから無茶はしないで」
「……」
この瞬間、どうして真希ちゃんが久しぶりに私と会おうとしたのか納得した。数日前に会った佐伯くんから私の様子を聞いたからなのだ。それで私に話を聞きたくなったのか。私はそれを理解したが、彼女が言った「無茶はしないで」という言葉に何も言えずにいる。
「由香里ちゃんがあの時のことをとても悔やんでいるのはわかる。だけど、今のあなたは死に向かいそうで怖いの。何もできないからって言っていつの間にか居なくなっていそうで、不安になってしまう。あなたにできることならまだたくさんあるはずなのに」
真希ちゃんは真剣な顔で言い切った。確かに、彼女の言う通りかもしれなかった。私は無意識のうちに心が死に向かっているのかもしれない。
「だから、お願い。死なないために生きていくためにあなた自身が望むことを見つけて。あなたまでいなくなったら、私はもう耐えられないから」
彼女の願いに私は首を縦に振るしかできなかった。だけど、生きていくために何を望んでいいのか私にはわからない。彼女は「ゆっくりでいいから探してみて」と話を付け加えてくれたけど、私にはそれを見つけられる自信がなかった。それから私達は近いうちにまた会う約束を交わして解散となった。