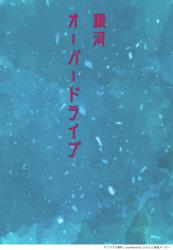試合から二日が過ぎて月曜日の朝、うつろな目でベット脇に置いてある置き時計を見ると遅刻ぎりぎりの時間だった。寝ぼけていた私は一瞬で目が覚めた。
「しまった!」
慌てて必要な物を通学鞄にまとめる。服をパジャマから制服に着替え終えて、リビングに出ると寝巻き姿のお母さんが眠そうに椅子に座ってテレビを眺めていた。見ていたのは朝のニュース番組で、この時報じられていたのは全国で起こっているいじめ問題だった。私にはどうだっていいことだったので、お母さんに挨拶をしてからすぐに出ようと思った。
「おはよう、お母さん! なんで起こしてくれなかったの?」
「ああ、おはよう由香里。いやね、下手に起こしてもどうせ起きないでしょ」
「それは、そうだけど……」
「でしょ。あ、そうだ、あなた学校でいじめられたりしてないよね?」
「そんなこと…… 、ないよ」
「あ、そっ。それならいいけど」
「じゃあ、行ってきます!」
「行ってらっしゃい」
私は誰かにいじめらているとは思わなかった。靴を履いて、玄関を出てからお母さんが言った言葉がなぜだか心に残った。階段を降りて駐輪場に置いてある自分お自転車に乗って漕ぎ出した。私の通う学校は街の真ん中に近い所にあり、私の家は真ん中から少し外れた場所だったので、少し遠かった。学校へはもう間に合わないことが確実だったのでゆっくりと走った。
走っている中で自分の心に掛かっている靄の正体について考えた。考えたがまるで答えは出なかった。と言うよりもこの時、私の心の奥底で答えは出ていたが、もう一方の自分が答えを出したくなかったと言った方が正しいのかもしれない。走っていると何台もの車が私の横を通り過ぎてゆく。気づいていた。それは今までのことを通して気づいていた。澄み渡る空の下で私は横を通り過ぎてゆく車たちをただ眺めながら自転車を漕ぐしかできなかった。
学校の校舎に入った時、すでに授業は始まっている時間だった。広い廊下を歩いていく。私の教室は正門から入って少し奥の方だった。奥の方へと進み終わると教室が見えた。恐る恐る扉を開けて教室へと入っていく。静かに教室へ入って自分の席に座ろうとすると、先生がそれに気づいた様子で私に向かって尋ねた。
「おい、佐野。なんで遅刻した?」
私は一瞬答えに困ったがすぐに正直な理由を言うことにした。だが、恥ずかしくて上手く言えなかった。
「ね、寝坊、しました!」
するとすぐに教室中で笑いが起こった。みんな大笑いしていて、中には椅子から転げ落ちている者もいた。それからなぜか先生まで腹を抱えて笑っていた。その様子を見て私まで笑えてきた。教室中が笑いに包まれていた。落ち着いたところで先生は、
「まあ、それなら仕方ない。今後は気をつけろよ」
と言ってくれたので私は遠慮なく自分の机に座って文房具を広げた。それからの授業は真面目に受けた。真面目に受けないとこの先進学できないからだ。私の学校は特に理由がなければ大学に進学するような所だった。みんな進学するものだから、みんなの中には競争意識があるのだと先生や大人は言うが、私はそうは思えなかった。みんながみんなにこうであれと見えない圧力をかけていた。私たちには見えないしがらみが多い。だからこそ、私たちは自由でないのだ。大人たちは私たちのことを自由だとも言うが、そもそも、私たちに自由なんてあるのだろうか。
私たち高校生が持てる自由ってなんだ。私たちは大人たちから与えられた三年間の時間と自由をもて余して、誰かを蹴落とし合っている。その果てに何があるんだ。私は心の奥底ではこう思っていた。でも、それを表に出して戦える程の力も勇気も持ち合わせていなかった。休み時間、そんなことを考え込んでいるとクラスメイトの一人、真由美ちゃんが私の席の前に立っていた。彼女は申し訳なさそうに、でもどこか見くびった感じでこう言った。
「由香里、ペン貸して〜」
彼女は私にペンを貸してくれとねだった。私にはそれを断れるほどの勇気もないので、ためらいながらも筆入れから使わないペンを取り出した。ペンが使えるか確認してから私は彼女にペンを差し出した。
「どうぞ」
「ありがとう〜」
彼女はペンを受け取った。それからすぐに私の机から離れていった。ちなみにペンはその授業が終わった後で彼女が返してくれた。
昼休みになって、昼食のための弁当を持ってこなかったことに気づいた。私は昼食を購買で買うことにした。教室から購買までは少し距離があって、時間が少しかかる。歩いていると大勢の同学年や先輩とすれ違う。そうすると、通りかかった同級生の一人、苑子ちゃんが声をかけてきた。
「お、由香里おはよう!」
「おはよう。てかもう、こんにちはの時間だよ」
「そうか、ごめんごめん」
「いいよ。気にしないで」
「わかった。そういえばさ、今度友美ちゃんの家に呼ばれたのよね。私初めて行くから、どうしたらいいかな?」
「うーんとね、マカロンとか持っていけばいいと思うよ。彼女、マカロンが大好きだから」
「オッケー。ありがとう!」
「うん。それじゃあ私、ご飯買いに行かなきゃだから、じゃあね」
「じゃあね!」
彼女を含めて同級生のみんなは私を見て、声をかけてくることが多かった。私は彼らへの違和感はあったが、人当たりを良くしようと頑張っていたり、バスケ部のリーダー的存在である友美に気に入られていたので、同級生たちは私には友好的に接してくれていた。大まかな理由はその二つであったが、そうしてくれたもう一つの訳があった。私と仲良くしておけば友美の機嫌を損ねないことに繋がるからだ。友美はバスケ部のリーダー的存在だった。それに加えて学年のネットワークをも取り仕切ろうとしていたので、彼女はバスケ部以外の多くの同級生たちとも繋がりを持っていた。同級生たちはそんな彼女の小さな欲望を恐れた。だからこそ、友美自身や私にいい顔をしようとしていたのだと思う。
彼女らとの挨拶が終わったので、私は購買に急いだ。好きな親子丼が毎日すぐになくなってしまうからだ。購買にたどり着いた時、親子丼はまだ売っていた。購買には名物のおばさんがいた。私が見るに良い年齢の重ね方をしていた彼女はどうやら何十年も前からここで働いているそうだ。私は彼女を一目見てからこう言った。
「すみません、親子丼ください!」
「はい、五百円ね〜」
「ありがとうございます!」
「あなたさ、来るときはいつも親子丼頼むよね。好きなのかい?」
「ええ、そうですね」
「それは、嬉しいね。いつもありがとう」
「どういたしまして」
私は見事に親子丼を手にした。私は急いで、教室へと戻って親子丼の容器の蓋を開けた。親子丼の匂いが鼻元にきた。鶏肉と卵を口に運ぶ。この学校の購買が売っている親子丼は美味しかった。なんの変哲も無い親子丼ではある。でも、五百円の価値はあると思えた。普段、同級生たちとの関わりに違和感を抱いていた私にとっては、昼ごはんを食べるときは無心でいられる時間だった。言い換えれば、それくらいしか、私には心が休まる時間が無かった。私が親子丼を食べている時、クラスのみんなはなぜか私に構わず他のことをしていた。やはり彼女らも本当のところは見えないヒエラルキーのために友達を持つことへの疲れを感じていたのかもしれない。後になってそう思う。
親子丼を食べ終えて午後の授業を受ける。この日の五時限目は日本史だった。
「ええと、今日は鎌倉時代のことを話すね〜」
日本史の先生は授業をこう始めた。今日は十世紀も前の話だった。先生は続ける。
「承久の乱の後に、鎌倉幕府は朝廷を監視するために六波羅探題を置いたのです」
私には遠い遠い過去の事にしか思えず、ただ空虚な天井を眺めていた。遠い過去で何があったのかなんて私には興味は無い。ただ、今をやり過ごすことで精一杯だった。私がこれからする選択は未来に何を残すのだろうか。授業中、先生の話す事を聞いて、板書をノートにまとめながらいろんな考えが頭の中を駆け巡っていた。一方で他のクラスメイトたちは真面目に受けている者もいれば、隠れてスマホを眺めている者もいる。
所詮世界はそんな物なのかもしれない。私にはこの先への希望がなかった。目線を変えて、窓の外を眺める。空は晴れている。私の気持ちなんて無視して。そうこうしているうちに授業が終わった。
「今日はここまで。この続きはまた次回」
「起立」
日直の声に従って私たちは立ち上がる。
「礼。ありがとうございました」
「ありがとございました」
授業が終わって休み時間、教室が瞬く間に騒がしくなった。今日の授業のノートを一通りまとめ終えてページを畳む。騒がしい教室に向かって少しだけため息を吐いた。すると、クラスメイトの一人である美里ちゃんが目の前にやってきた。
「ノート見せてもらえる?」
「いいけど」
「ありがとう!」
私はさっきまとめ終えたノートを開いて美里ちゃんに見せた。彼女はすかさずにスマホをポケットから取り出して、私のノートの写真を撮った。
「じゃあ、見させてもらうね」
「うん」
すぐに彼女は去っていった。
私は毎日、いろんな人からペンを貸して欲しい、ノート見せて欲しいなどのいろんな事が求められていた。それは一見するととても喜ばしいことではあるのだが、同時に疲れることでもあった。私は彼女らからいいように利用されているのではないか。逆にいえば私も彼女らをいいように利用しようとしているのではないか。そんな考えすら浮かんでしまうほどに私の心は貧しい。私の心の貧しさは、誰が引き起こしたのだろうか。それを誰かに問い詰めたくなるのだが、誰もそれに答えられる者など私の周りにはいなかった。みんな、心が貧しいのだ。この時代を生きる十代の我々はみんな、寂しいのだ。虚しいのだ。なぜそうなったかは誰のせいでもない。けど、私は私たちが寂しすぎる世代だということを頭の片隅で感じていた。閉塞感と絶望感がそこには存在していた。
「しまった!」
慌てて必要な物を通学鞄にまとめる。服をパジャマから制服に着替え終えて、リビングに出ると寝巻き姿のお母さんが眠そうに椅子に座ってテレビを眺めていた。見ていたのは朝のニュース番組で、この時報じられていたのは全国で起こっているいじめ問題だった。私にはどうだっていいことだったので、お母さんに挨拶をしてからすぐに出ようと思った。
「おはよう、お母さん! なんで起こしてくれなかったの?」
「ああ、おはよう由香里。いやね、下手に起こしてもどうせ起きないでしょ」
「それは、そうだけど……」
「でしょ。あ、そうだ、あなた学校でいじめられたりしてないよね?」
「そんなこと…… 、ないよ」
「あ、そっ。それならいいけど」
「じゃあ、行ってきます!」
「行ってらっしゃい」
私は誰かにいじめらているとは思わなかった。靴を履いて、玄関を出てからお母さんが言った言葉がなぜだか心に残った。階段を降りて駐輪場に置いてある自分お自転車に乗って漕ぎ出した。私の通う学校は街の真ん中に近い所にあり、私の家は真ん中から少し外れた場所だったので、少し遠かった。学校へはもう間に合わないことが確実だったのでゆっくりと走った。
走っている中で自分の心に掛かっている靄の正体について考えた。考えたがまるで答えは出なかった。と言うよりもこの時、私の心の奥底で答えは出ていたが、もう一方の自分が答えを出したくなかったと言った方が正しいのかもしれない。走っていると何台もの車が私の横を通り過ぎてゆく。気づいていた。それは今までのことを通して気づいていた。澄み渡る空の下で私は横を通り過ぎてゆく車たちをただ眺めながら自転車を漕ぐしかできなかった。
学校の校舎に入った時、すでに授業は始まっている時間だった。広い廊下を歩いていく。私の教室は正門から入って少し奥の方だった。奥の方へと進み終わると教室が見えた。恐る恐る扉を開けて教室へと入っていく。静かに教室へ入って自分の席に座ろうとすると、先生がそれに気づいた様子で私に向かって尋ねた。
「おい、佐野。なんで遅刻した?」
私は一瞬答えに困ったがすぐに正直な理由を言うことにした。だが、恥ずかしくて上手く言えなかった。
「ね、寝坊、しました!」
するとすぐに教室中で笑いが起こった。みんな大笑いしていて、中には椅子から転げ落ちている者もいた。それからなぜか先生まで腹を抱えて笑っていた。その様子を見て私まで笑えてきた。教室中が笑いに包まれていた。落ち着いたところで先生は、
「まあ、それなら仕方ない。今後は気をつけろよ」
と言ってくれたので私は遠慮なく自分の机に座って文房具を広げた。それからの授業は真面目に受けた。真面目に受けないとこの先進学できないからだ。私の学校は特に理由がなければ大学に進学するような所だった。みんな進学するものだから、みんなの中には競争意識があるのだと先生や大人は言うが、私はそうは思えなかった。みんながみんなにこうであれと見えない圧力をかけていた。私たちには見えないしがらみが多い。だからこそ、私たちは自由でないのだ。大人たちは私たちのことを自由だとも言うが、そもそも、私たちに自由なんてあるのだろうか。
私たち高校生が持てる自由ってなんだ。私たちは大人たちから与えられた三年間の時間と自由をもて余して、誰かを蹴落とし合っている。その果てに何があるんだ。私は心の奥底ではこう思っていた。でも、それを表に出して戦える程の力も勇気も持ち合わせていなかった。休み時間、そんなことを考え込んでいるとクラスメイトの一人、真由美ちゃんが私の席の前に立っていた。彼女は申し訳なさそうに、でもどこか見くびった感じでこう言った。
「由香里、ペン貸して〜」
彼女は私にペンを貸してくれとねだった。私にはそれを断れるほどの勇気もないので、ためらいながらも筆入れから使わないペンを取り出した。ペンが使えるか確認してから私は彼女にペンを差し出した。
「どうぞ」
「ありがとう〜」
彼女はペンを受け取った。それからすぐに私の机から離れていった。ちなみにペンはその授業が終わった後で彼女が返してくれた。
昼休みになって、昼食のための弁当を持ってこなかったことに気づいた。私は昼食を購買で買うことにした。教室から購買までは少し距離があって、時間が少しかかる。歩いていると大勢の同学年や先輩とすれ違う。そうすると、通りかかった同級生の一人、苑子ちゃんが声をかけてきた。
「お、由香里おはよう!」
「おはよう。てかもう、こんにちはの時間だよ」
「そうか、ごめんごめん」
「いいよ。気にしないで」
「わかった。そういえばさ、今度友美ちゃんの家に呼ばれたのよね。私初めて行くから、どうしたらいいかな?」
「うーんとね、マカロンとか持っていけばいいと思うよ。彼女、マカロンが大好きだから」
「オッケー。ありがとう!」
「うん。それじゃあ私、ご飯買いに行かなきゃだから、じゃあね」
「じゃあね!」
彼女を含めて同級生のみんなは私を見て、声をかけてくることが多かった。私は彼らへの違和感はあったが、人当たりを良くしようと頑張っていたり、バスケ部のリーダー的存在である友美に気に入られていたので、同級生たちは私には友好的に接してくれていた。大まかな理由はその二つであったが、そうしてくれたもう一つの訳があった。私と仲良くしておけば友美の機嫌を損ねないことに繋がるからだ。友美はバスケ部のリーダー的存在だった。それに加えて学年のネットワークをも取り仕切ろうとしていたので、彼女はバスケ部以外の多くの同級生たちとも繋がりを持っていた。同級生たちはそんな彼女の小さな欲望を恐れた。だからこそ、友美自身や私にいい顔をしようとしていたのだと思う。
彼女らとの挨拶が終わったので、私は購買に急いだ。好きな親子丼が毎日すぐになくなってしまうからだ。購買にたどり着いた時、親子丼はまだ売っていた。購買には名物のおばさんがいた。私が見るに良い年齢の重ね方をしていた彼女はどうやら何十年も前からここで働いているそうだ。私は彼女を一目見てからこう言った。
「すみません、親子丼ください!」
「はい、五百円ね〜」
「ありがとうございます!」
「あなたさ、来るときはいつも親子丼頼むよね。好きなのかい?」
「ええ、そうですね」
「それは、嬉しいね。いつもありがとう」
「どういたしまして」
私は見事に親子丼を手にした。私は急いで、教室へと戻って親子丼の容器の蓋を開けた。親子丼の匂いが鼻元にきた。鶏肉と卵を口に運ぶ。この学校の購買が売っている親子丼は美味しかった。なんの変哲も無い親子丼ではある。でも、五百円の価値はあると思えた。普段、同級生たちとの関わりに違和感を抱いていた私にとっては、昼ごはんを食べるときは無心でいられる時間だった。言い換えれば、それくらいしか、私には心が休まる時間が無かった。私が親子丼を食べている時、クラスのみんなはなぜか私に構わず他のことをしていた。やはり彼女らも本当のところは見えないヒエラルキーのために友達を持つことへの疲れを感じていたのかもしれない。後になってそう思う。
親子丼を食べ終えて午後の授業を受ける。この日の五時限目は日本史だった。
「ええと、今日は鎌倉時代のことを話すね〜」
日本史の先生は授業をこう始めた。今日は十世紀も前の話だった。先生は続ける。
「承久の乱の後に、鎌倉幕府は朝廷を監視するために六波羅探題を置いたのです」
私には遠い遠い過去の事にしか思えず、ただ空虚な天井を眺めていた。遠い過去で何があったのかなんて私には興味は無い。ただ、今をやり過ごすことで精一杯だった。私がこれからする選択は未来に何を残すのだろうか。授業中、先生の話す事を聞いて、板書をノートにまとめながらいろんな考えが頭の中を駆け巡っていた。一方で他のクラスメイトたちは真面目に受けている者もいれば、隠れてスマホを眺めている者もいる。
所詮世界はそんな物なのかもしれない。私にはこの先への希望がなかった。目線を変えて、窓の外を眺める。空は晴れている。私の気持ちなんて無視して。そうこうしているうちに授業が終わった。
「今日はここまで。この続きはまた次回」
「起立」
日直の声に従って私たちは立ち上がる。
「礼。ありがとうございました」
「ありがとございました」
授業が終わって休み時間、教室が瞬く間に騒がしくなった。今日の授業のノートを一通りまとめ終えてページを畳む。騒がしい教室に向かって少しだけため息を吐いた。すると、クラスメイトの一人である美里ちゃんが目の前にやってきた。
「ノート見せてもらえる?」
「いいけど」
「ありがとう!」
私はさっきまとめ終えたノートを開いて美里ちゃんに見せた。彼女はすかさずにスマホをポケットから取り出して、私のノートの写真を撮った。
「じゃあ、見させてもらうね」
「うん」
すぐに彼女は去っていった。
私は毎日、いろんな人からペンを貸して欲しい、ノート見せて欲しいなどのいろんな事が求められていた。それは一見するととても喜ばしいことではあるのだが、同時に疲れることでもあった。私は彼女らからいいように利用されているのではないか。逆にいえば私も彼女らをいいように利用しようとしているのではないか。そんな考えすら浮かんでしまうほどに私の心は貧しい。私の心の貧しさは、誰が引き起こしたのだろうか。それを誰かに問い詰めたくなるのだが、誰もそれに答えられる者など私の周りにはいなかった。みんな、心が貧しいのだ。この時代を生きる十代の我々はみんな、寂しいのだ。虚しいのだ。なぜそうなったかは誰のせいでもない。けど、私は私たちが寂しすぎる世代だということを頭の片隅で感じていた。閉塞感と絶望感がそこには存在していた。