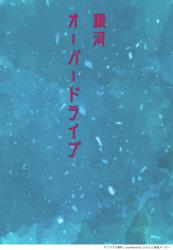次の日、私は学校へと向かって全速力で自転車を漕いでいた。この数日の中では一番足取りが軽かったように思う。真希ちゃんと直接会って話がしたかったのだ。だが、久しぶりに教室に入るとそこはもう私の知っている教室ではなかった。机は綺麗に並んでおらず、クラスメイトの何人かは大きな声を上げて、ゲームか何かに夢中になっていた。また、一部のクラスメイトはその壊れてしまった空気が怖くてたまらなかったのか、死んだような顔をして机に突っ伏していた。私は自分の席を探したが、その席は既に壊されていた。同じように咲の座席だったらしき物も破壊されていた。どうして、こうなってしまったのだろうか。まるで彼らが抱えていた鬱憤が咲が居なくなったことで、表に溢れ出したような景色だった。私の存在に気づいたのか、クラスメイト達から壊れた状態に追い打ちをかけるような冷たい空気が伝わった。
仕方なく、教室の隅にいるとやがて真希ちゃんが私の側までやってきた。
「久しぶり、由香里ちゃん!」
彼女は私の存在を確かめると突然私を抱きしめた。その力はとても強かった。
「私、あれからずっと心配してたんだから……」
そう言われると私は少しくすぐったい思いだったが、とても嬉しかった。
「ありがとう……」
私はそう言うことで精一杯だった。それでも真希ちゃんに意思は伝わったようで、私のことを離すと彼女は安心したような顔をした。
「よかった、元気そうで」
彼女は半泣きになりながらこう言った。彼女は話を続けた。
「友美ちゃんがあなたを襲ってから、どうだったの?」
私は彼女にはちゃんと事の全てを伝えなくてはならないような気がしていた。だからこそ、私は自分の中で伝えられると思ったことを真希ちゃんに丁寧に説明した。彼女は何も言わずに私の話を聞いてくれた。
「そうだったのね……」
説明を終えると彼女は少し寂しそうな顔をした。
「二人が死んじゃったと思うとやっぱり寂しいな」
彼女は少しあっさりとした調子でそう言った。一瞬だけ私は彼女はなんて冷たいんだと思ったが、あっさりとした調子で言うのも仕方がないことだと私は考えを改めた。。なぜなら、彼女は二人の死を直接見てはいないから。死を見なかったことは良いことだと思う。私はそれを見てしまったせいで、未だに何かに囚われている。
真希ちゃんが何かを言いかけた時だった。近くで誰かが舌打ちをした。舌打ちが聞こえた方を振り向くとクラスメイトの女子が私と真希ちゃんの会話を聞いていたようだった。それから少し大きな声でわざとらしく言った。
「かわいそうな人」
その言葉が、私にとってはとどめだった。自分の中で無意識のうちに考えていたある事がついに噴き出した。
「かわいそう、だって?」
私は彼女の顔を見る。彼女の顔はいかにも私のことを嘲笑していた。
「ええ、あなたはかわいそうな人よ」
私は何も考えずに彼女の胸ぐらを掴みかかった。
「違う! 私はかわいそうでも何でもない! ただ、私は友美と咲、両方のただの友達! 二人にとって私は加害者であり被害者なの!」
真希ちゃんを含め、周りにいたクラスメイトの何人かが慌てて私を宥めようとした。だが、それを私は無視して彼女の胸ぐらを掴み続けた。
「何よ、それ! 加害者でもあり被害者でもあるってどういうこと!」
彼女は迷惑そうに言った。それでも私は訴え続けた。
「どういうことって、よくよく考えて! 私達が二人にしたことを。きっと、私達は加害者でもあり被害者でもあるんだ! 二人はもう居ない。だから本当のところはわからない。でもね、私達は決してそのどちらかという訳でないの。私達皆んなで二人を傷つけたし、二人に傷つけられたの。だから、自分は被害者だなんてこれぽっちも思わないで!」
「それじゃあ、まるで私まで悪いみたいじゃない!」
彼女は半泣きで叫んだ。私ももしかするととんでもなくぐちゃぐちゃな顔になっていたのかもしれない。
「そう言っているんだ私は! 私達は皆んなで二人を失った罪を背負わなければならない! それは私達自身が招いてしまったこと。だから、この罪からは逃げられない!」
この時の私は二人が居なくなったのは、この学校にあったヒエラルキーのせいでもあったと考えた。家族と上手くいかず、学校内ヒエラルキーの上位にいることに拘ってしまった友美。そのせいで、関わることそのものを疎まれてしまった咲。二人はナイフや孔雀といったものを頼って生きていくしかなかったのだと思った。だから私は叫び続けた。
「これは、私達が勝手に作って勝手に悩んだり困ったりしているヒエラルキーが招いたことよ! それに苦しんだ二人は心を壊して死んでしまった。だとしたら、二人が死んだことは私達全員が抱えるべき罪なのよ!」
私は目が滲んで視界が悪くなっていた。それでも相手の女子がとても恐ろしげにこちらを見ていたことはわかっていた。
「はあ、あなたどうかしてる……」
「どうかしていて、結構! 私の心は死んだんだ! 二人が死んでしまった時に!」
「怖いよあんた……」
その言葉を聞いた瞬間、ずっと耐えていたものがどうしてか耐えられなくなった。
「……ああ、ああ、うわぁ!」
私はとうとう堪えきれなくなって泣き崩れた。周りは呆然として私のことを見つめていたように思う。やがて、事に気づいた先生が駆けつけた。
「おい、佐野何があった!」
私は何も説明できなかった。様子を見ていた真希ちゃんが代わりに説明をしてくれたらしかった。
「わかった。とりあえずここじゃない場所に運ぼう。佐野、立てるか?」
それからはあまり覚えていないのだが、私は先生と真希ちゃんに支えられて教室を後にした。この瞬間、クラスメイト達はどこか冷ややかな目を私に向けていたと思う。結局、私が言いたかったことはクラスメイト達には伝わらなかったのだろう。私は結局は一人でこの罪を背負うべきなのだと思った。
この事がとどめとなって、私の心は完全に壊れてしまった。自ら抱えてしまったことに耐えられなかったのだと思う。しばらくの間は何もできず、どこにも行けなくなっていた。そうこうしている間にも時間は流れ、いつの間にか高校生ですらなくなった。あの時に私のことを呆然と眺めていただけのクラスメイト達とはそれきりになってしまった。
二人を失ったことに整理がつけられずに時間だけが過ぎて三年が経った。
仕方なく、教室の隅にいるとやがて真希ちゃんが私の側までやってきた。
「久しぶり、由香里ちゃん!」
彼女は私の存在を確かめると突然私を抱きしめた。その力はとても強かった。
「私、あれからずっと心配してたんだから……」
そう言われると私は少しくすぐったい思いだったが、とても嬉しかった。
「ありがとう……」
私はそう言うことで精一杯だった。それでも真希ちゃんに意思は伝わったようで、私のことを離すと彼女は安心したような顔をした。
「よかった、元気そうで」
彼女は半泣きになりながらこう言った。彼女は話を続けた。
「友美ちゃんがあなたを襲ってから、どうだったの?」
私は彼女にはちゃんと事の全てを伝えなくてはならないような気がしていた。だからこそ、私は自分の中で伝えられると思ったことを真希ちゃんに丁寧に説明した。彼女は何も言わずに私の話を聞いてくれた。
「そうだったのね……」
説明を終えると彼女は少し寂しそうな顔をした。
「二人が死んじゃったと思うとやっぱり寂しいな」
彼女は少しあっさりとした調子でそう言った。一瞬だけ私は彼女はなんて冷たいんだと思ったが、あっさりとした調子で言うのも仕方がないことだと私は考えを改めた。。なぜなら、彼女は二人の死を直接見てはいないから。死を見なかったことは良いことだと思う。私はそれを見てしまったせいで、未だに何かに囚われている。
真希ちゃんが何かを言いかけた時だった。近くで誰かが舌打ちをした。舌打ちが聞こえた方を振り向くとクラスメイトの女子が私と真希ちゃんの会話を聞いていたようだった。それから少し大きな声でわざとらしく言った。
「かわいそうな人」
その言葉が、私にとってはとどめだった。自分の中で無意識のうちに考えていたある事がついに噴き出した。
「かわいそう、だって?」
私は彼女の顔を見る。彼女の顔はいかにも私のことを嘲笑していた。
「ええ、あなたはかわいそうな人よ」
私は何も考えずに彼女の胸ぐらを掴みかかった。
「違う! 私はかわいそうでも何でもない! ただ、私は友美と咲、両方のただの友達! 二人にとって私は加害者であり被害者なの!」
真希ちゃんを含め、周りにいたクラスメイトの何人かが慌てて私を宥めようとした。だが、それを私は無視して彼女の胸ぐらを掴み続けた。
「何よ、それ! 加害者でもあり被害者でもあるってどういうこと!」
彼女は迷惑そうに言った。それでも私は訴え続けた。
「どういうことって、よくよく考えて! 私達が二人にしたことを。きっと、私達は加害者でもあり被害者でもあるんだ! 二人はもう居ない。だから本当のところはわからない。でもね、私達は決してそのどちらかという訳でないの。私達皆んなで二人を傷つけたし、二人に傷つけられたの。だから、自分は被害者だなんてこれぽっちも思わないで!」
「それじゃあ、まるで私まで悪いみたいじゃない!」
彼女は半泣きで叫んだ。私ももしかするととんでもなくぐちゃぐちゃな顔になっていたのかもしれない。
「そう言っているんだ私は! 私達は皆んなで二人を失った罪を背負わなければならない! それは私達自身が招いてしまったこと。だから、この罪からは逃げられない!」
この時の私は二人が居なくなったのは、この学校にあったヒエラルキーのせいでもあったと考えた。家族と上手くいかず、学校内ヒエラルキーの上位にいることに拘ってしまった友美。そのせいで、関わることそのものを疎まれてしまった咲。二人はナイフや孔雀といったものを頼って生きていくしかなかったのだと思った。だから私は叫び続けた。
「これは、私達が勝手に作って勝手に悩んだり困ったりしているヒエラルキーが招いたことよ! それに苦しんだ二人は心を壊して死んでしまった。だとしたら、二人が死んだことは私達全員が抱えるべき罪なのよ!」
私は目が滲んで視界が悪くなっていた。それでも相手の女子がとても恐ろしげにこちらを見ていたことはわかっていた。
「はあ、あなたどうかしてる……」
「どうかしていて、結構! 私の心は死んだんだ! 二人が死んでしまった時に!」
「怖いよあんた……」
その言葉を聞いた瞬間、ずっと耐えていたものがどうしてか耐えられなくなった。
「……ああ、ああ、うわぁ!」
私はとうとう堪えきれなくなって泣き崩れた。周りは呆然として私のことを見つめていたように思う。やがて、事に気づいた先生が駆けつけた。
「おい、佐野何があった!」
私は何も説明できなかった。様子を見ていた真希ちゃんが代わりに説明をしてくれたらしかった。
「わかった。とりあえずここじゃない場所に運ぼう。佐野、立てるか?」
それからはあまり覚えていないのだが、私は先生と真希ちゃんに支えられて教室を後にした。この瞬間、クラスメイト達はどこか冷ややかな目を私に向けていたと思う。結局、私が言いたかったことはクラスメイト達には伝わらなかったのだろう。私は結局は一人でこの罪を背負うべきなのだと思った。
この事がとどめとなって、私の心は完全に壊れてしまった。自ら抱えてしまったことに耐えられなかったのだと思う。しばらくの間は何もできず、どこにも行けなくなっていた。そうこうしている間にも時間は流れ、いつの間にか高校生ですらなくなった。あの時に私のことを呆然と眺めていただけのクラスメイト達とはそれきりになってしまった。
二人を失ったことに整理がつけられずに時間だけが過ぎて三年が経った。