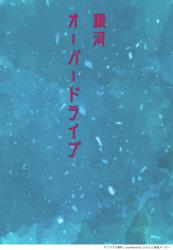翌日の正午過ぎ、私は借りたままだった服が入っている袋を持って、咲の家の前にいた。チャイムを鳴らす勇気が出せずに十分以上立ち尽くしていたら、先に玄関が開いた。中から出てきたのは咲のお母さんだった。
「どうしたの? うちに用があるのなら上がって」
彼女は何気ない顔で私を招き入れてくれた。私はどんな反応をしていいのかわからず、無言のままで家の中へと入った。
家の中に入るとそこには数ヶ月前には無かった咲の後飾りの祭壇が置かれていた。彼女が死んだという事実が私の心に再び迫ってきた。咲のお母さんは祭壇に手を合わせてから、キッチンの方へと向かった。私は部屋中を訳もなく見回してみた。よく見ると、未使用のダンボールが何枚もあり、引越し業者のロゴが書かれたダンボール箱にはいくつかの物が詰められていた。
ダンボール箱に目を向けていると後ろの方から咲のお母さんが戻ってくる気配があった。
「ああ、ごめんなさい。目につくようなところにダンボールが置かれてて」
「いえ、大丈夫ですよ……、それよりどうしてですか?」
「うーん、今度引っ越すのよ。ここに居続けてもあんまり意味がない気がして……」
「そうだったんですね……」
私は、咲が居なくなってしまってから、この家は大変だったのだろうとなんとなく察した。直接は聞けなかったがもしかしたら咲が事件を起こしたということがこの家や周りの関係を破壊してしまったのかもしれなかった。
それからしばらくの間、この部屋が静かになった。私はただ、彼女の遺影を見ることしかできずにいた。咲の遺影は少しばかり微笑んでいる。
先に話を切り出したのは咲のお母さんだった。
「最近の写真で笑ってるのが、これくらいしかなかったの。あの子の笑う姿をしばらく見ていなかったわ」
咲のお母さんは用意したお茶を一口飲んだ。それから彼女の話は続いた。
「でも、最後の数日間はあなたのおかげで笑顔の咲を見ることができたわ。佐野さんには感謝してもしきれないわね」
私の中で楽しそうな彼女の姿が思い浮かんだ。
「ありがとうございます」
私は最大限の気持ちを込めて頭を下げた。私は、咲にどれだけのことをしてやれたのだろうか。頭の中でこの考えがずっと場所を取っている。私はそれを正直に咲のお母さんに言ってみることにした。
「今、こんなことになってしまって、私は、咲にどれだけのことができたのだろうって考えてしまうんです」
「いや、あの時の咲にとっては十分なことをしたのだと思うわ」
「それなら、それなら幸いです」
私はまた頭を下げた。すると、彼女は何かに気づいたような顔をした。
「何か、あなたは心の奥で辛い物を抱えてる気がするわ。せっかくだから、どんなことを考えているのか教えてくれない?」
そう言われて私は頭の中にあるモヤモヤの正体が何なのかわからなくなってしまった。
「じゃあ、こんなことになって辛かったことって何?」
彼女が言い換えてくれた。言い換えてくれたおかげなのか、頭の中にあった物が噴き出てきた。いくつかの言葉が頭の中で再生される。
「なんも言わないのね、お前。この死神が!」
「これで少しは人の痛みがわかったか死神め」
「しーにがみ! しーにがみ!」
「今回の件で刑事さんや同級生から死神とかって言われたんです。事実そうかもしれないですよね。だって、私の友達だった二人が一斉に居なくなってしまったから。私は私のことを死神だってこれからずっと思うのでしょうか? 私のせいでこうなったのならば、私には大きな罪があるのでしょうか? それが頭の中でつっかえています……」
咲のお母さんは私の答えを聞いて私のために真剣に返事を考えてくれた。
「あなたは別に死神でもなんでもないんじゃないかな。あなたは咲と友美ちゃんを助けようとしただけでしょ。どうして死神呼ばわりされなきゃいけないわけ?」
「それは、私が……」
「あなたが責められる筋合いは無いんじゃないかな。少なくとも私はそう思っているけど」
この言葉を聞いて私は少しだけ心が軽くなった。今でも、この言葉が私を助けてくれている。彼女の話は続いた。
「咲が居なくなってから二ヶ月経って思うのは、本当は正しい人間なんてこの世のどこにも居ないんじゃないかって。みんなどこかでは正しいし、どこかでは間違っているんだよ。だから、あなたは死神ではないよ、きっとね」
「でも、世の中みんな正しくないのならば、だとしたらどうして私はこんなに苦しまなければならないの!」
私は思わず叫んだ。すぐに冷静になってまた苦しくなってしまった。
「ごめんなさい……」
「いいのよ。こんなことになったら誰だって、苦しくなるよ。私もね、咲が居なくなってしまって今、とっても苦しいのよ」
この時、私には彼女の目に涙が見えた。この時、彼女もまた苦しかったのだと思う。
彼女は目をハンカチで拭うと再び話し始めた。
「私、ここ数日で咲も友美ちゃんもこんなことになったのは学校のせいもあるのかなと思ってね。実際のところはどうなのかわからないけど、そういう面もあるんじゃないかな」
彼女の言葉を聞いて、私の中でぐちゃぐちゃになっていたものたちが少しずつ形を整えて言葉になり始めた。私の中でようやく言えそうな言葉が一つ見つかった。
「ありがとうございます。なんだか言いたくて言えなかった苦しいモヤモヤをようやく言葉にできそうです」
「そう、それなら良かったわ」
私はここでようやく渡すべき物を渡そうと持ってきていた袋を差し出した。
「あの、これ前に咲から借りたままになっていた衣服です。今更かもしれないですが、お返しします」
すると咲のお母さんは袋を受け取らなかった。
「これは、思い出としてあなたが持っていてください。その方がいい気がするの」
「そうですか。では、いただきます」
私はそれを手元の方に戻した。
日が傾き始めた頃に私は咲の家を出ることにした。
「じゃあ、気をつけてね」
見送られた時、咲のお母さんは笑顔だった。
「本日はありがとうございました」
私が頭を下げると彼女も頭を下げてくれた。
「いいのよ。また何かあったら連絡してね」
「はい、ではまた」
帰り道で私は明日は学校に行こうと決めた。学校に行って真希ちゃんらと久しぶりに話がしたいと思った。それから、自分にできることを少しずつやっていこうとも思っていた。
夕陽は既に落ちていて、辺りはほんのり暗かった。
「どうしたの? うちに用があるのなら上がって」
彼女は何気ない顔で私を招き入れてくれた。私はどんな反応をしていいのかわからず、無言のままで家の中へと入った。
家の中に入るとそこには数ヶ月前には無かった咲の後飾りの祭壇が置かれていた。彼女が死んだという事実が私の心に再び迫ってきた。咲のお母さんは祭壇に手を合わせてから、キッチンの方へと向かった。私は部屋中を訳もなく見回してみた。よく見ると、未使用のダンボールが何枚もあり、引越し業者のロゴが書かれたダンボール箱にはいくつかの物が詰められていた。
ダンボール箱に目を向けていると後ろの方から咲のお母さんが戻ってくる気配があった。
「ああ、ごめんなさい。目につくようなところにダンボールが置かれてて」
「いえ、大丈夫ですよ……、それよりどうしてですか?」
「うーん、今度引っ越すのよ。ここに居続けてもあんまり意味がない気がして……」
「そうだったんですね……」
私は、咲が居なくなってしまってから、この家は大変だったのだろうとなんとなく察した。直接は聞けなかったがもしかしたら咲が事件を起こしたということがこの家や周りの関係を破壊してしまったのかもしれなかった。
それからしばらくの間、この部屋が静かになった。私はただ、彼女の遺影を見ることしかできずにいた。咲の遺影は少しばかり微笑んでいる。
先に話を切り出したのは咲のお母さんだった。
「最近の写真で笑ってるのが、これくらいしかなかったの。あの子の笑う姿をしばらく見ていなかったわ」
咲のお母さんは用意したお茶を一口飲んだ。それから彼女の話は続いた。
「でも、最後の数日間はあなたのおかげで笑顔の咲を見ることができたわ。佐野さんには感謝してもしきれないわね」
私の中で楽しそうな彼女の姿が思い浮かんだ。
「ありがとうございます」
私は最大限の気持ちを込めて頭を下げた。私は、咲にどれだけのことをしてやれたのだろうか。頭の中でこの考えがずっと場所を取っている。私はそれを正直に咲のお母さんに言ってみることにした。
「今、こんなことになってしまって、私は、咲にどれだけのことができたのだろうって考えてしまうんです」
「いや、あの時の咲にとっては十分なことをしたのだと思うわ」
「それなら、それなら幸いです」
私はまた頭を下げた。すると、彼女は何かに気づいたような顔をした。
「何か、あなたは心の奥で辛い物を抱えてる気がするわ。せっかくだから、どんなことを考えているのか教えてくれない?」
そう言われて私は頭の中にあるモヤモヤの正体が何なのかわからなくなってしまった。
「じゃあ、こんなことになって辛かったことって何?」
彼女が言い換えてくれた。言い換えてくれたおかげなのか、頭の中にあった物が噴き出てきた。いくつかの言葉が頭の中で再生される。
「なんも言わないのね、お前。この死神が!」
「これで少しは人の痛みがわかったか死神め」
「しーにがみ! しーにがみ!」
「今回の件で刑事さんや同級生から死神とかって言われたんです。事実そうかもしれないですよね。だって、私の友達だった二人が一斉に居なくなってしまったから。私は私のことを死神だってこれからずっと思うのでしょうか? 私のせいでこうなったのならば、私には大きな罪があるのでしょうか? それが頭の中でつっかえています……」
咲のお母さんは私の答えを聞いて私のために真剣に返事を考えてくれた。
「あなたは別に死神でもなんでもないんじゃないかな。あなたは咲と友美ちゃんを助けようとしただけでしょ。どうして死神呼ばわりされなきゃいけないわけ?」
「それは、私が……」
「あなたが責められる筋合いは無いんじゃないかな。少なくとも私はそう思っているけど」
この言葉を聞いて私は少しだけ心が軽くなった。今でも、この言葉が私を助けてくれている。彼女の話は続いた。
「咲が居なくなってから二ヶ月経って思うのは、本当は正しい人間なんてこの世のどこにも居ないんじゃないかって。みんなどこかでは正しいし、どこかでは間違っているんだよ。だから、あなたは死神ではないよ、きっとね」
「でも、世の中みんな正しくないのならば、だとしたらどうして私はこんなに苦しまなければならないの!」
私は思わず叫んだ。すぐに冷静になってまた苦しくなってしまった。
「ごめんなさい……」
「いいのよ。こんなことになったら誰だって、苦しくなるよ。私もね、咲が居なくなってしまって今、とっても苦しいのよ」
この時、私には彼女の目に涙が見えた。この時、彼女もまた苦しかったのだと思う。
彼女は目をハンカチで拭うと再び話し始めた。
「私、ここ数日で咲も友美ちゃんもこんなことになったのは学校のせいもあるのかなと思ってね。実際のところはどうなのかわからないけど、そういう面もあるんじゃないかな」
彼女の言葉を聞いて、私の中でぐちゃぐちゃになっていたものたちが少しずつ形を整えて言葉になり始めた。私の中でようやく言えそうな言葉が一つ見つかった。
「ありがとうございます。なんだか言いたくて言えなかった苦しいモヤモヤをようやく言葉にできそうです」
「そう、それなら良かったわ」
私はここでようやく渡すべき物を渡そうと持ってきていた袋を差し出した。
「あの、これ前に咲から借りたままになっていた衣服です。今更かもしれないですが、お返しします」
すると咲のお母さんは袋を受け取らなかった。
「これは、思い出としてあなたが持っていてください。その方がいい気がするの」
「そうですか。では、いただきます」
私はそれを手元の方に戻した。
日が傾き始めた頃に私は咲の家を出ることにした。
「じゃあ、気をつけてね」
見送られた時、咲のお母さんは笑顔だった。
「本日はありがとうございました」
私が頭を下げると彼女も頭を下げてくれた。
「いいのよ。また何かあったら連絡してね」
「はい、ではまた」
帰り道で私は明日は学校に行こうと決めた。学校に行って真希ちゃんらと久しぶりに話がしたいと思った。それから、自分にできることを少しずつやっていこうとも思っていた。
夕陽は既に落ちていて、辺りはほんのり暗かった。