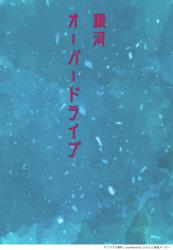「娘がいなくなって喜ぶ親がどこにいるっていうんだ!」
立ち上がるなり私は隣にいた男女に向かって怒鳴りつけた。私なりの全力の大声だった。
「あんた誰?」
驚かれつつも男性の方から問いかけられた。
「誰って、石崎友美の友達です」
私は堂々と答えた。
「ああ、君か。友美を殺した人の友達っていうのは」
彼は手に持っていたジュースを口に含んだ。
「どうしてそんな冷静なんですか……」
私は思ったことをそのまま口に出した。
「だって事実でしょ」
そう言う男性の言葉には自暴自棄のようなものが含まれているような気がした。
だが、この時の私にはそれを受け止められるほどの冷静さはなかった。
あまりにもいなくなった娘に対して失礼すぎる。私はこの二人に対して怒っていた。
「そうですけど、その態度は友美に失礼過ぎるのでは」
「失礼過ぎるって、それはあんたが決めることではないでしょ」
男性の意見には確かに一理あった。これは私が勝手に決めつけていいことではなかったし、ましてや死人の気持ちはわからないからだ。そう思いつつ私は彼らに対しての怒りがさらにこみ上げていた。
男性の方は平気そうな顔をしていた。もう一人の女性の方も平然そうにしていた。だが、二人の態度のどこかがおかしいと直感が告げていた。
「だって、私たちはあの子を産もうと思って産んだわけじゃないからさ、いなくなってもらって清々したのよ」
女性の方が私の目を見ながら軽い口調で語った。
「じゃあ、テレビで謝った時は何も感じてなかったってことですか」
私は思わず聞き返した。
「そうだよ。世間体を気にしてああしなきゃならないからああしただけ」
友美の両親は何も感じていないようだった。娘の死についてまるで他人事のように語っていた。彼らは平気そうにジュースを飲んだ。私の中でますます違和感が大きくなった。やはりこの大人たちを許せることができそうになかった。
私は友美の父親の頬を勢いよく叩いた。彼が飲んでいたジュースが地面にこぼれた。
「痛っ! 何するんだ!」
男性の方が私を怒鳴りつけた。私はそれに怯まないように強い口調で言い返した。
「何するんだって。当たり前のことをしたの!」
彼は拳を握って私のことを殴りかかろうとした。幸い友美の母親の方が彼の手を押さえてくれた。この瞬間、なんとなくだが彼が殴りかかろうとしたのは自分のことを責められたからだけじゃないような気がした。なぜなら二人の態度にはどこか矛盾したようなものがあったからだ。
「当たり前のことだって……」
「そう! こんなことになったのは何のせい? あなた達が友美のことを放っておいたからこんなことになったんでしょ! 私はあなた達を許したくない!」
私は全力で宣言した。私はこの二人を決して許したくない。そう固く思っていた。
「俺らのせいでこうなったって、言いがかりにも程がある」
友美の父親からは直前までの余裕が感じられなかった。言い返したいことがあるようだった。
だが、
「事実でしょ」
私がそう言った途端に彼は黙り込んでしまった。彼は頭を抱えて何かをか考え込んでいるようだった。彼は空を見上げて涙を浮かべた。その涙には何か苦しい物が感じられた。
やがて、友美の父親は空を見上げながら心の内を明かしてくれた。
「ああ、そうだな。確かに事実さ。もちろん、あんたの言う通り俺たちにも非がある。俺たちの無責任な態度のせいで友美を苦しめてしまった。だがな、あいつが苦しんでたのは俺たちのこともそうだが、学校のこともあったのじゃないかと今になって思うのさ」
彼は本当に悲しそうだった。
私は頭が真っ白になってしまった。
訳のわかならない感情が頭の中で駆け巡っていた。
その間に今度は母親の方が辛そうな顔をして、私に教えてくれた。
「私たちは友美のことをほったらかしにした。友美はだんだん壊れていったから次第に関わるのが面倒になってしまった。友美は気づいていたんだろうな、私たちがちゃんと自分と向き合ってくれていないことにね。心が壊れていく友美が怖かった。どうしていいのかもわからなかったから……」
はじめ、私は彼らは責任逃れのためにデタラメを言っているのではないかと思った。だが、二人の苦しそうな顔や言葉には嘘が無さそうだった。それに気づいた瞬間、私はその場で膝から崩れ落ちた。
「じゃあ、私はあの二人が死んだ責任をどこに求めたらいいの……」
思わず口に出してしまった。言ってしまった後で、これは許される言葉ではないと気づいた。友美の両親は私のことを怒ってもいいところだった。それでも彼らは怒らなかった。いや、怒れなかったのだと思う。
「責任か。俺たちにもこうなった責任はあるさ。頼むから俺たちのことを許さないでくれ。それが、君なりの弔い方なのなら」
彼らは友美が死んで苦しんでいたのだ。自分達の無責任さが原因でこうなってしまったと負い目を感じていたのだ。だからこそ、どうしたらいいのかわからなくなって、あんな態度になってしまったのではないか。私はそう思った。
そう思った瞬間、私の中で怒りが鎮まった。徐々に冷静さを取り戻して、やがて友美の両親に対して申し訳のないことをしてしまったと反省した。
「ごめんなさい。お二人のことを責めてしまって……」
私は彼らに向かって深く頭を下げた。
「いいんだ。友美が居なくなってから上手くいくようになったと言った俺たちの方も謝らないといけない。申し訳ない」
彼らは私に向かって頭を下げた。私はそれに対して何も返す言葉がなかった。
春の空は澄み渡って綺麗だったが私の心はぐちゃぐちゃのままだった。
友美の両親に謝られた後、自転車を押しながら私は考えた。
私たちにはああいう結末しか有り得なかったのか。
どうすれば、あの結末を回避できたのか。
この頃になると私の頭の中には、考えていても仕方のない、途方のないたらればしか出てこなくなっていた。
私は自転車に跨って、全速力で漕いだ。
「うわああ!」
行き場のない感情を叫びながら。
家に帰っても自分の部屋でずっと考え込んでしまった。
咲と友美の死には私たち全員が責任を負わなくてはいけないような気がしていた。私や二人の家族、学校の皆んなに刑事。その全員が最終的には二人を死に追いやってしまったからだ。二人のいた日々はもう戻ってこない。それが悔しかった。
「ねえ、二人とも。どうしていなくなっちゃったの……」
独り言だった。彼女たちがいなくなってしまった理由はなんとなくわかっていた。だけどどうしても納得することができなかった。
咲が死んでしまった直後に夢で見た、地獄へ向かうと言っていた二人の安らかな声がなんとなく頭の中で再生された。どうして、あんなに安らかそうだったのだろう。気がついたら夢の中の話なのにどうしても真剣に考え込んでしまっていた。
なんとなく思い立ってクローゼットの中に仕舞ってあった、咲から借りたままの衣服を取り出した。あれ以来着ることはなかったが、終ぞ彼女に返すことができなかった。それから更に思い返して、咲と一緒に買ったアクセサリーをタンスの中から取り出して机の上に置いた。
私はなんて大切な時間を彼女たちから貰ったのだろうか。二人との思い出の品々とスマホに保存されていた写真の数々を眺めて、あの二人が生きていた時間は二人がどれだけ喧嘩をしていようと、二人から傷つけられようと大切な時間だったと思う。
二人との日々を思い返して私は泣いた。泣いて泣いて、枕を濡らした。
一通り泣き終えて咲から借りた服を見つめた。
私は、彼女から借りたままだった服を今度こそ返そうと思い立った。
立ち上がるなり私は隣にいた男女に向かって怒鳴りつけた。私なりの全力の大声だった。
「あんた誰?」
驚かれつつも男性の方から問いかけられた。
「誰って、石崎友美の友達です」
私は堂々と答えた。
「ああ、君か。友美を殺した人の友達っていうのは」
彼は手に持っていたジュースを口に含んだ。
「どうしてそんな冷静なんですか……」
私は思ったことをそのまま口に出した。
「だって事実でしょ」
そう言う男性の言葉には自暴自棄のようなものが含まれているような気がした。
だが、この時の私にはそれを受け止められるほどの冷静さはなかった。
あまりにもいなくなった娘に対して失礼すぎる。私はこの二人に対して怒っていた。
「そうですけど、その態度は友美に失礼過ぎるのでは」
「失礼過ぎるって、それはあんたが決めることではないでしょ」
男性の意見には確かに一理あった。これは私が勝手に決めつけていいことではなかったし、ましてや死人の気持ちはわからないからだ。そう思いつつ私は彼らに対しての怒りがさらにこみ上げていた。
男性の方は平気そうな顔をしていた。もう一人の女性の方も平然そうにしていた。だが、二人の態度のどこかがおかしいと直感が告げていた。
「だって、私たちはあの子を産もうと思って産んだわけじゃないからさ、いなくなってもらって清々したのよ」
女性の方が私の目を見ながら軽い口調で語った。
「じゃあ、テレビで謝った時は何も感じてなかったってことですか」
私は思わず聞き返した。
「そうだよ。世間体を気にしてああしなきゃならないからああしただけ」
友美の両親は何も感じていないようだった。娘の死についてまるで他人事のように語っていた。彼らは平気そうにジュースを飲んだ。私の中でますます違和感が大きくなった。やはりこの大人たちを許せることができそうになかった。
私は友美の父親の頬を勢いよく叩いた。彼が飲んでいたジュースが地面にこぼれた。
「痛っ! 何するんだ!」
男性の方が私を怒鳴りつけた。私はそれに怯まないように強い口調で言い返した。
「何するんだって。当たり前のことをしたの!」
彼は拳を握って私のことを殴りかかろうとした。幸い友美の母親の方が彼の手を押さえてくれた。この瞬間、なんとなくだが彼が殴りかかろうとしたのは自分のことを責められたからだけじゃないような気がした。なぜなら二人の態度にはどこか矛盾したようなものがあったからだ。
「当たり前のことだって……」
「そう! こんなことになったのは何のせい? あなた達が友美のことを放っておいたからこんなことになったんでしょ! 私はあなた達を許したくない!」
私は全力で宣言した。私はこの二人を決して許したくない。そう固く思っていた。
「俺らのせいでこうなったって、言いがかりにも程がある」
友美の父親からは直前までの余裕が感じられなかった。言い返したいことがあるようだった。
だが、
「事実でしょ」
私がそう言った途端に彼は黙り込んでしまった。彼は頭を抱えて何かをか考え込んでいるようだった。彼は空を見上げて涙を浮かべた。その涙には何か苦しい物が感じられた。
やがて、友美の父親は空を見上げながら心の内を明かしてくれた。
「ああ、そうだな。確かに事実さ。もちろん、あんたの言う通り俺たちにも非がある。俺たちの無責任な態度のせいで友美を苦しめてしまった。だがな、あいつが苦しんでたのは俺たちのこともそうだが、学校のこともあったのじゃないかと今になって思うのさ」
彼は本当に悲しそうだった。
私は頭が真っ白になってしまった。
訳のわかならない感情が頭の中で駆け巡っていた。
その間に今度は母親の方が辛そうな顔をして、私に教えてくれた。
「私たちは友美のことをほったらかしにした。友美はだんだん壊れていったから次第に関わるのが面倒になってしまった。友美は気づいていたんだろうな、私たちがちゃんと自分と向き合ってくれていないことにね。心が壊れていく友美が怖かった。どうしていいのかもわからなかったから……」
はじめ、私は彼らは責任逃れのためにデタラメを言っているのではないかと思った。だが、二人の苦しそうな顔や言葉には嘘が無さそうだった。それに気づいた瞬間、私はその場で膝から崩れ落ちた。
「じゃあ、私はあの二人が死んだ責任をどこに求めたらいいの……」
思わず口に出してしまった。言ってしまった後で、これは許される言葉ではないと気づいた。友美の両親は私のことを怒ってもいいところだった。それでも彼らは怒らなかった。いや、怒れなかったのだと思う。
「責任か。俺たちにもこうなった責任はあるさ。頼むから俺たちのことを許さないでくれ。それが、君なりの弔い方なのなら」
彼らは友美が死んで苦しんでいたのだ。自分達の無責任さが原因でこうなってしまったと負い目を感じていたのだ。だからこそ、どうしたらいいのかわからなくなって、あんな態度になってしまったのではないか。私はそう思った。
そう思った瞬間、私の中で怒りが鎮まった。徐々に冷静さを取り戻して、やがて友美の両親に対して申し訳のないことをしてしまったと反省した。
「ごめんなさい。お二人のことを責めてしまって……」
私は彼らに向かって深く頭を下げた。
「いいんだ。友美が居なくなってから上手くいくようになったと言った俺たちの方も謝らないといけない。申し訳ない」
彼らは私に向かって頭を下げた。私はそれに対して何も返す言葉がなかった。
春の空は澄み渡って綺麗だったが私の心はぐちゃぐちゃのままだった。
友美の両親に謝られた後、自転車を押しながら私は考えた。
私たちにはああいう結末しか有り得なかったのか。
どうすれば、あの結末を回避できたのか。
この頃になると私の頭の中には、考えていても仕方のない、途方のないたらればしか出てこなくなっていた。
私は自転車に跨って、全速力で漕いだ。
「うわああ!」
行き場のない感情を叫びながら。
家に帰っても自分の部屋でずっと考え込んでしまった。
咲と友美の死には私たち全員が責任を負わなくてはいけないような気がしていた。私や二人の家族、学校の皆んなに刑事。その全員が最終的には二人を死に追いやってしまったからだ。二人のいた日々はもう戻ってこない。それが悔しかった。
「ねえ、二人とも。どうしていなくなっちゃったの……」
独り言だった。彼女たちがいなくなってしまった理由はなんとなくわかっていた。だけどどうしても納得することができなかった。
咲が死んでしまった直後に夢で見た、地獄へ向かうと言っていた二人の安らかな声がなんとなく頭の中で再生された。どうして、あんなに安らかそうだったのだろう。気がついたら夢の中の話なのにどうしても真剣に考え込んでしまっていた。
なんとなく思い立ってクローゼットの中に仕舞ってあった、咲から借りたままの衣服を取り出した。あれ以来着ることはなかったが、終ぞ彼女に返すことができなかった。それから更に思い返して、咲と一緒に買ったアクセサリーをタンスの中から取り出して机の上に置いた。
私はなんて大切な時間を彼女たちから貰ったのだろうか。二人との思い出の品々とスマホに保存されていた写真の数々を眺めて、あの二人が生きていた時間は二人がどれだけ喧嘩をしていようと、二人から傷つけられようと大切な時間だったと思う。
二人との日々を思い返して私は泣いた。泣いて泣いて、枕を濡らした。
一通り泣き終えて咲から借りた服を見つめた。
私は、彼女から借りたままだった服を今度こそ返そうと思い立った。