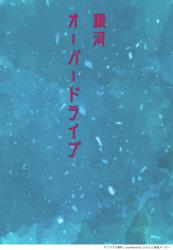事件の後、退院した私は警察からの聴取を受けた。事件に関するあれこれを聞かれた末、咎められることはなかった。どうやら、青木さんら事件に関わった警察官たちが私のことを庇ってくれたらしい。そうしているうちに事件から二ヶ月近くが経っていた。
三月の朝。私は久しぶりに学校へ行く準備をしていた。
「本当に大丈夫なの?」
荷物をまとめているとお母さんが私のことを心配してくれた。どうやらクラスのことが心配なようだった。
「まあ、無理はしないよ」
そう言いつつも私はこの時点で無理をしていた。あの事件以来、私はクラス全体のコミュニティーから追い出されていた。連絡がついたのは真希ちゃんをはじめとするほんの数人だけだった。私はそのことをお母さんには言えなかった。
荷物をまとめ終えた私は、制服を二ヶ月ぶりに着た。久しぶりに着ると少しの違和感があった。
「なんでだろ、あのきらきらしている割には中身空っぽで人を蹴落とすことばかり頭にあるクソったれどもに嫌気を感じたからかな」
制服を着た自分を鏡で見た瞬間、咲の言葉が頭の中で反響した。私はもう学校にいる何も知らない連中が嫌になり始めていた。だが、それは気のせいだと思って私は自分の気持ちに蓋をした。そうしないと私の日常が保てなくなってしまうのだから。
「じゃあ、行ってくるね!」
「気をつけてね!」
時間が来たので私は急いで家を出た。私は無理をして笑顔を作った。お母さんはそれでも笑顔で見送ってくれた。
季節が冬から春に変わろうとしていた。私はなんとなく寒さの残る道を自転車で走った。こうやって自転車で走ったのは二ヶ月ぶりだった。久しぶりに走る道は何も変わっていなかった。ただ、変わってしまったのは自分の心だった。咲と友美をほぼ同時に失ってしまった。この頃になると私は、これからどうしたらいいのだろうかとずっと考えていた。
学校に到着した時には、既に朝のホームルームが始まっている時間だった。私は下駄箱に靴を入れようと扉に手を触れた。
「痛い!」
取手に触れた瞬間何かが指に刺さった。私は慌てて取手の方を確かめた。そこにはカッターの刃先のような物がテープで貼りついていた。
「やーい、人殺し!」
「引っかかったね! きゃはは」
後ろを向くとクラスメイトの男の子と女の子が笑っていた。私の指からは血が出ていたのに。
「これで少しは人の痛みがわかったか死神め」
「しーにがみ! しーにがみ!」
死神という言葉を向けられたのはこれで二度目だった。確かに私は友美と咲を葬った死神なのかもしれない。そう思いながら私はただ二人のことを見つめることしかできなかった。
「何みてるの……」
「怖いんですけど……」
私の何に怯えたのかわからなかったが、二人は走り去ってしまった。
「おい、大丈夫か!」
担任の先生が駆けつけてきた。それからすぐに保健室で手当をしてもらった。手当が終わったところでカッターの刃が下駄箱に隠されていたことを伝えると先生は苦い顔をした。
「実はな、事件の後でクラスの仲がこじれてしまって、先生たちも手に負えないんだ」
「手に負えないって……」
「いろいろあるが、昨日は五人くらいで激しい口喧嘩をしていたよ。喧嘩を収めるのに一時間かかった……」
「どうして、そんなことに……」
「なんでだろうな……、クラスをまとめていた石崎があんなことになったから皆んなの何かが壊れてしまった。先生はそう考えている」
先生もまた苦しそうだった。二ヶ月前には目立っていなかった白髪がところどころ目立っていた。この二ヶ月での辛さが感じ取れた。
「佐野、俺はどうしたらよかったんだろうか……、何がいけなかったんだ……」
「それは、私にもわからないです……」
「そうだよな……、石崎と倉持の一番そばにいたのは、お前だもんな。佐野がわからないのなら先生はもっとわからないな……」
「ごめんなさい……」
「いいんだ、謝らなくて。謝るべきは先生の方だ」
先生の目は涙で溢れていた。私の方も心苦しかった。
「良い先生ってなんだろうな? 先生はわからなくなったよ。だから、今月で先生を辞める」
「そんな! それじゃ……」
先生はそれ以上は言わないでくれと言うように涙を拭いた。
「佐野、とりあえず今日は帰った方がいい。授業とかあれこれは気にしなくていいから、とりあえず帰れ」
「でも……」
「いいから」
私は誰にも気づかれないように学校を後にした。何もすることがなかった私はとりあえず、自転車を走らせた。街の中心の方へと自転車を漕いだ。並木道を眺めるとまだ桜は咲いていなかった。私は何気なくスマホのカメラで写真を撮った。
街の中心の方へと出た私は曇った心を少しでも晴らそうとそこで時間を潰すことにした。
まずはじめに立ち寄ったのは新年早々咲と行ったアクセサリーショップだった。
「ねえ、これ良くない?」
「うんこれで良いかも」
二人でアクセサリーを探した時のことを思い出した。思い出して楽しい気持ちになる反面、それから後のことを思い出すと悲しい気持ちにもなった。
途中で制服姿の私を見て怪しげに見てきた店員さんがいたのだが、何かを察したのかそのまま店の奥の方へと戻っていった。私にはそれがありがたかった。それから私は商品棚をしばらくの間見つめ続けた。
見つめ続けているとお腹が空いた。人間というのはどんな状況でもお腹が空いてしまうのかと悲しい気持ちになったが、仕方がないのでアクセサリーショップを出た。何かを食べられるお店を探すこと数分。空いていそうなハンバーガー屋さんを見つけられた。
私はそのハンバーガー屋さんでハンバーガーとポテトを食べた。どんよりとした気持ちなのに、ハンバーガーとポテトが美味しいと感じられた。なんでそう思ってしまうのだろうか。私は私自身のことが悲しくなった。
ハンバーガーを食べた頃には時刻は昼の一時を過ぎていた。私は一月に咲と一緒に行った場所を改めて回ることにした。
二人でシリーズ物の映画を観に行った映画館。
お腹が空いたからと食べに行ったイタリアン。
他にもその日のうちに回ったいくつかのお店。
咲との短くて幸せだった日々のことを思い出した。スマホの写真フォルダを見るとそこにはその日撮った記念写真が何枚かあった。それらを見ているとどうしてこうなってしまったのだろうと改めて感じた。どうして二人とも居なくなるようなことになってしまったのだろうか。もしあの日、友美がナイフを出さなければ。もし、友美が逃げなければ。もし、友美が咲を殺そうとしなければ。
疑問ともしもばかりが頭の中で溢れかえっていた。
場所を移動してベンチに座りながら私は咲と友美のことを考え続けていた。考えても仕方のないことなのにどうして考えてしまうのだろうか。
それは結局のところは私が二人のことを大切に思っていたからに他ならないのかもしれない。だからこそ、未だに私は二人のことでどうしたら良かったのだろうかと悩み続けている。
人がどんどん私の前を通り過ぎていった。私の気持ちなんてお構いなしに世界の時間は進み続けている。なんとなく通り過ぎていく人々を眺めていると一組の男女が隣に置いてあった別のベンチに腰掛けた。
「ねえ、このバック良くない?」
「良いよね」
隣の席で聞き覚えのある声がした。私はそれを思い出せずにどこで聞いた声なのかを考えた。
「ねえ、あいつが死んでからさ私達上手くいっていると思わない?」
女性の方が楽しそうにバックを見つめ続けていた。一方で男性の方も女性の様子を嬉しそうに見つめていた。
「そりゃそうさ。あいつは俺たちにとってめんどくさい存在そのものだったからな」
その瞬間、私はこの声をどこで聞いたのかを思い出した。テレビだ。テレビのニュースでカメラの前に向かって土下座をした夫婦の姿が頭に浮かんだ。それから目の前で話している二人が誰なのかもわかった。
友美の両親だった。彼らの言葉を聞いて私は彼らが自分の娘のことをめんどくさい存在と形容したことに強い怒りを覚えた。私はベンチから立ち上がって二人の前に立った。
三月の朝。私は久しぶりに学校へ行く準備をしていた。
「本当に大丈夫なの?」
荷物をまとめているとお母さんが私のことを心配してくれた。どうやらクラスのことが心配なようだった。
「まあ、無理はしないよ」
そう言いつつも私はこの時点で無理をしていた。あの事件以来、私はクラス全体のコミュニティーから追い出されていた。連絡がついたのは真希ちゃんをはじめとするほんの数人だけだった。私はそのことをお母さんには言えなかった。
荷物をまとめ終えた私は、制服を二ヶ月ぶりに着た。久しぶりに着ると少しの違和感があった。
「なんでだろ、あのきらきらしている割には中身空っぽで人を蹴落とすことばかり頭にあるクソったれどもに嫌気を感じたからかな」
制服を着た自分を鏡で見た瞬間、咲の言葉が頭の中で反響した。私はもう学校にいる何も知らない連中が嫌になり始めていた。だが、それは気のせいだと思って私は自分の気持ちに蓋をした。そうしないと私の日常が保てなくなってしまうのだから。
「じゃあ、行ってくるね!」
「気をつけてね!」
時間が来たので私は急いで家を出た。私は無理をして笑顔を作った。お母さんはそれでも笑顔で見送ってくれた。
季節が冬から春に変わろうとしていた。私はなんとなく寒さの残る道を自転車で走った。こうやって自転車で走ったのは二ヶ月ぶりだった。久しぶりに走る道は何も変わっていなかった。ただ、変わってしまったのは自分の心だった。咲と友美をほぼ同時に失ってしまった。この頃になると私は、これからどうしたらいいのだろうかとずっと考えていた。
学校に到着した時には、既に朝のホームルームが始まっている時間だった。私は下駄箱に靴を入れようと扉に手を触れた。
「痛い!」
取手に触れた瞬間何かが指に刺さった。私は慌てて取手の方を確かめた。そこにはカッターの刃先のような物がテープで貼りついていた。
「やーい、人殺し!」
「引っかかったね! きゃはは」
後ろを向くとクラスメイトの男の子と女の子が笑っていた。私の指からは血が出ていたのに。
「これで少しは人の痛みがわかったか死神め」
「しーにがみ! しーにがみ!」
死神という言葉を向けられたのはこれで二度目だった。確かに私は友美と咲を葬った死神なのかもしれない。そう思いながら私はただ二人のことを見つめることしかできなかった。
「何みてるの……」
「怖いんですけど……」
私の何に怯えたのかわからなかったが、二人は走り去ってしまった。
「おい、大丈夫か!」
担任の先生が駆けつけてきた。それからすぐに保健室で手当をしてもらった。手当が終わったところでカッターの刃が下駄箱に隠されていたことを伝えると先生は苦い顔をした。
「実はな、事件の後でクラスの仲がこじれてしまって、先生たちも手に負えないんだ」
「手に負えないって……」
「いろいろあるが、昨日は五人くらいで激しい口喧嘩をしていたよ。喧嘩を収めるのに一時間かかった……」
「どうして、そんなことに……」
「なんでだろうな……、クラスをまとめていた石崎があんなことになったから皆んなの何かが壊れてしまった。先生はそう考えている」
先生もまた苦しそうだった。二ヶ月前には目立っていなかった白髪がところどころ目立っていた。この二ヶ月での辛さが感じ取れた。
「佐野、俺はどうしたらよかったんだろうか……、何がいけなかったんだ……」
「それは、私にもわからないです……」
「そうだよな……、石崎と倉持の一番そばにいたのは、お前だもんな。佐野がわからないのなら先生はもっとわからないな……」
「ごめんなさい……」
「いいんだ、謝らなくて。謝るべきは先生の方だ」
先生の目は涙で溢れていた。私の方も心苦しかった。
「良い先生ってなんだろうな? 先生はわからなくなったよ。だから、今月で先生を辞める」
「そんな! それじゃ……」
先生はそれ以上は言わないでくれと言うように涙を拭いた。
「佐野、とりあえず今日は帰った方がいい。授業とかあれこれは気にしなくていいから、とりあえず帰れ」
「でも……」
「いいから」
私は誰にも気づかれないように学校を後にした。何もすることがなかった私はとりあえず、自転車を走らせた。街の中心の方へと自転車を漕いだ。並木道を眺めるとまだ桜は咲いていなかった。私は何気なくスマホのカメラで写真を撮った。
街の中心の方へと出た私は曇った心を少しでも晴らそうとそこで時間を潰すことにした。
まずはじめに立ち寄ったのは新年早々咲と行ったアクセサリーショップだった。
「ねえ、これ良くない?」
「うんこれで良いかも」
二人でアクセサリーを探した時のことを思い出した。思い出して楽しい気持ちになる反面、それから後のことを思い出すと悲しい気持ちにもなった。
途中で制服姿の私を見て怪しげに見てきた店員さんがいたのだが、何かを察したのかそのまま店の奥の方へと戻っていった。私にはそれがありがたかった。それから私は商品棚をしばらくの間見つめ続けた。
見つめ続けているとお腹が空いた。人間というのはどんな状況でもお腹が空いてしまうのかと悲しい気持ちになったが、仕方がないのでアクセサリーショップを出た。何かを食べられるお店を探すこと数分。空いていそうなハンバーガー屋さんを見つけられた。
私はそのハンバーガー屋さんでハンバーガーとポテトを食べた。どんよりとした気持ちなのに、ハンバーガーとポテトが美味しいと感じられた。なんでそう思ってしまうのだろうか。私は私自身のことが悲しくなった。
ハンバーガーを食べた頃には時刻は昼の一時を過ぎていた。私は一月に咲と一緒に行った場所を改めて回ることにした。
二人でシリーズ物の映画を観に行った映画館。
お腹が空いたからと食べに行ったイタリアン。
他にもその日のうちに回ったいくつかのお店。
咲との短くて幸せだった日々のことを思い出した。スマホの写真フォルダを見るとそこにはその日撮った記念写真が何枚かあった。それらを見ているとどうしてこうなってしまったのだろうと改めて感じた。どうして二人とも居なくなるようなことになってしまったのだろうか。もしあの日、友美がナイフを出さなければ。もし、友美が逃げなければ。もし、友美が咲を殺そうとしなければ。
疑問ともしもばかりが頭の中で溢れかえっていた。
場所を移動してベンチに座りながら私は咲と友美のことを考え続けていた。考えても仕方のないことなのにどうして考えてしまうのだろうか。
それは結局のところは私が二人のことを大切に思っていたからに他ならないのかもしれない。だからこそ、未だに私は二人のことでどうしたら良かったのだろうかと悩み続けている。
人がどんどん私の前を通り過ぎていった。私の気持ちなんてお構いなしに世界の時間は進み続けている。なんとなく通り過ぎていく人々を眺めていると一組の男女が隣に置いてあった別のベンチに腰掛けた。
「ねえ、このバック良くない?」
「良いよね」
隣の席で聞き覚えのある声がした。私はそれを思い出せずにどこで聞いた声なのかを考えた。
「ねえ、あいつが死んでからさ私達上手くいっていると思わない?」
女性の方が楽しそうにバックを見つめ続けていた。一方で男性の方も女性の様子を嬉しそうに見つめていた。
「そりゃそうさ。あいつは俺たちにとってめんどくさい存在そのものだったからな」
その瞬間、私はこの声をどこで聞いたのかを思い出した。テレビだ。テレビのニュースでカメラの前に向かって土下座をした夫婦の姿が頭に浮かんだ。それから目の前で話している二人が誰なのかもわかった。
友美の両親だった。彼らの言葉を聞いて私は彼らが自分の娘のことをめんどくさい存在と形容したことに強い怒りを覚えた。私はベンチから立ち上がって二人の前に立った。