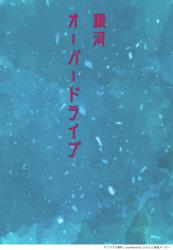咲が崖の下に落ちてから数時間が経った。警察はありとあらゆる手を使って彼女を探したが見つからなかった。彼女は落ちる直前に心臓の近くをナイフで刺したため、仮に見つかったとしても生存の可能性は絶望的に低かった。私は何もできず、近くの岩にただ無心で座っていた。途中で警察官の一人が気を利かせて毛布をかけてくれた。冷たい夜空の下で時間だけが過ぎていった。
しばらくすると車が一台やってきた。降りてきたのは吉原刑事だった。吉原刑事は私を見るなり近づいてきて、私のことを平手打ちした。
「あんたね! 死人を二人も出してどうするんだ! お前の方こそ狂ってるよ!」
その場に居合わせ警察官の一人が吉原刑事を止めようとしてくれた。
「吉原さん……」
「黙れ、このヒラが!」
結局、その警察官も青木さんと同じく彼女のことを止められなかった。
私は何も言えなかった。そうだ、私なのだ。結果的に私が二人を殺したんだ。私が全部の責任を果たさなくちゃいけないんだ。そう思った。
「なんも言わないのね、お前。この死神が!」
吉原刑事は私のことを殴った。自分の思い通りに行かなくて嫌だったのだろう。私は抵抗も何もせずにひたすら殴られ続けた。だって、私が死神だからだ。
「あはは! 死んじまえこの死神が!」
私はその場で倒れ込んだ。吉原刑事はなおも私を殴り続けた。他の警察官たちが吉原刑事のことを止めようとするが、止められなかった。
私はひたすらに殴られ続けた。ここで殴られ続けて死んでしまっても構わないとさえ思った。
「ねえ、あんたなんで抵抗しないの……」
だが、次第に吉原刑事の方が殴る勢いを抑えはじめた。
「なんで、なんで抵抗しないの……、怖い……」
「だって、私は死神だから」
吉原刑事が初めて後退りをした。彼女の顔は恐怖で溢れていた。
私は残った体力を使って立ち上がった。
「死神だからさ、感じないよ痛みなんて」
「じゃあ、あの二人が死んでも痛みはなかったの!」
「あったよ。でもね、おかげで今は何も感じないの」
「おかしい、おかしいよあんた……」
「おかしいのはどっちもでしょ」
「私は、おかしくない。狂ってない。断じて違う!」
「あら、そう。じゃあ、この状況を見て楽しんでいたあなたは正常だって言うの?」
「そうだ! その通りだ!」
「じゃあ、私のことを心底恨みながら、死んでくれ!」
今度は私が吉原刑事のことを殴った。他の警察官たちはもうこの状況を見ているしかできなかった。
私は死神だ。こんな刑事なんて殺してやる。そう思って何度も殴った。
さらに一発殴ろうとした、その刹那。
「やめて!」
「これ以上はやめて!」
なぜか、どこからか咲と友美の声がしたような気がした。幻聴だったと思う。それでも、私には二人が私のことを止めようとしているような気がして、私は吉原刑事を殴るのをやめた。
「ああ、ああ、そうね。私が愚かだった……」
「どうしたの……」
吉原刑事が私に尋ねた。
「どこかから二人の声がしたの」
「二人ともここにはいないのよ!」
「そうね、もう居ない。もう居ないけど、私の中にはいるの」
「二人はいないのよ! 目を覚ましなさいよ!」
「だめ、そんなことしたら私の心が死んじゃうよ……」
「だったら死ね」
そう言い残して吉原刑事は車の方へと戻っていった。
「ああ、そうね。もう二人はいないのよ……」
私は立っているのが精一杯だった。それでも咲と友美はもう居ないという現実に気持ちが引きずり戻されて、私はついに倒れてしまった。
「あああ!!」
私は叫んだ。自分の叫び声だけが冬の夜空に響き渡っていた。
「死んじゃったよ! 二人とも死んじゃったよ! 落ち着いて! 落ち着いてられるか! 死んじまえ! 死にたくねぇよ! 私は誰? あなたは私! 咲よ! いや、友美だよ! そんなことない! 私は私は、誰?」
これ以降、三日間の記憶が私にはない。一時的に自分が誰なのかで混乱しはじめた。その場にいた人から後で聞いた話だが、私は一人で会話を続けて、それから自分のことを殴りはじめたという。やがて、気を失ってしまったようで、気がついた時には病院のベットで横になっていた。
「目が覚めた!」
目が覚めた時、私のそばには青木さんと両親がいた。
「由香里!」
「よかった! 目が覚めて本当に良かった!」
「ここは?」
私は混乱していた。目が覚めたら朝だったからだ。
「病院よ。目が覚めて本当によかった!」
お母さんとお父さんは抱き合って喜んでいた。
「至急、医者を!」
そう言って、青木さんは部屋を後にした。それから彼が昼過ぎまで戻ってくることはなかった。
医者が来て、私のことを診察した。
「名前わかるかな?」
「由香里です。佐野由香里」
「なら良かった」
医者は診察道具を置いて、両親の方を向いた。
「もう大丈夫ですよ。あとは体の回復を待てば退院できると思います」
「ありがとうございます!」
「本当にありがとうございます!」
両親は深々と頭を下げた。医者は一礼すると病室を出ていった。
状況が落ち着いたのを見計らって、青木さんが私の病室に再びやってきた。
「まずは、うちの署の吉原について詫びなければなりません……」
青木さんは地面に座り込んで土下座をした。
「青木さん、そこまでしなくても……」
「いいや、これくらいしないと、何も変わらない」
少しの間土下座をしてから青木さんは立ち上がった。
「吉原刑事は謹慎処分となりました。じきに正式な対応が決まると思います」
「そうでしたか」
「私は、あなた、いや、あなたと倉持さんと石崎さんに何て言ったら良いのかわからないのです。私はあなた方に許されようとは思いません。ただ、あなたたちに謝っておきたかった。私はあなた方のことをありのままに受け止めておきたい。事件の加害者、被害者という関係性ではなく友達同士の三人としてあなた方のことを見ていたい」
私は何も言えなかった。気持ちの整理がついていなかった。何も言えずに時間だけが過ぎてしまった。
「謝るのは早急過ぎたかもしれませんね。では、失礼します」
青木さんが病室を出ようとした。私は今は気持ちがまとまっていなくとも言えることが一つあった。
「あの、待ってください!」
青木さんがこちらの方に振り返った。
「あの、ありがとうございます。謝ってくれて。咲と友美が許してくれるのかわからないし、私も今は気持ちの整理がついていないです。だけど、これだけは言えます。私たちを私たちと認めてくれてありがとうございます」
青木さんは少し微笑んで、一礼してくれた。
「こちらこそ、ありがとう」
青木さんは私の病室を後にした。
私たちは私たちなのだ。青木さんはこの事を受け止めてくれたのだ。
夜になって、お父さんとお母さんは眠ってしまっていた。一人で起きていた私は窓越しに夜空を見つめた。ビル街の光のせいで星は何も見えなかった。看護師さんが運んできてくれたスープを飲みながら私は無心になっていた。何かをしようとする力がほとんど湧かなかった。いつの間にか眠くなってしまって、気がついたら目を閉じていた。私の中には何も残っていなかった。
しばらくすると車が一台やってきた。降りてきたのは吉原刑事だった。吉原刑事は私を見るなり近づいてきて、私のことを平手打ちした。
「あんたね! 死人を二人も出してどうするんだ! お前の方こそ狂ってるよ!」
その場に居合わせ警察官の一人が吉原刑事を止めようとしてくれた。
「吉原さん……」
「黙れ、このヒラが!」
結局、その警察官も青木さんと同じく彼女のことを止められなかった。
私は何も言えなかった。そうだ、私なのだ。結果的に私が二人を殺したんだ。私が全部の責任を果たさなくちゃいけないんだ。そう思った。
「なんも言わないのね、お前。この死神が!」
吉原刑事は私のことを殴った。自分の思い通りに行かなくて嫌だったのだろう。私は抵抗も何もせずにひたすら殴られ続けた。だって、私が死神だからだ。
「あはは! 死んじまえこの死神が!」
私はその場で倒れ込んだ。吉原刑事はなおも私を殴り続けた。他の警察官たちが吉原刑事のことを止めようとするが、止められなかった。
私はひたすらに殴られ続けた。ここで殴られ続けて死んでしまっても構わないとさえ思った。
「ねえ、あんたなんで抵抗しないの……」
だが、次第に吉原刑事の方が殴る勢いを抑えはじめた。
「なんで、なんで抵抗しないの……、怖い……」
「だって、私は死神だから」
吉原刑事が初めて後退りをした。彼女の顔は恐怖で溢れていた。
私は残った体力を使って立ち上がった。
「死神だからさ、感じないよ痛みなんて」
「じゃあ、あの二人が死んでも痛みはなかったの!」
「あったよ。でもね、おかげで今は何も感じないの」
「おかしい、おかしいよあんた……」
「おかしいのはどっちもでしょ」
「私は、おかしくない。狂ってない。断じて違う!」
「あら、そう。じゃあ、この状況を見て楽しんでいたあなたは正常だって言うの?」
「そうだ! その通りだ!」
「じゃあ、私のことを心底恨みながら、死んでくれ!」
今度は私が吉原刑事のことを殴った。他の警察官たちはもうこの状況を見ているしかできなかった。
私は死神だ。こんな刑事なんて殺してやる。そう思って何度も殴った。
さらに一発殴ろうとした、その刹那。
「やめて!」
「これ以上はやめて!」
なぜか、どこからか咲と友美の声がしたような気がした。幻聴だったと思う。それでも、私には二人が私のことを止めようとしているような気がして、私は吉原刑事を殴るのをやめた。
「ああ、ああ、そうね。私が愚かだった……」
「どうしたの……」
吉原刑事が私に尋ねた。
「どこかから二人の声がしたの」
「二人ともここにはいないのよ!」
「そうね、もう居ない。もう居ないけど、私の中にはいるの」
「二人はいないのよ! 目を覚ましなさいよ!」
「だめ、そんなことしたら私の心が死んじゃうよ……」
「だったら死ね」
そう言い残して吉原刑事は車の方へと戻っていった。
「ああ、そうね。もう二人はいないのよ……」
私は立っているのが精一杯だった。それでも咲と友美はもう居ないという現実に気持ちが引きずり戻されて、私はついに倒れてしまった。
「あああ!!」
私は叫んだ。自分の叫び声だけが冬の夜空に響き渡っていた。
「死んじゃったよ! 二人とも死んじゃったよ! 落ち着いて! 落ち着いてられるか! 死んじまえ! 死にたくねぇよ! 私は誰? あなたは私! 咲よ! いや、友美だよ! そんなことない! 私は私は、誰?」
これ以降、三日間の記憶が私にはない。一時的に自分が誰なのかで混乱しはじめた。その場にいた人から後で聞いた話だが、私は一人で会話を続けて、それから自分のことを殴りはじめたという。やがて、気を失ってしまったようで、気がついた時には病院のベットで横になっていた。
「目が覚めた!」
目が覚めた時、私のそばには青木さんと両親がいた。
「由香里!」
「よかった! 目が覚めて本当に良かった!」
「ここは?」
私は混乱していた。目が覚めたら朝だったからだ。
「病院よ。目が覚めて本当によかった!」
お母さんとお父さんは抱き合って喜んでいた。
「至急、医者を!」
そう言って、青木さんは部屋を後にした。それから彼が昼過ぎまで戻ってくることはなかった。
医者が来て、私のことを診察した。
「名前わかるかな?」
「由香里です。佐野由香里」
「なら良かった」
医者は診察道具を置いて、両親の方を向いた。
「もう大丈夫ですよ。あとは体の回復を待てば退院できると思います」
「ありがとうございます!」
「本当にありがとうございます!」
両親は深々と頭を下げた。医者は一礼すると病室を出ていった。
状況が落ち着いたのを見計らって、青木さんが私の病室に再びやってきた。
「まずは、うちの署の吉原について詫びなければなりません……」
青木さんは地面に座り込んで土下座をした。
「青木さん、そこまでしなくても……」
「いいや、これくらいしないと、何も変わらない」
少しの間土下座をしてから青木さんは立ち上がった。
「吉原刑事は謹慎処分となりました。じきに正式な対応が決まると思います」
「そうでしたか」
「私は、あなた、いや、あなたと倉持さんと石崎さんに何て言ったら良いのかわからないのです。私はあなた方に許されようとは思いません。ただ、あなたたちに謝っておきたかった。私はあなた方のことをありのままに受け止めておきたい。事件の加害者、被害者という関係性ではなく友達同士の三人としてあなた方のことを見ていたい」
私は何も言えなかった。気持ちの整理がついていなかった。何も言えずに時間だけが過ぎてしまった。
「謝るのは早急過ぎたかもしれませんね。では、失礼します」
青木さんが病室を出ようとした。私は今は気持ちがまとまっていなくとも言えることが一つあった。
「あの、待ってください!」
青木さんがこちらの方に振り返った。
「あの、ありがとうございます。謝ってくれて。咲と友美が許してくれるのかわからないし、私も今は気持ちの整理がついていないです。だけど、これだけは言えます。私たちを私たちと認めてくれてありがとうございます」
青木さんは少し微笑んで、一礼してくれた。
「こちらこそ、ありがとう」
青木さんは私の病室を後にした。
私たちは私たちなのだ。青木さんはこの事を受け止めてくれたのだ。
夜になって、お父さんとお母さんは眠ってしまっていた。一人で起きていた私は窓越しに夜空を見つめた。ビル街の光のせいで星は何も見えなかった。看護師さんが運んできてくれたスープを飲みながら私は無心になっていた。何かをしようとする力がほとんど湧かなかった。いつの間にか眠くなってしまって、気がついたら目を閉じていた。私の中には何も残っていなかった。