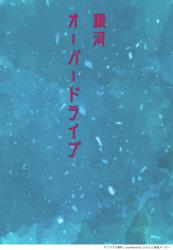時刻は夕方の十七時。私たちは九州の端の方までもうすぐのところまで到達していた。
「あと少しだ」
息を切らしながら咲が呟いた。彼女は覚悟を決めた顔をしていた。それに私は気がつかないふりをしてしまった。私が未だに後悔している瞬間の一つである。
もうすぐで目的地というところで突然、咲が足を止めた。
「由香里、私がどうして孔雀座を見たいのか教えてあげる」
「どうしたの急に?」
「私には、今ここで由香里に伝えなきゃいけないことがあるんだ」
「伝えなきゃ、いけないこと?」
咲は頷いた。この時の私はなぜ彼女がこのタイミングでこの話を切り出したのか意図が掴めなかった。
「良いかな?」
彼女は私に問いかけた。私は頷いた。
「まずね、私はいつか孔雀になりたいんだ。あの綺麗な羽が欲しいから」
「でも、孔雀の綺麗な羽って雄だけが持っているんでしょ?」
「それは知ってるよ。そこは私の夢なんだから聞かないで欲しかった」
「それはごめん」
咲はそれから再び歩き始めた。私もそれについていく。
「私が友美から嫌われた後でね、何気なく見た図鑑の孔雀が綺麗だったの。そこから調べていくと孔雀座っていう星座があるらしいって知った。孔雀座には何も物語がないの。私にはそれがちょうど良いと思えた。だって私にはどんな有名な星座も似合わないから」
「似合わないって、なんでそう決めつけるの? あなたにはまだまだこれから先の輝かしい未来が待っているのかもしれないのに……」
「いいや、それは私が認めたくないの。認めない方が楽なの……」
「どうして?」
「なんでだろ、あのきらきらしている割には中身空っぽで人を蹴落とすことばかり頭にあるクソったれどもに嫌気を感じたからかな」
これを聞いて私は咲が抱えていた影の一部を垣間見たような気がした。
私は自分の気持ちを見透かされたような気がした。
「それは言い過ぎな気が……」
「そうかな? 由香里だって本当は気づいているんでしょ。あいつらの醜さに」
それはその通りだった。当時の私には自分が抱えていた爆弾のような感情を認める勇気がなかった。
「なんかごめんね。こんなこと言っちゃって……」
「いや、いいの。むしろ、言ってくれてありがとう」
刹那、咲が驚いたような顔をした。それから私の答えがよほどだったのか、彼女は大笑いした。
「あはは、あはは!」
それに釣られて私も笑い始めた。
「ははは、あはは」
「何笑ってるの」
「そっちこそ、なんで笑ってるの」
「なんでって、咲が笑ったからだよ」
途中から私たちは半泣きになっていた。いつの間にか理由もわからなくなってただひたすらに泣き笑っていた。
「みんなのばかやろー!」
咲は夕暮れ空に向かって叫んだ。
「私たちのばかやろー!」
私も叫んだ。
「ばかやろーに祝福を!」
「乾杯!」
私と咲は拳を高く挙げた。
「私さ、孔雀の様に綺麗なドレスをいつか着てみたいんだ」
「それ、咲にとっても似合うと思う」
「ありがとう。着こなせるといいな」
「大丈夫だよ。私が保証する」
「それ保証になってないよ」
「そうだね」
そこから私たちは少しの間何も喋らずに道を進み続けた。その中で、私はこの先自分たちはどうなってしまうのかと考えた。
「ねえ、私たちこの先どうしようかな?」
何気なく私は咲に聞いた。
「どうするって?」
「だってさ、警察には追われているし、お金もないし、この先本当にどうなるのかなって思って」
「はは、それはそうだね」
「何か思いつくことある?」
「そうだね。そういえば、この先は海辺なんだけどさ。だったら船を盗もうよ」
「と言うと」
「盗んで、その船でどこか南の島にでも逃げよう」
「それは良いね」
「それでね、そこでカフェをやるの」
「どんな?」
「どんなって言われてもすぐには……、あ、思いついた」
「おお」
「コーヒーにこだわって良い豆を揃えておくの」
「品質重視だ」
「そうそう」
「それで大儲けしよう」
「だけど、それだけで大儲けできるかな」
「じゃあパイナップルジュースも売ろう」
「それは節操ないよ」
「じゃあ、もう少し工夫しないとね。由香里は何かある?」
「うーん。思いつかない!」
「ははは」
「あ、そうだ。ミックスジュースを売ろう」
「ミックスジュースね。それもありきたりじゃない?」
「うーん。やはり良いアイディアは出ないね」
「はは」
楽しくなってきたのか咲が話を続けた。
「あとさ、南の島に住むんだったら家にはブランコが付いているといいな」
「ブランコね。良いね」
「二人用のブランコでさ、二人で漕ぎながらその日のご飯のこととか話し合うの」
「すごい具体的だね」
「今考えたことなのにね」
「人間の想像力ってすごいね」
「同感」
私は南の島にある小さな家を思い浮かべた。その家には私たちが住んでいて、コーヒーやパイナップルジュースが売りのカフェを営んでいる。二人は毎朝、ブランコに乗ってその日の予定を決める。それからコーヒーやジュースの準備を始めて、時間が来たら店を開ける。店には馴染みのお客さんたちが来ていて、その人たちと他愛もない話で盛り上がる。そんな生活を思い浮かべた。
私は本当にそんな生活をしたくなってしまった。彼女となら楽しそうだなって思った。だが、そんな日が来ることはあったのだろうか。今でも幸せそうなその生活を思い浮かべてしまう。実は自分が一番乗り気になっていたのかもしれない。そう思う。
会話のキャッチボールが続いて、時間はどんどん過ぎていった。日が傾いた空を眺めながら私たちは道を進み続けた。旅のゴールはあとほんの少しのところまで迫っていた。
「ねえ、私たちなんでもできそうだよね」
咲の言葉には彼女の整理がついていない気持ちがそのままの姿で込められていたような気がした。
「そうだね」
私は深くも考えずに頷いた。この時、私は本当に自分たちならなんでもできると妙な自信を持っていた。
「私たちさ、友達だよ」
咲の気持ちが私の心に伝わってきた。私は嬉しかった。
「うん、私もそう思ってる」
「ならよかった」
そう言っていた彼女の顔は悲しそうだった。私はまたしても気づかないふりをしてしまった。この時、何か言ってあげられたら私たちの人生はどう変わったのだろうか。思い返す度にそんなことが頭を過ぎる。
私は彼女との時間がずっと続けば良いのにと思った。それでも、時間はどこまでも残酷だった。
「着いた」
「いよいよだね」
「そうだね」
ついに私たちは目的の場所へとたどり着いた。旅の終着点。私にとって一番忘れたくない一連の出来事の結末まであと少しだった。
「あと少しだ」
息を切らしながら咲が呟いた。彼女は覚悟を決めた顔をしていた。それに私は気がつかないふりをしてしまった。私が未だに後悔している瞬間の一つである。
もうすぐで目的地というところで突然、咲が足を止めた。
「由香里、私がどうして孔雀座を見たいのか教えてあげる」
「どうしたの急に?」
「私には、今ここで由香里に伝えなきゃいけないことがあるんだ」
「伝えなきゃ、いけないこと?」
咲は頷いた。この時の私はなぜ彼女がこのタイミングでこの話を切り出したのか意図が掴めなかった。
「良いかな?」
彼女は私に問いかけた。私は頷いた。
「まずね、私はいつか孔雀になりたいんだ。あの綺麗な羽が欲しいから」
「でも、孔雀の綺麗な羽って雄だけが持っているんでしょ?」
「それは知ってるよ。そこは私の夢なんだから聞かないで欲しかった」
「それはごめん」
咲はそれから再び歩き始めた。私もそれについていく。
「私が友美から嫌われた後でね、何気なく見た図鑑の孔雀が綺麗だったの。そこから調べていくと孔雀座っていう星座があるらしいって知った。孔雀座には何も物語がないの。私にはそれがちょうど良いと思えた。だって私にはどんな有名な星座も似合わないから」
「似合わないって、なんでそう決めつけるの? あなたにはまだまだこれから先の輝かしい未来が待っているのかもしれないのに……」
「いいや、それは私が認めたくないの。認めない方が楽なの……」
「どうして?」
「なんでだろ、あのきらきらしている割には中身空っぽで人を蹴落とすことばかり頭にあるクソったれどもに嫌気を感じたからかな」
これを聞いて私は咲が抱えていた影の一部を垣間見たような気がした。
私は自分の気持ちを見透かされたような気がした。
「それは言い過ぎな気が……」
「そうかな? 由香里だって本当は気づいているんでしょ。あいつらの醜さに」
それはその通りだった。当時の私には自分が抱えていた爆弾のような感情を認める勇気がなかった。
「なんかごめんね。こんなこと言っちゃって……」
「いや、いいの。むしろ、言ってくれてありがとう」
刹那、咲が驚いたような顔をした。それから私の答えがよほどだったのか、彼女は大笑いした。
「あはは、あはは!」
それに釣られて私も笑い始めた。
「ははは、あはは」
「何笑ってるの」
「そっちこそ、なんで笑ってるの」
「なんでって、咲が笑ったからだよ」
途中から私たちは半泣きになっていた。いつの間にか理由もわからなくなってただひたすらに泣き笑っていた。
「みんなのばかやろー!」
咲は夕暮れ空に向かって叫んだ。
「私たちのばかやろー!」
私も叫んだ。
「ばかやろーに祝福を!」
「乾杯!」
私と咲は拳を高く挙げた。
「私さ、孔雀の様に綺麗なドレスをいつか着てみたいんだ」
「それ、咲にとっても似合うと思う」
「ありがとう。着こなせるといいな」
「大丈夫だよ。私が保証する」
「それ保証になってないよ」
「そうだね」
そこから私たちは少しの間何も喋らずに道を進み続けた。その中で、私はこの先自分たちはどうなってしまうのかと考えた。
「ねえ、私たちこの先どうしようかな?」
何気なく私は咲に聞いた。
「どうするって?」
「だってさ、警察には追われているし、お金もないし、この先本当にどうなるのかなって思って」
「はは、それはそうだね」
「何か思いつくことある?」
「そうだね。そういえば、この先は海辺なんだけどさ。だったら船を盗もうよ」
「と言うと」
「盗んで、その船でどこか南の島にでも逃げよう」
「それは良いね」
「それでね、そこでカフェをやるの」
「どんな?」
「どんなって言われてもすぐには……、あ、思いついた」
「おお」
「コーヒーにこだわって良い豆を揃えておくの」
「品質重視だ」
「そうそう」
「それで大儲けしよう」
「だけど、それだけで大儲けできるかな」
「じゃあパイナップルジュースも売ろう」
「それは節操ないよ」
「じゃあ、もう少し工夫しないとね。由香里は何かある?」
「うーん。思いつかない!」
「ははは」
「あ、そうだ。ミックスジュースを売ろう」
「ミックスジュースね。それもありきたりじゃない?」
「うーん。やはり良いアイディアは出ないね」
「はは」
楽しくなってきたのか咲が話を続けた。
「あとさ、南の島に住むんだったら家にはブランコが付いているといいな」
「ブランコね。良いね」
「二人用のブランコでさ、二人で漕ぎながらその日のご飯のこととか話し合うの」
「すごい具体的だね」
「今考えたことなのにね」
「人間の想像力ってすごいね」
「同感」
私は南の島にある小さな家を思い浮かべた。その家には私たちが住んでいて、コーヒーやパイナップルジュースが売りのカフェを営んでいる。二人は毎朝、ブランコに乗ってその日の予定を決める。それからコーヒーやジュースの準備を始めて、時間が来たら店を開ける。店には馴染みのお客さんたちが来ていて、その人たちと他愛もない話で盛り上がる。そんな生活を思い浮かべた。
私は本当にそんな生活をしたくなってしまった。彼女となら楽しそうだなって思った。だが、そんな日が来ることはあったのだろうか。今でも幸せそうなその生活を思い浮かべてしまう。実は自分が一番乗り気になっていたのかもしれない。そう思う。
会話のキャッチボールが続いて、時間はどんどん過ぎていった。日が傾いた空を眺めながら私たちは道を進み続けた。旅のゴールはあとほんの少しのところまで迫っていた。
「ねえ、私たちなんでもできそうだよね」
咲の言葉には彼女の整理がついていない気持ちがそのままの姿で込められていたような気がした。
「そうだね」
私は深くも考えずに頷いた。この時、私は本当に自分たちならなんでもできると妙な自信を持っていた。
「私たちさ、友達だよ」
咲の気持ちが私の心に伝わってきた。私は嬉しかった。
「うん、私もそう思ってる」
「ならよかった」
そう言っていた彼女の顔は悲しそうだった。私はまたしても気づかないふりをしてしまった。この時、何か言ってあげられたら私たちの人生はどう変わったのだろうか。思い返す度にそんなことが頭を過ぎる。
私は彼女との時間がずっと続けば良いのにと思った。それでも、時間はどこまでも残酷だった。
「着いた」
「いよいよだね」
「そうだね」
ついに私たちは目的の場所へとたどり着いた。旅の終着点。私にとって一番忘れたくない一連の出来事の結末まであと少しだった。