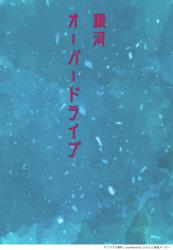友美が姿を消してから一晩。朝のニュースでは相変わらず話が続いていて、私たちの学校の前には報道陣が昨日よりも多い数で押し寄せていた。私は両親や先生方から勧められて学校を休むことにしていたが、この状況では行かない方が良かったとニュースを見て思った。登校中の同級生たちが何人か映った。マスコミの人々が彼らに声をかけた。
「すみません、今回の事件について何か知っていますか?」
リポーターが訊ねる。
「いえ知らないので、ちょっと……」
みんな、どう答えていいのか悩んでいたようだった。ある者はずっと考えて答えを絞り出し、またある者は簡単に答えて駆け足で去っていった。
それはそうだと私は思った。私だって理解が追いついていない部分があった。友美は一体何を考えているんだろう。そう思った瞬間、私は咲と初めて会話した時のことを思い返した。放課後、廊下で言われた言葉が思い返された。あの時私は咲の考えていることが理解できずにいた。だが、この二日間は友美の考えていることがわからなくなっていた。
状況は刻一刻と変化していた。警察が友美の家を調べはじめた。彼女の家がテレビの画面に映し出される。何人もの警察官らしき人物たちが家を出入りしていた。あの家には友美以外の住んでいる人はいなかった。彼女の人生が調べられていくのを見て私は彼女の人生に思いを馳せた。
テレビを夢中で見ていると玄関のチャイムが鳴った。お母さんがすぐに出ると警察の人が私に話を聞きに来たとのことだった。私が玄関に出ると、整った顔の男性と綺麗な女性が二人立っていた。男性の方が先に話をはじめた。
「……署の青木です。隣にいるのは吉原といいます。昨日の件についてお伺いしたいのですが、よろしいでしょうか?」
「はい、どうぞ」
私は青木さんという男性刑事と吉原さんという女性刑事の二人を家の中に入れた。お母さんが人数分のお茶を用意してくれた。
「まずは昨日の件で心が落ち着かないかとは思います。怪我の具合はどうですか?」
「まだ落ち着かないです。怪我もまだ痛みが残っています」
「そうですか。私たちも突然のことだったので今でも状況が飲み込めずにいます」
青木さんがお茶を飲んで、一呼吸置いた。真剣な目でこちらを見てきた。
「早速本題に入らせていただきます。昨日の夕方の詳細を教えてください」
「わかりました」
青木さんと吉原さんがそれぞれメモ帳とペンを取り出した。青木さんが質問を始めた。
「それでは、まず昨日の夕方何がありましたか?」
「昨日の夕方、私は石崎さんに呼び出されて、誰もいない教室で話をしていました。その途中で石崎さんがナイフを持ち出して、私のことを切りつけようとしました」
「それで?」
「慌てて左腕で庇ったら、切られました……」
私は切られた左腕の方を見せた。包帯を巻いてはいたがまだ痛みが残っていた。
「わかりました。佐野さんと石崎さんの関係は?」
「友達です。高校に進学して部活に入ったらなんとなく遊ぶことが増えて、友達になりました」
「なるほど」
青木さんが何かをメモに記した。両者無言になったところでずっと話を聞いていた吉原さんが手を挙げた。
「すみません。今聞くのもあれなのですが、石崎さんはどういった人ですか?」
頭の中で私は悩んでいた。この二人の刑事さんにどこまで言っていいのかを。どこまで言わなければ友美のことを守れるのかを。何も言えずにいると吉原さんはため息をついた。
「佐野さん。あなた友達だからと言って石崎さんのことを悪く言いたくないんでしょ。わかるよ。でもね。事はもう彼女のことを擁護できる段階ではないのよ」
彼女はバックの中から紙を一枚取り出した。それは写真だった。場所は街にある大きな公園で制服姿から着替えた友美の姿が写っていた。手にはナイフが握られていて、彼女のそばには倒れた犬が写っていた。
「昨日の夜中に撮られた物よ。朝になってその場所で刺し殺された犬が見つかっている。つまり、わかるよね」
「そんな……」
友美は超えてはならない一線を越えようとしていた。いや、私を殺そうとした段階で彼女は一線を越えたのだとこの時気づいた。
「彼女は人を殺す気満々よ。一刻も早く見つけないと取り返しのつかないことになる」
「吉原、それは言い過ぎでは……」
「うっさい、青木お前は黙ってろ」
吉原さんは青木さんのことを睨みつけた。
「佐野さん、あなたわかっているでしょ、あいつはもう擁護し切れないって」
それはその通りだった。私にはもう彼女のことを擁護できそうになかった。だからと言って、この高圧的な刑事を前に何も言うことができなかった。
「何も言わないってことはそれを認めるってことね。だったらあいつが何を考えているのか見当もつくんでしょ。教えて。教えなかった、あなたのもう一人の友達のことも捕まえるけど」
「吉原やめ……」
「引っ込んでろ、この能無しが!」
この刑事は青木さんのことを蹴り飛ばした。青木さんが倒れ込み、慌ててお母さんが駆け寄った。青木さんは気絶したようだった。
この刑事は狂っていた。誰かを捕まえるためならどんな手段に出ても良いと思っている。そんな狂った人間だった。
「それはやめてください!」
「あんたにそれを言う権利は無い。邪魔するならあなたも捕まえるわよ」
「うちでなんてことしてくれるの!」
お母さんがついに口を出した。
「お母さん。じゃああなたも逮捕しますよ」
「上等じゃない! 捕まえられるものなら捕まえてみなさい!」
そこから少しの間膠着が続いた。睨み合いが続いている中で誰かのスマホが鳴った。吉原刑事のスマホだった。
「はいもしもし、吉原です。はい。はい。わかりました。すぐ向かいます。え、青木? あいつは後で向かわせます。じゃあ失礼します」
通話切った吉原刑事は荷物をまとめ始めた。
「よかったわね。事件に進展があったわ。私は現場に行くからこの能無しのことは頼んだ。じゃあ」
言い残して彼女は颯爽と家を出ていった。
それから三十分ほどが経って青木さんが目を覚ました。私とお母さんはあの後のことを詳細に伝えた。
「うちの吉原がすみません……」
「何なんですか、あの刑事は!」
お母さんが責め立てた。青木さんは申し訳なさそうな顔をしていた。
「うちの署でもマッドドックと言われている刑事でして。まあ、さっきからずっと音声レコーダーで会話を録音していたので、後で上に報告しておきます」
「ありがとうございます……」
「こちらこそ、すみませんでした」
青木さんは深々とお辞儀をして帰っていった。
いくら狂った刑事だったとはいえ、吉原刑事が言っていることは間違えではなかった。友美はもう取り返しのつかない領域まで足を踏み入れていた。やはり彼女を助けることはできないのだろうか。いや、まだ手はあるはずだ。それを探そう。そんなことを思っていた矢先だった。
青木さんが帰ってから時間が経って日が傾き始めた頃、私のスマホが鳴り始めた。お母さんは買い物に出てしまっていて、静かな部屋に着信音だけが鳴り響く。佐伯くんからの着信だった。私は嫌な予感がした。急いで通話に応じた。
「もしもし」
「もしもし、佐野さん。大変なんだ。咲ちゃんと連絡がつかない。咲ちゃんのお母さんも心配している」
「そんな……」
「もしかしたら、石崎さんが……」
私は急いで外に出る準備を始めた。
「探しに行く」
「待ってよ。今、佐野さんが出たらまずい」
「そんなことはわかってる。でも、私が探さなきゃいけない気がする」
「……わかった」
私の言葉に押し切られたのか佐伯くんは渋々了承してくれた。
私は万が一の時のためにお母さんやお父さんに伝言を残して私は家を出た。冷たい夜に自転車を漕いだ。白い息が空に浮かんでは消えていった。
咲がいるとしたらどこにいるだろうか。私は思いつく限りの場所を探した。喧嘩をした川辺。映画館。アクセサリーショップ。どこにもいなかった。話によれば今日はいつもよりも多くお金を持って家を出たとのことだった。どうして連絡がつかないのだろうか。まさか友美が彼女のことを……、とも考えた。
私は彼女のことが心配だった。探し続けて一時間ほどが経って私は夜の道を歩き続けていた。すると、前方に人影が見えた。私は急いで近づいた。うっすらと顔が見えた。咲だった。
「咲!」
「……由香里」
彼女は泣いていたようだった。どうして。そう思った瞬間、自転車のライトに照らされて彼女の全身が見えた。
「何があったの……」
私の目の前には血塗れのナイフを持って傷だらけの咲がいた。
「私、友美を、友美を……」
泣きじゃくる彼女は今にも壊れそうなガラス細工のようだった。
「すみません、今回の事件について何か知っていますか?」
リポーターが訊ねる。
「いえ知らないので、ちょっと……」
みんな、どう答えていいのか悩んでいたようだった。ある者はずっと考えて答えを絞り出し、またある者は簡単に答えて駆け足で去っていった。
それはそうだと私は思った。私だって理解が追いついていない部分があった。友美は一体何を考えているんだろう。そう思った瞬間、私は咲と初めて会話した時のことを思い返した。放課後、廊下で言われた言葉が思い返された。あの時私は咲の考えていることが理解できずにいた。だが、この二日間は友美の考えていることがわからなくなっていた。
状況は刻一刻と変化していた。警察が友美の家を調べはじめた。彼女の家がテレビの画面に映し出される。何人もの警察官らしき人物たちが家を出入りしていた。あの家には友美以外の住んでいる人はいなかった。彼女の人生が調べられていくのを見て私は彼女の人生に思いを馳せた。
テレビを夢中で見ていると玄関のチャイムが鳴った。お母さんがすぐに出ると警察の人が私に話を聞きに来たとのことだった。私が玄関に出ると、整った顔の男性と綺麗な女性が二人立っていた。男性の方が先に話をはじめた。
「……署の青木です。隣にいるのは吉原といいます。昨日の件についてお伺いしたいのですが、よろしいでしょうか?」
「はい、どうぞ」
私は青木さんという男性刑事と吉原さんという女性刑事の二人を家の中に入れた。お母さんが人数分のお茶を用意してくれた。
「まずは昨日の件で心が落ち着かないかとは思います。怪我の具合はどうですか?」
「まだ落ち着かないです。怪我もまだ痛みが残っています」
「そうですか。私たちも突然のことだったので今でも状況が飲み込めずにいます」
青木さんがお茶を飲んで、一呼吸置いた。真剣な目でこちらを見てきた。
「早速本題に入らせていただきます。昨日の夕方の詳細を教えてください」
「わかりました」
青木さんと吉原さんがそれぞれメモ帳とペンを取り出した。青木さんが質問を始めた。
「それでは、まず昨日の夕方何がありましたか?」
「昨日の夕方、私は石崎さんに呼び出されて、誰もいない教室で話をしていました。その途中で石崎さんがナイフを持ち出して、私のことを切りつけようとしました」
「それで?」
「慌てて左腕で庇ったら、切られました……」
私は切られた左腕の方を見せた。包帯を巻いてはいたがまだ痛みが残っていた。
「わかりました。佐野さんと石崎さんの関係は?」
「友達です。高校に進学して部活に入ったらなんとなく遊ぶことが増えて、友達になりました」
「なるほど」
青木さんが何かをメモに記した。両者無言になったところでずっと話を聞いていた吉原さんが手を挙げた。
「すみません。今聞くのもあれなのですが、石崎さんはどういった人ですか?」
頭の中で私は悩んでいた。この二人の刑事さんにどこまで言っていいのかを。どこまで言わなければ友美のことを守れるのかを。何も言えずにいると吉原さんはため息をついた。
「佐野さん。あなた友達だからと言って石崎さんのことを悪く言いたくないんでしょ。わかるよ。でもね。事はもう彼女のことを擁護できる段階ではないのよ」
彼女はバックの中から紙を一枚取り出した。それは写真だった。場所は街にある大きな公園で制服姿から着替えた友美の姿が写っていた。手にはナイフが握られていて、彼女のそばには倒れた犬が写っていた。
「昨日の夜中に撮られた物よ。朝になってその場所で刺し殺された犬が見つかっている。つまり、わかるよね」
「そんな……」
友美は超えてはならない一線を越えようとしていた。いや、私を殺そうとした段階で彼女は一線を越えたのだとこの時気づいた。
「彼女は人を殺す気満々よ。一刻も早く見つけないと取り返しのつかないことになる」
「吉原、それは言い過ぎでは……」
「うっさい、青木お前は黙ってろ」
吉原さんは青木さんのことを睨みつけた。
「佐野さん、あなたわかっているでしょ、あいつはもう擁護し切れないって」
それはその通りだった。私にはもう彼女のことを擁護できそうになかった。だからと言って、この高圧的な刑事を前に何も言うことができなかった。
「何も言わないってことはそれを認めるってことね。だったらあいつが何を考えているのか見当もつくんでしょ。教えて。教えなかった、あなたのもう一人の友達のことも捕まえるけど」
「吉原やめ……」
「引っ込んでろ、この能無しが!」
この刑事は青木さんのことを蹴り飛ばした。青木さんが倒れ込み、慌ててお母さんが駆け寄った。青木さんは気絶したようだった。
この刑事は狂っていた。誰かを捕まえるためならどんな手段に出ても良いと思っている。そんな狂った人間だった。
「それはやめてください!」
「あんたにそれを言う権利は無い。邪魔するならあなたも捕まえるわよ」
「うちでなんてことしてくれるの!」
お母さんがついに口を出した。
「お母さん。じゃああなたも逮捕しますよ」
「上等じゃない! 捕まえられるものなら捕まえてみなさい!」
そこから少しの間膠着が続いた。睨み合いが続いている中で誰かのスマホが鳴った。吉原刑事のスマホだった。
「はいもしもし、吉原です。はい。はい。わかりました。すぐ向かいます。え、青木? あいつは後で向かわせます。じゃあ失礼します」
通話切った吉原刑事は荷物をまとめ始めた。
「よかったわね。事件に進展があったわ。私は現場に行くからこの能無しのことは頼んだ。じゃあ」
言い残して彼女は颯爽と家を出ていった。
それから三十分ほどが経って青木さんが目を覚ました。私とお母さんはあの後のことを詳細に伝えた。
「うちの吉原がすみません……」
「何なんですか、あの刑事は!」
お母さんが責め立てた。青木さんは申し訳なさそうな顔をしていた。
「うちの署でもマッドドックと言われている刑事でして。まあ、さっきからずっと音声レコーダーで会話を録音していたので、後で上に報告しておきます」
「ありがとうございます……」
「こちらこそ、すみませんでした」
青木さんは深々とお辞儀をして帰っていった。
いくら狂った刑事だったとはいえ、吉原刑事が言っていることは間違えではなかった。友美はもう取り返しのつかない領域まで足を踏み入れていた。やはり彼女を助けることはできないのだろうか。いや、まだ手はあるはずだ。それを探そう。そんなことを思っていた矢先だった。
青木さんが帰ってから時間が経って日が傾き始めた頃、私のスマホが鳴り始めた。お母さんは買い物に出てしまっていて、静かな部屋に着信音だけが鳴り響く。佐伯くんからの着信だった。私は嫌な予感がした。急いで通話に応じた。
「もしもし」
「もしもし、佐野さん。大変なんだ。咲ちゃんと連絡がつかない。咲ちゃんのお母さんも心配している」
「そんな……」
「もしかしたら、石崎さんが……」
私は急いで外に出る準備を始めた。
「探しに行く」
「待ってよ。今、佐野さんが出たらまずい」
「そんなことはわかってる。でも、私が探さなきゃいけない気がする」
「……わかった」
私の言葉に押し切られたのか佐伯くんは渋々了承してくれた。
私は万が一の時のためにお母さんやお父さんに伝言を残して私は家を出た。冷たい夜に自転車を漕いだ。白い息が空に浮かんでは消えていった。
咲がいるとしたらどこにいるだろうか。私は思いつく限りの場所を探した。喧嘩をした川辺。映画館。アクセサリーショップ。どこにもいなかった。話によれば今日はいつもよりも多くお金を持って家を出たとのことだった。どうして連絡がつかないのだろうか。まさか友美が彼女のことを……、とも考えた。
私は彼女のことが心配だった。探し続けて一時間ほどが経って私は夜の道を歩き続けていた。すると、前方に人影が見えた。私は急いで近づいた。うっすらと顔が見えた。咲だった。
「咲!」
「……由香里」
彼女は泣いていたようだった。どうして。そう思った瞬間、自転車のライトに照らされて彼女の全身が見えた。
「何があったの……」
私の目の前には血塗れのナイフを持って傷だらけの咲がいた。
「私、友美を、友美を……」
泣きじゃくる彼女は今にも壊れそうなガラス細工のようだった。